👉👉 🇺🇸 All Posts 🇬🇧 / 🇯🇵 記事一覧 🇯🇵 👈👈
♦️ はじめに
 なっちゃん
なっちゃん先生、手術前のバンコマイシンで顔が真っ赤になった患者さんがいて…“Red man症候群(レッドマン症候群)”って言われたんですけど、最近は別の名前になったって本当ですか?



そうだね.実は今では“Red man (person)”という表現は使わない方向になってるね.現在(2020年ごろから),正式には“Vancomycin infusion reaction(VIR)”または“Vancomycin flushing syndrome”と呼ばれているよ.


♦️名称変更の背景と文化的配慮
かつては,バンコマイシン投与後に顔や上半身が赤くなることから「Red man症候群」と呼ばれていました.しかしこの表現は「白人患者の皮膚所見に基づいた命名」であり,アメリカ先住民などに対する蔑称と重なるため,人種的に不適切であると指摘されました.
現在では、IDSA(米感染症学会)・SHEA・PIDSなどが共同声明を発表し,「Red man syndrome」の代わりに「Vancomycin infusion reaction(VIR)」という表現を推奨しています[IDSA 2020, JAMA 2021–2025]
♦️ なぜ,どのように生じる?🤔 〜病態生理〜
Vancomycin infusion reaction(VIR)は,IgEを介さない偽アレルギー反応(anaphylactoid reaction)です.
つまり,感作を必要とせず,肥満細胞や好塩基球が直接刺激されヒスタミンが放出される反応です.急速投与される場合に発症率が上昇するとされ,60〜120分かけて緩徐に点滴静注するよう指示がある理由です.
- IgE関与なし(=真のアレルギーではない)
- 投与速度に依存:速いほど発生リスク・重症度が上昇
- 1 gを60分未満で投与 → 発症率上昇
- 再曝露で耐性を示すこともありますが,再発することもある
♦️ アナフィラキシーと紛らわしい?!😳
🔷 臨床症状とアナフィラシーとの鑑別
VIRは「紅潮+掻痒+軽度の低血圧」が典型です.
症状がそれにとどまらず,呼吸器症状や高度の血圧低下など,多臓器症状を伴う場合はアナフィラキシーを疑い,区別がつかないときは安全のためにアドレナリン対応を優先します.以下に比較のための表を提示します.
| 項目 | Vancomycin infusion reaction(VIR) | アナフィラキシー |
|---|---|---|
| 発症機序 | ヒスタミン直接放出(非IgE性) | IgE介在性免疫反応 |
| 発症時期 | 投与中または直後(4–10分以内) | 投与直後〜数分 |
| 皮膚症状 | 顔・頸部・上胸部の紅潮・掻痒 | 蕁麻疹・全身紅斑 |
| 呼吸器症状 | 通常なし | 喉頭浮腫・喘鳴・気道狭窄 |
| 血圧低下 | 軽度(まれに重度) | 顕著なショック可 |
| 血清トリプターゼ | 正常 | 上昇することが多い |
🔷 VIRの予防と治療 〜まずは起こさないことが大事〜😡
リスクとしては前述した通りなので,投与速度を適切に守ることがまずは重要です.
| 項目 | 推奨内容 |
|---|---|
| 投与速度 | 1gあたり60分以上(最大10 mg/min) |
| 希釈 | 適切に希釈して緩徐に投与 |
| 事前投与 | 高リスク患者では抗ヒスタミン薬(H1+H2ブロッカー)を前投与 |
| 併用薬注意 | オピオイドなどヒスタミン放出薬との同時投与を避ける |
発症時の対応は以下の通り.
- まず投与を中止
- バイタル確認・気道確保(呼吸状態確認)
- 軽症例:抗ヒスタミン薬投与
- 重症例または鑑別困難時:アドレナリン投与・アナフィラキシー対応
- 症状軽快後,必要なら速度を落として再投与は可能
♦️ 以上を踏まえた,周術期・麻酔領域での注意点☝️
麻酔導入前から投与されているバンコマイシン投与は,VIRとアナフィラキシーの鑑別が難しく,誤って全身反応と判断されるリスクがあります.
🔷 推奨投与タイミング⏰
- 投与開始:麻酔導入の60〜120分前 (=手術開始時には投与が完了している状態)
- 覚醒時の患者で観察できるように投与するのが理想
🔷 注意ポイント
- 投与中の紅潮・低血圧 → VIRを疑う
- 同時投与薬(モルヒネ,筋弛緩薬など)もヒスタミン放出を増強する
- 周術期管理チーム試験などでも,「VIRとアナフィラキシーの鑑別・対応」が定番テーマになりうる.
🔷 名称変更についてもう一度☝️
「Red man syndrome」は医学的にも理解されやすい名称でしたが,患者の多様性を尊重する観点から,今では’’Vancomycin infusion reaction”が正式です.
医療や工学の分野でも,かつては機器制御で “master/slave” という言葉が使われていましたが,現在は “primary/secondary” や “leader/follower” などに置き換えられています.このように,科学的正確性+文化的感受性の両立が求められる時代になりましたね😊
🌍 地域による違い
| 項目 | 日本(🗾) | 米国・欧州(🌍) |
|---|---|---|
| 用語 | 「Red man症候群」という表記が一部の教科書・添付文書などで依然使用されている(2025年時点でも完全には置換されていない) | “Red man syndrome” は廃止され、すべて “Vancomycin infusion reaction(VIR)” に統一 |
| ガイドラインの権威・更新状況 | 日本感染症学会や添付文書などでは用語変更の反映がやや遅れている | IDSA/SHEA/PIDS(2020年共同声明)以降、主要ガイドライン・教育資料で全面的にVIR表記に移行 |
| 投与速度の基準 | 通常「1gあたり60分以上」を推奨(臨床現場でも広く遵守) | 同様に「最大10 mg/min」を上限として明示(1gを60分以上) |
| 周術期の投与タイミング | 手術部位感染予防の観点から、麻酔導入60〜120分前に投与開始・完了を推奨 | CDC・AAOSなどのPerioperative Antibiotic Guidelinesでも同様のタイミングを明記 |
| 文化的感受性の取り扱い | 医学用語における差別的表現見直しはまだ議論途上。日本語医学教育では「Red man」表記が説明的に残るケースも | 2020年以降、JAMAやAMAなどがinclusive language方針を打ち出し、差別的・人種的に不適切な用語の修正が強く推奨されている |
| 教育現場での扱い | 学生・研修医教育では「Red man症候群(旧称)→VIR(新称)」の両方を教える移行期にある | 医学部・大学院・病院教育プログラムでは「Red man」の使用は禁止または非推奨と明記 |
📝 まとめ(Take Home Points)
- Red man症候群は、現在「Vancomycin infusion reaction(VIR)」と呼ばれる
- 病態は非IgE性ヒスタミン放出反応で、急速投与が主因
- 予防の鍵は「ゆっくり投与」+「抗ヒスタミン前投与」
- 周術期ではアナフィラキシーとの鑑別が重要
- 医学用語も倫理的・文化的にアップデートされる流れに注目
🔗 Related articles
- to be added
📚 References & Further reading
- Martel TJ, Jamil RT, Afzal M. Vancomycin Infusion Reaction. StatPearls. 2025.
- IDSA/SHEA/PIDS Position Statement: Replace “Red Man Syndrome” with “Vancomycin Infusion Reaction.” Hosp Pediatr. 2020;10(7):623–624.
- JAMA Inclusive Language Initiative (2021–2025). JAMA Network 👉 名称について
- Renz CL et al. Oral antihistamines reduce the side effects from rapid vancomycin infusion. Anesth Analg. 1998;87(6):1340–5.
- CDC/AAOS. Perioperative Antibiotic Guidelines. 2025.
- Cureus 2024. Vancomycin Flushing Syndrome: A Case Report.
- Medsafe, 2023. Infusion-related reactions: not all allergy-related.
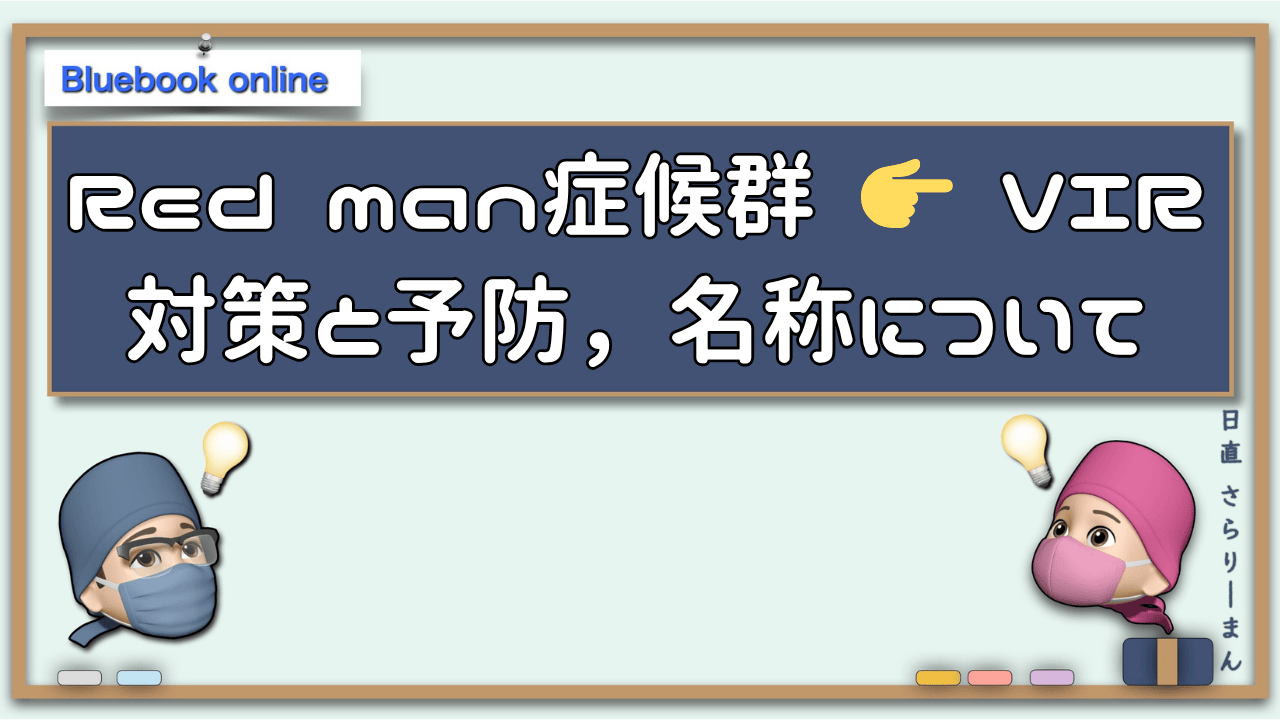
コメントを投稿するにはログインしてください。