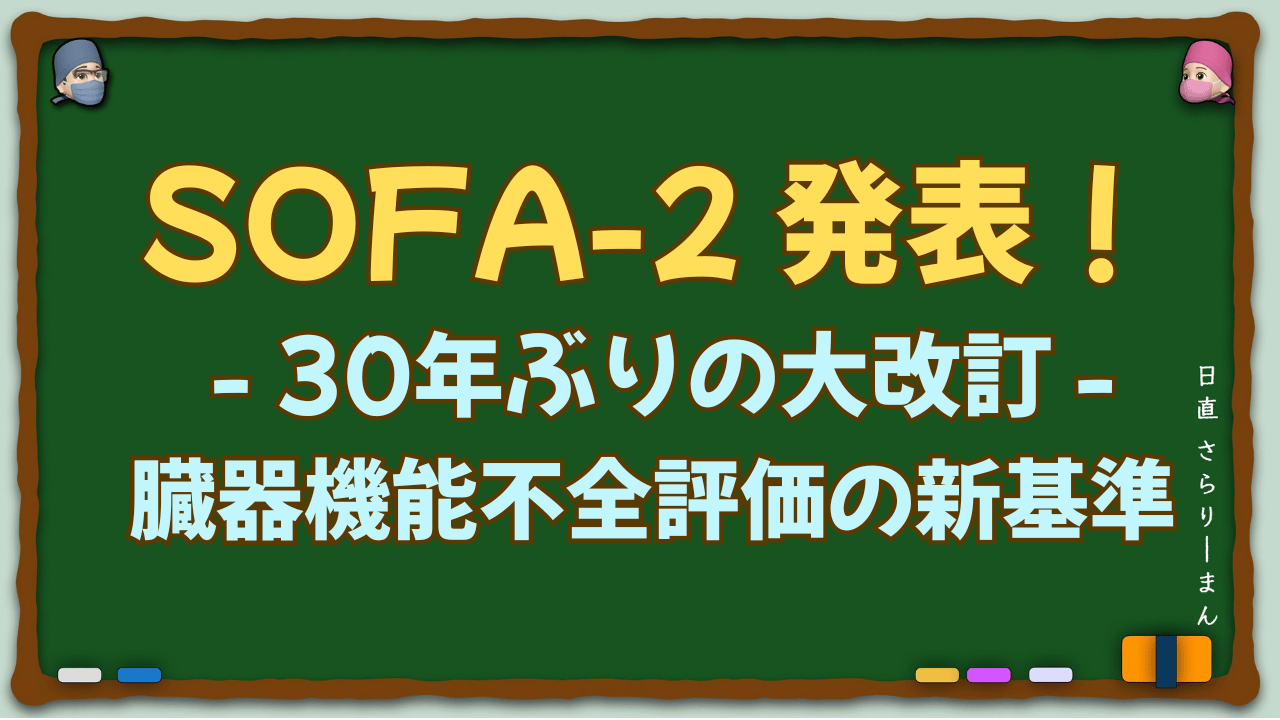👉👉 🇺🇸 All Posts 🇬🇧 / 🇯🇵 記事一覧 🇯🇵 👈👈
♦️ はじめに:集中治療における評価法の進化
集中治療の現場は,この30年間で大きく変貌を遂げました😊.非侵襲的換気療法や高流量鼻カニュラ酸素療法が日常的に使用され,持続的腎代替療法(CRRT)が普及し,ECMOや補助人工心臓といった機械的循環補助デバイスの臨床導入が進んできました.しかし,1996年に策定されたSOFA(Sequential Organ Failure Assessment)スコアは,こうした近年の治療法を十分に反映できていませんでした.
そして2025年10月,国際的な専門家コンセンサスと大規模データ検証に基づいて,SOFA-2スコアが誕生しました🎂.世界各国から集まった60名の専門家グループが修正Delphiプロセスを用いて合意形成を行い,9か国から集められた334万例(!)を超えるICU患者データで開発・検証されました.
SOFA-2の死亡予測精度(AUROC)は従来版(SOFA-1)と同等かわずかに向上していることが示され,多様な医療環境(所得水準や地域の違い)で安定した性能が確認されています.
重要なのは,SOFA-2は単に予測精度を追求するのではなく,ECMOやCRRTなど現代の高度な臓器サポート治療を適切にスコアに組み込むことで,スコアが実際の臓器機能不全の重症度をより正確に反映することを目的としている点です(従来のSOFAでは,スコアと重症度が必ずしも一致していませんでした).
🎓 試験対策のポイント:SOFA-2は敗血症診療やICUアウトカム評価における「共通言語」として機能します.今後,麻酔科専門医試験・周術期管理チーム試験でも出題される可能性があるため,新しい閾値と解釈ルールをしっかり押さえておきましょう👍
♦️ SOFAスコア改訂の背景と必要性
1996年版のSOFAは,6つの臓器(呼吸・循環・肝・腎・凝固・中枢神経)における機能不全を0~4点で段階評価し,経時的に追跡する(Sequential)という特徴を持っていました.しかし,現代の集中治療領域では,呼吸サポートの選択肢が大幅に拡大し,血管作動薬の使い分けや組み合わせが洗練され,機械的な補助循環の導入も一般的になるなど,臓器サポート治療の選択肢と運用方法が大きく変化してきました.
SOFA-2は,この現場の変化を反映するため,評価変数の定義や閾値を全面的に見直しました.SOFA-2はAPACHE IIやSAPS IIのような純粋な予測モデルとは本質的に異なり,主目的は臓器機能不全の程度を客観的に記述し段階分けすることにあります.「この患者の30日死亡率は○%」と個別予測するツールではなく,重症度が高いほど死亡率も高いという整合性を持った評価ツールであることを理解しておくことが重要です☝️.
【補足】SOFA-2の開発プロセスと,その性能・検証結果
🔷 開発プロセス
SOFA-2の開発は,まず60名の国際専門家が修正Delphiプロセス,系統的レビュー,変数選定を実施しました.その後,9か国から集められた約334万例のICUデータを用いて,学習と検証が行われました.この過程は,設計段階を記述したコンセンサス論文と,最終スコアのデータ駆動型開発と外的妥当化を報告したJAMA論文という二本柱で公表されています.
📊 開発と検証のポイント ・方法論:修正Delphi法と大規模レジストリデータによる反復検証 ・一次目的:臓器機能不全の段階的記述と、死亡リスクの適切な層別化 ・結果:予測精度の向上に加え、現代の臓器サポート(HFNC、ECMO、RRT、機械的循環補助)を適切に反映
🔷 性能・検証結果
主要評価項目はICU死亡率で,SOFA-2は従来版と同等以上の予測性能が確認されています.再分類分析でも,不適切な分類が減少していることが示されました.
さらに重要な点として,日々の変化量(ΔSOFA)や入室期間中の最大値(最大SOFA)といった動的指標でも優れた性能が保たれている点と,所得水準や地域が異なる多様な医療環境においても,その性能が安定していた点です.これは臨床的に実装していく上で,大きな後押しとなっています👍.
今後の課題としては,地域ごとの再キャリブレーション(補正),小児患者への適用可能性の検討,ICU外(救急部門,一般病棟)での使用可能性の検証などが挙げられます.
♦️ SOFA-2スコアの詳細:6つの臓器システム
SOFA-2でも評価する臓器の数は6つのまま維持されました.内容は以下の通りです.名称がより生理学的に正確になりました.具体的な点数等については,必ず原著論文を参照してください.
- Brain(脳),Respiratory(呼吸器),Cardiovascular(循環器),Liver(肝臓),Kidney(腎臓),Hemostasis(止血系).
- 各システムの0~4点の配点ルールが,現代の実臨床に合わせて刷新されています.
🧠 脳(Brain)
GCS(Glasgow Coma Scale)による評価基準が再設定されました:
重要な変更点として,せん妄のために治療薬を必要とする状態は,GCS 15であっても1点として評価されるようになりました.また,鎮静下の患者については,鎮静前の最終GCSを用いるという明確なルールが提示されました.不明な場合は0点とカウントしますが,臨床判断は慎重に行う必要があります.
評価の一貫性を保つため,鎮静深度(RASSなど)と合わせて記録し,スコアリング目的の薬剤投与にならないよう記録テンプレートを整備することも重要かもしれません.
🫁 呼吸器(Respiratory)
呼吸器系の評価では,酸素化能力を示すPaO₂/FiO₂比が複数の閾値(おおむね200〜300 mmHg台を中心とした段階的基準)で評価されます.値が低いほど重症度が高いことを示します。
さらに,「高度な呼吸サポート」には,HFNC,NIV(CPAP/BiPAP含む,非侵襲的換気),IMVが含まれます.呼吸目的でECMO(VV-ECMOまたはVA-ECMO.循環補助のVA-ECMOの場合は循環器でも加点)が該当します(加点).
重要な追加事項として,動脈血ガス分析が実施できない状況では,SpO₂/FiO₂比(S/F比)による代替評価が可能になりました.ただし,この代替評価はSpO₂が98%未満の場合に限定されます.S/F比とP/F比の換算関係については,複数の研究で妥当性が支持されています👍
🌐 国際的な視点: SpO₂/FiO₂比による代替評価は,動脈血ガス分析の頻回実施が困難な医療環境(低・中所得国,救急外来,一般病棟など)でのSOFA-2の適用を可能にします.開発チームは,世界中のICUで使用できる「包括的」なスコアを目指し,この代替指標を組み込んだようです.日本のICUでは動脈血ガス分析が標準的ですが,一般病棟での早期警告スコアとしての応用も期待されています.
🫀循環器(Cardiovascular)
血管作動薬の評価は,ノルエピネフリンとエピネフリンの合算用量で段階に評価されます(baseとして👉補足参照):
機械的循環補助(MCS:Mechanical Circulatory Support)として,VA-ECMO,IABP,LVADなどが明確にスコアに組み込まれました.
MAP(平均動脈圧)のみでの段階評価は,血管作動薬が利用できない,または使用禁忌である特殊な状況での代替として位置づけられています.
具体的な用量基準や点数配分は原著論文をご参照ください。
- 薬によっては,化学的に「塩の形(重酒石酸塩や塩酸塩)」で製剤化されています.
- しかし,同じ1mgでも塩の重さを含むかどうかで有効成分の量が違うため,世界的には「as base=有効成分そのものの量」で統一して表す決まりがあります.
- 日本のノルアドレナリン製剤,アドレナリン製剤はすでに「ベース換算」で表示されているので,これまで通りのμg/kg/minの計算でOKです.
💡 日本での実情: LVADは主に重症心不全の長期管理に使用され,急性期ICUでの使用はECMOやIABPに比べると限定的です.一方,Impellaなどの経皮的補助循環デバイスは急性期にも使用され,よく見られるようになってきました.
🤎 肝臓(Liver)
肝臓の評価では,ビリルビン値の閾値が現代の臨床実態に合わせて再調整されました.SOFA-1と比較して,より細かな重症度の層別化が可能になっています.
開発過程では,ASTなどの代替指標も検討されましたようですが,世界中で測定可能で臨床的に確立されているという理由から,最終的にビリルビンが維持されました.
具体的な閾値については、原著論文をご確認ください。
💛 腎臓(Kidney)
腎臓系では,クレアチニン値と尿量に基づく評価に加え,腎代替療法(RRT)の取り扱いが明確化されました.
SOFA-2では,RRTが実施されている場合,または特定の電解質・酸塩基平衡異常の基準を満たす場合に最高点とします.これにより,RRTを必要とする重症腎機能不全がより適切に評価されるようになりました.
慢性的にRRTを受けている患者の扱いについても注記されています。
⚠️ 重要な注意: SOFA-2におけるRRT基準は,あくまでスコアリングのための基準です.実際の透析導入の適応判断は,個々の患者の全身状態,電解質異常の程度,酸塩基平衡異常,体液バランスなどを総合的に評価して決定します.スコアが治療適応を規定するものではないことに注意が必要です.
🩸止血系(Hemostasis)
止血系では,血小板数による評価基準が調整されました.これらの閾値は,DIC(播種性血管内凝固症候群)などを背景とした死亡リスクの層別化に,より適合するよう設定されています.
SOFA-1からの変更により,より細かな段階評価が可能になりました.
具体的な閾値については、原著論文をご確認ください。
🙅 【補足】除外された臓器システム:消化器と免疫
開発の初期段階では消化器系や免疫系の追加も検討されていました.しかし,消化器系については十分なデータの質が得られず,予測妥当性を確認できなかったようです.
免疫系については,白血球数やリンパ球数がU字型の関連を示したことに加え,内容妥当性に問題があることが指摘されました.感染や炎症への生体反応として白血球やリンパ球が増加することは、むしろ正常な免疫応答である可能性があり,「機能不全」として評価することの妥当性が疑問視されたことによります.
最終的には,測定の普及の程度と臨床的な受容性を優先し,モデルの単純性と汎用性を保つため,6つの臓器による評価を維持する判断が下されました.
❓ なぜ追加しなかったの🤔? 👉 データの質と量の課題 ・U字型関連など統計学的な解釈の難しさ ・内容妥当性(生理学的な意味づけ)の問題 ・世界中で測定可能かという普遍性の観点
🔷 SOFA-1との比較:何が変わったか🤔
SOFA-2では以下の点が主に変更されました⬇️.詳細な比較については,コンセンサス論文をご参照ください.
🔸 評価変数の名称
- より生理学的に正確な名称へ(Coagulation → Hemostasis など)
🔸 評価閾値の調整
- 各臓器システムの閾値が現代の臨床データに基づいて再設定
- P/F比、血管作動薬用量、クレアチニン値、血小板数など
🔸 現代的治療の組み込み
- HFNC、NIV、ECMOなどの高度呼吸サポート
- 機械的循環補助(MCS)の明示
- RRTの扱いの明確化
🔸 代替評価の追加
- SpO₂/FiO₂比による代替評価(動脈血ガス不可時)
- MAP単独評価(血管作動薬使用不可時)
🔸 特殊状況への対応
- 鎮静下患者のGCS評価ルール
- せん妄治療薬使用時の扱い
- 慢性透析患者の扱い
♦️ 実臨床での使い方:ベッドサイドでのSOFA-2
🔷 欠測値の取り扱い(測定していないデータの取り扱い)
SOFA-2では,欠測値の補完方法が明確化されました:
- ICU入室1日目の欠測値:0点(正常値)として補完
- 2日目以降の欠測値:LOCF(Last Observation Carried Forward:最終観察値の繰り越し法)を使用
これは,測定されていない項目は安定しているか,臨床的に重要でないと推定する方法です.完全症例分析(欠測があるケースを除外)と比較すると,実臨床でより広く適用できるアプローチとされています.
🔷 代替評価の使用条件
- SpO₂/FiO₂比:動脈血ガス分析が実施できない場合に使用可能ですが、SpO₂が98%未満の時に限定されます
- MAP単独評価:血管作動薬が利用できない、または使用禁忌の場合にのみ使用します
🔷 特殊な状況での評価
- 鎮静下の患者:鎮静前の最終GCSを使用します
- ECMO使用時:
- 呼吸目的のECMO → 呼吸器系で最高点
- 循環目的のVA-ECMO → 呼吸器系と循環器系の両方で該当点を付与
- 慢性透析患者:注記に従ってカウントします
🔷 経時的評価(Sequential Assessment)の重要性
SOFA-2は単一時点の評価だけでなく,ICU滞在中の推移を追跡することで真価を発揮します:
- 入室時スコア:ベースラインの重症度評価
- ΔSOFA(デルタSOFA):初日から現在までの変化量
- 最大SOFA:入室期間中の最高値
- 日々の推移:臓器機能の改善・悪化の傾向
これらの動的指標により,治療効果の判定や予後予測においてより有用な情報が得られます.
まとめ:現代の集中治療に相応しい,新しい評価基準😊
- SOFA-2は,現代の臓器サポート治療を適切に反映するよう,評価変数・閾値・運用ルールを全面的に再設計した「新しい共通言語」です.死亡予測の性能も確認され,多様な医療環境(所得水準の違いや地域の違い)で一貫した性能を示しています.
臨床現場では、以下の点が実装の鍵となります:
- ベースラインを揃えた一貫した採点運用
- S/F比やMAP単独評価など代替指標の正しい適用条件の理解
- ECMO,RRT,機械的循環補助の厳密な記録
- 経時的評価(ΔSOFA、最大SOFA)の活用
教育面では,新しい閾値と例外ルールの暗記に加え,「記述スコアである」という本質的な位置づけを理解し,APACHE/SAPSとの役割分担を説明できることが重要です.
今後の展望としては,小児患者への適用,ICU外(救急部門,一般病棟)での使用可能性,地域別のキャリブレーション,動的評価(ΔSOFA、最大SOFA)のさらなる活用などが注目されます.日本の電子カルテ実装では,ノルエピネフリン当量やS/F比の自動計算機能を組み込むことで,実務の効率化が期待できます.
📝 Take Home Messages
SOFA-2は,国際的な専門家グループによる厳格な開発プロセスと大規模データ検証を経た新しい評価基準です.今後,Surviving Sepsis Campaignなど主要国際ガイドラインの次回更新時(通常3-5年ごと)に,正式な推奨として組み込まれることが予想されます.日本国内では,日本集中治療医学会や日本救急医学会による評価が進行中であり,次回の日本版敗血症診療ガイドライン更新時に反映される可能性があります.医療機関でのSOFA-2導入を検討される際は,各施設のICU運営方針,電子カルテシステムの対応状況,多職種チームへの教育体制などを総合的に勘案し,段階的な移行計画を立てることが推奨されます.
🔑 Key Points
- 🚨 SOFA-2は6つの臓器評価システムを維持しながら,定義・閾値・運用ルールを全面刷新
- 📊 死亡予測精度は従来版と同等以上で,多様な医療圏で安定した性能を示す
- 🔍 呼吸器系:P/F比の段階的評価,高度な呼吸サポートの考慮、ECMO使用で最高点、S/F比による代替評価が可能(SpO₂<98%)
- 💉 循環器系:ノルエピネフリン+エピネフリンの合算用量評価、機械的循環補助(MCS)を明示
- 🩺 腎臓系:RRTの実施または特定基準充足で最高点,ただし治療適応の判断とは別
- 🧠 脳:せん妄治療薬使用時の評価ルール,鎮静前GCSの使用を明確化
📚 References & Further reading
- Moreno R, Rhodes A, Salluh JIF, et al. Rationale and Methodological Approach Underlying the SOFA-2 Update. JAMA Netw Open. 2025;8(10):e2840786. Available from: https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2840786
- Ranzani OT, Singer M, Salluh JIF, et al. Development and Validation of the SOFA-2 Score. JAMA. 2025;334(18):1842–1856. doi:10.1001/jama.2025.20516. Available from: https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2840822
- Pölkki A, Law A, Rehn M, et al. Optimal Cutoffs for PaO₂/FiO₂ in Revised SOFA. Crit Care Explor. 2025;7(5):e10233. Available from: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12571143/
- Fukuda Y, Nakada TA, Oda S, et al. Utility of SpO₂/FiO₂ in Acute Hypoxemic Respiratory Failure. Acute Med Surg. 2021;8:e683. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33493229/
- Plečko D, Bennett N, Ukor I, et al. A framework and analytical exploration for a data-driven update to SOFA. Crit Care Resusc. 2025;27(1):45-54. Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1441277225000092
🔗 Related articles
- 追加予定
⚠️ Copyright & Disclaimer
Original Publications
- Ranzani OT, Singer M, Salluh JIF, et al. Development and Validation of the SOFA-2 Score. JAMA. 2025. doi:10.1001/jama.2025.20516
- Moreno R, et al. Rationale and Methodological Approach Underlying the SOFA-2 Update. JAMA Network Open. 2025.
- Full articles available at: https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2840822
Disclaimer
- この記事は、上記の原著論文に基づく教育目的の要約です。
- 記事に含まれる情報は、医学的助言や治療の代替となるものではありません。
- 臨床現場での実践は、最新のガイドライン、個々の患者の状況、および担当医の判断に基づいて行ってください。
- この記事は独立した教育リソースであり、American Medical Association、European Society of Intensive Care Medicine、またはSOFA-2開発グループによる公式な承認や推奨を受けたものではありません。
- 本記事の内容は、著者による原著論文の解釈を反映したものです。
- 日本国内での実装については、日本集中治療医学会などの関連学会のガイドラインもご参照ください。
- 臨床判断は必ず原著論文を参照の上、各施設のプロトコルと担当医の判断に基づいて行ってください。
- 著者は、本要約に基づいて行われた臨床判断について一切の責任を負いません。
Educational Purpose
- この要約は、周術期管理および集中治療に携わる医療従事者を対象としています。
- 読者は、完全かつ権威ある情報については、原著論文および所属施設のプロトコルを参照することを推奨します。
- 本記事で使用されている表は、原著論文のデータを基に著者が独自に作成したものです。
日本での使用に関する注意
- 本記事で紹介されている薬剤・治療法の使用に際しては、日本での承認状況、添付文書、保険適用の条件を必ず確認してください。
- 日本国内の実践については、日本麻酔科学会、日本集中治療医学会などの関連学会が発行するガイドラインを併せて参照してください.
著作権に関するお問い合わせ
- 本記事は教育目的で作成されており、原著者および著作権者の権利を尊重しています。
- 記事掲載は引用ルールに則り細心の注意を払っておりますが、掲載内容にご懸念がある場合は、下記までご連絡ください。速やかに対応いたします。
- ✉️ classicanesthesia4@gmail.com