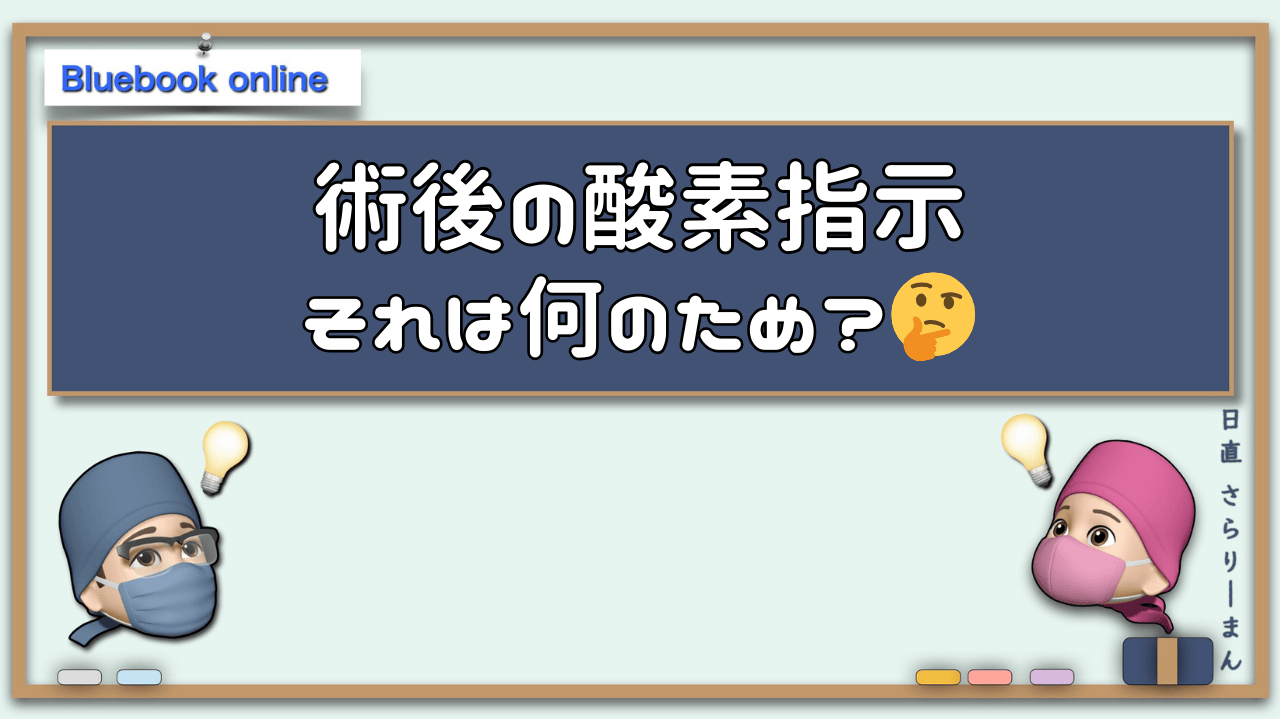👉👉 🇺🇸 All Posts 🇬🇧 / 🇯🇵 記事一覧 🇯🇵 👈👈
♦️ はじめに
「術後酸素3(or 4)L,3時間で」
よく耳にする言葉ではないでしょうか?全身麻酔で気管挿管をして,手術終了したら抜管して,術後は酸素マスクをつけられて病棟に帰っていく.ありふれた光景ですね.
この酸素3L/分を通常の酸素マスク(特に密閉感の強い,古いタイプ)で投与することには議論があります.実際,「なぜ3〜4Lなのか,なぜ3時間なのか」には明確なエビデンスはなく,慣習的に使われている設定であることも多いです.
今日は「なぜ,全身麻酔後に(ほぼ)ルーチンで酸素投与をするのか?」について簡単にお話しします.
♦️ 事実:全身麻酔後は低酸素血症になりやすい
全身麻酔や,特に開腹・開胸手術は呼吸に大きな影響を与え,低酸素血症を来しやすくなります.術前の併存症(高齢者,高度肥満,呼吸器疾患など)があればさらにリスクが上がります.
教科書を開けば呼吸への影響,原因,合併症等が大量に書かれていますが,ここでは絞って「まず覚えるべきポイントを2つ」を整理します.以下の理由があるため,原則的に酸素投与が行われてきました.
🔷 ① 麻酔薬残存による呼吸抑制 → 低換気・上気道閉塞
麻酔薬(吸入麻酔薬や静脈麻酔薬)の残存によって呼吸中枢が抑制されます.現在の薬は比較的クリアランスが速いですが,高齢者や臓器障害のある患者ではリスクが高まります.
本来はPaO₂低下やPaCO₂上昇があれば「呼吸しよう!」と反応が起きますが,麻酔薬はこの両方を抑制します.結果,呼吸努力が低下し低換気となります.
さらに舌根沈下による上気道閉塞が生じやすく,特に肥満患者や高齢者では要注意です.上気道閉塞自体に対しては酸素投与は無効であり,気道確保が必要です.
🔷 ② 手術(特に開腹・開胸)による疼痛 → 咯痰排出抑制・無気肺形成
開腹・開胸手術では疼痛が強く,硬膜外麻酔などが不十分だと深呼吸が阻害されます(浅呼吸).
咳も痛いため喀痰排出が不十分となり,活動性も低下するため肺胞虚脱(無気肺)が広範に起こるリスクがあります.もちろん,十分な鎮痛がされていれば影響はかなり緩和されます.
特殊例としては,上肢の手術で腕神経叢ブロック(特に斜角筋間アプローチ)を行っている場合,横隔神経がブロックされることによる呼吸機能低下が生じることがあります.健常者ではほとんど問題になることはありませんが,高齢者やCOPD患者さんなどは呼吸困難感や低酸素血症を来すことがあります.
♦️ ただし,酸素は“治療薬”ではない☝️
🔷 酸素は治療薬ではない
ここが大事です.酸素投与はあくまで 対症療法(時間稼ぎ) です.肺炎で低酸素になっている患者に酸素だけ投与しても治りません(もちろん本人の免疫力や,時間が解決することもありますが・・😅).
つまり,低酸素血症の本質的な原因の改善が必要です
🔷 必要ないのに高流量酸素を投与してはいけない
「低酸素がダメなら,予防のために10L/分くらい入れておけばいいじゃん?」と思うかもしれませんが,NGです.
理由は以下の通りです.
- みかけ上SpO₂が高く保たれてしまい,潜在的な低酸素血症がマスクされる
- 長時間になると酸素毒性や,特定の患者ではCO₂ナルコーシスのリスクがある
例えば大きな無気肺や軽度の肺塞栓があれば,本来SpO₂が低下して医療者が気づくはずです.しかし,高流量酸素で95%以上に保たれてしまうと,治療介入が遅れるリスクがあります.
逆に言えば,高流量酸素を投与しなければSpO₂が保てない状況は,「何かよくないことが起きている」サインと考えるべきです.
🔷 実際の経過
多くの術後低酸素血症は時間経過とともに改善します.麻酔薬は代謝・排泄されますし,疼痛も鎮痛薬でコントロールできます.背側無気肺も深呼吸や体位調整で改善可能です.
したがって通常は 3〜5L/分の酸素投与で十分にSpO₂が保たれますし,この程度であれば現実的には許容範囲でしょう.しかし,上記のように,それでも低下する場合は,必ず原因検索が必要です.
♦️ 国際的には・・?🤔
「術後酸素投与」は世界的にも広く行われていますが,“一律ルーチン”から“個別調整”へシフトしつつあります.以下は主要ガイドライン・学会の現状です(各詳細は後掲の参考文献を参照).
| 学会・機関 | 現在の推奨内容 |
| ASA(米国麻酔科学会) | PACUでは必要に応じて酸素投与.SpO₂/換気モニタリング下で調整。固定的な「3L/3時間」ルールはない |
| WHO(世界保健機関) | 挿管患者では FiO₂ 80%を術中+術後2〜6時間継続をSSI予防として推奨.ただし議論が多く採用は限定的 |
| ESAIC(欧州麻酔集中治療学会) | 実際の現場ではWHO推奨は必ずしも遵守されていない.近年は滴定(titration)・過剰回避がトレンド |
| BTS(英国胸部学会) | 医療現場全般で「目標SpO₂範囲を処方し,その範囲に合わせて酸素を滴定」することを推奨 |
| ASCRS(米国大腸直腸外科学会 2024/25) | SSI予防目的での高FiO₂はルーチン推奨しない(条件付き) |
| 最近のレビュー | 「術後患者は今も酸素を受けるが,必要最小限の投与・SpO₂に基づいた調整が主流に」 |
📝 まとめ
- 術後は麻酔や手術の影響で低酸素血症になりやすい.
- 多くは時間経過,鎮痛,体位調整で改善できる.
- 通常は3〜5L/分程度の酸素投与で十分.
- 酸素は治療薬ではなく,あくまで対症療法.
- 漫然と高流量酸素を投与すると病態を見逃すリスクあり.
- 酸素でSpO₂が保てない場合や,高流量を必要とする場合は早期に原因検索を!
📚 References & Links
- American Society of Anesthesiologists (ASA). Practice Guidelines for Postanesthetic Care. Anesthesiology. 2013;118:291–307.
- World Health Organization (WHO). Global Guidelines for the Prevention of Surgical Site Infection. Geneva: WHO; 2018 update.
- ESAIC. Practice of Oxygen Use in Anesthesiology — ESAIC Member Survey. 2022.
- British Thoracic Society (BTS). Guideline for Oxygen Use in Adults in Healthcare and Emergency Settings. Thorax. 2017.
- American Society of Colon and Rectal Surgeons (ASCRS). Surgical Site Infection Prevention Toolkit. 2024/25 edition.
- El Maleh Y, et al. Updated meta-analysis on intraoperative FiO₂ and SSI. 2023.
- Wang H, et al. Perioperative oxygen administration for adults undergoing non-cardiac surgery. 2024 review.
- Suzuki S, et al. Oxygen administration for postoperative surgical patients: a narrative review. 2020.