👉👉 🇺🇸 All Posts 🇬🇧 / 🇯🇵 記事一覧 🇯🇵 👈👈
♦️ はじめに
研修医やコメディカルの皆さんは,テンポラリー(一時的)ペースメーカを内頸静脈から入れて,怪しげな(笑)ダイヤルのついた発生器がぶら下がっているのを見たことがあると思います.手術前に,患者さんの胸(ペースメーカ直上)に丸い機械を当てて,昔のPCみたいなプログラマで設定している場面も見ますよね(最近は遠隔管理も普及).心外膜リードを縫い付けて心臓外科からリードが「ひょいっ」と渡され,麻酔科側で設定…という心外科手術の“あるある”も.
心電図同様に苦手意識が出がちで、麻酔科専門医試験では筆記・口頭ともによく問われます。ここで基本を固めましょう!
ペースメーカの他に ICD(植込み型除細動器),CRT-D(再同期+ICD) がありますが,まずは通常のペースメーカから.

♦️ 何のために入れる?
細かい適応は循環器の教科書に山ほどありますが、要は症候性の徐脈で心拍出が不十分なときに入れます。
代表例:
- 洞不全症候群(SSS)
- 高度房室ブロック(Mobitz II、完全房室ブロック)
- 徐脈性心房細動
- 心筋梗塞後の循環不全
- 心臓手術後の一時的支持(テンポラリー)
細目は教科書や各ガイドラインを参照.全部覚えるのは無理笑)
♦️ ペースメーカコード(NBGコード)
「VVI 40でバックアップね」と言えると“デキる”感が出ますが・・大丈夫,気のせいです👍笑。まずは1~3文字目がわかれば十分会話になります。
1=刺激部位,2=感知部位,3=感知への反応(4はレート応答,5は多点ペーシング).
🔷 1番目のコード(O/A/V/D)
コードの1番目の文字は刺激部位です.どこが刺激されているのかが重要なので1番目にきています.
- Oは刺激なし(ペースメーカの意味なし!),
- Aは心房(Atrium)のA
- Vは心室(Ventricle)のV
- Dは両方(dual)のDです.Doubleではありません.
🔷 2番目のコード(O/A/V/D)
2番目はどこで患者自身の興奮信号を感知しているかです.自分で頑張って興奮しようとしているのに勝手に機械に刺激されてはかないませんし,興奮信号がない場合にはしっかりと刺激してもらわなければいけません.
文字の意味は1番目の刺激部位と同様です。
🔷 3番目のコード(O/I/T/D)
3番目は2番目で感知の結果,ペースメーカ自身がどう反応するかです. 3つの文字が使用されます.
- Oは刺激しない,ではなく興奮のあるなしに関係なく刺激する,の意味です(非同期ペーシング) .場合によってはspike on Tなどからの心室性不整脈を起こすリスクがあります
- Iがinhibited(抑制):感知したら抑制(刺激しない)
- Tはtriggered(感知に同期して刺激する)
- Dは上記と同様dualです
言葉がわかりにくいですが,同期して刺激するとは,「心房の興奮はあるが,心室に伝達されない場合に,心房興奮に同期して心室の刺激を行うこと」です.心房興奮がなく,心房を刺激してその刺激が心室に伝達されなければ心房刺激に同期して心室を刺激します.
Dは両方です.実際に見るのはIかDがほとんどです.
どれくらいの強度で刺激するか,どの程度の興奮信号までは興奮なしとするか,ありと判断するかは、ペースメーカの設定(刺激強度と閾値の設定)で変更することができます.
🔷 ぷちまとめ
通常用いる場合にはこの3つを把握しておけばなんとかなります.
普段見るペースメーカのモードはVVI,DDDがほとんどです.たまーにVDD,DDIもいますが.AAIはほとんど見ないですね.
🔷 4番目のコード(O/R)
4番目は心拍数調節機能です.運動(体の動き)や体温,分時換気量を感知して体の需要に合わせて心拍数を増加させる機能のことです.文字コードはOがなし,R(Response)が心拍応答機能ありです.DDDRと書かれているのを見たこともあると思います.
自己心拍がしっかりと増える人はいいですが,完全ペースメーカ依存の患者だとこの機能がないと少し走っただけで倒れてしまうでしょうね.
🔷 5番目のコード(O/A/V/D)
5番目は複数部位(多点)ペーシング(両心房・両心室,同一心房あるいは同室心室内での複数の刺激部位,もしくはこれらの組み合わせ)で,Oはなし,A,V,Dは上記と同様です.心臓の再同期療法(CRT)などで用いられます.
♦️ 術前に何をチェックする✅?
🔷 まずはペースメーカー手帳📓!
- 適応疾患
- 設定モード
- 電池残量
- 最近のチェック日.
- 持参していなければかかりつけ医に連絡.
🔷 検査所見
- 胸部X線:デバイス位置,リード本数・走行.
- 心電図:スパイクの有無・形、依存度(自前で打ってるか).
🔷 メーカー担当や臨床工学技士に連絡
- 依存の有無判定・最新のデバイスチェック(目安:PMは過去12か月以内,ICD/CRT-Dは3〜6か月以内)
- 必要に応じた術前プログラミング計画(例:依存あり→非同期,ICDOFF)
- 術中立会い・術後再設定の段取り。
🔷 電気メスの使用計画とバックアップ
- モノポーラか、バイポーラ/超音波で代替できるかを外科と事前共有。
- いざという時のバックアップ:経皮/経静脈ペーシング機器の準備。
♦️ 術中・麻酔中の設定と注意点⚠️
🔷 術中の設定と麻酔
麻酔法は基本なんでもOK.ペースメーカが入っているからといって,特別な麻酔法を選ばなければならないということはありません.ただしモニタの“ペーシングスパイク除去”はOFFに(スパイク見えないと怖い.そんな機能があること自体知らない人もたまに見かけますが・・😅).有効拍出が出ているかをSpO₂/動脈圧/聴診などで常時確認します.
🔷 設定変更はなぜ必要?
主因は電磁干渉(EMI)回避するため.電気メス,RFA(ラジオ波焼灼),ESWL(超音波結石破砕術),MRI(条件適合なら可),放射線療法,MEPや神経刺激などが要注意.ここでは頻用する電気メスに絞ります.
- モノポーラ電気メス:棒状のアクティブ電極〜分散電極(対極板)で体を電流が横断します.
- バイポーラ電気メス:通電はピンセット先端間のみで完結.
ペースメーカ患者で問題となるのはこのモノポーラを使用する時です.術中に電気メスを使用する際に心電図が乱れるのを見たことがあると思いますが,その電気メスの電気刺激を心臓の興奮と間違えて感知してしまって(I:抑制),適切に刺激が行われない場合があります.
自己心拍がしっかりとある患者であれば大丈夫ですが,ペースメーカに依存しきっている患者の場合は高度の徐脈をきたしてしまう場合があります(ペースメーカからすれば,だって自分で打ってるじゃん.俺いらないでしょ.という感じです)
こういったことを防ぐために術前にプログラミングの変更が必要になります
余談ですが,躁うつ病は別名双極性障害と呼び(躁と鬱の二極),英語ではbipolar disorderと呼びます.精神科医の先生が言うバイポーラはそっちの方ですので,間違えないようにしましょう(間違えないか😅)
🔷 モノポーラ電気メスを使うなら(具体策)
- 可能ならバイポーラ/超音波を使用
- 短時間・間欠(例:1–2秒単位、十分な間隔)・最小出力
- 可能ならCUT優先(COAGで強いEMI→失神/無拍の症例報告あり)
- 対極板は術野に近く,ペースメーカー本体から離す(目安≥15 cm),電流経路が装置を横切らない位置
- 除細動器待機,除細動パッドは装置を避けて貼付
- 本体直上10–15 cmでの使用は避ける(故障リスク).
- 装置世代の進歩でEMI耐性は改善していますが,“近接・高出力・長通電”は今もリスクです.
🔷 術中の基本方針
細かなことは色々ありますが,基本的な変更は3種類です.
まずは心拍数調節機能やICD機能などは手術直前に切っておきます.心拍数調節機能は,人工呼吸の影響により予期せぬ頻拍が起こる可能性があるため,ICDは電気メスの刺激ノイズを細動波を勘違いして不必要な電気ショックをしてしまう可能性があるためです.
そして非同期ペーシング(AOO、VOO、DOO)にするか,最低心拍数を保障したモード(AAI、VVI、DDI)にするかです.
前者はペースメーカ依存患者にモノポーラー電気メスを使用する場合で,ペースメーカがきちんと動いてくれていないと,自分では十分な心拍数が維持できない人用です.
後者は自己心拍が比較的十分(50bpm以上)あり,ペースメーカはいざという時に動いてくれれば大丈夫な人用です.
非同期ペーシングとはその名の通り,自己の興奮があろうがなかろうが刺激するモードです.電気メスの刺激ノイズがあろうが感知しませんので,一定の心拍数を維持できるメリットがあります.一般的には手術の侵襲に応じて自己心拍よりも速いペーシングレートで設定します(通常80〜90程度か).
患者の自己心拍が十分にある場合には非同期ペーシングを行うことでspike on T(T派の上にペーシング刺激が乗る)からの心室性不整脈を起こすことがあります(実際に起こすことはまれのようですが).
このような自己心拍が十分な患者の場合は,もし自己心拍が何らかの理由でなくなった場合に最低限の心拍数が保障されるようにペースメーカを設定します.
AAIやVVI、DDIがそれにあたります.ただし,房室間の伝導障害がある場合や,心房細動の場合はAAIは刺激がうまく伝わらないためNGです.
ほとんどペースメーカに依存していない患者では特に何も設定変更しない場合もあります.
手術が無事終了したら、ペースメーカの動作チェックと、再プログラミングをきちんと行いましょう.
最近のCIEDはEMI耐性が向上していますが,「近接・高出力・長通電・不適切な電流経路」は依然としてトラブルの温床です.“術前計画+立会い+術後再設定”が三種の神器.
- レート応答やICD治療をOFF(人工呼吸などで予期せぬ頻拍/不適切ショックを避ける).
- 依存あり患者:非同期(AOO/VOO/DOO)で一定HR維持(多くは80〜90/min程度に設定)
- 依存なし(自己心拍が十分):VVI/AAI/DDIなど最小限保障で十分(房室伝導障害/心房細動ではAAIはNG)
- 術後は必ず再チェックして元設定へ.
医師たちがいかにもドヤ顔で言っていますが,それほど難しいことを言っているわけではないことがわかったと思います笑.ペースメーカアレルギーにならないようにしましょう!
♦️ ペースメーカー不全(ざっくり)
🔷 ペースメーカ不全(ざっくり整理)
最後にペースメーカ不全について簡単に.ペースメーカ不全とは文字通りペースメーカがきちんと作動してくれない状況を指します.できれば起こってほしくないですけどね.幸い私が担当した症例では起きたことはないです(心臓外科手術以外においては).
ペースメーカ不全の原因は,大まかに以下の2つに分けるとわかりやすいです.
- 出力(output)とそれに対する反応がおかしい
- センシング(感知)がおかしい
🔷 出力がおかしい
出力が正常になされない理由としては,ペースメーカ本体の近くでの電気メス刺激によりジェネレータ自体が故障した(まれ),バッテリーがない(術前のチェックで回避可能),リードが断線または位置のずれ,オーバーセンシングが起こった場合(後述),混線している(心房への出力を心室リードが誤ってセンスして抑制をかける)場合などです.
補足ですが,心臓外科手術中の術野に直接縫い付けたペーシングワイヤーの場合には,瘢痕組織などは強い出力が必要になったり,場所を変更する必要があります.
- ジェネレータ自体の故障(まれ)
- バッテリーの枯渇:術前のチェックで回避可能
- リードの断線または位置のずれ,
- オーバーセンシング
- 混線
🔷 センシング(感知)がおかしい
センシングの異常としてはアンダーセンシングとオーバーセンシングがあります.こう言った不適切なセンシングは,電気メスの干渉や抗不整脈薬の投与,心筋虚血,酸塩基平衡障害,電解質異常などにより,ペーシング閾値の変化が生じることで生じます.なにやら難しそうな用語ですが大したことはありません.
アンダーセンシングとは「空気が読めない人」,よく言えば「鈍感力」がある状態です.きちんと自分の心臓が興奮しようとしているのに気づかず(気づけば抑制をかけます)、不適切な時に刺激します.
オーバーセンシングとは「どうでもいいことまで気にしすぎる人(知覚過敏)」のことです.周りの関係ない刺激(電気メス、スキサメトニウム使用時の筋電図など)を心臓の興奮と勘違いして抑制をかけてしまいます.
私は以前はオーバーセンシングな人間でしたが,年齢を重ねるにつれアンダーセンシングな人間になりつつあります・・・😅.
- アンダーセンシング=空気読めない人:自前の興奮に気づかず不適切に打つ
- オーバーセンシング=何でも気にする人:関係ない電気ノイズ(電気メス,EMGなど)を興奮と誤認して抑制 (抗不整脈薬,心筋虚血,pH/電解質変動で閾値がズレても起きます).
🔷 ペースメーカ不全で徐脈になったら・・・
ではペーシング不全が生じて,高度の徐脈を生じた際にどのように対応すればいいのでしょうか.
- 非同期ペーシングを行なっていない場合で,マグネットモード(ペースメーカ本体の上にマグネットを置く)を用いると,非同期ペーシングになるので,オーバーセンシングの場合は改善します.でも勝手にしないほうがいい(メーカーによってマグネットモードの動作が違うことあり).
- または,一時ペーシング(経皮,経静脈)を行います.まぁこれですね.下記はすぐに効果が出るわけではないので.
- 心筋の脱分極閾値を低下させる,あるいは心拍数上昇の目的に交感神経作動薬を使用する(アドレナリン、ドパミン、イソプロテレノールなど)こともあります.反応すればいいけど.
- 血中のカリウム,カルシウム,マグネシウム濃度を是正する(血液ガス採取).アミオダロンは脱分極閾値を上げるため,使用している場合は減量あるいは中止する.
- 他に手段がない場合には,直接心外膜でペーシングすることを考慮します(最終手段).
- (計画なしの)マグネットは安易に使わない:機種依存.PMは一定レートで“マグネットモード”,ICDは抗頻拍のみ抑制でペーシングは通常通りが一般的.事前計画下で.
- 一時ペーシング(経皮/経静脈)を素早く準備.
- 交感神経作動薬(アドレナリン,ドパミン,イソプロテレノール等)で閾値低下/心拍上昇を図る.
- 電解質異常があれば是正,アミオダロンは閾値↑に注意.
- 最終手段:心外膜直刺激.
📝 まとめ
☝️基本事項
- CIED(Cardiac Implantable Electronic Device) =ペースメーカ・ICD・CRT-D の総称。
- 適応は「症候性徐脈で心拍出が不足する場合」が中心。代表例は SSS、高度房室ブロック、徐脈性心房細動など。
- NBGコードは 1=刺激部位、2=感知部位、3=感知後の反応(I:抑制、T:同期、O:反応なし)、4=レート応答、5=多点ペーシング。 → よく使うのは VVI、DDD。
☝️術前チェック
- 必ずペースメーカ手帳を確認(適応疾患、モード、電池残量、直近チェック日)。
- 胸部X線でリード数・位置を確認。
- 心電図で依存度やスパイクを確認。
- 臨床工学技士/メーカー担当に依頼:術前チェック・設定変更・術中立会い・術後再設定。
- 手術計画確認:電気メスの種類(モノポーラかどうか)、使用部位を主治医と共有。
- 一時ペーシングの準備(経皮・経静脈)。
☝️術中管理
- 麻酔法は原則自由。ただしモニタの「スパイク除去機能」はOFF。
- 有効拍出は SpO₂・Aライン・聴診で常時確認。
- ICDの除細動機能とRate responseはOFF。
- 依存あり → 非同期モード(AOO/VOO/DOO、通常80–90/min)。
- 依存なし → VVI/AAI/DDIなど最低限保障。
- ほとんど依存していなければ設定変更しない場合もある。
- 手術終了後は必ず元の設定に戻す。
☝️電気メス使用時の注意
- 第一選択はバイポーラ or 超音波メス。
- モノポーラを使うなら:
- 短時間・間欠・最小出力
- CUTモード優先(COAGはEMIが強い)
- 本体から15cm以上離して使用、電流経路がCIEDを横切らないよう対極板を貼付
- デフィブレータ常備、パッド装着位置もCIEDを避ける
- 本体直上での使用は禁止。
☝️ペースメーカ不全
- 出力異常:電池切れ、リード断線、ジェネレータ故障。
- センシング異常:
- アンダーセンシング=空気が読めない → 自己興奮に気づかず不適切刺激
- オーバーセンシング=過敏 → 電気メスなど関係ないノイズで抑制
- 対応:
- マグネットは機種依存(原則は計画下で使用)
- 一時ペーシング(経皮・経静脈)
- 交感神経作動薬投与(アドレナリン,ドパミン,イソプロテレノールなど)
- 電解質補正,アミオダロン使用中なら中止考慮
- 心外膜直接ペーシング
🔗 Rerated Article
📚 References & Links
- ASA Practice Advisory (2020) Perioperative Management of Patients with Cardiac Implantable Electronic Devices. Anesthesiology 2020;132:225–252. 👉 米国麻酔科学会による最新の実務指針. 術前評価~術後再設定までのフローチャートが載っており,麻酔科医が日常臨床で「何を確認・依頼すべきか」を整理している.
- HRS/ASA Expert Consensus (2011, reaffirmed later) Perioperative management of patients with implantable defibrillators, pacemakers and arrhythmia monitors. Heart Rhythm 2011. 👉 ペースメーカ/ICDの周術期管理に関する古典的かつ今も引用されるコンセンサス.EMI対策(モノポーラ vs バイポーラ)、マグネットの反応などの基本事項を整理.
- EHRA Consensus (2022) Prevention and management of interference due to medical procedures in patients with CIEDs. Europace 2022. 👉 欧州心臓リズム学会による最新レビュー.特に「どの医療機器がどの程度干渉リスクを持つか」を表形式で整理.MRI・放射線治療など新しい項目もカバー.
- AHA Scientific Statement (2024) Periprocedural Management and Multidisciplinary Care of Patients with CIEDs. Circulation 2024. 👉 多職種チームでの管理を強調した最新総説. 循環器医・麻酔科医・CE・外科医の役割分担を明確にしており,教育資料としても有用.
- 症例報告(COAGでEMI→無拍).Electromagnetic interference in a cardiac pacemaker during cauterization with the coagulating, not cutting mode. Basem Abdelmalak, Narasimhan Jagannathan, Journal of Anaesthesiology Clinical Pharmacology,2011年10月
👉 「凝固モードで強いEMI→重篤な徐脈」という具体的なトラブル例. CUTモード優先を推奨する根拠として臨床的にインパクト大.
📚 おまけ:おすすめ教科書
あらためてペースメーカーのおすすめ教科書は詳しく特集する予定ですが,以下のものがおすすめです👍
🔷 まずは基本的なところから
📚 ペースメーカー心電図が好きになる!(改訂第2版)
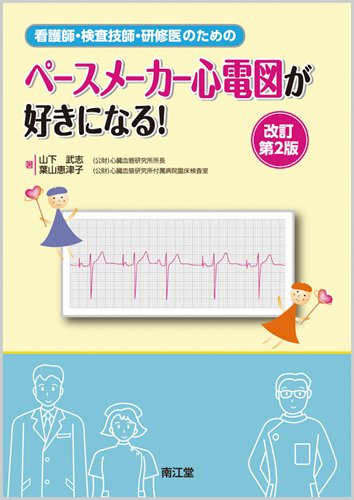
看護師・検査技師・研修医のためのペ-スメ-カ-心電図が好きになる!
好きになるかはおいといてまずはここから笑
📚 個人授業 心臓ペースメーカー 適応判断から手術・術後管理
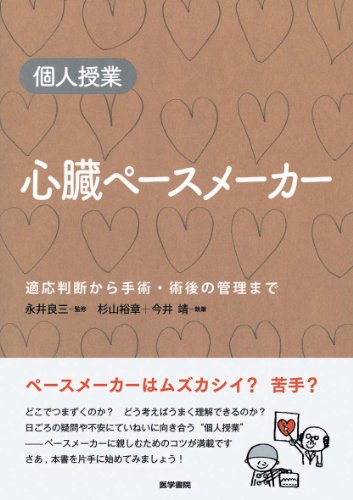
個人授業 心臓ペースメーカー―適応判断から手術・術後管理まで
わかりやすくかかれています.会話形式なのが好みの分かれるところ.
🔷 本格的に勉強したい人は・・・
📚 理解して使いこなす麻酔科機器:モニター・ICU機器・ペースメーカー
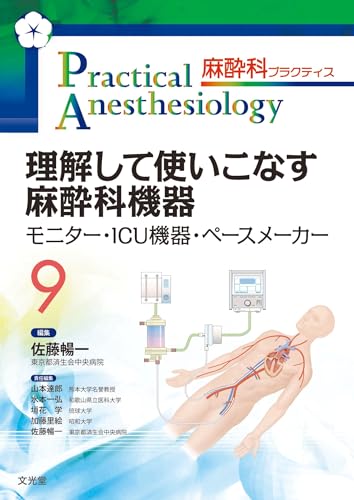
理解して使いこなす麻酔科機器 (麻酔科プラクティス 9): モニター・ICU機器・ペースメーカー
その名の通り麻酔科医向けのシリーズ本.ペースメーカだけでなく,麻酔関連でよく使う機器がだいたい載っている.わかりやすくまとまっています.
📚 ペースメーカー・ICD・CRT実践ハンドブック
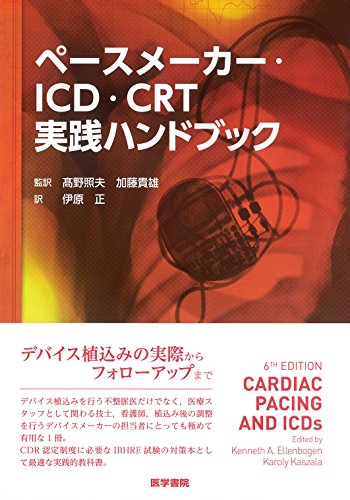
ペースメーカー・ICD・CRT実践ハンドブック
はい,万人にお勧めするものではないです😅笑.循環器専門医など向け.この分野ではバイブルになりうる本.もとは洋書.
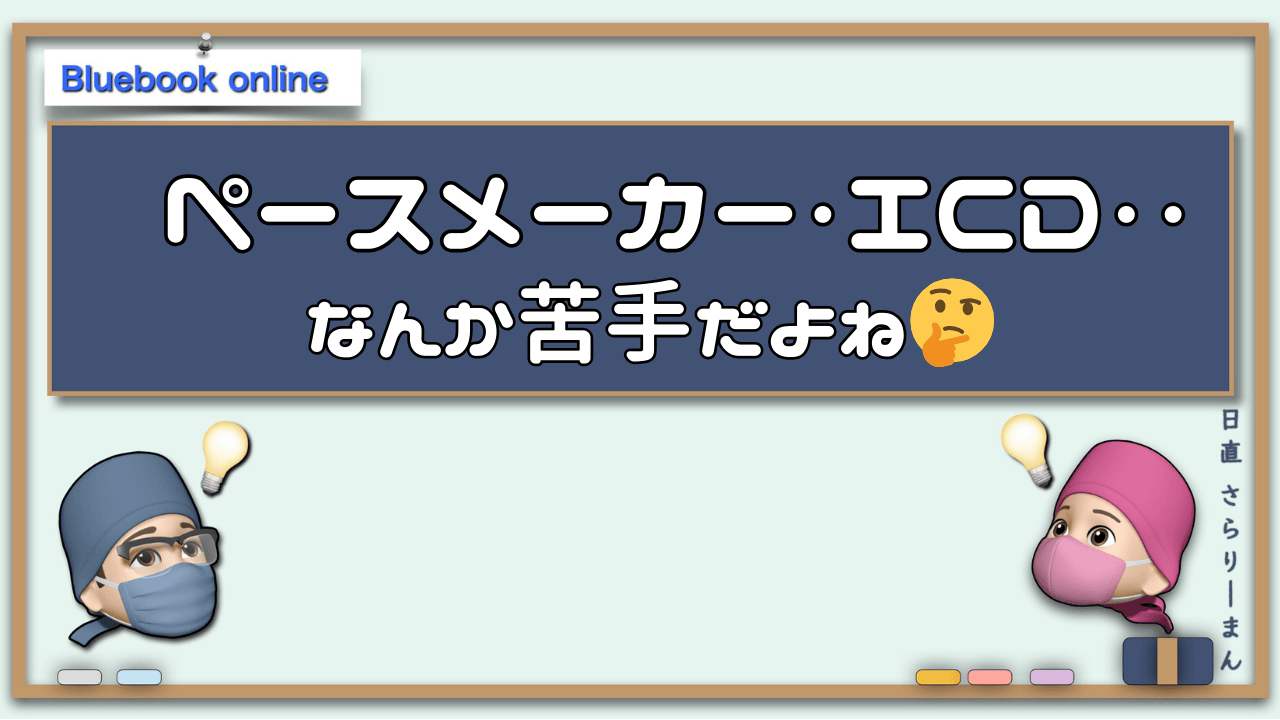
コメントを投稿するにはログインしてください。