👉👉 🇺🇸 All Posts 🇬🇧 / 🇯🇵 記事一覧 🇯🇵 👈👈
♦️ はじめに
循環モニタリングと聞いてはじめに思い浮かぶのはおそらく以下の2つではないでしょうか?
- 血圧(非侵襲的・観血的)
- 心電図
☝️ 最近はどこでも血圧測定器が置いてますね.

☝️ 一般的な13cmのマンシェット(著者撮影)
糖尿病と並んで万病の元の一つである高血圧.血圧測定は血糖測定よりも非侵襲的で簡便であるため,今や家庭・外来・病棟・手術室・果ては色んなお店の休憩スペースなど,どこでも血圧測定器を見かけますよね!
ここでは血圧測定の基本,非侵襲的血圧測定(non-invasive blood pressure:NIBP)について,簡単に説明していきます。
観血的動脈圧測定(俗に言うAライン)は別の記事で取り上げたいと思います.試験においては主に「測定に影響を与える要因について」が重要です.
♦️ 血圧測定今昔
昔(今の50〜60歳くらいの先生が若手麻酔科医だった頃かな)は自動血圧計なんてものはほとんどなく,麻酔科医はマンシェットの間に聴診器を挟み込んで,数分おきにシュコシュコと手動で血圧を測っていたのです・・!今では想像もできないかもしれませんが・・😱
もちろん今みたいなデジタルの自動麻酔記録装置なんてない時代ですから(自動で鉛筆が動くアナログな自動記録装置はありましたが・・・見たことあります・・?笑),記録も手動です.昔の麻酔科医の先生は今とは違う大変さがあったのです!(私はそのような話を聞きながら育った世代です🤗。初期のころは私も手書きでしたが・・✏️).
エピソードとして語るのはいいのですが,それをことさら強調するようになると「老害、懐古厨」などと陰で揶揄されるのでほどほどにしましょう😅(私も気がつくと昔の話をしてしまいがちで気をつけています).
♦️ 測定方法
🔷 聴診法(コロトコフ法)
閑話休題.上記の麻酔科医や看護師さんがシュコシュコと聴診器を使いながらする測定方法は「聴診法(コロトコフ法)」と呼ばれる一般的な方法です.
これはカフを膨らませてその圧で血流を止めたあと空気を少しずつ抜き,血流が流れ出した時の音(これがコロトコフ音)と音が消失した時の圧を水銀柱(古い?)や,メーターを見ながら測定する方法です。
ただし,慣れてない人と熟練した人では測定値に誤差が出やすいです.特にカフの脱気が早すぎると収縮期血圧は低めに測定されてしまいます(タイミングを逸してしまうため).また雑音環境も誤差の要因になります.
現在では水銀を使用しない装置(アネロイド型や電子型)が主流です。(水銀式は2021年より製造・輸出入が禁止).
🔷 オシロメトリ法
オシロメトリ法は主に自動血圧計で用いられます.カフを膨らませ血流を止め,徐々に圧迫を解除していくところまでは聴診法の手順と同じです.
オシロメトリ法では動脈の拍動に伴って発生する血管壁の振動の変化(圧脈波)をセンサで捉えることで血圧を測定します(へぇ🤔)
- 振幅が急激に大きくなる部分 → 収縮期血圧(推定値)
- 振幅が最大になる部分 → 平均血圧(比較的正確)
- 振幅が急激に小さくなった部分 → 拡張期血圧(推定値)
つまり平均血圧ははっきりしていますが,最高と最低は機種ごとに異なるアルゴリズムで推定されます.昔はセンサの性能が不十分で誤差が大きかったようですが,最近では聴診法との差はほとんどないようです.
♦️ 正しいマンシェット幅の選択や巻き方
マンシェットの幅は,巻く部位の直径の1.2〜1.5倍程度が適正(サイズに関しては教科書や資料によっても微妙に違います).別の表現としては,腕の周囲長の40%.
巻く強さは,指が1〜2本くらい入るくらい(曖昧ですがね).
☝️ この数字は覚えておいてください!そしてそれらが適切でないと以下のことが生じます⤵️
🔷 適切なマンシェットの幅
- 幅が狭すぎる → 血圧が高く測定される
- 幅が広すぎる → 血圧が低く測定される
成人で通常の体格なら13cm幅が標準的に選択されます.小児や小柄な人では10cm,7cm,5cmと小さくなっていきます.狭いと測定血圧が高くなるのは,短い距離で動脈を圧迫して血流遮断しなければならず,遮断に必要な圧が本来必要な圧以上になるためです.
🔷 腕に巻くときの強さ
そして,巻く強さも重要です.
- 巻く強さがゆるい → 血圧が高く測定される
- 巻く強さがきつい → 血圧が低く測定される
ゆるいと中の膨らむゴムの袋が測定部位との隙間に余裕がある分外に膨らんでしまい,動脈を圧迫する部位での力が弱くなります.そのため余分にカフを膨らませなければならず,見かけ上測定値が高くなってしまいます.
でも,肥満患者で上腕の形がワイングラスみたいな形状になっている人とか,はっきり言って困る😅!
🔷 測定時の腕の高さも重要!
腕の高さ(心臓との位置換気)によっても血圧が変動します.目安として,高さが10cm変わると血圧は約7.4 mmHg変動します.
- 腕の位置: 血圧測定を行う腕(上腕動脈)の高さは,心臓(右心房)と同じ高さにするのが原則です.
- 腕が心臓より低い位置にあると,静水圧の影響で測定値は本来より高くなります.
- 腕が心臓より高い位置にあると,測定値は本来より低くなります.
🔷 その他の注意点
また,その他の注意点として,以下のものは覚えておきましょう.
- 収縮期血圧と拡張期血圧の差を「脈圧」と呼びます.
- 測定間隔は少なくとも5分おき(ASAの麻酔モニタリング基準にも記載).逆に,頻回すぎる測定は末梢神経障害の原因になりうる.
- 透析患者のシャント側での測定はNGです.潰してしまう可能性があります.リンパ浮腫のある側や,点滴ライン側も避けます(仕方ない場合もあり).
📝 まとめ
- NIBPには「聴診法(コロトコフ法)」と「オシロメトリ法」がある
- オシロメトリ法:平均血圧は比較的正確だが,収縮期・拡張期は推定
- マンシェット幅は腕周囲長の40%前後。狭いと高値,広いと低値
- 巻き方:ゆるいと高値,きついと低値
- 測定間隔は最低5分ごと(ASA基準)
- 禁忌部位:透析シャント側,リンパ浮腫側
🔗 Related articles
📚 References & Links
- 日本麻酔科学会 安全な麻酔のためのモニター指針(2019年改訂版)
- 日本の麻酔科医にとってはおなじみのゴールデンスタンダード.
- 過去の試験でも問われたことがあります.
- Miller’s Anesthesia, 9th Edition, Chapter on Monitoring
- 世界的スタンダードの教科書.
- 聴診法とオシロメトリ法の原理・測定精度の比較が詳しく記載.
- 動脈ラインとの比較に関しても解説あり.
- でも読むのは大変😅
- Pickering TG, et al. Recommendations for Blood Pressure Measurement in Humans and Experimental Animals. Hypertension. 2005;45:142–161
- 高血圧学会と心臓病学会が共同でまとめた血圧測定の精度に関する古典的ガイドライン.
- オシロメトリ法の原理や限界が詳細に述べられています.
📚 おすすめ教科書
🔷 全看護師・研修医必読!
鉄板の讃岐先生の本です😊 お値段もやさしめなのでぜひ👍
手術室のモニタリング“あるあるトラブル”解決塾
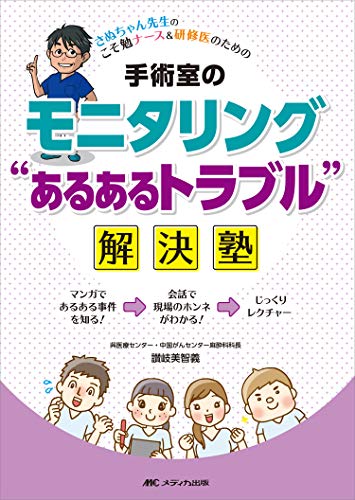
手術室のモニタリング“あるあるトラブル”解決塾: さぬちゃん先生の こそ勉ナース&研修医のための
Dr.讃岐のサラサラ明解! 手術室モニタリングの極意: 異変・急変を見逃さない!
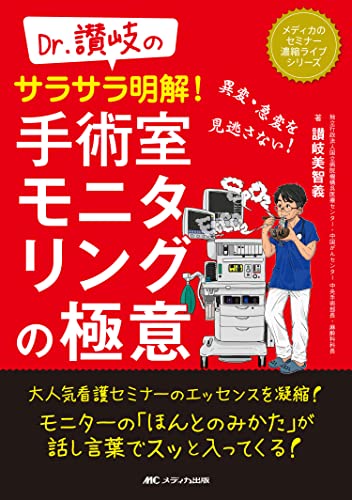
Dr.讃岐のサラサラ明解! 手術室モニタリングの極意: 異変・急変を見逃さない! (メディカのセミナー濃縮ライブシリーズ)
🔷 麻酔科専門医研修にはこれ
神経・呼吸・循環・筋弛緩・体温のモニタリングについてきれいにまとめられています。カラーで見やすく、内容もわかりやすく書かれているため、かなりおススメではあるのですが・・・ちょっと高い!
麻酔科医のための周術期のモニタリング
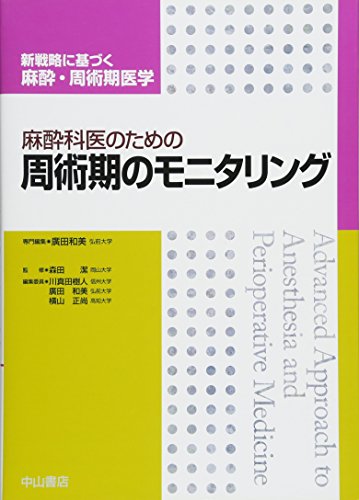
麻酔科医のための周術期のモニタリング (新戦略に基づく麻酔・周術期医学)
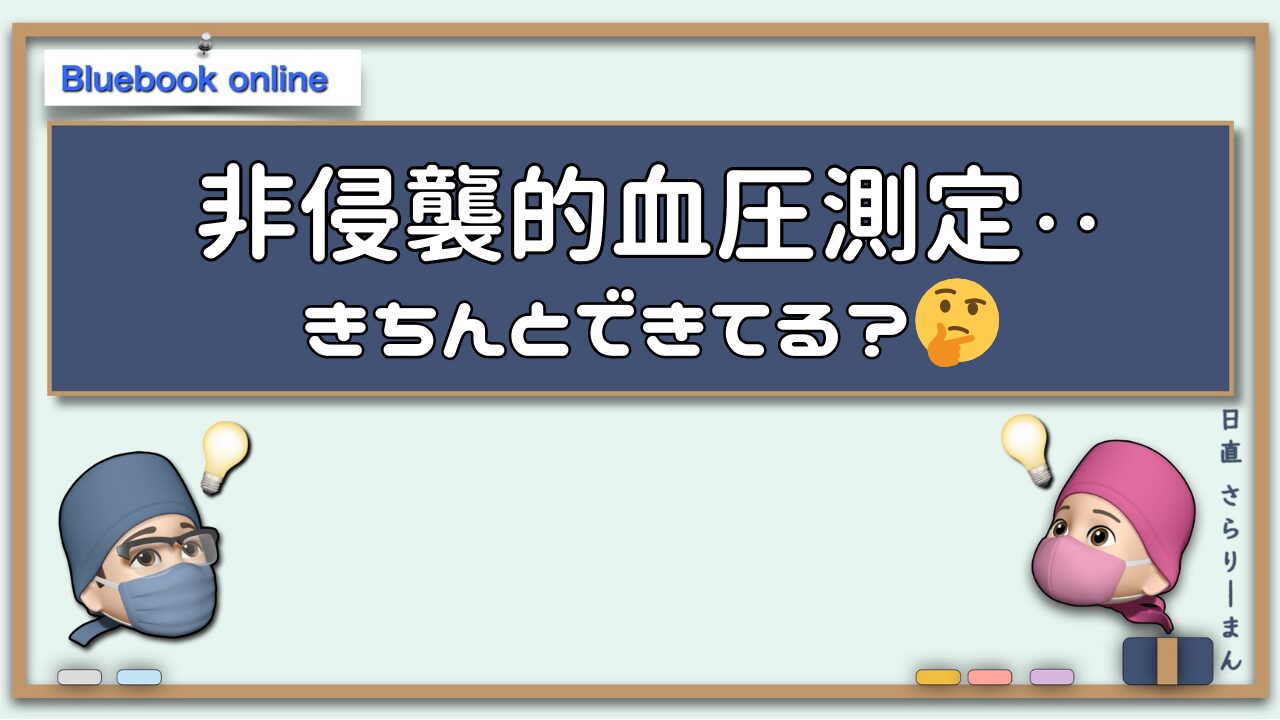
コメントを投稿するにはログインしてください。