👉👉 🇺🇸 All Posts 🇬🇧 / 🇯🇵 記事一覧 🇯🇵 👈👈
♦️ はじめに
 まっすー
まっすー先生,入院患者さんでで“点滴がすぐ抜ける”と訴えがあって,穿刺がつらいみたいです.PICCを入れるほどではないけど,何かいい選択肢はありますか?



最近はMidlineカテーテルとかあるね.通常の末梢静脈ルートより確実でPICCより侵襲が少ない“中間”的ルートとして適してるよ.短〜中期の静脈確保に実用的だね.



そうなんですね,とりあえず夜中に入れることにします.



Midnightカテーテルとか言うなよ?💢
ミッドラインカテーテル(midline catheter)は,1950年代に登場した比較的古い血管アクセスデバイスで,末梢静脈から挿入し,先端が中心静脈(SVC)まで達さない“長めの末梢カテーテル”です.当初は医師のみが挿入を行っていましたが,その後しばらく臨床現場から姿を消していました.
しかし近年,超音波ガイド技術の普及やPICC・中心静脈カテーテルに比べた合併症リスクの低さが再評価され,2010年代後半から2020年代にかけて再び注目を集めるようになりました.
現在では、5〜14日程度の中期静脈路確保や,難血管アクセス患者への対応など,従来の末梢静脈路とPICCの“中間的”な位置づけとして広く活用され始めています.
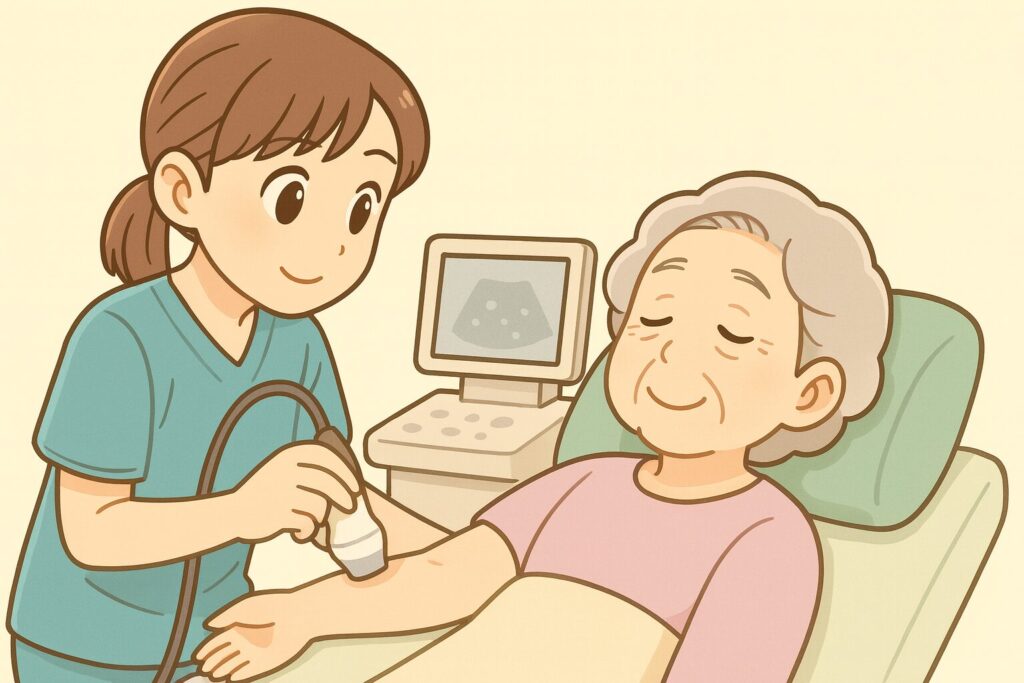
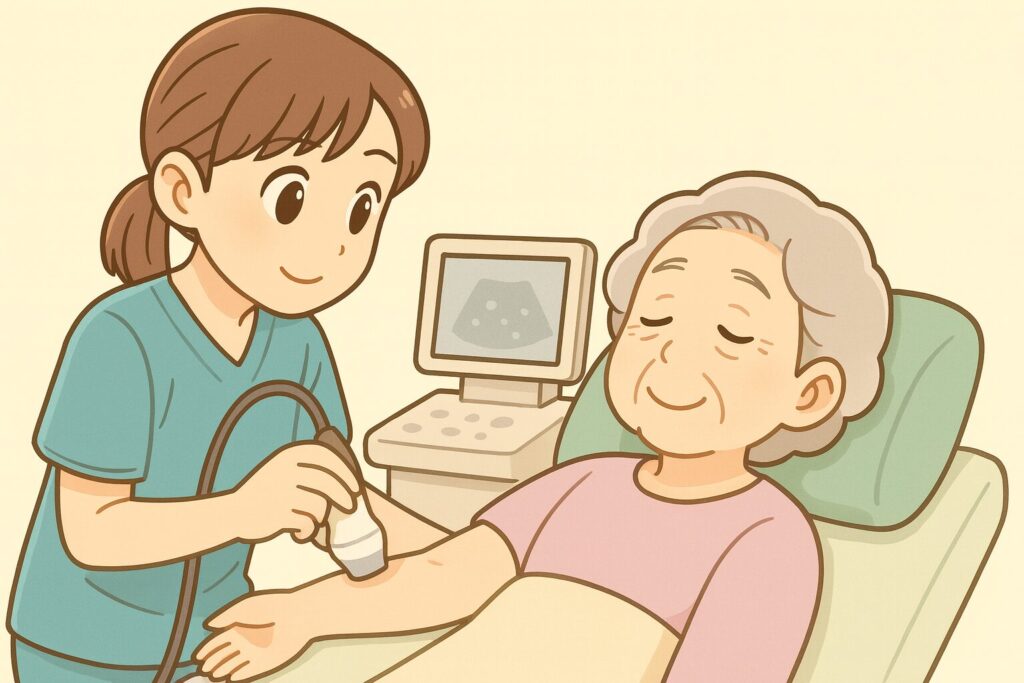
♦️ Midlineカテーテルの概要
🔷 定義😤
Midlineカテーテルは,上腕(通常はbasilic/cephalic/brachial系)などから挿入し,先端を腋窩~上腕近位の静脈に留置するタイプの末梢カテーテルです.
ポイントは先端が胸腔内の中心静脈(SVC)に到達しないこと.一般にカテーテル長は製品により差がありますが,臨床では数センチ〜20cm程度のものが使われ,留置目安は短期〜中期(施設やガイドラインでは概ね5~14日を参照することが多い)とされています.この点はINS(Infusion Nurses Society)の基準や各種ガイドレビューで示されています.
🔷 適応と禁忌
現時点での臨床的な使い分けは以下の観点で決められます.
- 投与する薬剤が末梢静脈で安全に投与できるか(pH・浸透圧・刺激性=vesicant の有無を確認する)
- 予定される治療期間(短期/中期/長期).
- 患者の血栓リスク/静脈の状態.
具体的には,末梢静脈で安全に投与できる薬剤(例:一般的な多くの抗菌薬)を数日〜2週間程度持続投与する場合に Midline は適しています.
一方で 強刺激薬(vesicant)や高浸透圧輸液,長期の中心静脈栄養(TPN) は原則として中心ライン(PICC・中心静脈カテーテル)での投与が推奨されます. また,既往に深部静脈血栓や高度な血栓傾向がある患者や透析予定の患者では慎重に判断する必要があります.
🔷 挿入手技とその管理:現場でのポイント☝️
挿入は無菌下・超音波ガイド下が推奨されます.典型的な手順は以下の通り⤵️
- 抗凝固状態の確認
- 超音波で静脈評価
- 無菌操作で穿刺 👉 ガイドワイヤー挿入 👉 カテーテル留置
- 先端位置の確認(X線/透視/超音波)
- ドレッシング固定・フラッシュ・記録.
慣れるまでは特に「静脈評価」「固定の仕方」「フラッシュの頻度」を丁寧に守ることで早期トラブル(閉塞・抜去・漏出)を減らせます.施設ごとのプロトコル(フラッシュ量・ヘパリンロックの有無等)を確認しておきましょう.
🔷 Midlineカテーテル挿入の利点👍
多数の観察研究と系統的レビューからは,次のような利点が報告されています.
- 通常の静脈穿刺に比べて穿刺回数が減り,安定した点滴ルートを確保できる.そのため患者満足度も向上する👍
- PICCと比較する観察研究/メタ解析において,midlineはCRBSI(カテーテル関連血流感染)発生が低下する傾向が示されています(ただし,血栓,特に表在静脈血栓の発生がやや多いという報告もあります).
🔷 Midlineカテーテル挿入の欠点😫
Midlineの主要な合併症は感染・血栓・閉塞・浸出です.最近のシステマティックレビューや大規模試験では,「midlineはCRBSIが低い傾向だが,総合的な合併症率や血栓については研究により差があり,一概に安全性で上回るとは言い切れない」という結論が多く示されています.
そのため,合併症の予防には挿入時の無菌操作,ドレッシング管理,規定のフラッシュプロトコル,日々のサイトチェックが重要です
またmidlineは中心静脈到達がないため,TPNや強刺激薬は原則禁忌である点に留意が必要です(残念😞).
🔷 合併症が疑われた場合の対処 ⛑️
発赤・熱感・発熱など感染を示唆する所見ばある場合
- まずドレッシングと固定部位を確認し、すぐにラインの使用を中止します.
- 周辺とラインからの血液培養を採取し,臨床的に感染の重症化が疑われる場合や,改善が認められない場合は速やかにカテーテル抜去を検討します.
ライン閉塞が疑われる場合
- まず規定のフラッシュ(生理食塩水による注入)で再開通を試みます.
- フラッシュで改善しない場合はカテーテルの屈曲や固定不良,位置異常など,機械的問題を確認し,必要に応じて再留置を検討します(フラッシュ・機械的評価は INS の手技基準に準拠).
腫脹や局所の疼痛があり血栓が疑われる場合
- すぐに使用を停止し,超音波エコー等で評価します.
- 深部静脈血栓や,その既往がある患者など,臨床的リスクが高いと判断される場合は,抗凝固療法の開始を血管外科や循環器等と協議して判断します.
- 血栓関連のリスクや頻度については文献に差があるため,各施設のガイドラインと照らして行動することが重要です.
♦️ PIV(末梢静脈ライン),Midline,PICCの使い分け
実臨床では,以下の3点(薬剤の刺激性/治療予定期間/血栓リスク・静脈状態)を評価して選択します.
- 短期(数日)で末梢投与可の薬剤 → PIV が第一選択.ただし,確保困難な場合は無理をしない.
- 数日〜2週間で末梢投与可の薬剤 → Midline が実用的(搬送・転科後も扱いやすい).
- 14日以上,あるいは TPN・刺激性のある薬剤投与が予定されている → PICC や中心静脈ラインを選択.
♦️ エビデンスの現状について
最近は観察研究に加えて RCT も増えており,系統的レビューも多数出ていますが,研究デザイン・アウトカム定義の違いにより結論は一様ではないようです🤔.
多くのガイドラインは Midline の有用性を認めながらも,推奨の「強さ」や「エビデンスの確実さ」は低〜中程度と評価することが多く,最終的には各患者の背景と施設の運用体制を踏まえて個別判断することが推奨されています🤔
📝 まとめ:Take Home Points
- Midline は PIV と PICC の中間に位置する,短期〜中期の実用的な選択肢.
- 投与する薬物が末梢静脈で安全に投与できるか(pH/浸透圧/vesicant の確認)と,予定留置期間,患者の血栓リスクを総合して選択しましょう.
- エビデンス的には,CRBSI は低い傾向がある一方,血栓や早期抜去など研究間で差があるため,最新のレビューと自施設データを参考に運用ルールを作る必要があります(今後どんどん増えてくればまた変わっていくでしょう😊).
📚 References & Further reading
- [1] Gorski LA, Hadaway L, Hagle ME, et al. Infusion Therapy Standards of Practice (8th ed.). Infusion Nurses Society; 2021. (INS standards — midline の適応・禁忌・手技に関する標準記載.
- [2] Urtecho M, Torres Roldan V, Nayfeh T, et al. Comparing complication rates of midline catheter vs peripherally inserted central catheter: a systematic review and meta-analysis. Open Forum Infect Dis. 2023;10(2):ofad024. (Midline は CRBSI が少ない傾向だが superficial thrombosis 増加などの報告あり).
- [3] Thomsen SL, Boa R, Vinter-Jensen L, Rasmussen BS, et al. Safety and efficacy of midline vs peripherally inserted central catheters among adults receiving IV therapy: a randomized clinical trial. JAMA Netw Open.2024;7(2):e2355716.(RCT:midline と PICC の安全性/有効性比較)
- [4] Lai J-Y, et al. Comparison of complication rates between midline catheters and peripherally inserted central catheters: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. J Hosp Infect. 2024;151:131–139. (RCT群のメタ解析:総合合併症率や早期抜去などの解析を含む)
- [5] Canadian Agency / Rapid Review. Midline Catheters for Administering Intravenous Infusion Therapy (Rapid Review / Health Technology Assessment). 2025. NCBI Bookshelf NBK613813. (臨床効果・安全性の総括と推奨のまとめ:ベシカント/TPNなどの禁忌についても言及).
- [6] Fabiani A, et al. The longer the catheter, the lower the risk of complications: Results of the HERITAGE study comparing long peripheral and midline catheters. Am J Infect Control. 2024 Nov;52(11):1289–1295. (長めカテーテルと合併症率の関係を観察的に評価).
- [7] Bentridi A, Giroux M-F, Soulez G, et al. Midline Venous Catheter vs Peripherally Inserted Central Catheter for Intravenous Therapy: A Randomized Clinical Trial. JAMA Netw Open. 2025;8(3):e251258. (大規模ランダム化試験:MVC は PICC の非劣性を示せず、VC関連有害事象が多かった等の所見)
- [8] Souri Y, Cancino C, et al. Clinical evaluation of the PowerGlide Pro midline catheter — dwell time, complications and outcomes for various medications. [Journal / PMC] 2024. PMC11602871. (製品ベースの観察研究;在置日数と合併症のデータ)
♦️ エビデンスレベルに関する補足
🔷 INS(Infusion Nurses Society)Standards of Practice に関する補足
- INS では推奨ごとに Level I–V のエビデンス分類が用いられます(Level I=メタ解析/系統的レビュー、Level II=RCT、Level III=準実験、Level IV=観察研究、Level V=症例報告・専門家意見).
- Midline に関する多くの推奨(適応・禁忌・手技)は Level II–IV(RCT・コホート・SR)に,一部は専門家合意(Level V)に基づきます.
- 「5–14 日間の留置を想定」→ Level IV.
- 「強刺激薬・高浸透圧・TPN は禁忌」→ Level III–IV.
- 「血栓既往や静脈温存症例は慎重適応」→ Level V.
🔷 欧米主要ガイドライン・レビューの要点
- Canadian Agency Rapid Review(2025)は複数のガイドラインを整理し,Midline の有用性を概説しつつ,エビデンスの質は限定的であるとまとめています.
- Review(2025)や WHO(2024)は全体として「エビデンスの確実性は低〜中等度」としています.今のところ,臨床適用の最終判断は個々の患者背景と施設運用を前提に行う必要があるようですね🤔
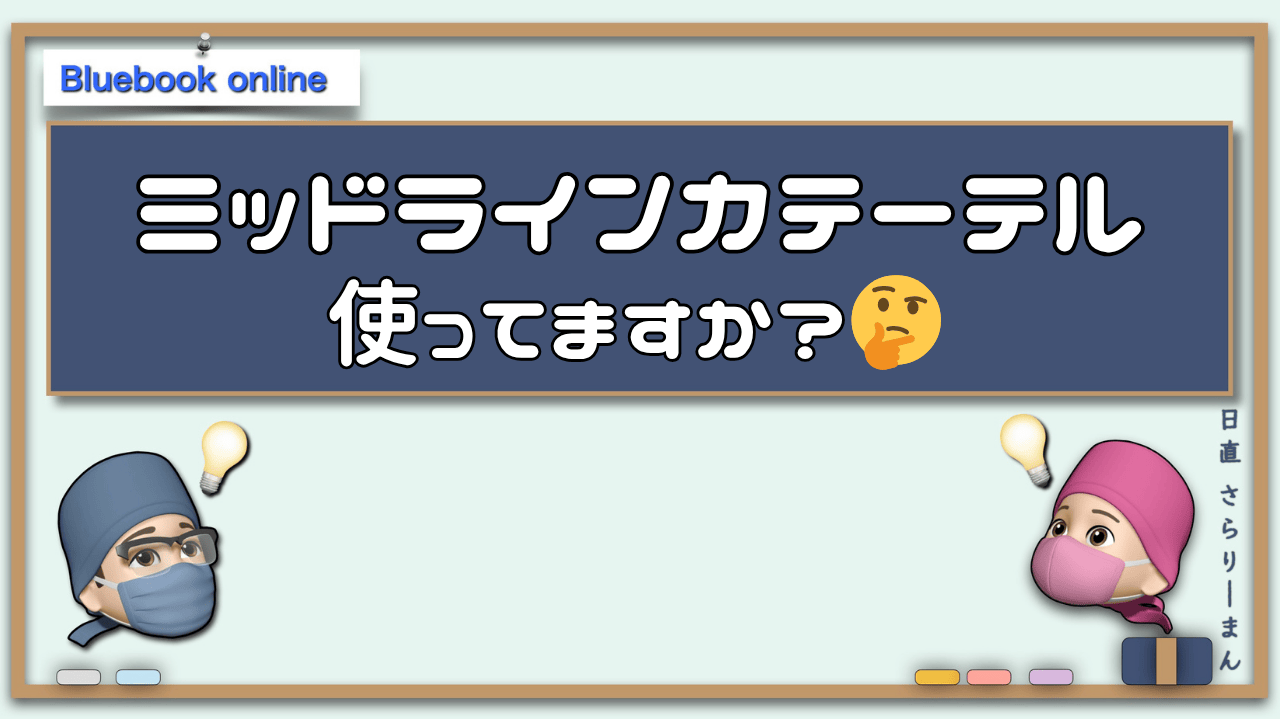
コメントを投稿するにはログインしてください。