👉👉 🇺🇸 All Posts 🇬🇧 / 🇯🇵 記事一覧 🇯🇵 👈👈
♦️ はじめに
 まっすー
まっすー以前,腕神経ブロックをした患者さんが“舌がしびれる”って言ったことがあって,結局それだけですんだんですけど,これって大丈夫なんでしょうか?



やば.局所麻酔薬中毒(LAST)の初期症状だったかもしれないよ.投与してからどれくらいだった?



数分以内でした



投与量によっては,LASTは秒単位で出ることもあるから,まずは投与を止めて,すぐに患者さんの意識や呼吸,血圧の測定など対処しないとね.
局所麻酔薬中毒(Local Anesthetic Systemic Toxicity:LAST)は,実際にはまれではありますが,発症すれば命に関わる重篤な合併症です.
ほとんどの場合,投与後数秒から数分以内に中枢神経症状(不安感,耳鳴り,口唇のしびれ,金属味,痙攣など)が現れ,続いて心血管症状(徐脈,低血圧,不整脈,心停止など)が進行していきます.
報告によって異なりますが,末梢神経ブロックなどでの発生頻度はおおむね0.03%前後といわれています(StatPearls 2022,Cleveland Clinic 2025).
発症はまれでも,症状の進行は非常に速いため,「疑う」「止める」「対応する」をいかに早く行えるかが生死を分けます.
この記事では,局所麻酔薬中毒の臨床像,リスク因子,そして初期対応の考え方を,試験対策にも役立つように整理していきます😊


♦️ 発症のタイミングと特徴
LASTの多くは注入後数秒〜数分で発症します.半数の患者さんが50秒以内,4分の3が5分以内に症状を示すという報告があります.
ただし,持続カテーテルや血流の豊富な部位への投与では,数時間後に遅れて発症することもあります(ScienceDirect 2025).
そのため,ブロック直後に異常がなくても安心せず,リスクの高い患者さんでは少なくとも30〜45分程度の観察を行うことが推奨されています.
☝️ ある報告では,上腕ブロック直後にわずか50秒で全身けいれん→心停止となった例がありました(StatPearls 2022).一方,持続カテーテルからの吸収によって数時間後に遅れて発症したケースもあります(ScienceDirect 2025).つまり,「直後にも,数時間後にも起こりうる」ことを常に念頭に置き,観察と記録を怠らないことが重要です.
🔷 中枢神経系の症状:CNS
局所麻酔薬中毒の初期症状の多くは,中枢神経系の興奮として現れます.
患者さんが「耳鳴りがする」「気分が悪い」「金属の味がする」「口がしびれる」などと訴えた場合,それは警告サインです.
そのまま放置すると,全身性の筋けいれんや意識消失,さらには呼吸停止へと進行することがあります.
興奮期のあとに意識が沈静化していく「抑制期」に移ると,呼吸抑制・昏睡・無呼吸を呈することもあります.特に鎮静薬を併用している場合は,これらの初期サインがマスクされるため要注意です.
🔷 心血管系の症状:CV
CNS症状に続いて現れることが多いのが心血管系の異常です(一気に濃度上昇した場合は同時に生じることもある).
初期には一時的に血圧や心拍数が上がることもありますが,すぐに徐脈や血圧低下,心室性不整脈へと進みます.
とくにブピバカインのような心毒性の強い薬剤では,CNS症状が目立たずに突然の心停止を起こすケースも報告されています.
🔷 診断の考え方☝️
LASTの診断は臨床的判断が基本です.
特定の検査で確定できるものではなく,「局所麻酔薬の投与後に特徴的な症状が現れたかどうか」を重視します.
鎮静,低酸素,低血糖,脳梗塞などの鑑別は必要ですが,疑った時点で治療を優先すべきです.
特にブロック中や直後に「口のしびれ」「耳鳴り」「痙攣」が出た場合は,まずLASTを疑うことが鉄則です.
♦️ LASTのリスク因子
LASTのリスクが高まる患者要因としては以下が知られています.
- 年齢が6歳未満または60歳以上
- 少ない筋肉量
- 心疾患や肝障害患者,
- 糖尿病などの代謝異常がある患
👉 薬剤の代謝・分布が変化して中毒が起こりやすくなります
また,肋間や頸部など血流の豊富な部位への注入や,高濃度・大量投与も危険因子です.
さらに,連続注入(カテーテル管理)では,遅発型の中毒が数時間〜1日後に起こることもあります.
♦️ 予防のためにできること☝️
最も重要なのは「予防」です.
超音波ガイドを使って針先位置を確認し,少量ずつ分割注入(incremental injection)することが有効とされています.吸引して血液が戻らないことを確認することも忘れずに行いましょう.
また,高濃度の局所麻酔薬を使うときは,リスクに応じて用量を減らすことも大切です.
各施設では,LAST発症時にすぐに行動できるよう,脂肪乳剤や救命薬を備えた“LASTキット”**を整備したり,対応手順を書いたものをすぐに見える場所に貼ったりするなど,スタッフ全員がその使い方を共有しておくと安心です.
- 針の先端を超音波で確認しながら手技を行う.
- 局所麻酔薬は少量,分割投与を行う.
- 血液の逆流を確認する(強く引くと血管内でも引けないことはある)
- 高濃度の局所麻酔薬は,量を調整する(極量も意識).
- 発症時に備えて教育も.
♦️ 初期対応(Immediate management)
実際に症状が出たら,迷わず次の手順をとります.以下はASRAチェックリスト(2020)などの国際的推奨をもとにした一般的な流れです.
治療の詳細やエビデンスについては,次回の記事で特集します.
- 投与を直ちに中止し,周囲に助けを求めます(Call for help).
- 酸素投与を行い,必要ならバッグマスク換気や挿管を行って気道を確保します.
- 痙攣がある場合はベンゾジアゼピン系薬(例:ミダゾラム)を優先して静注します.バルビツール酸系やプロポフォールを多用すると,心抑制が悪化するおそれがあります.
- 循環のサポートを行います.徐脈・低血圧・不整脈があれば標準的な救命処置(ACLSに準ずる)を実施します.
- 脂肪乳剤療法(Lipid Emulsion Therapy)を準備します.重症例(難治性痙攣や循環虚脱など)では早期に投与を検討しますが,具体的な投与量や速度は各施設のプロトコルに従うようにしてください.
- 注入量・症状・対応内容を記録し,専門チーム(中毒センターやICU)に早期連絡します.
📝 Summary:Take Home Points
- 局所麻酔薬中毒(LAST)はまれですが,秒〜分単位で進行する危険な合併症です.
- 多くは中枢神経症状(口唇のしびれ,耳鳴り,金属味,痙攣)が先行しますが,大量急速投与や,ブピバカインでは心血管症状が先行することもあります.
- 初期対応は気道確保・酸素投与・痙攣の制御・循環管理が基本です.
- 脂肪乳剤療法は重症例で救命的効果を示すことがありますが,施設のプロトコルに従ってください.
- 超音波ガイドや漸進注入,観察時間の延長など,予防こそが最大の対策です.
📚 References & Further reading
- Mahajan C, et al. Local Anesthetic Toxicity. StatPearls, 2022. NCBI Bookshelf
- Cleveland Clinic. Local Anesthetic Systemic Toxicity (LAST): Symptoms & Treatment. 2025.
- NYSORA. Local Anesthetic Systemic Toxicity. 2024.
- EMCRIT / IBCC. Local Anesthetic Systemic Toxicity (LAST). 2025.
- Utah Poison Control. Management & More. 2022.
- Japanese Society of Anesthesiologists. 局所麻酔プラクティカルガイド, 2017.
- APSF. 局所麻酔薬中毒(LAST)再訪:発展のパラダイム. 2021.
- Shalaby M, et al. Delayed Local Anesthetic Systemic Toxicity. ScienceDirect, 2025.
🔗 Related articles
- 追加予定
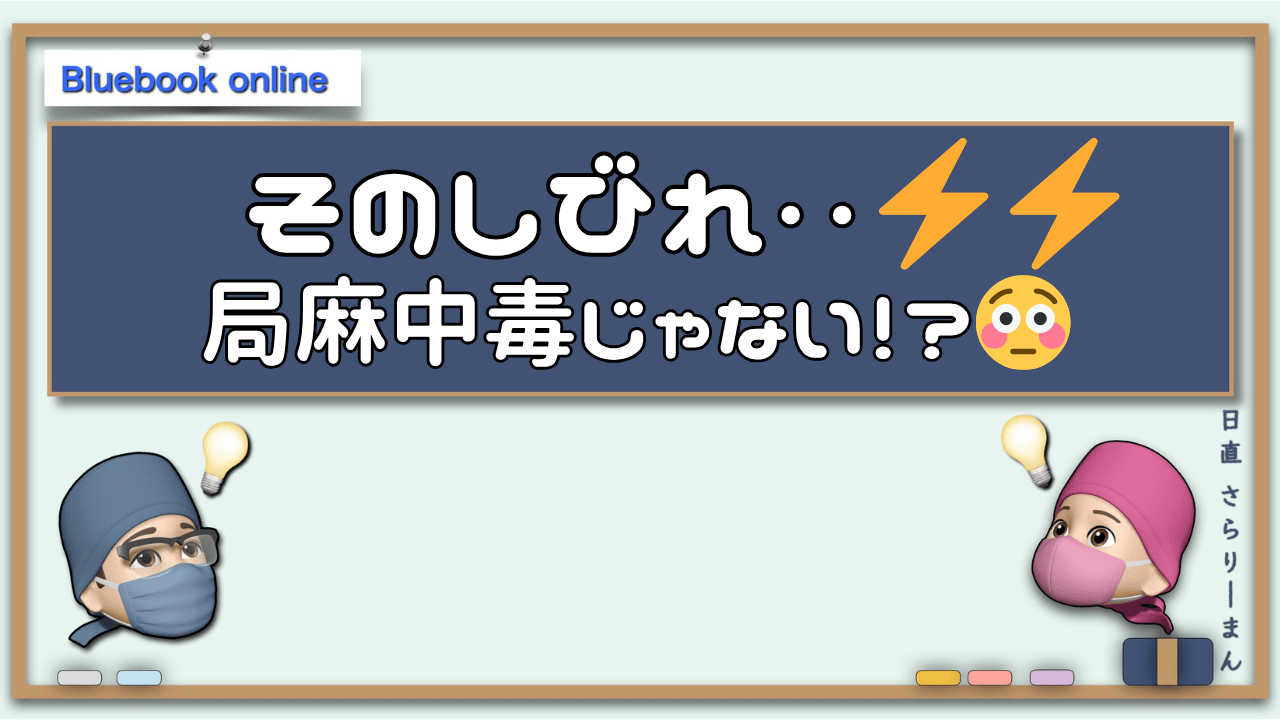
コメントを投稿するにはログインしてください。