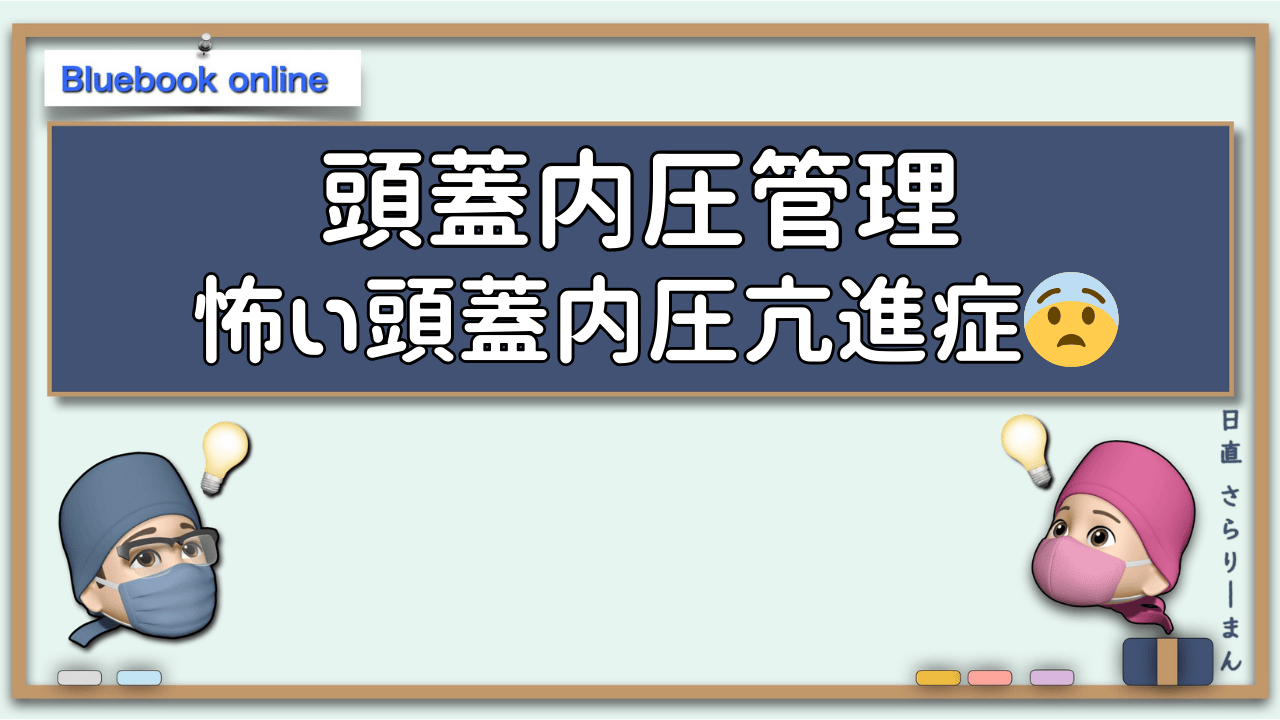👉👉 🇺🇸 All Posts 🇬🇧 / 🇯🇵 記事一覧 🇯🇵 👈👈
♦️ はじめに
頭蓋内圧(ICP)は麻酔科専門医試験でも,筆記試験・口頭試験問わず頻出の分野です.主に頭部外傷や脳神経外科手術において注意を払うべき問題となります.
主に問われるのは,頭蓋内圧の構成要素や規定因子,頭蓋内圧亢進症の症状やバイタルサイン,術中の麻酔方法や頭蓋内圧管理などになります.
♦️ 頭蓋内の構成要素 🧠
頭蓋の中にはみなさんご存知の通り脳実質(約80%).脳脊髄液(約10%)、血液(約10%)が含まれています(この容量の割合は教科書ごとに5%程度のずれがありますがだいたいこんなものです).
固く柔軟性のかけらもない頭蓋骨の中にこれらが詰め込まれているため,あまり余裕がありません.脳腫瘍や血腫のような占拠性病変が発生したり,脳浮腫が生じたりすることで,比較的容易に頭蓋内圧は上昇してしまいます.
♦️ 頭蓋内圧(ICP)の正常値とその規定因子
🔷 ICPの正常値と亢進状態
ICPの正常値:5〜15mmHg
こういった数値は覚えるしかありません.
目安として,これが20mmHgを超えるとなんらかの治療介入が必要となります.一般的にはこの20mmHg以上がが5分以上継続した場合に「頭蓋内圧亢進状態」と定義されています(Brain Trauma Foundation BTF、SCCMによるEmergency Neurological Life Support ENLSによる).
ICPが上昇し続け,60mmHgを超えるような高圧になるとほぼ全脳虚血になると言われています(脳灌流圧=平均動脈圧ー頭蓋内圧のため)😨.
閉鎖腔に存在するとは言え,若干は代償機構が存在するため血腫などによる容積増加が軽度の場合にはICPはあまり上昇しません.しかし、代償機構の限界を超えると逆上がり練習機(今もあるのかな)のように急激にICPは増加します.
🔷 頭蓋内圧の規定因子には何がある?
冒頭でも述べたように,頭蓋内圧を規定する要素は脳実質,脳脊髄液,血液のそれぞれの圧ということになります.
そして,脳灌流圧は平均動脈圧から頭蓋内圧を引いたもので表されます.
脳灌流圧 = 平均動脈圧 – 頭蓋内圧
♦️ 頭蓋内圧亢進状態の評価・症状
まず,主観的な症状の訴え(自覚症状)と客観的な評価(身体所見・画像)に分けて考えていきましょう.
🔷 自覚症状
頭の中がパンパンになればいかにも頭は痛くなりそうですし,頭痛で吐き気も出そうですし(私も偏頭痛持ちで気持ち悪くなります),ひどくなると意識障害も出て痙攣も起こし,最終的には(脳ヘルニアを起こし)昏睡・呼吸停止にもなります.これらは想像しやすいと思います(最後は自覚してないと思いますが).
🔷 客観的な所見(他覚症状)
他覚的な身体所見としては複視(外転神経麻痺),うっ血乳頭などがあります(複視自体は自覚症状ですが,外転神経麻痺としては他覚所見).
バイタルサインとしては,高血圧,徐脈,呼吸異常があり,これらはCushingの3徴候と呼ばれています.
ひどい脳出血患者などではこのバイタルで運ばれてきて脳外科の先生が「早く早く!」と手術室スタッフを急かしていることがありますね.こういう患者さんは頭を開けたら開けたで急激に血圧が下がったりして大変です・・(ー ー;).
客観的な評価のうちCT画像ではどうでしょうか.脳出血や広汎な脳梗塞による脳浮腫では正中が健側に偏位していますね(midline shift).他には脳室・脳溝の圧排、脳溝消失などが見られます.
🔷 症状のまとめ
以上,まとめると以下のようになります.
- 自覚症状:頭痛、悪心嘔吐、意識障害、痙攣、昏睡、呼吸停止
- 身体所見:高血圧、徐脈、呼吸異常、うっ血乳頭、複視
- 画像所見:正中の健側への偏位、脳室圧排、脳溝消失、脳ヘルニア(末期)
♦️頭蓋内圧亢進症患者の麻酔
以上の流れから、頭蓋内圧を上昇させない脳に優しい麻酔を心がける必要があります.
頭蓋内圧は上記の3因子,脳実質(細胞成分→外傷や脳虚血などによりナトリウムや水分が細胞内に貯留、体液・血液成分→血液脳関門の破綻による血管外へのタンパク流出が起こり水分が貯留),脳脊髄液,血液のどれかが増加すれば上昇します.
もちろん細かな内容についてはICP上昇の原因疾患や、他の合併症との絡みなどもあるので、ここで説明するのはあくまで基本的なものとして捉えてください.
🔷 麻酔導入時の注意点
懸念として,挿管刺激や浅麻酔による交感神経刺激により血圧が上昇して,脳血流量(脳血液量)が増加することが挙げられます.そのためフェンタニルやレミフェンタニルを用いて十分な鎮痛のもとで挿管操作やヘッドピン固定を行います.
また脳血流量を増加させるとされている揮発性吸入麻酔薬、ケタミン、亜酸化窒素を用いず,主にプロポフォールを使用することが多いです.
全身状態や合併症、アレルギーの有無や気道確保困難が予想されるかにもよりますが,緊急であればレミフェンタニル(あるいはフェンタニル),プロポフォール,ロクロニウムを用いた迅速導入,予定症例では急速導入というのが無難かなと.
☝️【補足】
一般的に使用されるデスフルラン,セボフルラン,イソフルランは通常使用する濃度では大きな問題にならないと考えられています(脳血管を拡張させる作用も持つが,脳代謝を抑制することによる脳血管収縮作用も持っているため相殺される).
もちろん高濃度で用いればICPが上昇するようですが,レミフェンタニル麻酔が全盛の昨今,そのような高濃度が必要とされることはまずないため,吸入麻酔薬を用いても問題はないと考えられます.ただし試験的には「TIVAがより安定してICP管理に有利」と整理されることが多いです.
🔷 麻酔維持の注意点
上記の通り,吸入麻酔薬を積極的に推す理由はないので,プロポフォール、レミフェンタニル(+フェンタニル)による全静脈麻酔(TIVA)が第一選択とされることが多いです.
血圧が上昇すれば,脳梗塞や脳出血などの障害部位では脳血流の自動調節能が破綻しているため,脳血流が増加しICPが上昇するおそれがあります.
逆に低血圧になれば通常の患者であれば耐えられる血圧でも脳虚血を起こす恐れがあるため,血圧の維持には注意が必要です(上げすぎず,下げすぎず).
🔷 術中の頭蓋内圧管理・調整(特に脳外科手術🧠)
何度も挙げている通り,脳のコンパートメントは脳実質,脳脊髄液,血液からなるため,頭蓋内圧を下げるためにはそれぞれの圧を下げることを考えます.
脳実質を縮小する方法
- 脳浮腫を取る,あるいはICP上昇の原因となっている血腫や腫瘍の除去・摘出.
- マンニトール投与による浸透圧利尿,高張食塩液やフロセミド投与が行われることがあります.
脳脊髄液を減少させる方法
- 脳室ドレーンや脳室穿刺吸引など(急激なICP低下は出血や脳ヘルニアを起こすことがあるため注意).
血管容量を減少させる方法
- 静脈還流を促進:頭部を30度程度挙上,頸部過屈曲や胸腔内圧上昇(過剰な換気圧やPEEP,バッキング)を避ける.
- 脳血管を収縮:軽度過換気(PaCO₂ 30〜35mmHg程度)が一時的に有効だが,持続すると虚血リスクがあるため短期的手段にとどめる.低酸素血症(特にPaO₂ 50〜60mmHg以下)は著明に脳血流量を増加させるため是正が必要.
📝 まとめ(Take Home Pointes)
- 頭蓋内圧の正常値は 5–15 mmHg,20 mmHg以上が治療介入の目安.
- 構成要素は脳実質・脳脊髄液・血液(Monroe-Kellie doctrine).
- Cushingの三徴は「高血圧・徐脈・呼吸異常」.
- 麻酔はTIVA(プロポフォール+レミフェンタニル)が安定してICP管理に有利.
- ICP管理の手段:頭部挙上,軽度過換気,胸腔内圧低減,マンニトール/高張食塩液,必要に応じてドレナージや腫瘍・血腫除去.それぞれのコンパートメントを意識した対処.
🔗 Related articles
- 追加予定
📚 References & Further reading
- Managing Intracranial Pressure Crisis(Viarasilpa,2025)
最近の文献をもとに,ICPクライシス(危機的な高ICP時)の管理戦略を総合的に提示している - Monitoring the injured brain: ICP and CBF(Steiner 他,2006)
傷害脳における ICP と脳血流(CBF)の関係とモニタリングについて解説.かなり引用されている. - Management of increased intracranial pressure: A review(Marik,1999)
比較的古いが,ICP 管理の基礎を押さえている総説. - Initial Diagnosis and Management of Acutely Elevated ICP(Kareemi 他,2023)
急性に ICP が上昇した症例への初期対応を焦点にしたレビュー記事 - Increased Intracranial Pressure(StatPearls)
ICP の病態,評価,管理方法を比較的簡潔にまとめてあるオンラインリソース. - Intracranial Pressure Monitoring(StatPearls)
ICPモニタリング技術と意義について整理された解説.