👉👉 🇺🇸 All Posts 🇬🇧 / 🇯🇵 記事一覧 🇯🇵 👈👈
Contents
♦️ はじめに
 さらりーまん
さらりーまん最近CLABSIの院内指標が厳しくなってるけど,きちんとできてる?



たぶん・・最近感染起こしてないし・・.穿刺は全部エコーでやってますけど,感染って穿刺よりその後の管理が肝なんですよね?



ルーメンは最小限,ハブはキャップで守る,ドレッシングはCHG付きを週1で交換……チェックリストに落とし込んでます!



じゃぁ今日は改めて,用語の整理→危険因子→必須対策→追加策→合併症→エコーガイドの安全性の順に,エビデンスを一気に棚卸ししておこうか👍


♦️ 用語の整理:CLABSIとCRBSIの違い・・知ってますか?🤔
できれば略語は4語くらいまでにしてほしいんですけどね!😅 似ている両者ですが,以下のように説明されます.現場ではそれほど気にする必要はないと思いますが,一応ね😊
- CLABSI:こちらはサーベイランス(監視指標)の言葉です.「48時間以内に中心ラインが入っていた患者さんの一次性菌血症で,他の原因が見つからないもの」を数えます.実際には他の部位が見逃されて過大にカウントされることもあるので,「現場の診断」とは役割が違います.
- CRBSI:医師が診断に使う言葉です.「本当にカテーテルが原因だったか」を,カテーテル血と末梢血の培養結果(差動時間陽性など)で証明して判断します.検査体制や臨床状況によっては証明が難しいことがあります.
♦️ 今,どのくらいカテーテル関連の感染症が起きているのか??
- 米国の一般ICUでは,CLABSIはおおむね 0.8/1,000 catheter-days程度まで下がっているとされています.
- catheter-daysとは,患者1人にカテーテルを1日留置したら1カテ日」と数える指標です.
- 10人に1本ずつカテーテルを10日間入れていたら「10人×10日=100カテ日」となります.
- 上記の場合,1,000日分のカテーテル留置あたり0.8件.言い換えると,おおよそ0.08%(=1,000例中0.8例)と,非常に低い発生率.
- 低中所得国(LMICs)では依然として高く,INICCの集計では12.5→4.5/1,000へと改善しているものの,まだ差があるようです.
- 中国のICUメタ解析では,全体で2.65/1,000(成人ICU2.57,小児ICU3.12)と報告されています(地域差あり).
いずれにせよ,対策を正しく積み上げれば減らすことのできる感染と捉えられています.
♦️ カテーテル感染の危険因子:どのリスクを減らせる!?🤔
「変えられるもの(介入できる)」と「変えにくいもの(背景)」に分けて考えます.メタ解析からのオッズ比(厳密にはちょっと違いますが,簡単に言えばリスクの度合い)も書いておきますね😊.
🔷 対策で変えられるもの(ここに力を入れる必要があります👍)
- カテーテル日数が長い:5日以上(OR 2.07),7日以上(3.62),14日以上(4.85)でリスクが段階的に上がります.毎日の「本当に必要?」が大事です.
- ルーメン数が多い:多ルーメンは感染リスク↑(OR 3.41).必要最小限に.
- 大腿静脈など部位要因:挿入部位による差(OR 2.41).大腿は回避できれば回避を.
- TPN(中心静脈栄養):OR 2.27.接続回数や開放時間を最小化します.
- ラインの入れ替え回数が多い:OR 3.50.一度で安全に決められるようエコーと手技の訓練を.
🔷 変えにくいもの(リスクを意識してケアを厚く)
- 長期ICU滞在(OR 4.05),高齢(≥60歳;OR 2.19),糖尿病(OR 3.06),免疫抑制(OR 2.87)など.こうした方は特に基本の徹底を意識します.
👉「日々の必要性チェック」「一本を丁寧に」「開放・接続を減らす」が重要です.
♦️ まずやる対策
☝️以下はCDC/SHEA/WHOの共通する柱です.
🔷 まずは・・・
- 必要性について,毎日再評価します(すでに留置している場合,不要なら抜去).
- 挿入・維持に関わるスタッフの教育と能力
🔷 挿入時
- 手指衛生 → マキシマムプレコーション(帽子・マスク・滅菌ガウン・滅菌手袋・全身ドレープ).
- 皮膚消毒:アルコール含有クロルヘキシジン(通常2%,少なくとも0.5%超)を十分乾くまで.(乳児は濃度と皮膚反応に注意).
- 部位選択:成人では大腿回避,非トンネル型は鎖骨下>内頸>大腿が感染面で有利(腎疾患は鎖骨下回避👉鎖骨下静脈の狭窄や閉塞が起きやすいため.将来のシャント作製時に問題となりうる).
- エコーガイドで穿刺回数・機械的合併症を減らす(無菌を崩さない:プローブカバー・滅菌ゲル).
- ルーメンは最小限.
🔷 挿入のあと(維持)
- クロルヘキシジン含有ドレッシング(成人)を基本に,透明被覆は少なくとも7日ごと(汚染・剥離はすぐ交換),ガーゼは2日ごと(ただし,日本ではまだ使用は一般的ではないようです).
- ハブ・コネクタ消毒:しっかりこする/消毒キャップの併用も有効(手擦拭の代替ではなく補完).
- 輸液セットは通常最大7日で交換(血液・脂肪製剤は別基準).
- 不要ラインの即時抜去とCLABSIサーベイランス&フィードバック.
これだけで多くの施設で感染率ははグッと下がると言われています👍
🔷 その他の特殊な対策
- 抗菌・防腐剤含浸カテーテル(CHG/銀スルファジアジン,ミノサイクリン/リファンピンなど):海外では市販されており,高リスク環境や再発例で検討されます👉日本においては現在使用されていないようです.
- 抗菌ロック療法:長期カテーテルで再発例など選択的に.エタノールは有害事象に注意👉日本においては「特定の場合に限って検討可能」とされており,ルーティンでは推奨されていません(長期留置用の透析カテーテルによる感染再発防止,化学療法,免疫不全患者などに限定的に.保健適応もまだありません).👉海外では専用の製剤も市販されているようですが,日本においてはまずは標準の感染予防を徹底するのが優先とされています.
- 消毒キャップ(消毒剤を含ませた特殊キャップ)の使用:ハブ汚染を減らす報告あり.一部の大学病院やICUで導入が進んでいるようです.
注意:予防的全身抗菌薬やルーチンの定期入れ替えは,原則推奨されません.
♦️ 補足:代表的な合併症(感染以外も「起こさないための対策」を)
🔷 穿刺関連の合併症
- 動脈穿刺・血腫・気胸/血胸・心タンポナーデ・空気塞栓・不整脈・神経損傷など.
→ エコーと静脈前壁を貫かせない手技,ガイドワイヤーを深挿ししすぎない等で予防します(JSAの実務ガイドに安全手順がまとまっています).
抜去時の空気塞栓にも注意(空気不透過ドレッシングで被覆・体位配慮など).
🔷 エコーガイド下穿刺の安全性(感染は“間接的”に下がる)
- 何が良くなる? 失敗回数↓/動脈誤穿刺↓/気胸↓など機械的合併症が確実に減ることが,RCTやメタ解析で示されています.
- 感染そのものは「無菌操作」と「維持管理」の質で決まります.エコーは**“安全に一回で決める”ための強い味方**と理解してください(プローブカバー・滅菌ゲルは必須).
手技はシミュレーターで練習を!😊
📝 まとめ(Take Home Points)
- 「CLABSI」と「CRBSI」は目的が違う
- 世界的にはCLABSIは減少傾向.基本の感染予防の徹底を!
- 感染を起こしやすい条件を知り,対策できる部分に集中
- 長期留置・多ルーメン・大腿静脈・TPN・不十分な管理が主なリスク.
- 対策は「最短日数・最小ルーメン・最適な部位で入れる」,そして「入れたら丁寧に維持して早く抜く」こと
- “感染予防バンドル”が基本中の基本
- 手指衛生(ABHR)
- マキシマムプレコーションの遵守(ガウン・手袋・マスク・ドレープ)
- アルコール含有クロルヘキシジンでの皮膚消毒
- ルーメン最小化,透明ドレッシング(CHG含有),ハブの消毒・キャップ使用
- 毎日の必要性再評価と早期抜去
- エコーガイドは「安全に挿すための基本技術」
📚 References & Further reading
- CDC: Strategies for Prevention of Catheter-Related Infections (2024)
- 米国CDCによる中心静脈カテーテル関連感染の予防策を網羅的に提示する最新版ガイドライン。手指衛生・消毒薬選択・バンドル戦略など
- WHO Guidelines for the Prevention of Bloodstream Infections and Related Events (2024)
- 世界的に有効な感染予防策に関する最新ガイダンス(主に末梢・中心静脈カテーテル)
- SHEA/IDSA: Strategies to prevent CLABSI in Acute Care Hospitals (2022)
- 急性期病院における中心ライン感染の厳密な予防バンドル推奨
- PMC: Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-Related Infections (2011, CDC, SHEA, IDSA, 他合同声明)
- 教育・バリア、手指衛生、クロルヘキシジンなど主要予防策の推奨グレードが細かく記載されている
- ScienceDirect: Systematic review of CLABSI prevention (2024)
- 世界中の感染予防対策の実装状況・効果を大規模レビュー
- Frontiers in Public Health: Meta-analysis of CLABSI rates in ICUs (2025)
- ICUで実際にどの程度CLABSIが発生しているか、世界とアジア圏べースで大規模データの比較あり
- PLOS ONE: Risk factors for CLABSI (2024)
- 感染発症リスクや修正可能因子・非修正因子の大規模分析
- PubMed: Systematic review and meta-analysis of CLABSI risk factors (2023)
- 栄養管理法・カテ種・免疫抑制など感染と相関する因子まとめ
- 日本麻酔科学会『中心静脈カテーテル プラクティカルガイド』(2017年版).
→ エコーガイド下穿刺手技,合併症(空気塞栓・心タンポナーデ),抜去時管理などを解説.
🔗 Related articles
- 追加予定
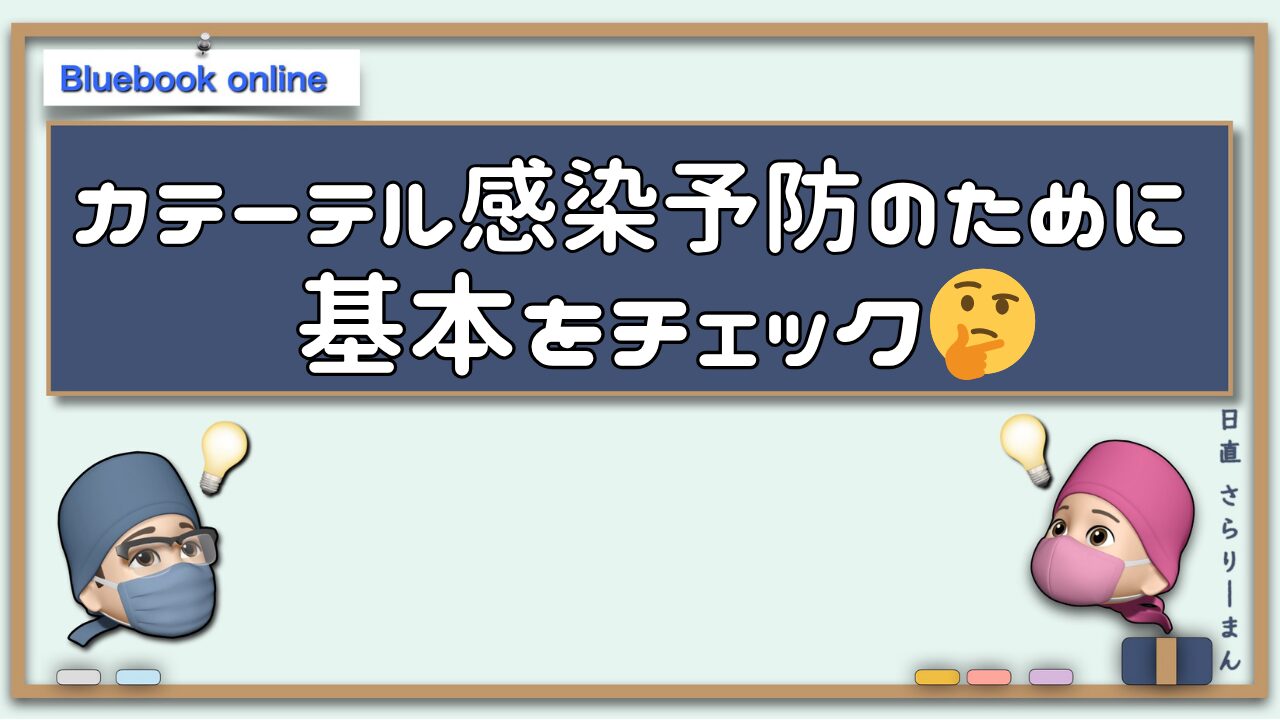
コメントを投稿するにはログインしてください。