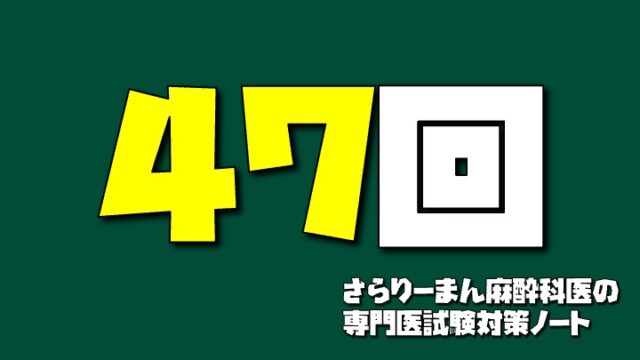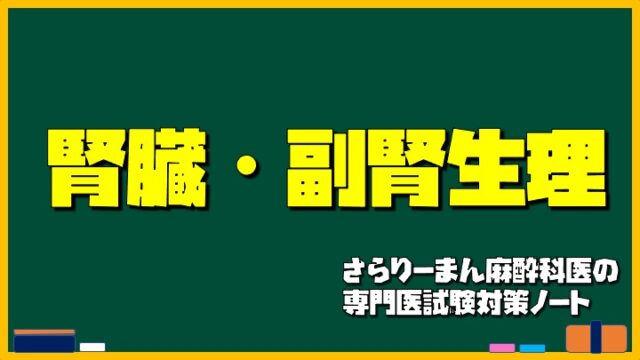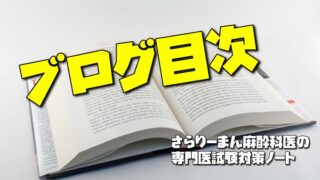物理・薬理
薬理
isobologramとは何を判断するためのものですか?
- 等しい作用を有する薬物の必要量それぞれ縦軸と横軸にとったもので、そのグラフの曲線の形状でその薬物同士が相加的(単独効果の和と同等)、相乗的(単独効果の和より強い)、拮抗的(単独効果の和より弱い)を判断するための手法です。
🌟isobologramのグラフが一直線の場合、上に凸の場合、下に凸の場合、それぞれどのような意味を持ちますか?
- グラフが一直線であれば相加的、上に凸であれば拮抗的、下に凸(反比例グラフのような)であれば相乗的であることを示す。(59A87)
🌟isobologramでは高い反応率を必要とするほどグラフは原点方向に近づきますか?遠ざかりますか?
- 高い反応率を必要とするほど原点方向から遠ざかます(例えば58A39、57A26のように50%の患者で血圧変動を防ぐ薬物濃度の曲線だとします。それを90%の患者で有効な量にすると両方の薬物とも多量が必要になるためグラフは原点から遠ざかる)。逆に低い反応率では原点に近づく。(59A87)(58A39)(57A26)(56B1)
🌟isobologramでは高齢者ではグラフが原点方向に近づきますか?遠ざかりますか?
- 高齢者では薬物の必要量が減少するため、曲線は原点方向に移動します。(59A87)
🌟補足
- 56B20ではケタミン+イソフルラン(相乗的)、ケタミン+ミダゾラム(拮抗的)、デクスメデトミジン+フェンタニル(相乗的)、フェンタニル+セボフルラン(相乗的)、プロポフォール+亜酸化窒素(拮抗的)の組み合わせが示されて、それぞれが相加的、相乗的、拮抗的かの判断ができることが前提でグラフを選択するという問題が出題されています。(58A43)(56B20)
物理・化学法則など
沸点・氷点・臨界圧・臨界温度はどういう温度ですか?
- 沸点は蒸気圧と大気圧が一致する温度、
- 氷点は液体が固体化する温度
- 臨界圧は臨界温度で気体を液化するのに必要な最小の圧
- 臨界温度はどのような圧を加えても気体を液化できない温度です。
Gay-Lussacの法則とは何ですか?
- 圧力を一定とした場合、体積は温度に比例します。
🌟Fickの法則とは何ですか?
- 膜を隔てた分子の拡散速度は濃度勾配に比例します。(57B25)
Grahamの法則とは何ですか?
- ガスの拡散は分子量の平方根に反比例します。
Coulombの法則とは何ですか?
- 2つの電荷間に働く力は、2つの電荷の積に比例し、距離の2乗に反比例します。
Henryの法則とは何ですか?
- 液体に溶け込む気体の量は分圧に比例します。
🌟Ohmの法則とはなんですか?
- 電気回路における両端の電位差は抵抗と電流に比例します。懐かしい。(57B25)
🌟Lambert-Beerの法則とはなんですか?
- 溶液を通過する光の吸光度が、それ自体の通過する経路長に比例する一方、溶液の濃度に比例します。(57B25)
Hagen-Poiseuilleの法則とはどのような法則ですか?
- 流量は管の両端の圧差に比例し、流体の粘度に反比例し、管の半径に反比例し、管の長さの4乗に比例します。(54A33)
🌟Hagen-Poiseuilleの法則は層流と乱流どちらの場合に成り立ちますか?
- 層流のときに成り立つ。(54A33)
層流から乱流への変化が、低い流速で起こりやすくなるのはどのような場合ですか?
- 流体の密度が高いほど、粘性率が低いほど低い流速で起こりやすくなります。
🌟Bernoulliの定理は何の計測に用いられますか?
- ベンチュリ管による流量計測に用いられます。(57B25)
- 速い流速で通過する流体の狭隘部と非狭隘部の差圧を測定することで流量が計測できます(TEEとかで使ってます)。
統計学
確率の基礎知識・標本の分布
全く知識がないとこの分野は外国語に聞こえます!笑
専門医試験のために一から統計を勉強する人はいないでしょうしその時間もないはずなので、過去の出題だけは抑えておきましょう!
確率の基礎知識・標本の分布など
検出力とは何ですか?
- 帰無仮説が真でない場合に、その仮説を正しく棄却できる確率を意味します。第二種の過誤(β)を1から引いたもの等しいです。
🌟サンプル数が多くなると検出力はどうなりますか?
- 増大します(サンプル数が大きくなると過誤が減少する)。(60A47)(58A52)(57A58)(55A89)
サンプル数が多くなると信頼区間はどうなりますか?
- 狭くなります。
🌟第一の過誤とは何ですか?またこの確率は何に等しいですか?
- 帰無仮説が真である場合にその仮設を棄却する確率を意味します。この確率は有意水準αに等しいです。(56B5)
🌟第二の過誤とは何ですか?また第一の過誤と第二の過誤とはどういう関係ですか?
- 帰無仮説が真でない場合にその仮設を誤って採択する確率を意味し、βと略されます。αとβにはトレードオフの関係にあります。
- αを低く設定すると第一種の過誤を犯す確率は減りますが、逆に第二の過誤を犯す確率βを増が増大します。(60A47)(58A52)(57A58)(55A89)
🌟データのばらつきを評価する方法として何が用いられますか?
- 分散が用いられます。一般的に分散の平方根である標準偏差(standard devation:SD)が利用されます。(56B5)
- パラメトリックなデータ3群間の比較には、分散分析が用いられます。(53B49)
🌟平均値の標準誤差(standard error of the mean:SEM)は何を示す指標ですか?
- 平均値の正確さを示す指標(ばらつきの評価ではない)。標準偏差が等しくても、サンプル数が大きければ標準誤差は減少します。(平均値の標準誤差はサンプル数に依存しない)(60A47)(58A52)(57A58)(56B5)(55A89)
🌟2群間に有意差がない場合、帰無仮説が真であると断定できますか?
- できません。(60A47)(58A52)(57A58)(55A89)
🌟正規分布ではデータ値の95%はどの範囲内に存在しますか?
- ±2標準偏差以内に存在します。(60A47)(58A52)(57A58)(55A89)
- ちなみにデータの68.27%が平均値±1標準偏差以内、95.45%が平均値±2標準偏差以内、99.73%が平均値±3標準偏差以内に存在します。
- 臨床検査の基準値は、通常平均値±2標準偏差として求めています
🌟正規分布のパラメータは何ですか?
- 平均値と標準誤差です。(56B5)
🌟平均値の信頼区間は標準偏差が大きいほどどうなりますか?
- 広くなります。(53B50)
オッズ比とは何ですか?
- ある事象が生じる確率(p)とその事象が生じない確率(1-p)の比率を指します(ある事象の生じる確率が50%である場合、オッズは1.0)。
陽性的中率は何に依存して変化しますか?
- 対象群の有病率に依存して変化します。
サンプル数に依存する指標には何がありますか?
- 標準誤差や95%信頼区間です。
サンプル数に依存しない指標には何がありますか?
- 分散、標準偏差、四分位間範囲です。
平均値と最頻値が一致しないものには何がありますか?
- F分布(自由度が無限大であれば一致)、χ2分布(自由度が無限大であれば一致)、二項分布です。
自由度mを含む統計分布には何がありますか?
- F分布
- t分布
- χ2分布 です。
バイアスと改善手段
🌟ランダム化臨床試験は何を最小限にする臨床研究の方法ですか?
- バイアスを最小限にする臨床研究の方法です。(53B49)
- 試験では確証バイアスにポジティブコントロールが無効、が出題(54B49)
🌟観察バイアスには何が有効ですか?
- 盲検化です。(54B49)
🌟選択バイアスには何が有効ですか?
- ランダム割り付けです。(54B49)
propensity analysisは何のために用いられますか?
- 観察研究における選択バイアスを制御するために用いられます。
🌟出版バイアスには何が有効ですか?
- 臨床試験登録制度が有効です。(54B49)
🌟解析バイアスには何が有効ですか?
- 治療意図(intention to treat)が有効です。(54B49)
研究方法など
メタアナリシスはあるテーマに基づくあらゆる研究を収集し、それぞれの質を評価した上でエビデンスとして抽出・整理・統合します。
🌟メタアナリシスにおいて研究を抽出するデータベースは単独のものですか?
- 単独とは限りません。(54B50)
🌟メタアナリシスの評価は単独で行っても良いですか?
- 単独の評価者によるバイアスが生じる可能性があるため、複数の評価者によって評価されるべきです。(54B50)
🌟収集した文献に出版(報告)バイアスが存在しないかを評価するのに用いられる方法は何ですか?
- ファンネルプロットが使われます(某ガン●ムの武器ではないです)。(54B50)
フォレストプロットとは何ですか?
- メタ解析の結果を示すために用いられます。論文でよく見かける黒の菱形のマークや四角形のやーつです
🌟結果の信頼区間の上限と下限が1(対数オッズでは0)をまたいでいると有意差はどう評価されますか?。
- 有意差がないと評価されます。(54B50)
横断研究(cross-sectional study)とは何ですか?
- ある特定の対象に対して、疾患や障害における評価、介入効果などを,ある一時点において測定し,検討を行う研究のことです。
- バイアスの影響が入りやすく,原因と結果の因果関係が明確ではないという欠点があります。
🌟症例対照研究では相対危険度は計算できますか?
- できません(できるのはコホート研究)。(56B5)
治療必要数(NNT)
NNTとは何ですか?
- number needed to treatの略で、1例の有害事象を減らすために治療が必要な患者数のことです。治療効果を示す指標として用いられます。
- NNTが”小さいほど”治療効果が大きいです。
🌟NNTはp値と関連がありますか?
- ないです。(59A85)(58A10)(57A23)(55B7)
🌟NNTの信頼区間は対称性、非対称性どちらを示しますか?
- 非対称性を示します。(59A85)(58A10)(57A23)(55B7)
🌟NNTは何から算出されますか?
- 事象の有無を示す2値データから算出されます。(59A85)(58A10)(57A23)(55B7)
🌟NNTは前向き・後ろ向きどちらの研究に基づきますか?
- 前向き研究です。(59A85)(58A10)(57A23)(55B7)
🌟NNTは何の逆数ですか?
- 絶対リスク減少の逆数です。(59A85)(58A10)(57A23)(55B7)
変数
変数には何がありますか?
- 質的内容を指すカテゴリー変数と量的内容を指す連続変数があります。
カテゴリー変数と連続変数はそれぞれ何が含まれますか?
- カテゴリー変数には名義変数と順序変数があります。
- 連続変数には間隔変数と比例変数があります。
🌟名義変数とは何ですか?
- 名義変数は順序に関係なく量的な意味を持たない単なる名称が割り当てられた変数を指し、電話番号や患者番号などが該当します。(56B4)
質量や長さは何変数ですか?
- 比例変数です。
検定方法
Friedman検定はノンパラメトリック検定ですか?
- そうです。
🌟一元配置分散分析はパラメトリック検定ですか?
- そうです。(57B4)
🌟Kruskai-Wallis検定はノンパラメトリック検定ですか?
- そうです。正規分布の前提を必要としません。
- 正規分布していないデータの3群間の比較に用います。(53B49)
🌟対応のある2群データの比較研究で、データ分布に偏りがある場合に用いる検定は何ですか?
- Wilcoxon順位和検定です。(52B50)
🌟Student’s検定はデータが正規分布をとっていることを前提としますか?
- はい。Student’s t検定とは、母集団が正規分布に基づくという前提のもとに検定する手法です。(53A99)(52A98)
Mann-Whitney検定とは何検定に対応するノンパラメトリック検定ですか?
- Student’s検定に対応するノンパラメトリック検定です。別名はU検定。
🌟対応のない二群における連続変数(非正規分布)の比較に適切な検定方法は何ですか?
- Mann-Whitney検定です。(60A19)(59B45)
🌟名義変数の2群間の比較には何検定を用いますか?
- χ二乗検定を用います。(53B49)
🌟対応のない二群の割合の比較には何検定を用いますか?
- χ二乗検定です。(60A19)(59B45)
🌟生存分析で累積生存率(累積死亡率、累積罹患率などを含む)を推定するためにはどのような方法を用いますか?
- Kaplan-Meier法を用います。(58B5)
🌟二つの累積生存率曲線の差の検定にはどのような方法を用いますか?
- Logrank検定、一般化Wilcoxon検定を用います。(58B5)
🌟Coxの比例ハザードモデルを用いれば何の検定が行えますか?
- 交絡変数の影響を除いたうえで相対危険の推定と検定を行うことができます。(58B5)
- 筆記試験では生存分析に用いるもので、Kaplan-Meier法、Logrank検定、Coxの比例ハザードモデルを選ぶ。(58B5)
麻酔の歴史
とても覚える気には慣れないでしょうから(笑)、試験に出たパターンは抑えておきましょう。
問題によっては筆記試験問題集の解説と麻酔科スタンダードⅢの麻酔科年表が1年ずれているところもあります(問題を解く上では問題なし)
🌟歴史的に最も早く行われた麻酔は何ですか?
- 華岡青洲の通仙散を用いた全身麻酔(1804年)(59A29)(58A3)(52A100)
最も古く臨床応用された麻酔薬は何ですか?
- (選択肢の中では)リドカイン(1948年) (57A14)
🌟クラーレを用いて神経筋接合部の発見につながる生理学的実験を行った人物は誰ですか?
- Claude Bernard (55B1)
🌟Mortonのエーテル麻酔公開実験は何年ですか?
- 1846年 (59A29)(54A100)
🌟コカインの抽出は何年ですか?
- 1856年 (54A100)
コカインの点眼による局所麻酔はいつくらいですか?
- 1800年代後半
🌟酸素の発見はいつくらいですか?
- 1770年代 (53A100)
🌟Griffith HRは何をした人ですか?
- クラーレの臨床応用(59A29)
🌟Bierは何をした人ですか?
- 初めて脊髄くも膜下麻酔を行った。(59A29)
🌟John Snowはどういう人ですか?
- エーテル吸入器やVitoria女王のクロロホルム麻酔で有名。世界で最初の麻酔科専従医(59A29)
ちなみに日本麻酔科学会が設立されたのはいつですか?
- 1954年です。