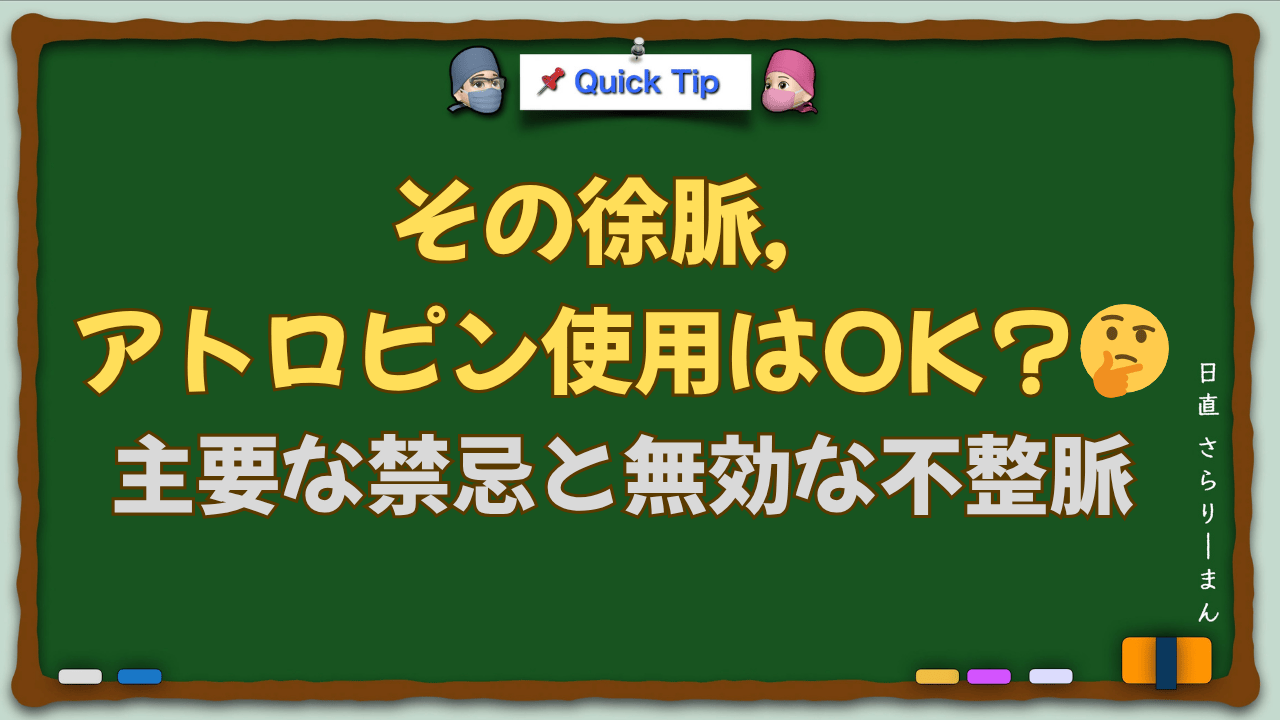♦️ Introduction
68歳の患者さんが脊髄くも膜下麻酔中に突然,症候性徐脈(心拍数38 bpm)を発症しました.最初に思いつくのはアトロピンの投与かもしれません.しかし,これはアトロピンが効く徐脈でしょうか?🤔
✅ 答え:この症例ではアトロピンは有効です👍.
脊髄くも膜下麻酔による徐脈は,交感神経遮断と相対的な迷走神経優位が原因です.迷走神経が介在する徐脈であるため,アトロピン 0.5〜1 mg静注が第一選択となります😊
しかし—すべての徐脈がこのように単純ではありません.
誤った状況でアトロピンを使用すると,全く効果がないばかりか,実際に害を及ぼすこともあります.特に,患者さんに高度房室ブロックの既往がある場合,心筋梗塞を合併している場合,または急性閉塞隅角緑内障の既往がある場合などです.
アトロピンが効かない,または避けるべき主要な状況を見ていきましょう👍
🤔 なぜアトロピンは一部の徐脈で効かないのか
アトロピンは抗ムスカリン作用薬です.副交感神経受容体でアセチルコリンをブロックします(副交感神経遮断薬).
心臓の刺激伝導系では,洞結節と房室結節での迷走神経緊張を減少させます.迷走神経の抑制が減ると,交感神経の影響が優位になり,心拍数が上昇します.
アトロピンの効果は洞結節と房室結節に限定されます. 徐脈が房室結節より下位の問題(房室結節下ブロック)から生じている場合,アトロピンは問題に到達できません(ヒス・プルキンエ系の伝導障害には効果を発揮できない).このような場合,アトロピンの投与は効果がなく,効果的な治療を遅らせる可能性があります.
代表的な不整脈は,高度房室ブロック(MobitzⅡ型房室ブロック,完全房室ブロック)です.
日本では硫酸アトロピン注(0.5 mg/1 mL)が広く使用されています.成人の徐脈に対する通常用量は0.5〜1 mgで,必要に応じて追加投与を行います.保険診療では特に施設基準は不要で,救急時の使用が認められています.
🙅 アトロピンが害を及ぼす可能性がある場合:主要な禁忌
アトロピンは適切な状況では有効ですが,誤った状況では危険になり得ます😓.投与前に,以下の禁忌が存在しないことを必ず確認しましょう.
👀 急性閉塞隅角緑内障
おそらく最も有名なアトロピンの禁忌です.アトロピンは眼のムスカリン受容体をブロックすることで瞳孔を散大させます.この散大により房水流出が障害され,眼圧が急激に上昇し,急性閉塞隅角緑内障を引き起こす可能性があります.これは失明のリスクも伴う危険な合併症です.
ただし,開放隅角緑内障の場合は必ずしも禁忌とはなりません.
白内障手術後の患者さんでは,前房隅角が広くなっているため,閉塞隅角緑内障のリスクは大幅に低下します.白内障術後の患者さんでは,通常アトロピンを安全に使用できます.
患者さんの緑内障のタイプや前房の解剖が不明な場合は,可能であれば眼科コンサルテーションを行い,コメントをもらっておきましょう👍
🫀 冠動脈疾患(CAD)
心筋梗塞の既往がある場合や,重症冠動脈疾患(3枝病変など)の患者さんでは,投与は慎重に行います.
標準的な0.5〜1mgのアトロピン投与でも,心拍数を30〜40 bpm上昇させる可能性があり,心筋酸素需要を急激に増加させる可能性があります.
これにより心筋虚血に陥り,危険な心室性不整脈を誘発したりする可能性があります.このような状況では,ペーシングなどの他の介入を考慮したほうがよいかもしれません.
🚰 閉塞性尿路疾患
前立腺肥大や膀胱出口部閉塞のある患者さんでは,アトロピンの抗コリン作用により排尿筋機能が抑制され,急性尿閉を引き起こす可能性があります.高齢男性患者さんでは,使用前に必ずこのリスクを考慮しましょう.
🤔 どのような不整脈がアトロピンに反応しないか?
一部の徐脈性不整脈は,投与量に関係なくアトロピンに反応しません.このような場合は,他の治療方法を考慮する必要があります.
🔹 高度房室ブロック
アトロピンはMobitz II型および第三度(完全)房室ブロックには無効です.これらは房室結節下ブロックであり,つまり伝導障害が房室結節より下位で発生しているため,アトロピンは効果がありません.
💡 重要な区別:
- Mobitz I型(Wenckebach型):
- 通常房室で発生し,アトロピンで改善することが多い.特に迷走神経緊張の亢進(例:睡眠中,迷走神経刺激後,または鍛錬されたアスリート)が原因の場合.
- Mobitz II型:
- 房室結節より下位で発生し,アトロピンには反応しません.
🔹 心臓移植患者
まだまだ出会う頻度は多くないと思いますが😅,心臓移植患者では,心臓は除神経されています.つまり,迷走神経支配が残っていません.
副交感神経緊張がないため,アトロピンが作用する基盤がありません.その結果,完全に無効であり,これらの患者さんでは使用を避けるべきです.
🔹 β遮断薬過量投与
アトロピンは,β遮断薬過量投与(や効果が過剰な場合)による徐脈の第一選択薬ではありません(多少効果があるかもしれませんが,アトロピンは迷走神経を抑制することで,相対的な交感神経優位にするだけなので,β受容体がブロックされている以上,効果は限定的です).
これらの患者さんには静注グルカゴンが有効とされています.グルカゴンはcAMP経路を介して心臓を直接刺激し,ブロックされたβ受容体を迂回して作用します.
このため,β遮断薬投与中患者のアナフィラキシーショックにおいて,アドレナリンの効果が不十分な場合の投与が行われることがあります.
🇯🇵 日本の状況: 日本では,グルカゴンは低血糖の治療にのみ正式に承認されています.β遮断薬過量投与に対する使用は適応外ですが,この使用法は国際的な救急ガイドラインで支持されており,集中治療の現場では一般的です.
✅ では代わりに何をすべきか:代替管理
ではアトロピンが効かない場合,または禁忌の場合は何をすべきでしょうか🤔
🔹 経皮ペーシング(TCP)
患者さんが血行動態的に不安定で,アトロピンに反応しない場合は,直ちに経皮ペーシングを考慮します.頻繁に使うものではないので,定期的に操作方法を確認しておきましょう!(麻酔科専門医試験口頭試問でも問われたことがあります).
- 実施には体外式ペースメーカー本体と習熟した医療スタッフ(循環器内科,心臓外科医師,麻酔科医,救急医,臨床工学技士など)が必要です.
- 多くの施設では手術室や集中治療室に配備されていますが,一般病棟ではすぐに利用できないこともあるため,施設の体制を事前に把握しておくことが重要です☝️
- 除細動器の心電図電極を貼る.
- モニターに心電図波形が出ることを確認.
- ペーシングパッドを右前胸部と左側下部胸壁に貼ります.
- ケーブルを適切に接続します.
- モードは「デマンド」で.「フィックス(固定レート)」に合わせると R on T からの TdP のリスクがあり.
- ペーシングレートを60〜80bpm程度に合わせて,スタート/ストップボタンを押してペーシング開始します.
- 心電図モニターでペーシング波形(ペーシングによる QRS)が出るまでペーシング強度(mA)を上げていきます(ペーシング閾値の確認).出力値は確認できた閾値よりも5〜10mA高く設定します.
- 最終的にきちんとペーシングに合わせて脈拍が触知できるかを確認することが重要です.
- 電気メスの刺激でオーバーセンシングが生じる場合は固定レートで刺激します.

手術室には必ず除細動器があるはずなので,心臓外科がない施設ではめったに使わないとは思いますが,確認しておいてください!
🔹 カテコラミン投与
アドレナリンまたはドパミンの持続投与により,心拍数を上昇させ,血圧を安定化できます(投与しすぎて,血圧も心拍数も爆上がりしないように・・😅).
日本🇯🇵ではドパミン(イノバン®注)が広く使用されています.海外ではアドレナリン(ボスミン®注)もよく用いられます.
徐脈に対するアドレナリンの持続投与は,通常0.01〜0.1 μg/kg/分から,ドパミンは5μg/kg/分程度から開始することが一般的です.いずれも保険適用があり,救急・集中治療領域で標準的に使用されています.
🔹 グルカゴン
現時点では適用外使用とはなりますが,β遮断薬またはカルシウムチャネル遮断薬の過量投与が疑われる場合の特異的拮抗薬として覚えておきましょう.
📝 まとめ:Take Home Messages
アトロピンは迷走神経が介在する徐脈,洞性徐脈やMobitz I型房室ブロックなどにのみ効果的です. 高度房室ブロック,急性閉塞隅角緑内障,心臓移植後,重症な冠動脈疾患の患者さんでは無効または危険です.
🔑 Key Points
- 迷走神経緊張による症候性洞性徐脈,およびMobitz I型房室ブロックには効果あり.
- Mobitz II型または第三度房室ブロックにはNG(病変は房室結節下のため無効).心臓移植患者(迷走神経支配なし)では完全無効です.
- 急性閉塞隅角緑内障では禁忌です.
- アトロピンが効かない場合や禁忌の場合は,経皮的ペーシングまたはカテコラミン投与(エピネフリン,ドパミン).
- β遮断薬過量投与患者における徐脈にはアトロピンは限定的.高度な徐脈の場合はグルカゴン考慮
📚 References & Further reading
- McLendon K, Preuss CV. Atropine. StatPearls. 2023 Jul 5. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470551/ [Open Access]
- JRC Cardiac Arrhythmia Task Force. Initial Dose of Intravenous Atropine for Patients With Symptomatic Bradycardia. Circ Rep. 2025 Sep 26. Available from: https://www.jstage.jst.go.jp/article/circrep/advpub/0/advpub_CR-25-0169/_html/-char/ja [Open Access]
- WikiAnesthesia Editors. Atropine. WikiAnesthesia. 2024 Jan 9. Available from: https://wikianesthesia.org/wiki/Atropine [Open Access]