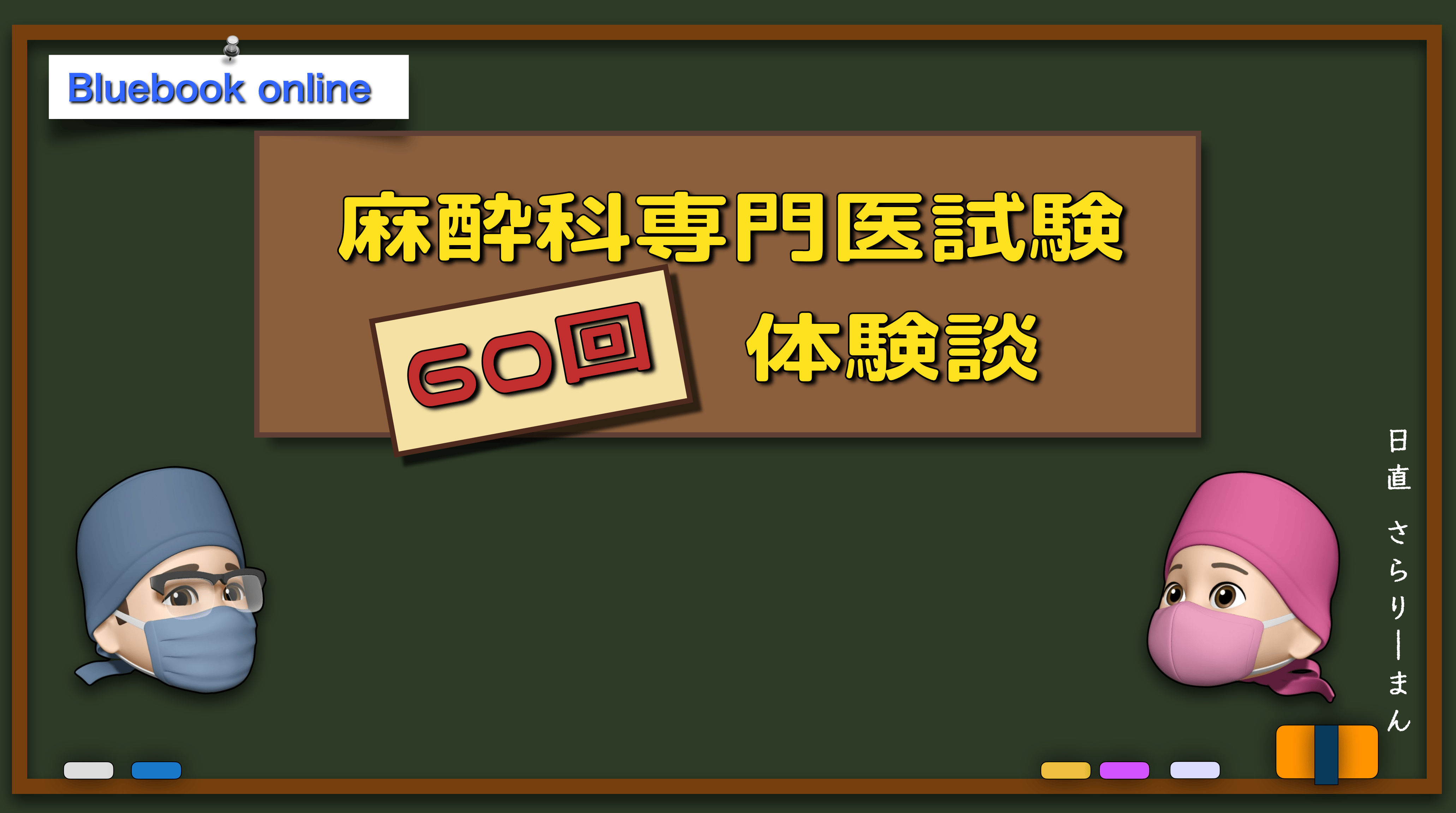60回麻酔科専門医試験体験談:その1
<筆記試験>
神戸会場で受験しました。
巨大なホールで長机に一人一席。時計は大きなデジタル時計が最前列に配置されていました。
A問題:計90問
内容は例年通り、過去問題集の内容とほぼ一致していました。
しかし、数問は新規と思われる問題がありました。新規の問題は普段の臨床の知識でカバーできると思われます。
驚いたのが、過去に不適切問題とされていた問題が出題されていて、自己採点時に気付きました。
1〜2問落とした印象です。
対策:過去問題集を2014年〜2020年の計7年分を何周もしました。
どうしても同じ間違いをする問題が数問ありましたのでそこは重点的に記憶しました。先輩から、脊髄反射で解かねば時間が足りないとのアドバイスもあり、一問数秒で解くように繰り返しました。
その他には試験を解き終わっても見直しをしつこくする事でしょうか。
本番でも2問ほど見直しで間違いを見つけて助かりました。
B問題:計55問
新規の内容ばかりでした。体験談からも、落ち込むなとの事でしたので確実に取れる問題のみを解答し、明らかにお手上げな問題についてはあまり時間を割かぬように時間配分を調整しました。
対策:新規の内容ですが、過去のB問題の改変のような問題(静的コンプライアンスではなく、動的コンプライアンスを求める)もありますので、過去のB問題を解く事も重要かと思います。
調べるのが億劫になり自己採点していませんが、半分くらいの出来かなと思います。
C問題:計55問
こちらも新規の問題でした。臨床問題でBよりは解きやすい印象でした。Bと同様に確実に取れる問題と分からない問題は時間配分に注意しました。半分くらいの出来かなと思います。
対策:一緒に受験した先生からは簡単だったとの事でしたから、純粋に麻酔科で研修されて試験に望まれる先生からすると簡単だった様です。
当たり前ですがやはり普段の臨床が大切なのかもしれません。
※テキストなど
A問題は過去問題集で十分かと思います。
B問題は過去問題集をやりつつ、自分の苦手な分野や経験の浅い分野の知識を補足できる様な教科書を読む事が重要と思います。これはC問題対策としても良いかも知れません。(私は筋弛緩モニターが苦手で、ブロック、ペイン、緩和、移植が経験が浅く、簡単な教科書で勉強しました。)
<口頭試験>
集合時間までに広い待機室で待機。試験内容説明の時間が来ましたらスマートフォンやパソコン、タブレット関係は学会の用意する茶封筒に入れて自分のバッグに入れるよう言われました。
待機室でも自分の受験番号に従って座席は決まっていますが、試験会場であるホテルの客室へは5人ほどのグループで呼ばれ、業務用エレベーターに5人くらい乗せられ、客室へ移動しました。
廊下に椅子があり、試験監督とペアで椅子に座ります。
時間が来たら、症例内容の書かれた紙を渡され、付属のボールペンでメモを取る事を許されます。内容確認、メモの時間は5分間です。
反省と対策
反省としては、やはり自分の経験の浅い緩和や鎮痛の基本的な対応が出来なかった事です。問診が基本ですので、当たり前の事が出来ませんでした。しかし、口頭試験をまとめた青本、緑本はかなり役に立ったと思います。特に返答の仕方、ごくシンプルな答えが求められるのだと勉強になりました。口頭試験の2日前に、口頭試験対策本が発売されていて驚きました。慌てて電子書籍で購入し、読んでみましたが、難しい。理想的な回答が記載されていましたが、口頭試験本番で冷静にここまでの回答を全て用意するのは難しいのではと感じました。
まずは青本や緑本で口頭試験の流れと解答の仕方を掴むのが良いかもしれません。時間があったので、YAO/ARTUSIOの臨床麻酔「質疑応答」等を購入して読みましたが、普段の臨床に向けての勉強には良いと感じました。
私の試験官は幸い優しい先生方でしたが,人によっては冷たい(?)対応をされた方もいたようです.
此処からは私の個人的な意見ですが、
①やはり人間性を見ている可能性があります。
試験前に試験委員会の方から激励の言葉があったのですが、知識共に人間性も評価しているようでした。例え間違っていても自分の思考ロジックを自信を持って伝える事が出来れば良いのかもしれません。
優柔不断や自信の無さは、すぐに見抜かれるものです。
②もう一つは時間でしょうか。事前に「試験時間18分ほど、テキパキと」と言われ尚更スピードを上げましたが、なかなか時間内に終われない受験生も多いそうです。考え込まない方が良いのかもしれません。
60回麻酔科専門医試験体験談:その2
試験管の先生方が穏やかに進行してくださったおかげで、落ち着いて答えることができました。
もちろん全てが過去問通りではありませんが、大まかな点は過去問でインプット、アウトプットを繰り返す練習をしていたおかげで対処することができました。
口頭試験はとにかくアウトプットの練習が大切だと感じました。試験直前2週間は、あえて職場の最寄り駅から少し離れたところで下車し、30分程度緑本を片手に声に出して答える練習をしながら通勤していました。
口頭試験は出題される問題によって難易度も異なるため、運の要素もだいぶ強いかと思います。
とにかく一発アウトにならないよう広めにカバーすることが大事かと思います。
そのために、青本が大変有用でした。
また、口頭試験の勉強を平行して行うことで、筆記試験の理解度も上がっていったように感じます。
これらの本を作成してくださったこと、心より感謝申し上げます。
本当にありがとうございました。
60回麻酔科専門医試験体験談:その3
筆記試験
1年半ほど前から過去問を解き始めました。少し早いかと思っていましたが、途中忙しくて勉強できない時期があったので早く始めてよかったです。過去問は7年分を5周ほどしましたが、間違える問題はいつも同じようなところなので、途中からはそこだけやり直していました。詳しいところはLiSAの過去の記事を読んで勉強していました。
A問題は過去問をやれば解けますが、B問題はほぼ手応えなし、C問題も思っていたより難しく感じました。
試験時間が長くお昼休憩がないので短い休憩時間につまめるものを持って行った方がいいと思いました。
口頭試験
筆記試験に飽きたら口頭試問の過去問をしていました。こちらは5年分を青本をもとに勉強させてもらい、とても助かりました。
60回麻酔科専門医試験体験談:その4
無事に合格できました。さらりーまん先生ありがとうございました。オンライン版が暇な時に眺めるのにぴったりでした。
勉強方法
過去問7年5週
暗記に自信がないので3月くらいからコツコツ。
問題を見たら選択肢見なくても答えがわかるくらいの条件反射を目指した。
さらに古いのも少し手を出したが、ガイドラインの変更もありそうなので、Aだけでもよかったかも。
口頭は過去問をみて、何が聞かれそうか予測を自分で事前に5分間で立ててみて、実際に声に出して答える、というのをやってみた。期間は筆記の勉強に飽きてきたあたりから。本腰入れたのは筆記後。実際の試験も5分間で問題文を読んで、聞かれそうなことを紙に書き込んで、という感じだったので役だったと思う。さらりーまん先生の緑本を解答のように使った。緑本読んでるだけだと、ふんふん、って感じで流し読みしてしまったので、実際の試験っぽく私は声に出してみました。
口頭試験
ポートピアに宿泊。(学会からの予約の方が安く取れた)前日も定時まで仕事で着いたのは21時くらい。コンビニの場所と、集合場所の確認をした。朝食付きプランで、+300円くらいでルームサービスにできたので、遅めの朝からお部屋でご飯にしました。お昼ご飯食べる時間も微妙だったのでちょうどよかったです。
2日目13時だったのでそこまでの症例の情報を集めて、ヤマからまだ出ていない分野を復習。緊張していたので、同期と喋りながら待機。
スーツの人がほとんど。私服の人も少ないがいた。
待機時間の短いグループだったので、待機室は30分もいなかった。待機室からは試験官同伴でお手洗いにいけたが、ドナドナされるといけない
ヤマから出題されて、かなりスタンダードな質問だったので、試験時間が5分ほど余ったが、雑談の雰囲気はなくて、5分無言待機でした。「試験時間は後5分あるので、何か付け足したいことがあれば述べてください。なければ5分待機です」試験官ににこりともしないし、誘導もないし、気持ち的には辛かったですが、点が足りないなら後から振り返って聞かれるかな、と思ったのでお行儀良く、5分待ちました。
結果は11/4に出します、と告知はあったものの、時間の発表はなく、学会HPを何度も見ましたが、繋がらず焦らされました。16時ごろの発表でした。無事受かっていて安心しました。さらりーまん先生、本当にありがとうございました。
60回麻酔科専門医試験体験談:その5
無事に3教科、合格することが出来ました。
今回、体験記を書くにあたり自分が受験生時に欲しかった情報に絞って書いてみます。
●筆記試験
試験会場は五反田TOCメッセでした。会場にはでかいモニター時計がありました。試験問題は冊子形式で書き込みはOK。持ち帰りも可能。
C問題の画像等は過去問のように不鮮明ではなく、画像集をまとめた光沢紙の別冊子が配られます。
解答用紙は短冊みたいに細長い。初見では少しびっくりしました。
昼ご飯休憩無いがA問題で時間余るので途中退室する人が多かった印象です。休憩スペースなどの用意はないため注意が必要です。自分は近くの喫茶店まで歩きました。
筆記試験対策としては、過去問7年分。A,Bは7周、Cは3周したが過剰でした。A問題は初見問題無し。昨年以前の削除問題が3問あり、それ以外はおそらく満点。B,C問題は噂に聞いていた通り意味不明。対策のしようが無い印象。削除問題に関しては過去問にも解説が無く、自分で調べるしかありません。
●口頭試験
ポートピアホテルに前泊。部屋が空いていたためか無料アップグレードしてくれて快適でした。チェックアウトは12時だが、フロントに言えば14時くらいまでチェックアウトを延ばすことも可能です。(2000円/1時間かかる)
口頭試験の集合時刻になると、電子機器類の電源を切り用意された茶封筒に入れるよう指示される。その後、試験が終わるまでは一切触れない。集合場所には時計の用意はなし。試験時間になると、受験番号が若い人から8人ずつ呼ばれ、ドナドナエレベーターに乗り込んでいく。
呼ばれるまでは集合場所で待機。この時に紙媒体の参考書や教科書などは読むことが出来る。飲食も可能。トイレに行く際にはスタッフがついてくる。従業員用エレベーターで8 or 9階まで運ばれ、客室の廊下にある試験部屋の前の椅子に順次座っていく。そこで試験スタッフから症例の紙とボールペンを渡され、5分間症例を読みメモを取る時間が与えられる。
紙はA4用紙で上部に症例の情報。余白は多くメモ欄が足りないということは無さそう。5分のタイマーが鳴ると一度症例の紙とボールペンは回収され、入室の直前に再び症例の紙だけ渡されました。
試験中はその紙を見る事も可能です(見る余裕はなかったですが).部屋には荷物置きがあり、まずそこに荷物を置くように伝えられる。
「受験番号とお名前をどうぞ」→「では席にお座りください」→試験官の先生の自己紹介→「それでは早速始めます」という流れ。
口頭試験の本番では、質問文はモニター等には一切表示されません!!!
モニターに表示されるのは過去問のスライドや画像のみです。
自分は事前練習で質問文を眺めながら答える練習をしていたため、本番のこの状況にかなりパニクってしまいました。
試験後、冷静になって思い返すと言いそびれた項目がいくつもあることに気付き、かなり凹みました。知識はあるのにそれを本番で発揮出来なかったことに対する悔しさが残りました。しかし緊張のせいで実力が発揮出来ないのは他の受験生も一緒です。緊張感の中でも自分の実力を発揮出来るよう、試験前のシミュレーションは目上の先生にお願いするといいと思います。
友人と練習するのは気楽ですしアウトプットの練習にはなりますが、本番の緊張感には遠く及びません。
60回麻酔科専門医試験体験談:その6
無事合格することができました。ありがとうございました。
口頭試問の体験記を書かせていただきます。(検査値などの具体的な数字はあやふやです)
朝一から●番目の枠だったので、ポートピアに前泊することにしました。自分の日程が判
明した後に麻酔科学会のサイトから予約して2万円弱でした(シングルルーム朝食付き)
朝食は通常7時からのようでしたが、10月29-31日のみ6時半から、となっていて、受験生や試験官の先生に配慮してくれているのかなと思いました。
朝食ビュッフェは非常に美味しくて、レストランの景色も良くて、朝食付きにしておいて
よかったです。ちょっと食べ過ぎましたが。
●時集合だったので10分前に会場に行きました。他の受験生も既に結構入っておられました。みんなスーツだったのでスーツで来てよかったです。
コロナの紙を提出して、ストラップをもらって、中へ入って椅子に座りました。PC、スマ
ホなどは電源切って机の上の封筒に入れて鞄の中に、とのことで、待ち時間それで勉強してもいけないとのことでした。鞄がない人には、紙袋が用意されていました。 教育委員長の先生からお話で、場を和ませようと「北野天満宮でみんなのためにお守りを買ってきました」と見せて下さっていました.その後説明してくれる方が何故かカタコトでした。
●時に第一陣が出ていって、●時に第二陣(自分たち)が案内されました。その際は紙
媒体の勉強道具も鞄に入れ、上着含め全部持って退室しました。
例の裏のエレベーターで8階へ。アルファベット順に並んで廊下の椅子に座りました。左右
の部屋は一個飛ばしになっていました。アクリルの衝立があって隣にスタッフの方が座っ
ていました。
少し待って、スタッフの方が一斉に説明を始めましたが、他の皆さんも近いので廊下全体
がざわざわして聞こえにくかったですが、内容は例年通りでした。
紙を渡されて、5分見て、渡されたボールペンでメモを書き込んで良いとのことでした。
後半しどろもどろでしたが、終始試験官の先生方がうなづいてくれたり、優しいリアクシ
ョンだったので助かりました。
長文駄文で申し訳ありません。少しでも皆さんの参考になれば幸いです。
60回麻酔科専門医試験体験談:その7
大変お世話になりました。お陰様で、筆記、口頭、実技ともに合格することができました。
以下、体験談です。
①筆記:4月から過去問開始。1冊終えるのに2か月かかりました。平日は帰宅後は一切勉強せず、週末は9月中旬から行動制限して勉強に集中しました。最終的に過去問5年5周、A問題のみ7年分を全問暗記するつもりで何周もしました。当日はA問題は余裕を持って回答できましたが、B,Cはまるで手ごたえなく終わりました。どうせみんなできないだろうと割り切っていたため不安はありませんでした。
②口頭:筆記が終わるまで何も対策はしていませんでした。筆記から口頭までの数日間で青本、過去問を見て、同期と何度か練習をしました。もう少し早くから対策していればより安心して受験できたかもしれませんが、結果的にこの期間でもなんとかなりました。
会場となるホテルには前泊しました。当日はロビーに受験生がたくさんいましたが、だいたいの方がさらりーまんさんの過去問を読んでいた気がします。
集合時間になり前室に集められました。時間がくるとスタッフに番号を呼ばれ、試験会場となるホテルのワンフロアにエレベーターで連れていかれました。今年は受験生が2学年と多かったせいなのか例年通りなのかわかりませんが、試験部屋はたくさんありました。(10部屋くらい?)
自分の部屋の前に連れていかれ、問題を確認。5分間タイマーで測られ、その間にメモを取りました。時間が来ると部屋に通されます。面接官2名、スライドを使って進められました。出題の順番は正確には覚えていないですが、以下の通りです。
部屋に入るまでは元気があれば大丈夫だろうと思ってましたが、途中で答えられなかった項目があったり、面接官の一挙一動に進むごとに徐々にメンタルが削られ、まったく手ごたえがないまま終了し、ああ落ちたなと思って部屋を出ました。
来年もまたここに来るんだと覚悟を決めていましたが、どうにか受かっていました。二度と受けたくありません。
最後まで諦めないこと、間違っていてもいいからとにかく発言すること、相手の目を見て話すことを守っていれば、たとえ質問の答えがわからなくてもなんとかなるのかもしれません。
さらりーまんさん、本当にお世話になりました、ありがとうございました.
60回麻酔科専門医試験体験談:その8
3科目とも合格を頂きました。
筆記試験
4月頃〜過去問5年分×3周で勉強
直前1ヶ月までは中々身が入らず最後に慌てる形になりました…
よく間違える問題は青本を通読しましたが、全部は読み切れませんでした
試験は神戸会場で受験、前泊(ポートピアホテル)だったので当日は時間に余裕がありました。
誓約書(COVIDに関する)を提出し、検温を行い、マスクを着用して会場入り。
前方に大きくスクリーンで時計が表示されていました。前の方の席なので腕時計を持って行きましたが、スクリーンでも時間は確認できました。ただ後方の席の場合は見えにくい可能性があるので、時計は持参するべきです(apple watchは禁止です)。
しかし合間で昼食を食べる時間がないので、しっかり朝ご飯を食べていったほうが良いと思います。おにぎりやサンドイッチ・ウイダーインゼリーをたくさん持っていきましたが、結局トイレを除いた休憩は5分程度で、会場の自分の席で、おかしを摘まむくらいしかできませんでした。
会場の温度はちょうどよかったですが、着脱可能な上着があった方が対応しやすいと思います。
試験は途中退室される人が3割くらいいたようですが、私はマークの確認などをしていたら時間いっぱいかかってしまいました。
B問題は全く歯が立たずに焦りましたが、A,Cは過去問の知識で解ける問題が多いです。過去問の他の選択肢などももう少し掘り下げて勉強していれば本番焦らずにすんだのに…と後悔していますが、合格でほっとしました。
口頭試問
1日目のスケジュールでした
(おそらく、1日目が新専門医機構受験者、2日目が旧専門医制度受験者の初年度受験、3日目が浪人生…だと思います)
前泊はポートピアホテルで、なんと7:50集合。ホテルは試験終了後のチェックアウトで余裕で間に合いました。
誓約書提出と、検温を行い、40人ほどが同じ部屋に待機。電子機器切って袋にいれます。鞄が小さい人は、紙袋の貸し出しなどもあり、親切な対応でした。
試験中に携帯が鳴った人は強制退室になったのを見たと先輩から聞いていたので、何回も電源は確認しました。
そこから6人ずつ呼ばれていき、例のドナドナエレベーターへ。
ホテルの客室をワンフロア貸し切りで試験でした。
廊下の椅子に座り、問題用紙を渡され、5分メモの時間。
さらりーまんさんのまとめ本で効率よく勉強出来て合格を頂きました。ありがとうございました。
60回麻酔科専門医試験体験談:その9
<試験対策>
私は4月ごろからパラパラと勉強を始めました。勉強量は結果的に過去問7年分5周、青本2周、猫の巻1周、口頭試験対策本2周、麻酔科合格トレーニング2周行いました。
勉強のスケジュールとしては開始はゆっくりで、過去問を1周終わったのが7月下旬でした。そこから自分が合格基準に達するのに危機的状況であることを把握し、ようやく8月から本腰入れて勉強を始めました。過去問3周終わった段階で1度青本を一周、そして再び過去問2周して、最後に青本を一周しました。
<筆記試験>
まず、スケジュールが分かった段階で昼食用の時間が無いことに驚きました。当日はA問題は試験時間が余るのでその時間を利用して持参したパンを会場のホテルの隅っこで食べました(行儀が悪いかなーと思ってこっそり食べてました。)
A問題:過去問。しっかり過去問やっててよかったーと気分上々で退室
B問題:い、一問目から全く分からない新作問題。次のページこそは過去問ベースの問題であれ!!とページを捲るも、結局ページを全て捲り終わるまで新作が出続け終了。手応えの無さにすっかり意気消沈して、涙目で終了。
C問題:B問題の出来なさ具合のショックを引きづりながら開始。折れた心を必死に励ましながら回答。最後までB問題での動揺を引きづりながら終了。
<口頭試験>
筆記が日曜日にあり、次の金曜日が試験日でした。
同じ時間帯の待機グループの中で1番初めに呼ばれました(8−10人くらいが一緒に呼ばれたような気がします)。
事前情報通り、試験部屋の前の廊下で待機中にペンと問題が書かれた紙配られました。5分時間が与えられたので、麻酔方法、問診で聞きたいこと、注意すべき合併症など予想のつく限りメモを書きました。時間が経つと1度紙は回収されました。部屋に入り、試験が始まるとメモを書いた問題用紙が再配布されました。
<合格発表>
最後に、合格発表は口頭試験日の翌木曜日でした。昼ごろから麻酔科学会のHPが重くなり表示エラーが頻発しました。15時頃まではアクセスに成功しても結果は出ていませんでした。最終的に17時ごろアクセスに成功して、結果を知ることが出来ました。口頭試験は受かると思っていましたが、筆記に関しては全く自信がなく、5割くらいは落ちるかなと思っていました。結果的に全て合格していました。
口頭・筆記ともに青本がとても役に立ちました。ありがとうございます。
今後受験される先生方の合格を願っています。
60回麻酔科専門医試験体験談:その10
【勉強内容】
<筆記対策>
・さらりーまん麻酔科医先生の青本に一通り目を通した
・過去問直近5年分×3周(A,B問題のみ5周程度)
6月ごろから青本をなんとなーく読み始めました。なにせページ数が多いので移動の最中や麻酔中に気楽に目を通す感じ(難しいところは飛ばし読み)で、一度はすべて目を通したという状態にしました。知らなかった知識も得ることができ、読み物としても面白かったので苦ではなかったです。だらだらと一通り目を通すのに2か月近くかかりました。その後は辞書として使用されることになりました。
8月ごろから過去問を始めました。とりあえずA-C問題を解いた(というより暗記)しました。はじめは意味不明で時間がかかりますが、3周する頃には瞬殺で答えが見えてきます。
何回解いても結局間違える問題は決まってくるので、携帯に保存して試験前に見ることにしました。
<口頭対策>
麻酔科学会ホームページにある過去問7年分を自分なりに回答してみた・さらりーまん麻酔科医先生の緑本で足りないところを補足した
試験の2週間前になり初めて口頭試験対策に入りました。似たり寄ったりの質問も多いのですが、日ごろ馴染みのない症例の麻酔に関しても出題があったので1日1年分するのにも苦労しました。
筆記試験が終わってからの1週間もありますが、麻酔器の始業点検が出たらオワルなとか、前年度フォンタン術後の症例が出題されたし他の先天性心疾患術後の血行動態についても復習しておいた方がいいかなとか、欲が出はじめて時間が足りなく感じたので、もう少し早くから対策を立てていてもよかったかなと思います。
【筆記試験】
神戸会場。22℃/10℃曇り。室温は薄手の長袖で暑くもなく寒くもなくという感じでした.
服装はフォーマルな方からラフな私服の方まで様々でした。
受験者数は400人ほどで、1部屋に収容、1台の長机に1人が座りました。A問題90問(105分)、B問題55問(100分)、C問題55問(110分)と、例年と同じような感じでした。各問題間の休憩時間が15分しかないのと試験終了30分前になると途中退室不可になるので、余裕のあるA問題で途中退室し、食事を兼ねた長い休憩を取りました。
B問題は安定の意味不明さで1問目からにやつき(なにも分からないぞ)が止まりませんでした。そして終わったあとの手応えのなさ。例年の体験記にもあるように毎年ほとんどの方がそういう感じになると思うので落胆する必要はないと思います。C問題でなんとかなると考えていたのですが、本年度から試験作成委員の先生方が変わった(と後から聞いた)影響なのか、C問題の毛色が例年と変わって選択肢が若干B問題チックな臭いがしました。
会場でも試験後に同様な雰囲気が流れていたような気がします。やはりほとんどプールのA問題をいかに落とさないかが鍵になるかと思いました。
【口頭試験】
フォーマルからセミフォーマルな格好の受験生しか見かけなかったです。
試験の1時間ほど前に待機室で説明が行われます。それ以降は電子機器の使用ができなくなるので、直前まで資料に目を通したい場合は紙媒体を持ち込む必要があります。鞄は試験会場まで持ち歩くことになります。
時間になると10人ぐらいずつ受験番号が読み上げられ、待合室の外に1列に並び、俗に言うドナドナエレベーターに案内されます。各フロアでまた並びなおし、客室の前に設置されたパイプ椅子へと各人誘導されます。座ったあと、案内係の方から簡易な説明があります。その後、ボールペンとバインダーに挟んだ設問用紙(症例提示)が渡され、5分間見ることが可能です。書き込みも可能です。5分後にいったん係の方に預けますが、入室時に再度用紙のみ手渡され試験中も見ることができます。用紙は退室時に返却します。
試験場所は客室で、2名の試験官の先生と対面。右手にテレビモニターがあり、設問の状
況進行とともにスライドが表示される形式でした。試験時間は各人20分です。
———————————————————————————————–
試験後に10分近く時間が余る。ここで合格を確信する試験官の先生からの「よく頑張っていますね」などから始まるいわゆるピロートークは発生せず。早く終わってもこちらから話しかけることができませんので、とお心遣いの言葉をいただきました。前のスライドでも見ますか?前の質問でなにかこれを答えておきたかったということがあれば言ってください、となりましたが前の質問の答えが、次のスライドで表示されていたり、そもそも質問され
た内容をそのときははっきり思い出せなかったりで、ほとんど新たに答えることはありませんでした。
ただ、最後の質問への回答が的を射ていなかった雰囲気しか感じなかったので再度質問をお伺いしました。
例えば、先生は術後回診とかやりますよね。どんなことを見ますか→痛みの程度やどのような痛みかとか(やはりうーん?感)
————————————————————————————————
考えてもどういうことを答えるのが良いか思い浮かばないまま試験が終了しました。あとから振り返ると例年までにみられたザ接遇のような問題はなく、最後の質問はすぐに投薬云々の話ではなく、患者さんへの問診や身体所見を取るなど、接遇に近いことを聞いていたのかなとも思いました。
【その他】
さらりーまん麻酔科医先生の対策本を、受験年の4月に購入させていただきました。
青本は自身が今後も辞書としても使用でき、また手術室で働く他職種の方にも興味を持ってもらえると思いますし、是非見てほしいものです。
緑本は独立して口頭試験用になり、コンパクトで大変便利でした。また、webでも拝見できるのでこれも役立ちました。
口頭試験が10月末でしたが10月初旬に口頭試験対策の別の著書が発売されたということで世間はざわついていたようです。そちらはオリジナル問題に解説を加えることでレベルアップを図れるものとなっています。
試験の傾向をつかむためにも過去問には目を通される方が多いと思います。それに対する回答例を示してくれいている緑本はやはり手元に一冊あると心強いと思いました。
以上、長くなりましたが参考になれば幸いです。
60回麻酔科専門医試験体験談:その11
A問題
全て過去問。私は過去6年分を3周しました。その際間違えた問題には印をつけ、3周後は複数回印のついた問題だけに絞って完全に覚えきれるまで何度でもやり直しました。
B問題
例年通り、ちんぷんかんぷんでした。自信もってかけたのは2割いかないぐらいだと思いましたが、結果半分ぐらいは取れていたと思います。
C問題
私には難しく感じました。こちらのほうがB問題より取れていないかもしれません。
試験の間は15分しかありませんでした。試験終了15分前からは退室できなくなるため、終了の20分前には退室しようと思っていました。
今回は2学年同時受験だったため、トイレなどの混雑を避けるためと、間に外気に当たって何か食べたかったからです。
A問題、B問題は1問1答形式のため、しっかり時間を余らせて、マークミス、計算ミスのないことを3回確認して外に出ました。
前日にパンとチョコレート、飲み物を用意していたので、間で食べました。かなり集中力を使うので、気分転換ができたことは大きかったと思います。
C問題は難しかったのもあり、時間ギリギリまで試験に取り組みました。
終わった後は疲労困憊でした。
口頭試験:(うろ覚えです)
集合時間に所定の場所に行くと40人くらいの受験生が集まっていました。
一人ずつ決められた席に座り、呼ばれるまでは資料など見てもよかったのですが、試験の説明時に携帯電話やタブレットなどは電源を切って用意されている封筒にしまわなければならないので、最後に見たいものは紙媒体にしておくことをお勧めします。
かなり緊張してしまい、本番はものすごく震えていたと思います。
試験官は男性2人。一人の先生が問題を出し、答えていく。もう一人の先生はPCに向かってポチポチしていたので、その先生が採点していたのではないかと思います。
お二人とも私の緊張を解こうと和やかに進めてくださり感謝しています。
時間はかなり余りましたが、談笑などは特になく、沈黙が3分以上続いたと思います。(笑)
初日に終わったので、他の方に比べると楽だったかもしれませんが、筆記試験後の勉強時間は4日しかありませんでした。
悪性高熱症候群や局所麻酔薬中毒など、ガイドライン上で診療の手順や薬剤投与量か規定されているものは確実に覚えました。
意識下挿管などは施設によってある程度やり方が違うので、大体の流れが言えるようにしておけば十分かなと思いながら練習しました。
すべての試験が終了した次の木曜日に合格者発表がありました。
試験後は時間がたてばたつほどあれも言えばよかった、これも言えてないというのがどんどん出てきて数日間はそわそわしていました。
筆記試験・口頭試験ともにポートピアホテルに前泊しました。移動がないので気持ち的に楽でした。試験前日はシングルはかなり早くに埋まってしまいますので、早めのチェック・予約がおすすめです。
60回麻酔科専門医試験体験談:その12
【勉強】
筆記試験は4月から勉強開始。
過去問7年分(第53回~59回)やりました。1周目はとても時間がかかりましたが、2周目以降はどんどんスピードがあがりました。試験2週間前からはA.B問題のみやり、ほぼ答えを暗記している状態になりました。
口頭試験は約1ヶ月から勉強開始。
緑本を3周ほど読みました。また、麻酔科学会が出しているガイドラインを読み、局麻中毒や悪性高熱症、産科出血の対応などは覚えておきました。
【筆記試験】
前日はホテルに宿泊。試験会場の下見をしようと思いましたが、シャッターが閉まっていて近くには行けませんでした。
朝食は8時半頃に行くとレストランのブッフェは混んでいたため、早めに行った方がいいかもしれません。和食のお店も開いていたためそちらに行きました。(宿泊客が多い日は開店するらしいです)
当日は10~11時集合、入場時に誓約書の提出や体温測定がありました。11時から注意点の説明があり、11時20分に試験開始。
前に大きなデジタル時計が置いてあり、その時計で試験時間が設定されていました。室温は適温でした。机は横長で1人1つずつあり、広々と使えました。
休憩時間は試験の間に15分ずつしかなく、昼食休憩もなかったため、多くの人がA問題を早めに終えてホテルのロビーで食事をとっていました。休憩時間内なら、試験会場でも飲食は特に制限はありませんでした。
試験については、A問題は過去の削除問題から3問出ていましたが、それ以外は全て分かりました。ほぼ、過去5年以内から出ていたように思います。B.C問題は全然手応えありませんでしたが、周囲も同じような感じでした。
【口頭試験】
筆記試験同様、前日はホテルに宿泊。試験が午前中だったため、朝7時頃にレストランのブッフェに行くとかなり空いていて、ゆっくり朝食をとることができました。(試験前のため精神的には落ち着きませんでしたが)
集合時間少し前に集合場所に行き、誓約書提出と体温測定。注意点の説明があり、試験時間まで待機。時間になるとエレベーターにのり宿泊部屋の1室へ。部屋の前で症例の紙とボールペンが渡され、自由に書き込み。5分後に回収され、前の受験生が出てきてしばらくしたら部屋に入室。2人の試験官の先生が正面に座っておられ、右手にスライドが表示されていました。荷物を置き椅子に着席したら試験開始となりました。部屋に時計はありませんでした(見つけれませんでした)。
試験の雰囲気は淡々と進んでいく感じで、圧迫面接のような雰囲気はありませんでしたが、誘導などの助け舟も一切ありませんでした。
とても緊張したため、スライドに表示されている内容が処理しきれませんでした。そのため書いてあった細かい内容はあまり覚えていません。また、問題もどのくらいあるかわからなかったため、時間切れになったらまずいと思い、何回も腕時計を見てあと何分か確認しました。緊張と時間切れになるかもという焦りで後半は自分でも何を言ったかあまり覚えていません。
前半は1問1答のような形式だったためテンポよくいけたと思いますが、後半の方は自分が話終えると「もういいですか?」と聞かれ不十分なんだと思いつつも他に思いつかなかったため、次の問題にいきました。
結果的には5分ほど時間が余りましたが、雑談は一切なく沈黙のまま終わりました。
後で振り返ると試験内容は過去問と比較すると簡単な方だったのではないかと思いますが、手応えは全くありませんでした。
【結果】
3科目とも合格。特に口頭試験は不安しかありませんでしたが、結果的には合格でした。口頭試験に関しては、ほぼ緑本でしか対策していませんでしたが合格することができてよかったです。
ありがとうございました。
60回麻酔科専門医試験体験談:その13
●月に出産を控えていたので、筆記試験の勉強は産休から始めました。最初全く答えが分からず調べるのに時間をかけていましたが、まずは過去問全体を見て答えを覚えるのが先だなと後悔しました。覚えるのが遅いので、何回も過去問を繰り返し、不安な問題は書き出しました。余裕が出てきたら、大事なガイドラインを何度も見てました。今年は去年の採点除外から出てて、確認してなかったので後悔しました。
口頭試問は、息抜きにサラリーマン先生の本をみて勉強してました。私は経験症例が少ないので、口頭試問の過去問だけの冊子でなく、青本も読ませてもらいとても参考になりました。
本当にサラリーマン先生のおかげです、ありがとうございました!
本番で後悔したこととして、試験官のいる部屋に入った後、名前と受験番号を確認されましたが、すでに鞄に受験番号のわかる用紙をしまっていて最初からワタワタしてしまいました。次の受験者には気をつけてもらいたいです。
試験官が優しい方で、時々頷いてくれました。聞き手役としてのただの頷きかもしれませんが、ポイントの高いところだったかも知れないです。
試験対策としてまとめていただき、試験勉強の参考になるだけでなく、今後の臨床の勉強にもなりました。
おかげさまで無事3科目合格しました。
本当にありがとうございました!!
60回麻酔科専門医試験体験談:その14
おかげさまで無事合格することができました。
筆記試験は各所で言われている通り、直近5年分を3周と、何度も間違えるところをプラスで2周ほどやりました。
A問題はそれで大体9割はカバーできたような手応えでしたが、BとCは自信無かったです。
口頭試問は筆記試験終わってからさらりーまん麻酔科医さんの緑の本を読んで、友人と試験官ごっこ(笑)をしてアウトプットの練習を少ししただけです。
部屋に入る前に簡単なシナリオを渡されて、5分ほど読んで書き込む時間がありました。
試験官は2人で、1人が質問担当、2人目はパソコン画面見てチェックを入れていた感じでした。そちらの人はほとんどしゃべりませんでした。
ここ数年、外科医やICU担当医、家族なんかに説明する問題があったのでこれはきっと挿管困難で動揺歯折ってしまってICしろって言われると思ったけど全然聞かれませんでした…
()内は私が答えた内容です。
60回麻酔科専門医試験体験談:その15
お勉強のやる気がなかなか出ず結局8月中旬辺りから勉強し始めました。ますばA問題だけ一周してその後ABC問題含め3週程度したと思います。大体四日に1冊見るペースでしました。麻酔中と帰宅後平日は1-2時間土、日は3-4時間勉強したと思います。遅くなって勉強し始めたので本を買ったものの見る余裕はありませんでした。
本番ではA問題は8割は正解したと思いますがB,Cは2割は正解できたのかなぁと感じでした。
口頭試問に関してはさらりーまん麻酔科の口頭試問対策本を10月辺りから過去問を声を出して読んでいました。時間に余裕がある時だけ読んでたと思います。ベースの知識で分からない所は少し他の教科書も除いたりしましたが基本対策本しか読んでません。
本番は緊張のあまりにメモした事実を忘れてメモは見ませんでした。
詳しい回答は全く出来ませんでしたが合格しましたので多少答えられない項目があっても最後まで何か話せて辿り着けたら合格なのかなぁと思いました。
60回麻酔科専門医試験体験談:その16
この度はお世話になりました。おかげさまで無事に全分野合格しました。
以下に簡単ではありますが、体験談を記載します。
1.筆記試験に関して
対策としては、7年分を5周から7周くらいしたと思います。
■A問題
直近のB問題からの出題も多かったですが、過去問をしっかりやれば対応は容易かと思います。ただ、削除問題が3題程あった記憶があり、今後は削除問題も独自で調べて勉強していく必要かあると感じました。
■B問題
難しいの一言。過去問から得た知識で対応こんな問題が多いですが、皆同じであり、過去問しっかりやって答えの暗記だけではなくある程度理解しておけば、合格点は余裕かと思います。
■C問題
今回のC問題は難しかった。今年は難化した印象。
選択肢を絞り込みきれない問題が多く、手応えはあまり良くない。
B問題同様、過去問と日常臨床をしっかりやっておけば合格点は余裕かと思います。
60回麻酔科専門医試験体験談:その17
おかげさまで3科とも一発合格しました。ありがとうございました。
問題のことなどはほかの方が詳しく書くと思いますので、それ以外のことについて多めに記載しました。
筆記
過去問をやるのみかと思います。青本は辞書的な使い方をしました。巻末の計算問題まとめも大変役立ちました。私は10月に異動があったので、少し早めに勉強を始めました。5年分を周回して勉強し、去年の過去問を8月ごろ模試的に解いてみたらある程度できたので,自信がつきました。9月は口頭の勉強をして10月に再び過去問を周回しました。Bは難しすぎて途中で帰りたくなりました。
会場は場所によってはクーラーの風で寒く感じた人もいたようなので、冷え性の方はひざ掛けがあると安心です。
五反田会場の女子トイレは数が多くあまり混雑しませんでした。休憩が15分しかなく、昼ご飯の時間がなかったため、皆さんAをさっさと終わらせて退出して軽食を食べているようでした。途中退室しないと休憩時間はトイレ行ったら終わります。(笑)
皆さん普段着で来ていて、スーツの方はいませんでした。時計は前方3か所のモニターに大きく表示されていました。
口頭
アリストンにとまりましたが、ベッドは固いし朝食はおいしくないし(朝食のメインがフライドポテトと天ぷら(笑)、ご飯に芯が残っていたetc)で、強くポートピアホテルを薦めます。アリストン12000円台、ポートピアは17000円台だったかと思いますが、周りの話を聞くにポートピアはグレードアップしてくれたりベッドも寝心地がよく朝食も充実しているようでした。午後受験の方は少し離れたビジネスホテルでも十分かと思います。午後組はチェックアウトしたあと結局ロビーなどで勉強することになるので。
会場では控室に入るとタブレット類を封筒にいれさせられ、以後見ることはできません。30分ほど待機時間があり、紙資料での勉強はOKです。その後職員用エレベータで8か9階までいくと、すぐに部屋の前の椅子にすわらされて問題とボールペンが渡されます。目を通し、問題点などをペンでメモできます。私は緊張でのどが渇いてしまい、お茶を飲んでいいか聞いたところダメでしたので、控室にいるうちにトイレや水分補給は済ませたほうが良いかと思います。
問題は5分で回収され、ほどなく前の受験者が部屋からでてきて、入れ替わるように入室しました。入室の際に先ほど回収された問題用紙はまたもらえます。
試験官は中堅の女医さんとベテランの男性医師でした。女医さんが質問をし、男性の先生が採点していました。女医さんはなかなかクールな方で、こちらが何か言ってもリアクションが薄かったです.最後の質問がおわると、その後男性の先生が解説チックなコメントをし始めたところで外からノックされ退室しました。残り時間わずかだったことにこの時気づき、内心ヒヤッとしました。
試験後話した同期は時間超余った!といっていたのでかなり焦りましたが、その同期の回答は一部間違っていました。試験官によって問題を進めるペースは違いますし、正解が得られなくても進めてしまう試験官もいるんだと思います。余った時間が少なかったりアフタートークの盛り上がりに欠けても心配はいらないと思います。
私は心外の問題だったのですが、はじめは「心外かあ、まあそんな難しくなさそうだしあまり緊張しないだろう」くらいに思っていましたが、いざ試験官を目前にすると本当に緊張しました。
ですが質問は臨床に即したものばかりでしたので、実臨床の経験と知識をもとに着実に答えていけばよいかと思います。
実技 評価用紙の提出
青本は、会場で「あれ、なんだっけ?!」とド忘れしてプチパニックになったとき(意外とありました笑)にすぐに調べられるので持っているとかなり安心でした。口頭試問の回答は自分で作るだけではなく、青本を見ることにより他の人がどうこたえるのかや自分では思いつかなかった回答を把握できるので大変参考になりました。ありがとうございました。
60回麻酔科専門医試験体験談:その18
麻酔科医5年目、1回目の受験でしたが、おかげ様で無事に合格していました。振り返ってみて、もう2度と受けたくない、と思わされる試験だったので、受かっていて本当に良かったです。
医局の先輩方は皆さん青本で勉強されていたので私も自然に購入に至りましたが、本当に助かりました!!!普段から辞書的な感じで使用したり、計算問題の解答が分かり易かったり、(過去問集の解説では理解できないものでも、青本では理解できました!)ガイドライン等もチェックしておくべきものは一覧で載っていて、手間が削減されて有難かったです。
また、ちょこちょこ書いてあるギャグや小ネタに、勉強中の沈みがちな気持ちがほっこりしました(笑)ホームページ上の受験体験談も読ませていただき、勉強法が他の人から大幅に外れていないか、など確認する上で参考になりました。
私も今後受験される先生には是非購入をおススメしたいと思います。(受験会場でもみんな持ってました!全国の麻酔科医から支持される青本すごい…さらりーまん麻酔科医先生は、麻酔科医辞めても印税だけでセレブ生活送れるのではないか、などと勝手に想像していました笑)
【試験勉強を始めるにあたって】
★過去問購入・青本購入は早めに!(4月以降は売り切れてる年度のものもありました)
★受験に必要な単位を満たしてるかの確認、書類集めは早めに!(各単位は、受験の前年度3月までのものが有効であることが多いです。単位の取得漏れがあったことに6月の出願時になってから気づき、結局受験資格が得られなかった知り合いも実際にいましたので要注意。必要症例数のカウントも直前にやると地味に労力取られますのでお早めに。)
★勉強の開始時期は余裕をもって!(個人能力・キャパシティに因るところも多分にあるとは思いますが…自分の場合は日中の仕事+深夜までのオンコール急患業務+家事など、試験勉強以外の日常の疲れやモチベーション低下が予想以上に影響大で、なかなか勉強が進まなかったです。でも、細々ながらでも4月から継続して勉強していたことが、試験直前の焦りの軽減に繋がりました。)
【具体的勉強法】
●筆記:結果的に過去問7年分(A・B:直近5年分は7回以上、6・7年前の分は5回程度。C問題:3回)しました。「問題を解く→答え合わせ(丸覚えではなく、解説もしっかり読む)→青本・各種ガイドラインの関連内容を読む」の繰り返しでした。最初の1・2周目は分からない問題の方が圧倒的に多くて全然勉強が進まず投げ出したくなりましたが、繰り返しやっているうちに自分の苦手分野が自然と分かってきたので、その分野に関しては「
麻酔への知的アプローチ問題集」の問題も解いたりして、周辺知識の補完に努めました。直前期は、ネットからマークシートをダウンロード・印刷して時間を計りながら解いてみたり、実際の形式に慣れる練習をしました。あとは、スマホのアプリ(2000円くらい?200問くらいプールされていたはず)で過去問集が発売されていたので、試験直前の寝る前や移動のときとか、何かしてないと不安な時にはそれをやって気を紛らわせたりしてました。
●口頭試問:過去問ダウンロード→答えを書く→緑本で答え合わせの繰り返し(5年分くらい?)と、上級医の先生と面接形式で練習をしました。実質、筆記試験が終わったあとの1週間での対策でしたが、おそらく問題ガチャがアタリの方だったので問題なかったです。でも、筆記試験の疲れで2日間くらいはまともに勉強出来なかったことや、小児や心外など難しい問題にあたっていたら…と思うと、もっと早くから対策していた方がよかったな、
という反省が残りました。
【試験の感想】
~宿泊場所・会場について~
試験会場のポートピアホテルに前泊。食事は前日夕・当日朝共にルームサービスで注文。(お財布はイタいけど美味しくてラクチン、かつ感染対策になり良かったです。当日に頼むと予約いっぱいで無理な時間帯も多かったので、事前にネット注文しておくとよさそうです。)試験当日の寝坊を過度に心配しなくていい点も良かったです。加湿器のない部屋に泊まったら乾燥がひどくて喉の調子を壊したので、喘息等ある人は注意が必要かもしれません。
当日は検温・コロナに関する宣誓書提出の上で、10時半くらいには試験会場入室。みんなラフな格好。スクリーンに大きく時計が表示されていて、持参した時計はなくても大丈夫でした。また、極端に寒いわけではないけれど、上着・ひざ掛けを持っていってて良かった、と思う温度感でした。昼食の時間がないのも要注意。休み時間には自分の席での飲食可だったので、エネルギーゼリーやチョコレートバーなど食べてしのぎました。トイレは近くに1か所しかなくて混むので、休み時間になったらすぐにいった方がいいです。
~筆記試験~
●A問題:選択肢にひねりが加わっているものはありつつも、過去問さえちゃんと理解して出来るようになっていれば大丈夫。半分くらいの人は途中退室していたような…計算ミス・マークミス(マークシート小さくて、楕円が横長でマークしにくい)に十分注意して解き進めて、ほぼ解けました。他の方もおっしゃってますが、後から振り返って、ここは9割~満点を狙うくらいの気持ちでやらないとB・Cはきついんだな、と思いました。
●B問題:1問目から「なんじゃこりゃ?」と言いたくなる新傾向の問題が続き、順番通りに解いていくと意気消沈しそうだったので、まず全部の問題をパラパラ通読して解ける問題から落ち着いて確実に得点することを意識。でも結局手ごたえ半分くらい。なんとも後味が悪かったです。レミマゾラムやスインプロイク等の新しめの薬に関する問題(私自身はやってないですが、Twitter上の予想問題?とかで話題になってたらしく、それを見てた人は出来たらしいというのを後日知りました。余裕があれば、振り回されない程度にSNSでの情報収集もしてみてもいいのかも…)、吐き気止めのツボ=内関など臨床に即した問題、神経解剖に関する難しめの問題、薬の具体的な知識(HESや胎盤を通過する薬の具体的な分子量)などの問題が印象深かったです。個人的には「過去問やったくらいじゃ、麻酔科学を勉強したうちに入らないぞ!」という麻酔科学会からのメッセージが込められているのではないか?と思わされる内容でした。(苦笑)
●C問題:B問題よりは気持ちが楽になるかと思いきや、またもや「あれ?思ったより難しい…」というのが解き始めた感想でした。正しい選択肢を選ぶ、というのはもちろんそうですが、出題者がどういう意図でその問題・選択肢を提示してきているのか、ということを意識して解答しました。(そうすると連問の1問目は分からなくても、2・3問目は分かるという問題もありました。)カルボキシヘモグロビン血症?メトヘモグロビン血症?の問題、腕神経叢ブロックの詳細なアプローチ法に関する問題には面食らい、こちらも手ごたえは5割5分程度でした。でも、過去問のA・B問題で既出の内容をアップデートした問題も確実に存在していたので、そういった問題で失点しないことが大切なのだと痛感しました。
~口頭試験~
10/29(金)~31(日)の3日間に振り分けられての試験。大体50人くらいの人が同じ時間帯に受験する様子。まず大部屋に集められて、試験本部からの説明・激励(!落とすための試験ではないこと、自分の家族の麻酔を任せられるような、国民の期待に応えられるような立派な麻酔科医になることを期待している旨お話がありました。北野天満宮の合格祈願お守りを見せてくださり、なんだかウルウルしました。)
電子機器の電源を切って、配布された封筒に入れるよう指示あり。(9割5分の人がスーツかそれに準ずる服装。かつてラフな服装で受かった先輩もいましたが(優秀な方なので問題なかっただけかも?)、服装によっては審議になるという噂も聞いていたので、自分はスーツで臨みました。)その後、6~8人くらいずつ呼ばれてドナドナエレベーター→試験室(客室を改装)の前に連れていかれます。試験室の前でA4の問題用紙とボールペンが配布され、5分だけ目を通し、メモをすることが許されます。その後1度問題用紙回収、試験開始時に再度配布されました。時間が来たら入室して、受験番号・氏名を言って着席します。
試験官は男性2人。1人は問題の読み上げと、何か答えたらパソコンのマウスポチポチ(点数づけしてる?)、1人は横で聞いている。追加の問題や、所見は室内のテレビに随時表示されます。終始和やかな雰囲気でした。1つの設問に対して複数回答する必要がある際は、答えている間に自分でも何を話しているか分からなくなってパニックになりましたが、解答の途中でズレたことを言った場合(設問に対する答えになってないときとか)、試験官が引き戻してくれるので、間違っていてもいいから気にせずドンドン答えて良さそうです。そして求められている解答を答えきったら、解答している途中でも次の設問に進められます。(逆に、自分としては答えきったつもりでも次の問題に進められない場合は求められている解答ではないので、追加で解答する必要あり。)あと自分の場合は、答えたい内容があっても専門用語が出てこず、それを正直に試験管に伝えたら、「専門用語じゃなくていいから、普段外科医と話しているような感じでフランクに答えていいですよ。」とおっしゃって下さってありがたかったです。ま
た、答えを言うときはその根拠も述べながら解答すると、試験官もうんうん、と頷きながら聞いて下さっていた印象です。(例:「硬膜外施行・腎機能低下があるので、5日前からダビガトラン休薬」、「体重45kg、肝機能は問題ないので、アセリオは15mg/kgの○○㎎使用」など)結果としては、5分程時間が余り、少し雑談もありました。「何か言い残したことは?」とか「どんな麻酔科医になりたいですか?」など聞かれました。←はじめ、設問の続きかと思って答えに悩んでいたら「これは問題ではありません(笑)」とのことでした。(笑)
60回麻酔科専門医試験体験談:その19
今年は口頭試問のみの受験でした。
8月半ば辺りから、昨年購入した青本を気が向いた時に捲り始めたと思います。
まず全容の把握と、“こんなのもあったな”と思い出すことに費やし、9月中旬より、少しずつ勉強する量と集中度を高めて試験対策をしました。頻出する項目については、診断基準や投薬のdoseに関して隅々まで把握し、記憶するようにしました。そういったものは日常診療の中でもよく遭遇し、そこまで苦にならず勉強できたと思います。
しかし勤務先で実施されていない手術や、経験のない手術に関しては勉強の難易度は上がり、かけた時間に比して身につく事柄はどうしても少なかったように思います。
そのため、試験対策として、丸ごと切ってしまえたら楽だなと思う分野もありましたが、これまでの傾向を見るとそれは得策ではないと感じて止めました。深入りはせず、要点を抑えることが肝要だと思います。
青本はそういったあまりなじみのない分野(小児心臓血管外科や、ペインなど)に関して要点が簡潔にまとまっており、コンテンツを何度か読めば押さえておくべきポイントが把握できたことが、とても素晴らしかったと感じます。時折参考文献なども示してくださるのもありがたく、青本のみでは掴みきれない部分は、参照先などを頼りに理解することに努めました。
最初は、過去問の解説だけを読んでいましたが一問一答も役に立つと気が付き、筆記試験対策のページもさらさらと読むだけでも記憶の定着にとても良かったので読んでいました。
−他、役に立ったと感じたこと
・研修医とあたる症例で、その症例の問題点や関連する知識について、ある程度の水準で指導することを目的に前もって調べる
その上で実際に話して、教えることは自分の記憶の定着にとても良かったです
・他科の先生が研修医にしている指導をぬすみ(!)聞きしたり、ふとした時に術式や患者管理に関するちょっとした疑問を聞いてみる
・ガイドラインは前もってざっと読んで要点のみ把握しておく
60回麻酔科専門医試験体験談:その20
この度無事に合格いたしました。先生の青本のおかげです。ありがとうございます。
以下感想です。
筆記試験
3月くらいからダラダラ過去問開始しました。本腰入れたのは6月くらいからで最終的に過去問6年分をAB5回C問題3回解いて直前に不安に駆られて7年目をAB問題だけ2回解いて臨みました。
C問題は難化、Bは例年通りかと思います。
A問題9割以上取れないと他での巻き返しはよほど普段から薬剤の添付文書読んでいたり幅広く勉強する癖がついている人でない限り無理ではないのかと思います。
あとは不適切問題や採点除外問題からも出ているので解答を作っておくことをお勧めします。
口頭試問
9月から筆記試験と並行して青本とガイドライン中心に勉強しました。青本は一周しかしませんでしたが、わたしの周りは2周した人が多くすこぶる不安なまま臨みました。
朝イチの組でした。
噂のドナドナエレベーターに乗ってホテルの廊下で降ろされて各々試験部屋の前に案内されます。時間になると受験生に1対1で付いてる係の人から一斉に注意事項が伝えられるので少し困惑…
問題文を裏返し渡されます。
問題文は以下
今年の口頭試問の合格率は8割弱、筆記試験は9割だったので口頭試問の対策も筆記と並行して行なっていく必要があるかと思います。
60回麻酔科専門医試験体験談:その21
さらりーまん先生、大変お世話になりました。
無事に60回麻酔科専門医試験を合格することができました。
以下、簡単に感想・体験談を書かせて頂きます。
・筆記試験はやはり過去問、特にA問題をいかに取りこぼさずに得点できるかが引き続き重要でした。私は6年分暗記できるくらいまで解きましたが、見たことのない出題は無かったと思います。B問題は例年通りほぼ新作、難関なのは通常どおりでしたが、今年はC問題も難化したように感じられ、自信をもって回答できたのは3、4割程度の体感でした。心外からの出題が多かったほか、二酸化炭素吸着剤の組成や脳波解析など掘り下げた問題が多く苦戦しました。自信を持って答えられた部分も、過去の類問によるところが多かったので、マニアックな設問に気を取られすぎず、皆が解ける部分を確実にとっていく姿勢が重要だと思います。休憩時間はほぼ設けられていませんでしたが、A問題を早めに終えて退室し昼食をとりました。15分休憩の間はガイドラインを眺めていましたが、そこからの出題もありました。
・口頭試問対策は、青本の口頭試問パートを使用しました。約半年前から筆記試験対策の合間に過去問を解くことから始めました。時間をはかり、正答部分を隠して声に出して回答する練習をしました。苦手な分野については青本の厚い方に分野別にまとまっているので、そちらを重点的に読んで補いました。
会場はスーツの方がほとんどでした。口頭試問の待機場所ではスマホ・タブレット端末が使えないので、当日も青本の薄い方を持参していきました。
私の試験官からは、答えに詰まっても特に誘導などはありませんでしたので、完全に答えられなくてもある程度詰まってしまったら次に進んでもらいました。とても緊張しましたし、前泊もしたので長丁場になり大変疲れました。直前は体調や気持ちの管理に努めました。
・試験1年以内の出産だったため、準備は1年前くらいから過去問を眺める感じでスタートしていました。夏終わりに復職し、麻酔の合間に勉強していました。とにかく時間はありませんでしたので、効率よく勉強できるさらりーまん麻酔科医先生の参考書にはとても助けられました。オンライン版も、子供を抱っこしながら勉強することができてかなり隙間時間を利用するのに役立ちました。
60回麻酔科専門医試験体験談:その22
青本、筆記試験会場でも持っておられる先生方がたくさんいました。
試験後に医局でこのことを他の先生方にお話してたら、3つ上の先生が「僕青本持ってなかったけどみんなけっこう持ってて焦ったよー」って言っておられました。なんかもう、持ってるだけでアドバンテージを感じました…!
逆に言うと、青本のこと知らなかったら、持ってなかったら、当日になってめちゃめちゃ焦ってただろうなと思います。会場で青本を持っておられない先生方は、自分でまとめたノートを見返しているようでした。今振り返っても、正直、ノートにまとめる時間なんてなかったです。覚えが悪いところは少しノートにまとめましたが、ほとんどは青本に書き込んだので、ノートにまとめるのは数ページで済みました。
口頭試問の会場でも、緑の本を持っておられる先生方を何人も見ました。最後の最後に見返すのにも、見やすいし、ポイントまとめて書いてあるし、読みやすいし、さらりーまん麻酔科医先生のコメントもあるしで、戦うのには十分すぎました!
青本にはかなり書き込んだし、今回の試験勉強でいろいろたくさん学んだので、これからも、普段臨床してて、過去の試験問題にはあったけどどんな内容だったか忘れちゃったー、とか、その疾患と麻酔の全体を軽く把握するのとか、あらためて勉強するときの、さらっと思い出すのとかに使わせていただこうかなと思っています。
さっそく入局1年目の先生方にも青本のこと教えました笑 私は青本のこと知ったの去年の夏頃でしたが、下の先生方にはぜひ今のうちから青本というのがあるということを知っておいてほしかったので。
私は機構専門医の方なのでまだ満4年経ってないし、なんなら来年の春に満4年を迎えたとしても、専門医って名乗るには知識も技能も経験も全然足りないと思うので、今回の試験合格に満足せず、日々の臨床でたくさんの症例を経験して、勉強していきたいと思います。
この度は青本を通してさらりーまん麻酔科医先生にたくさん助けていただきました。本当にありがとうございました。専門医になるべくこれからもがんばります!
60回麻酔科専門医試験体験談:その23
●筆記
3年前から少しずつ対策を始めました。
子育てで清書を一から読む勉強時間が取れなかったので、第58回青本を買い日々の麻酔計画・対策のポイント辞書的に利用させていただきました。それぞれの術式のポイントが整理されていたので、試験対策を超えて勉強になりました。
過去問集は最終的に5年分と遡って2年分ABを6周しました。2年前から解き始めましたが、とくに一周目はちんぷんかんぷんすぎ&これは早く解きすぎても忘れると悟り一旦やめました。結局は1年前から再スタートしました。4月に最新の第60回青本をゲットしたので、一問一答として片っ端から読み潰そうとも思ってトライしましたが、だいぶ古い問題も入っているので効率が悪いかもと気づき途中で断念し、苦手分野の辞書的+まとめとして使いました。一周目はとにかく辛いですが、なんとなく全体像が見えると思います。
とにかく過去問命です!A問題をいかに落とさないか、それに尽きると思います。本番で解く初見のBC問題はわからなさすぎて笑っちゃうくらい精神をえぐってきますが、それに耐える試験だと思って諦めずに最後までやりました。
会場は東京で、今年度はTOCの一ヶ所だけだったので、久しぶりに同期や大学の同級生に会えて無駄にテンション上がりました。笑
会場は11時集合〜C問題試験終了17時25分で間の休憩は15分と短いです。とにかく疲れます。合間につまめるおやつと水分は必須です。
設備的に困ることは特になかったです。
●口頭
筆記と並行で少しずつ対策、が理想ですが、3ヶ月前ともなると筆記を落としたくない不安と膨大な問題を前にした虚無感からなかなか手につかず。時々気が向いたときに「さらりーまん口頭試問対策(緑本?)」をぱらぱらめくるのが精一杯でした。
終わってみての反省ですが、口頭試問対策はもちろん日々の麻酔にも直結しますしC問題対策(一部ですけど)にもなるということ。細かい数字を覚えるのは直前でも間に合いますが、やっぱり毎日の麻酔をいかに一つ一つ理由を考えて繰り返し調べて真面目に取り組んでいるか、だと思います。
あとは頭では分かっていても実際に誰かにスムーズに説明することは難しいので、上司や同期に口頭試問の模擬をやってもらい声に出す練習はおすすめです。
いかに理解していないかという現実を突きつけられるのが怖いですけど。
あとは突然9月末に発売された「麻酔科専門医合格トレーニング(水色本)」という口頭試問対策本がヤマらしいと噂を聞いて慌てて買って直前の5日で読みました。問題としてはけっこう難しのも入っていてビビりました。
3日間のうち2日目の午後一番、まずは50人?くらいの中部屋に集合させられ、iPadやケータイの電源を切って紙袋に入れました。そのあと10人ずつのグループに分けられドナドナエレベーター(業務用のやつ)で8階に移動→ホテルの部屋が並ぶ廊下(試験会場は大部屋をパーテーションか何かで区切ったところだと思っていたのでびっくり)→各部屋の前で1人ずつ座って待機→合図で一斉に課題の書いた紙が配布(自由にメモしてOK)→5分間見たら回収→ドアが開き、前の受験者が出てくる→試験開始時間の合図→中に入り試験が始まる→20分経つとドアが開けられ試合終了
60回麻酔科専門医試験体験談:その24
お陰様で無事に三科目合格しました。
さらりーまん麻酔科医先生の対策本なしの受験勉強は考えられません。
もし再受験が必要になったとしたらまた利用したいと思っていました。(実際に一度目に受験失敗した先輩は二度目は対策本購入して合格したそうです)
<筆記試験>
過去問7年分3回、間違えた問題は追加で2回くらい解きました。最後に苦手分野を青本の一門一答でさらいました。
子育て、オンコールもしながら論文書くことになったり、本格的に勉強始めたのは4月くらいでした・・・かなりきつくてもっと早く始めるべきでしたが、コロナのおかげで手術件数が減り、非常に助かりました。
五反田TOCで受験しました。開始遅めの11時で、会場から2時間圏内に在住のため当日入り。
会場は広くて快適、室温は暖かめで、ヒートテックは直前に脱ぎました。笑 でもC問題当たりからは冷えてきたりして、寒暖差の調節がしやすい服装が必要だと思いました。
一人当たり長テーブル一つで広々使えました。飲み物、ティッシュ、ハンカチは机に置いてOK、常備薬NGでした。
トイレはたくさんあり、休み時間直後は女子トイレは長蛇の列でしたが回転は早そうでした。
休み時間に自分の席で軽食は食べられました。お弁当を広げたりする人は見かけませんでした。
A問題は過去問通り。BC問題は新傾向でした。今後はこの傾向だと思うので勉強初めの早いうちに今回の問題に目を通す必要があるかなと思います。でも結局はA問題を完璧にやるのが最優先だと思います。BC散々だったけど受かりました。
<口頭試験>
口頭試問対策本をひたすら読みました。試験を受ける同期がいたら問題を出し合うのが重要だと思います。私は同期が身近に居なかったので、直前に上司にお願いして実際に病院のカンファレンス室で模擬試験を2回くらいやってもらったのですが、これが本当に良かったです。いつもならわかることが、この雰囲気だけでも喋れなくなります。笑
この焦る気持ちを事前に体験しておくことが、当日ビビらないために重要かもしれません。
ポートピアホテルまで4-5時間でしたが、集合時間が遅かったので当日入りしました。が、やはり日帰りは結構疲れました。私は家族の事情で前日入りしませんでしたが、できればしたほうが良さそうです。
到着したらロビーで勉強しながら集合時間を待ちます。下の階にもソファーがあったりしてそれなりに座って寛げます。
集合したら電子機器類は電源off。とにかく待つ時間は長いですが、この時には落ち着かなくて文字を読んでも何も頭に入ってきませんでした。笑 ドナドナエレベーター乗ってからは早かったです。あっという間に終わります。
私は呼吸器外科の症例でスタンダードな内容が問われ、最後に術後開胸症候群のペインの接遇、という、おそらくかなりラッキー問題でした。(詳細は他の方が書いているので割愛します)が、時間はかつかつだったので、テキパキ答えないと危なかったです。答えながら問題を忘れてしまうような解答が長い問題に関しては、もう一度問題を教えてくれたりしますが、時間のロスになるので問題のメモしておいたほうが良さそうです。(試験管にメモしていいか聞きました)
終わってから思ったことは、推敲しすぎず、考えながら思いつくことはどんどん口に出して言うべきということ。試験官の反応で、ある程度加点されているかは分かるかもしれません。
以上、冗長になりましたが、体験談になります。
この度は本当にありがとうございました。