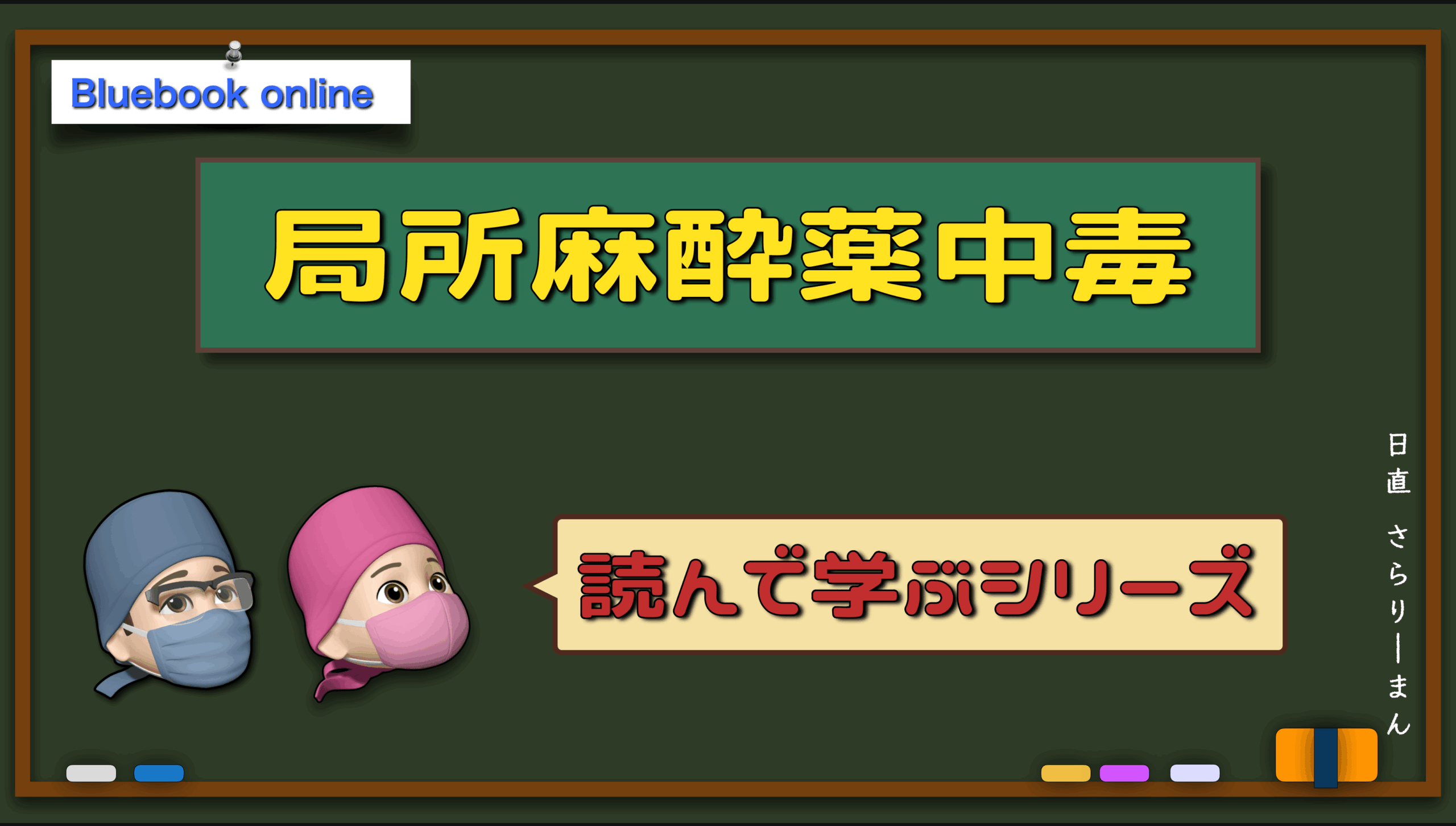はじめに
😊 さらりーまん麻酔科医とまっすーのいつものやりとり
 さらりーまん
さらりーまん今日は局所麻酔薬中毒についての特集



試験でもよく出ますもんね.



末梢神経ブロックが普及したことで昔より局所麻酔薬もがんがん使うようになったからね



私もブロック好きです.



じゃぁ局所麻酔薬中毒に関するキーワードを挙げていって



え.そんないきなり言われても.幅広いし.うーん🤔
【分割投与】【最大投与量】【血管内誤投与】【色んな増悪因子】【神経系症状と循環器系の症状】【脂肪乳剤】とかですかね.



そんなとこだね.じゃぁ局所麻酔薬中毒の原因は何?



ナトリウムチャネルの遮断です.リドカインが抗不整脈薬として使われるのもそれですよね.



そうそう.量が適正だと問題ないけど,量が多かったり,ブピバカイン(マーカイン®)なんかの心筋細胞のナトリウムチャネルとの結合が強固で,いわゆる「心毒性が強い」局所麻酔薬はひとつ間違えば危険だね.



昔は10%リドカインなんかもあったんですよね?



私が医師になったときにはもう使われてなかったけど,それでたくさんの事故が起きたみたいだね.ブピバカインも今は脊髄くも膜下麻酔で少量使用される程度だからリスクは減った.同じ長時間作用性のものもロピバカインやレボブペ⚫△X・・



言えてないですやん



(むぅ)レボブピバカインなんかは心毒性が低い局所麻酔薬だね.ちなみに神経系の症状と循環器系の症状のどっちが早いんだっけ



神経系です.耳鳴りとか,変な味とか興奮症状とかが初発症状です.



典型的にはね.ただ高濃度が大量に入った場合は一気に意識消失して循環抑制が出ることもあるし,全身麻酔中や鎮静中だと神経系の症状がマスクされるから気づかずに対応が遅れる可能性もある.



めんどくさがらずに気をつけて,少量ずつ分割でゆっくり入れるようにします.



ほんで起きたときはどうする?



100%酸素と必要に応じて気道確保,脂肪乳剤.ベンゾジアゼピン系



脂肪乳剤の量は?



20%脂肪乳剤を1.5mL/kgボーラス投与、大人ならおよそ100mLを約1~2分で注入.持続は0.25mL/kg/分で開始.改善がなければ5分後にもう一度ボーラス投与.持続投与を倍速に上げることを検討。最大投与量はおよそ12mL/kgまで.



おー,素晴らしい.ちなみに普通しないと思うけど試験的な注意点は?



不整脈でリドカイン使用しないとか,プロポフォールは脂肪乳剤の代わりにならないとか・・まぁしませんよね.



だいたいOKだから,後は1つずつ詳しく見ていこか
局所麻酔薬中毒(LAST)とリスク因子
🔷 はじめに
局所麻酔薬中毒は,LAST(Local Anesthetic Systemic Toxicity)とも呼ばれ,硬膜外麻酔や末梢神経ブロック,あるいは局所浸潤麻酔などで使用される局所麻酔薬が,全身に過剰に吸収・移行し,中枢神経系および心血管系にさまざまな症状を引き起こす合併症です.
適切に対処しなければ致命的になりうる医原性の合併症で,局所麻酔薬の過量投与や,意図しない血管内への注入・誤投与,あるいは組織からの徐々な吸収(特に量が多い場合)によって血中濃度が中毒域に達することで発症します.
実際の頻度はそれほど高くなく,区域麻酔下の症例での発生率は文献によって差がありますが,おおむね0.03%前後と報告されています(aspf.org).しかし症例の報告頻度は過少申告や見逃し(特に鎮静下での軽症発症)も影響すると考えられており,実際にはもう少し高い可能性も指摘されています.
日本麻酔科学会も2017年にASRAのガイドライン等を参考に,「局所麻酔薬中毒への対応プラクティカルガイド」を策定しています.日本麻酔科学会のウェブサイトからDLできますので,必ず目を通しておきましょう!
🔷 局所麻酔薬中毒のリスク因子(患者因子)
これに関しては筆記試験でも頻繁に問われている内容ですので,整理しておきましょう.
低酸素血症・アシドーシス(呼吸性・代謝性ともに)
酸素飽和度の低下やpHの低下が生じると,局所麻酔薬の毒性が増強します.
高度の低酸素血症や高二酸化炭素血症が生じると,脳血管が拡張し脳血流が増加します.そのため薬物が中枢に移行しやすくくなります.
またアシドーシスが生じると,局所麻酔薬のタンパク結合率が低下して遊離型が増えるため、中毒症状が出やすくなります.
高齢者・小児
高齢者は心機能・肝機能・腎機能の低下や薬物分布容積の変化,小児(特に乳幼児)では代謝酵素活性が未熟なため,血中濃度が上がりやすいことが一因とされています.
低体重・筋肉量が少ない患者
小さなおばあさんや小児が該当しますね.全身の分布容積が小さいほど血中濃度は上昇しやすくなるため,るい痩や栄養状態の悪い患者では注意が必要です.
肝機能・腎機能が低下している患者
現在用いられている局所麻酔薬はほとんどがアミド型局所麻酔薬(リドカイン,ブピバカインなど)であり,これらは主に肝代謝で,肝硬変や肝障害があると代謝が遅延し,血中濃度が上がるおそれがあります.
エステル型局所麻酔薬(プロカイン等)は血中コリンエステラーゼにより代謝されますが,肝不全や腎不全では酵素活性低下やタンパク結合率が低下し,毒性発現リスクが高まります.
虚血性心疾患,心不全,不整脈などの心臓関連疾患
房室ブロックや脚ブロックなどの伝導障害がある患者では,心筋の薬物に対する脆弱性が高くなるとされています.
また,心拍出量が低下している患者では局所麻酔薬の肝代謝が遅れることも知られており(高肝抽出率薬),心不全患者では中毒症状が出やすいという報告があります.



まぁこれら全部リスクになりそうだなぁと想像がつきますね



日ごろから「これはリスクだ!」とか思うし,投与時に気をつけることも変わらないけど,知っておくことは大事.
🔷 局所麻酔薬中毒のリスク因子(手技・薬剤因子)
血管内誤投与
通常,皮下などに投与された局所麻酔薬は徐々に吸収され,血中濃度の上昇も緩やかです.しかし,血管内に直接投与された場合には一瞬にして濃度が上昇してしまいます.63回の専門医試験でも出題されましたが,硬膜外麻酔では血管穿刺の可能性が常にあり,実際に硬膜外の局所麻酔での中毒発生率は1万件中1~11件ほどと報告されています.
さらに末梢神経ブロックでは使用薬量が多いため(量的には硬膜外麻酔の2〜4倍にもなる),仮に一部が血管内に入った場合の影響も大きくなります(発生率は1万件中2~3件程度とも).
そもそも量が多かった(過量投与)
患者に対する必要以上の高用量を投与した場合は,全身毒性を生じるリスクが(もちろん)高まります.特に複数部位への局所麻酔(上肢と下肢など)や持続投与では総量が許容量を大きく超えないように注意がが必要です。
米FDAは脂肪吸引術等で用いるtumescent麻酔におけるリドカイン投与量の上限を35 mg/kgまでと勧告していますが,このような特殊例を除き一般的には製薬会社提示の最大用量(例えば1%リドカイン20mL=200mgなど)を超えないようにします.tumescent麻酔に関しては筆記試験でも出題されています.初めて知ったときはその量にびっくりしましたけどね.
局所麻酔薬の種類
ブピバカインは心臓への親和性が高く(結合しやすい),他の局所麻酔薬に比べて中毒発現時に重篤な心毒性を示します.レボブピバカインやロピバカインはブピバカインよりも安全域が広いとされ,リスクが下るとされていますが,それでも高用量では安全とは言えません(ロピバカインが原因のLAST症例も多数報告されています).まぁ,「禁静注」と書かれてますからね.
リドカインは中枢神経症状(痙攣など)は起こしやすいものの,心停止までなる頻度は低い傾向があるとされています.
ちなみに,コカインは交感神経興奮による高血圧・不整脈を引き起こしやすい特殊な薬剤です.昔コカインって局所麻酔薬なんだと初めて知ったときは驚きました.
投与方法:反復投与,持続投与
カテーテル留置による持続硬膜外や持続神経ブロックでは,投与開始時は問題なくても,数時間から,場合によっては数日遅れて中毒症状が出現する遅発性のLASTも報告されています.初回投与や開始初期は濃度が許容範囲でも,徐々に蓄積して閾値を超える場合があるためです.
投与部位:深部組織への投与,血流豊富な部位への投与
肋間神経ブロックや傍脊椎ブロック,軟部腫瘍切除での局所浸潤麻酔など,血流の多い部位では薬物の吸収が速く血中濃度が上がりやすくなります.逆に末梢の皮下や神経周囲へのブロックは比較的吸収が穏やかです.部位による吸収速度の違いも把握しておく必要があります.
特に肋間神経ブロックは局所麻酔薬中毒になりやすいブロックの代表で,試験でも出題されていまs.



吸引テストも強く引くと血液が引けない場合がありますもんね.日々ゆっくり引くようにお願いしてます.



大事だね.少量,分割投与が基本.面倒だからといって油断して雑に事を進めると後悔することになるよ.



は〜い.あと,量に関してですが,tumescent麻酔での投与量を聞いたときはびっくりしましたよあたしゃ.



何キャラやねん.
- 麻酔科学会のプラクティカルガイドは絶対読んでおこう.
- 低酸素・高二酸化炭素,アシドーシス,心疾患,肝腎機能低下はリスクが高い.あと高齢者と子ども,るいそう.
- ブピバカインは心毒性強い.
- 血管内投与と過量投与,反復投与,持続投与,深部ブロック,血流豊富な部位へのブロック(肋間神経ブロックなど)はリスク.
局所麻酔薬中毒の病態生理
局所麻酔薬の濃度が中毒域に達すると,主に中枢神経系と心血管系に毒性症状をきたします.機序の根幹は,局所麻酔薬が興奮性細胞膜上の電位依存性ナトリウムチャネルを遮断することによります.
本来は痛覚伝導の抑制に有用なこの作用ですが,過剰濃度では脳神経細胞や心筋細胞の電気活動まで抑えてしまうために,様々な症状が出現します.
🔷 中枢神経系への影響
血液中の局所麻酔薬が血液脳関門を通過して脳に達すると,中枢神経系の興奮と抑制のバランスが乱れます.初期には大脳皮質の抑制性ニューロンが麻痺するため相対的に興奮優位となり,患者は耳鳴り,口唇や舌のしびれ,金属味,見当識障害,多弁,興奮といった精神神経症状を呈します.
さらに血中濃度が上がると全てのニューロン活動が抑制され,意識レベルの低下,痙攣,さらに進行すると昏睡や呼吸停止に至ります.
初期の軽度症状が出ずにいきなり痙攣に至る例もあり,症状の出方は一定ではありません.実際痙攣が最初の主要症状となる場合も多く,症例の約50%で痙攣が初発であったという報告もあります.
痙攣が遷延すれば低酸素血症やアシドーシスを招き,これがさらに毒性を悪化させるという悪循環にも陥ります.
🔷 心血管系への影響
心筋の興奮収縮系も局所麻酔薬のナトリウムチャネル遮断で影響を受けます.
刺激伝導系では,徐脈や房室ブロックなどの伝導障害が起こり得ます(洞房結節や房室結節でのインパルス形成・伝導が抑制).重症の場合は,心室筋の伝導速度低下や不応期延長によって、心室性期外収縮や心室頻拍・心室細動などの致死的不整脈も誘発されます.
心筋収縮力そのものも低下するため、血圧低下(循環虚脱)を来します.前述の通り,特にブピバカイン中毒ではナトリウムチャネルへの結合力が強く解離が遅いため,重篤な不整脈と難治性の心停止が昔から報告されてきました.
局所麻酔薬中毒による心停止はPEA(無脈電気活動)や心静止として認められることが多いですが,その前段階として著明な徐脈と血圧低下が数分間進行しつつ悪化していく経過が報告されています(麻酔科は頻脈はそれほど怖れないのですが,徐脈は本当に怖い・・).徐脈+血圧低下は最終段階(心停止)一歩手前と考え,迅速な対処が不可欠です.
🔷 症状の特徴と進行
局所麻酔薬中毒の臨床症状は,上記の中枢神経系の循環系の症状として現れます.典型的にはまず中枢神経症状が出現し,続いて心血管系症状が現れるとされていますが,実際の出現順序や重症度は症例により様々です.
初期の前駆症状としては、前述の耳鳴り、口唇や舌のしびれ、金属味などの感覚異常や,焦燥感・多弁・錯乱など精神神経症状が挙げられます.客観的には血圧上昇や頻脈がみられることもあります.
この段階で気づいてまだ投与途中であれば,投与を中止すればそれ以上進展しない場合もあります.症状が進行すると全身痙攣発作や意識消失といった主要な症状が出現します.
痙攣は繰り返すほど患者の状態を悪化させるため(低酸素,アシドーシスによる悪循環),早期に抑止することが重要になります.
心血管系の症状は,中枢神経症状に続いて起こるか,あるいは鎮静下ではマスクされたり,濃度上昇が急速な場合は神経症状を経ずに突然循環器系の症状(血圧低下,徐脈,心電図の異常)が出現することもあります.
経過の典型例では,初期には頻脈や高血圧(交感神経刺激に伴う)も見られますが,その後徐脈・低血圧になり,やがて致死的不整脈(心室頻拍、心室細動)や心停止に至ります.特に重症のLASTでは急速な悪化が特徴的で,数分以内に循環が破綻することもあります.
そのため,区域麻酔施行時には,鎮静下でもバイタルサインの僅かな変化に注意を払い,疑わしきは投与停止・対処を取る準備が必要です.「もしかしてLASTかも?」と思わせる早期兆候が一つでも出現したら,躊躇せず初期対応を開始することが推奨されます.
LASTの治療は時間との戦いであり、早期治療介入が予後改善につながるからです



先生は自分でされてて起こしたこと有ります?



自分でやってるときはないかな.ただ整形外科のターニケットを用いた静脈内局所麻酔(Bierブロック)で呼ばれたことはあるね.その時はしびれと多弁になってた.



知らずにすると怖いことって結構ありますよね.症状の種類と変化はしっかりと覚えておきます.
- 典型的には精神神経症状→循環器系の症状の順.実際には様々.
- 精神神経症状は耳鳴り、口唇や舌のしびれ、金属味などの感覚異常や,焦燥感・多弁・錯乱など.
- 循環器系の症状は,初期には頻脈や高血圧,その後徐脈・低血圧,最終的に致死的不整脈(心室頻拍、心室細動)や心停止.
- 鎮静下や血中濃度上昇が急速な場合はいきなり循環器系の症状も出現することがある.
- LASTを疑ったら初期対応を素早く!
局所麻酔薬中毒の治療と対応
局所麻酔薬中毒が疑われた場合の初期対応については,ASRAや日本麻酔科学会のガイドラインにおいて,ほぼ共通した流れが推奨されています.一応stepを踏んでいますが,脂肪乳剤の投与も含めて同時進行で迅速に準備,対処を行います.
脂肪乳剤の登場以前は,ブピバカイン中毒による心停止は蘇生困難で死亡率も高いものでした.しかし現在では脂肪乳剤療法が標準治療として確立し,救命率の向上に大きく貢献しています.AHA(米国心臓協会)の中毒による心停止ガイドライン(2023年改訂)にも,「局所麻酔薬毒性には20%脂肪乳剤投与が有効である」との記載が明記されました
前駆症状を疑うなど,異常を認めたら直ちに局所麻酔薬の投与を停止しし,応援を依頼します.手術中であれば手技を中断し,他のスタッフにも状況共有します.整備していればLASTセット(20%脂肪乳剤など)を持ってきてもらいます(当院は救急カートに入れてます).
100%酸素投与と,必要に応じて気道確保し,補助換気を行います.痙攣により自発呼吸の停止や,誤嚥の危険があるため,リスクが高いと判断すれば速やかに気管挿管して人工呼吸管理を行います.低酸素・高二酸化炭素血症の是正は悪循環を防ぐため最優先であり,これだけで中枢神経症状の悪化を防ぐ効果が期待できます.
痙攣を発症,持続している場合はベンゾジアゼピン系薬(ジアゼパムやミダゾラム等)の静注で発作を止めます.ベンゾジアゼピンが第一選択ですが入手困難な場合(ほとんどの手術室や救急外来等ではあるはず),バルビツレートやプロポフォールの少量投与も選択肢です.ただしプロポフォールは心抑制作用が強いため少量にとどめる必要があり,また脂肪乳剤の代用にはならないことに注意が必要です(プロポフォールの製剤は10%脂肪乳剤に溶解されていますが、有効脂肪濃度が低い上,プロポフォール自体の陰性変力作用が問題となるため).
なお筋弛緩薬は痙攣による外傷リスク低減の目的で使用することは可能ですが,中枢神経症状そのものの治療にはなりません(物理的に動かなくしているだけ).
血圧低下や致死性不整脈が生じた場合に備え,循環作動薬の用意や必要なら心肺蘇生(CPR)の開始を検討します.重要なのは、通常のACLSプロトコルとは若干異なる点です.
アドレナリン(エピネフリン)は使用可能ですが、通常より少なめの用量に抑えることが推奨されます.具体的にはボーラス投与で1回あたり<1µg/kg程度(通常の蘇生では1mgが推奨)を目安に用います.過量のエピネフリンはかえって脂肪乳剤による心筋機能回復を妨げる恐れがあるためです.またバソププレシンの投与は避けるべきとされています.バソプレシン投与により血管抵抗を極端に上昇させても,局所麻酔薬で収縮不全に陥っている心臓は十分な拍出ができず有害と考えられているためです.
β遮断薬やカルシウム拮抗薬も陰性変力作用で心機能を低下させるため禁忌です.さらに抗不整脈薬の使用も注意が必要です.特にリドカインなどのクラスIB抗不整脈薬(局所麻酔薬でもある)は絶対に使用してはいけません(ナトリウムチャネル遮断で生じているのにナトリウムチャネル遮断薬は投与しないでしょうけど).
心室頻拍に対してアミオダロンなどを用いるかはケースバイケースですが,まずは脂肪乳剤投与による効果を期待しつつCPRを継続します.必要であれば経皮ペーシングや電気的除細動も一般のACLSに準じて行います.
局所麻酔薬中毒に対する特異的治療として確立されているのが20%脂肪乳剤(イントラリピッド等)の静脈投与です.症状が重篤化する前にできるだけ早期に投与を開始します.詳細な推奨投与方法はガイドラインを参照してください!(局所麻酔薬中毒への対応プラクティカルガイド)
- ポイントは,ボーラス投与量と,投与後の持続投与と追加投与量,総投与量(上限)です.
重症例では経皮的心肺補助(VA/VV ECMO)の導入も考慮されます.ASRAガイドラインでは「CPRが効果不十分な場合に備え,早めに心肺バイパスチームに連絡すること」と提言されています.そこまでできる施設とできない施設とがあるでしょうけど.
局所麻酔薬中毒で心停止に陥った場合でも,長時間の蘇生後にECMO導入で回復したケースも報告されています.最善を尽くして蘇生を継続することが大切です.



ここが一番大事ですね.まずは初動を早くですね.



そう.迷うくらいなら酸素いって,脂肪乳剤を投与する.イントラリピッドを投与して全身に悪影響が出ることはほとんどないだろうから.それよりも治療が遅れるほうが致命的になる.



できる限り予防,発症したら早期治療っすね!
- まずは応援,酸素投与と気道確保!
- 痙攣を止めるのは基本ベンゾジアゼピン.
- 通常のACLSとはちょっとことなる.アドレナリンは控えめに
- 何といっても早期の脂肪乳剤(20%イントラリピッド)!.
局所麻酔薬中毒を起こした場合の予後
局所麻酔薬中毒は,迅速かつ適切に対処できれば多くの場合で回復可能です.特に脂肪乳剤療法の普及後は予後が改善したとされています。
近年のレビューでは,2014~2016年に報告されたLAST 47例中死亡は2例(4.3%)にとどまったとの分析があります.また2017~2020年の報告36例でも致死率は数%程度とされています(anesthesioljournal.com).しかし,これらは症例報告ベースの数字であり,重篤例は報告自体が少ない可能性もあります.
実臨床においては,脂肪乳剤投与のタイミングが予後を大きく左右します。例えば早期に適切な処置がなされ心停止を免れれば後遺症なく退院できる患者も多い一方,対応の遅れた症例では低酸素による不可逆的脳障害が残存した報告もあります.また高齢者や重篤な心疾患患者では一旦心停止に至ると救命困難なこともあり,症例によって差が大きいのが現状です。
結局のところ「予防に勝る治療なし」であり,リスクの高い患者には特に慎重な投与と観察を行って中毒を起こさないことが最も重要です.それでも発生した場合には,本記事で述べたようなガイドラインに沿った対応を迅速に実施することが必要です.
📝参考文献
- American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine (ASRA). Practice Advisory on Local Anesthetic Systemic Toxicity, 3rd edition, 2017.
- 日本麻酔科学会. 局所麻酔薬中毒への対応プラクティカルガイド, 2017年.
- American Heart Association (AHA). Guidelines for Resuscitation from Toxicity-Induced Cardiac Arrest, 2023.
- Weinberg G, et al. “Local Anesthetic Systemic Toxicity (LAST) Revisited: A Paradigm in Evolution.” APSF Newsletter 36(2), 2021. etc..