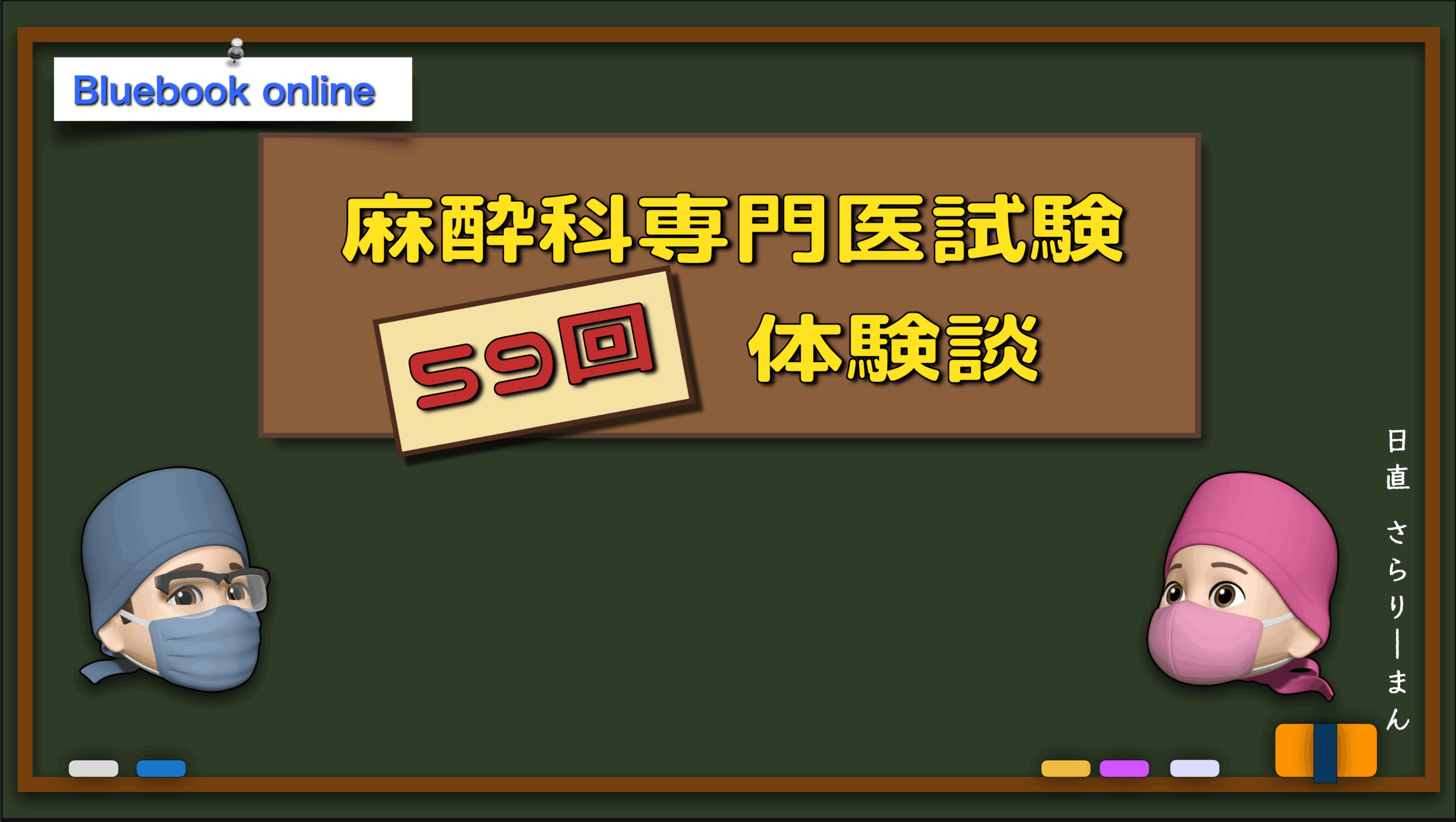皆様からの感想はこちらから
59回麻酔科専門医試験体験談:その1
今年59回でも受験してどうにか合格できましたのでその報告をさせていただくたくメールいたしました。
口頭試験のみだったので昨年購入した青本メインで7月ころから対策し、口頭試験に向けては誰よりも勉強、練習したと自信をもって臨みましたが、昨年よりよかったのは設問最後までいったことくらいでした。
しかしその後、体験談にあるような言い残したことや世間話をするわけでもなく、退室してくださいと言われ、部屋を出たら自分ひとりでした。救いようがなかったんだと思い不合格を確信しましたが、なぜか合格していました。昨年の感覚で不合格なら今年も不合格と思える出来でしたが、よくわかりません。合格はホッとしました。
過程はどうであれなんとか2年かけて合格できたのは青本のおかげです。
本当にありがとうございました。
59回麻酔科専門医試験体験談:その2
私は2019年に1回目の受験で、筆記のみ合格。
実技・口頭は落第し、2020年に2回目の受験でした。
筆記:受験なし 合格済み
実技:コロナ禍により実技評価書類提出
私は、専門医プログラムが始まる前に麻酔科になったので、現在所属している施設の麻酔科のトップによって実技を評価してもらい、その評価表をおくる、という形でした。
めちゃくちゃ慌ててしまい、落ちたなと思っていましたが、口頭試験の実地試験に回りました。
実地試験
口頭試験の実地は、勤務病院で行われました。
前もって、実地試験が可能である日時を聞かれ学会に提出。
2週間くらい後に、日時の決定の連絡がありました。
試験官がどこに何時に集合したらいいかと聞かれ、それに答えました。
13〜17時の間で実地試験とのことで、時間を連絡しました。
また、病院宛に「実地試験のお願い」という手紙を出したいので、その内容を確認してほしいとの連絡あり。
(試験官として〇〇病院の00先生がお伺いさせていただきます・・・・みたいな手紙)
試験当日は、2人の試験官がいらっしいました。
導入前に、症例提示。この症例の麻酔上の問題点、外来カルテと同意書の記載を確認されました。
入室前に、始業点検などのこと(麻酔前に確認することを簡単に教えてと言われました)を聞かれましたが患者さんが入室したので、それは途中で「あ、じゃあいいですよ-」と言われ中断。
いつも通りに麻酔してみてくださいねーと声をかけてもらい、普通に導入。
導入後、導入のまとめをして、と言われました。
導入の話をして、麻酔維持のプランも話しました。
その後試験官はうちの上司に連れられて部屋を出て行きました。
控室で上司と雑談をしていた様子です。
その後、30分くらいしてお戻りになり抜管のプランを教えてください、それを確認して引き上げますと。
抜管のプランと、考えられるリスクと対処を答え終わりました。
上司から聞きましたが、「なんの問題もありません、なぜ実地試験に回ったのかが不思議です」と言っていただきました。実地試験にいらした試験官の先生方は大変優しかったですが、要所要所、質問はきちんとされておられました。
さらりーまん麻酔科医様には、大変お世話になりました。
本当にありがとうございました。
59回麻酔科専門医試験体験談:その3
<準備>
地方からの受験、子育て中です。
書類申請受付が始まったらすぐに申請を出せるよう、5月までに必要書類や単位の確認をしておきました。過去問の問題集もほとんど買い揃えました。53回(2014年度)はオンラインや近くの書店では購入できませんでしたが、先輩から頂いたものがあったので助かりました。
書類を出すまではなんとなく落ち着かず、勉強に着手する余裕はありませんでした。
申請後に筆記試験の勉強を始め、結果7年分を3周+間違えた問題を正答できるまで繰り返しました。
口頭試験の勉強も並行して(片方に飽きたらもう片方、という感じで)やっていました。口頭試験の対策は青本のみです。本当に助かりました。ありがとうございました。
感染多発地域に赴くのは本当に恐怖でしたが、細心の注意を払いながら行きました。
幸か不幸かgo toの影響で旅費がかなり安くなったので、ホテルの値段は気にせずに、筆記試験の際は東京会場に最も近いホテルに前泊、口頭試験はポートピアホテルに前泊・後泊しました。前泊しなくとも集合時間には間に合いそうでしたが、移動中に勉強するのはなかなか難しかったため、前泊しておいて良か
ったと思います(家族に感謝)。
口頭試験はお昼過ぎの集合だったため、連泊する部屋でギリギリまで勉強できたのが良かったです。ただホテルのラウンジで勉強している方も多かったので、チェックアウト後にラウンジで過ごすのでも大丈夫と思います。
感染予防のため食事はほとんどルームサービスにしました。go toのチケット?も使えましたし、時間短縮にもなって良かったと思います。
<筆記試験>
体験談にかなり寒いとありましたが、自分の時は適切な室温だったと思います。
持ち物が「受験票、誓約書、筆記用具、マスク」だったため、腕時計を持参するのを忘れてしまいました。壁時計が何箇所かありましたが自分の席からは見づらく、会場の方に相談すると、1つをホワイトボードのところに移してくださり、さらに「試験中に手を上げてくれれば時間を教えますよ」と優しく答えてくださって感動しました。ただ腕時計は必要だったと反省しています。
A問題はほとんど解けました。
BとC問題はやはり絶望的で、どれをマークするか決めるのに時間がかかりました。早めに退室したいと思いましたが到底無理でした。
みなさんが言われているように重箱の隅をつつくような問題が多いので、そこは諦めて、いかにA問題を落とさないかが大事だと思います。過去問を完璧に解けるようにして、ただ正解を覚えるのではなく、他の選択肢や解説をよく読んでおくのもBやCに応用されると思います。
やはりCOVIDやECMO, あと凝固機能、抗凝固薬の拮抗薬や休薬については時代を反映したものかなと思います。
<口頭試験>
誘導はなかったですが、「先生ならわかっていると思うけどね」と声をかけてくださったり、温かい雰囲気ではありました。
時間いっぱいかかったため心配でしたが、結果合格していました。
実技試験が評価表になったので、口頭試験の際に少し実技試験の内容が入るのではないかと思っていましたが、実際は手術申し込みからICU入室まで盛りだくさんな内容になっていたので、ここに麻酔器の始業点検や、実技試験の内容を盛り込むことは難しかったのではないかと思います。
勉強ももちろん大切ですが、日曜日に東京で試験、そのあと金曜日に神戸で試験を受けること自体が、気力・体力ともに試されたというか、鍛えられたと思います。
体調を万全にして(家族を含め)、なるべく気持ちを落ち着かせて試験に臨むことが大事だと思います。
59回麻酔科専門医試験体験談:その4
無事に、麻酔科専門医試験に合格いたしました。昨日、学会から連絡がありました。
今までの体験談で、2度と受けたくないと先生方がおっしゃっている気持ちがとてもよく分かりました。青本は、口頭試問対策にとても参考になりました。
勉強
筆記試験の勉強は4月頃からパラパラと過去問を解き始めました。
ただ、1周目は知らない・見たことない知識問題だらけでかなりのスローペース。開くことが辛かったです。
第58回試験の際に第52回試験からの出題が何問かみられたため、第52回から第58回までの7年分を解きました
。最終的には、最低5周、直近3年は7周やりました。
口頭試問対策は、筆記試験が終わった後の1週間でやりました。もう少し早めからやっていれば、と感じました
。
また青本に載っていた一問一答の模範解答から、筆記試験のB問題での選択肢のものがあったり、して悲しい気持ちになったことは覚えています。
一問一答はとても役に立ちました!!!
筆記試験
今年はCOVID-19の影響もあり、東京は2会場(有明と神田)に分割でした。
A問題は、見たことがない問題はありませんでした。おそらく満点。
B問題は例年通り難しく、確実にわかる問題はあまりほとんどありませんでした。
C問題は、心臓外科の問題が例年より多い印象でした。こちらも4割くらいしかわからず。
例年の体験談で、B問題が終わった後は皆さんかなり落胆されている印象を受けていましたが、全く自分も同じでした。時間がかなり足りなく焦りました。
また、マークシートが意外と小さくびっくりしました。
第58回から血液凝固分析装置の問題がでてきたということもあり、もう少しその勉強をしておけばよかったと思いました。また、学会のホームページに載っている様々なガイドラインをもう少し目を通しておけばよかったです。たまたま前日に見たガイドライン(最近更新されたわけではなく、本当にたまたま興味で見た)から出題されたりとラッキーもありました。
口頭試問
2日目1番目のグループでした。
今までは午前・午後など大きな分け方でしたが、今年はCOVID-19のこともあり、かなり細かくグループ分けされてました。前日の昼頃に神戸入り。会場のポートピアホテルに宿泊しました。
前日は、部屋で青本の一問一答の復習をしながら過ごしました。
当日は8時に集合。およそ40人ほどが大きな部屋に集まりました。
その後、さらにそれを前グループと後グループにわけ、そのグループの中でも6人ごとに移動。
噂のドナドナエレベーターで上の階へ。試験はホテルの一室で、まずは廊下で待機。開始10分前に問題が配られ、5分間でメモをとって良いと言われる。5分後一度紙は回収、入室時に再度渡されました。
試験官は2人。左にはモニター。こちらとの間にはパーテーションが置かれてました。
59回麻酔科専門医試験体験談:その5
筆記試験
A問題はいつも通り過去問から出ている様子で、ほとんど変わらない内容で出題されまし
た。7年分復習しました.
B問題で学会のガイドラインから問題が何問かでましたが重箱の隅をつつくような感じで自信をもって解答できませんでした。B問題よりC問題のほうが解けるだろうと思っていましたが、悩んでしまい、正答率も悪かったと思います。午後からどんどんテンションが下がっていく試験でした。
実技試験:なし
青本が届いたときはこんなに分厚くて文字も小さく内容が多い!と焦りました。しかしすべて覚えていなくても合格できます。青本は過去問をすべて網羅していて、本当によいお守りになったと思います。さらりーまん先生の本を参考書にして次以降の方もがんばってください!
最後になりましたが、さらりーまん先生本当にありがとうございました。
59回麻酔科専門医試験体験談:その6
筆記試験
コロナ対策なのかいつも通りなのか知りませんが、A,B,C問題の休憩時間が15分だけでお昼休憩なし。
昼前から夕方までぶっ通し。トイレに並ぶのでそれだけで10分ぐらい経過する。
休憩時間内であれば試験会場で飲食可能、試験中は飲み物だけ可。
とても疲れる日程だったので、A問題を時終わってから早期退室して休憩した方が良かったかもしれません。
でもビビりだったので結局全て最後まで受けました。
受験生のマナーがとても良くて滞りなく終了したので、偉い先生が終了後に褒めてくれました。
それを聞いて謎に感動して拍手したい気分になりました。
口頭試問
ほとんどの受験生が黒っぽいスーツ(もしくはスーツっぽい私服)でした。白ジャケットで行ったのでちょっと気まずい思いをしました。
青本持っているひとが沢山いました。
大きな部屋で説明を聞いて、8名ぐらいずつ呼ばれてついていきます。
バックヤードの業務用エレベーターにのって8階か9階でおりて、受験するホテルの部屋の前で待ちます。
20分ぐらいだと思いますがとても緊張して嫌な時間でした。
前の受験生が部屋からでると症例が書かれた紙を渡されます。
読んだり書き込んだりできる時間が5分間あり、その後入室します。
面接官:ベテランぽい男性の先生と、中堅ぽい女性の先生
面接官の先生はとても親切でした.
例年聞かれている「この患者のリスクはなんですか」という問題が無くてびっくりしました。
また手術に関する質問は皆無で、単にCVとるオペを作っただけって感じでした。
オンライン版について
今回コロナ禍がきっかけでさらりーまん麻酔科医さんが用意してくださったオンライン教材はとても役に立ちました。iPadで見ていたのですが、書籍にはない良い点が沢山あります。
・文字が大きい。更に大きくできる。カーニングと行間のサイズとフォントが良い。あと私の好みだけど文字がブルー系で落ち着く。
・書籍だと片側のページを片手で押さえつけ、もう片方の手で答えを隠しながら進める必要があるが、
電子版なら指一本でスクロールして答えを隠しながら1問ずつ進められる。
・出先でも携帯などで勉強できる
今までは目が疲れるので電子書籍より紙派でしたが、産まれて間もない子供の世話をしながらの受験勉強をする上で、指一本で勉強できるサイトはとても助かりました。
両手使って机に向かって勉強できる時間はあまりないですが、
サイトがあれば抱っこしたり授乳しながらでも勉強できました。本当にありがとうございます。
可能であれば来年以降の受験生にも開放してあげてほしいと思います。
長々と書いてすみません。この体験談が何かお役に立つと幸いです。
59回麻酔科専門医試験体験談:その7
筆記試験に関して
4月から開始。過去問4年分。
6月に転勤になり自動車通勤から電車通勤になり、通勤時間に青本の通読開始。
最新版が出版されたら購入し合計5年分。
最終的に、A問題とB問題は5年分覚えるまで。
他の先生も書いておられますが、5年分が一番費用対効果、時間対効果が良い気がします。
国試と同様に周りと同じことをするのが肝心と思います。
A問題は良好、B問題は手応えなし。C問題は意外と簡単に感じました。
実技試験
免除。
口頭試問
青本の過去問、一問一答をひたすら唱える。
本番は悪性高熱の既往のある頸部手術。
気道に関しては準備したが聞かれず、術中覚醒への対応。
後から振り返ると、不十分な回答もあったかと思いましたが,時間は余りました。
準備、想定していたより簡単な印象でした。
3科目とも合格。
お世話になりました。本当にありがとうございました。
59回麻酔科専門医試験体験談:その8
筆記試験について
試験勉強は過去問を5年分やりました。
56回、57回を一通りとりあえずやった後、55回を1問1問解きつつ56、57回の類似問題を見直し。55-57回をもう一度復習してから力試しに58回。
58回をやっていると、どうも52回の過去問が多く出ている気がしたので、最後試験の1週間前から滑り込みで53回の過去問に手を出しました(去年52回だったら今年は53回じゃね?という安易な考えです)。これで5年分です。
今年はコロナの影響がいくつかあり、
①誓約書の提出が必要…2週間以内に自身や家族で風邪の症状がなかったか、とか、適切な防護をせずに診療に従事していなかったか、とかのアンケートに丸付けをした後、嘘ついてません!にサインする紙を提出する必要がありました。
②マスク着用義務…写真照合の時だけ外す感じです。
③会場に入室する際に検温+アルコール消毒…誓約書渡して検温してアルコール消毒すれば名札がもらえる
④昼食なし…これが地味に嫌でした。昼食がない代わりに11時開始だったのですが、10時代に昼食を食べる気にもなれず、各試験間の休憩も15分のみ。結局A問題を早めに切り上げて会場を出て食べることにしたのですが、会場を出て座る椅子も数えるほどしかなく、そこには先客が。ロビーで食べている人もいましたが、一般人もいらっしゃるそこそこの良いホテルのロビーでコンビニおにぎりをほおばる気にもなれず。結局会場に車で来ていたので、駐車場に行き自分の車の中で食べました。
A問題
予想がドンピシャ当たり,サクサク解けて早めに出られました。40分くらい経つと出て行く人が多かったです。
B問題
は??って感じでした。しょっぱなから分からん!
でも、毎年そうだよ、お前が分からん問題はみんなも分からんよ、という先輩の教えを胸になんとか最後までマークしました。自信がある問題だけ数えてみたら、全体の25%くらいでした…。コロナを思わせる症例もあって、おぅおぅやっぱり出してくんのか…!と思いました。
C問題
めちゃくちゃできた訳でもめちゃくちゃできなかった訳でもない感じです。最後の方は疲れてきて、分からん問題は何回見ても分からんわ!と思って少し早めに帰りました笑
口頭試問について
試験勉強は正直あまりできていない中で受験しました。筆記試験勉強を主にしている中で、筆記試験勉強に疲れたら青本の過去問をやってみるという感じでした。結局3年分+αくらいの分しか目を通せていませんでした。筆記試験でコロナが出たので、何か聞かれると思い学会の提言などをチェックしていましたが、何も聞かれませんでした…
この段階で試験官が、「えーじゃぁこれで終わりですかね。あと1−2分したらノックされると思うんで、それまで少し待っててください」と。友人に聞くとこの時間に「もう一回リベンジでさっきの質問答えてみて」と言われた方もいたそうです。私はひたすら世間話で、「やっぱ関西はしんどいっていう表現使うんですね〜。辛いとかって意味ですよね〜」みたいなことを話されました。私は「はぁーそうですね、気づきませんでした苦笑」みたいなことを言って終わりました。
終わった後に全然できた感がなかったので、めちゃくちゃ不安でしたが、先輩に「世間話したら勝ちや」と言われなんとか合格発表まで平静を保っておりました。
結果合格でした。自信がなくてもハキハキと話したりするのが良いんだと思います。
青本お世話になりました。今後も臨床で使っていける物だと思います。
59回麻酔科専門医試験体験談:その9
口頭試験
ホテルの客室が試験場所で、廊下で待機して入室前に5分間下記の症例について書かれた紙とボールペンを渡されて、書き込むことができた。5分後紙は一旦回収されて、部屋に入るときに再び渡される。試験中は私物のボールペンなどは一切使うことができず、メモは取れなかった。試験時間は20分だったと思います。待機中は私語一切禁止でした。
2分ほど時間は余りました。担当の試験官は終始無言で、他の人の話を聞くと私の試験官は誘導とかもなく結構しんどかったです。
口頭試験の勉強は筆記試験が終わってから始めたので、実質3日ほどしかできていません。青本の問題と回答例を口に出して読む、という方法で五年分をさらっと1周しました。小児、心外、気道確保関連はある程度自分の中で解答を考えていました。
実際の問題は、後から考えればそれほど難しいものではなかったと思います。しかし、試験の雰囲気から緊張し、普段通りに考え発言することがとても難しかったです。加点方式だからとにかくしゃべれと先輩からは言われていましたが、ベラベラと話せる雰囲気ではないため、間違っているかもしれないことを言える度胸が必要な試験だと感じました。
試験が終わった直後は落ちた…と思いましたが、合格することができてよかったです。
ありがとうございました。
59回麻酔科専門医試験体験談:その10
●昨年初回受験で口頭試験が不合格であったため、今回は口頭試験の再受験です。
●おかげさまで無事に合格することができました。(内容的には前回以上にボロボロだったと思うのですが…)
●新型コロナ対策として、集合場所に入る前に『誓約書』の提出、検温、手指消毒などがありました。
●昨年同様、問題は1例のみ。20分間。
●試験官2名+受験者1名、ホテルの一室で。試験官との間に透明なシートかアクリル板があったと思います。
●昨年同様、症例の設定が書いてある紙にメモをとる時間が5分間。
それ以外も間違ったりしたので、絶対に不合格だと思っていたのですが、なぜか合格できました。
先生の資料のおかげです。ありがとうございました。
今後とも何卒よろしくお願い致します。
59回麻酔科専門医試験体験談:その11
今年は口頭試問の過去問をオンラインで参照できたので、授乳しながらでも勉強することができ、とても助かりました。
育児中で忙しい中合格できたのは、さらりーまん麻酔科医様のおかげです。本当にありがとうございました。
以下体験談となります。
筆記試験について
本格的に勉強を始めたのは6月からです。第53-57回の5年分をまず解きました。1周目が終わったのが9月初めでした。そこから第53-57回を3周し、力試しで第58回を解いてみました。
口頭試問について
部屋に入る前に5分間の制限で症例の紙を渡されました。閲覧中はメモをとっても構わないとのことでした。5分後に回収されましたが、入室前にまた返却してもらい、試験中はその紙を見ることができました。
総合的な感想
筆記は皆さんも言われている通りA問題でどれくらいとれるかが勝負だと思います。6年分解きました.
口頭試問ですが、試験官の先生は、答えを導き出そうと助言をしてくださったりもしましたが、解答を間違った問題も多々あり、絶対落ちたと思っていました。多分ギリギリの合格だったと思います。もう一生受けたくありません。
59回麻酔科専門医試験体験談:その12
●筆記試験
専門医の先生達からの御告げでは、『過去問中心で良い。A問題は過去のA,B問題からのプール問題。B問題は誰も解けないので気にしない。Cは臨床をやっていれば解ける。』という人が多かった。
さらに去年受験した先生の感触では、3年分だと合格はしたが終わった後すごく嫌な気分になった、7年分やると十分だったという人の意見を参考にしました。
5年分を最終的には6周とさらに古い2年分を3周しました(合計7年)。
6,7年前の過去問はA,B問題の見たことない問題だけ解きました。(過去5年分やれば見たことある問題がかなり多いので)
今年はコロナの影響で入室時に体温測定があり、発熱のある場合や試験中に頻回に咳込んだ者は受験できなくなる可能性があると書かれていたので緊張しました。
長机の真ん中に受験生が1人ずつ座るというスタイルでした。
このような世界情勢で出ないはずがないと思ってはいたがCOVIDの問題やECMOの問題が目立った。
2019年度から過去問の毛色が変わったと(Bが難化、Cも正常や経過観察を正解とするなど)思っていたが臨床重視の問題へシフトしていくということなのだと思う。
もし、もう一度受験なら何の対策をするかなと考えると。ガイドラインからの出題は、重箱の隅をつくようなものも出ている(出尽くして来ている)ので、まだ出題されていない箇所も含めてガイドラインは毎日枕元に置いてそれを眺めてから寝るといいかもしれない。
○口頭試験を受けて
2019年度から大問は1題となった。緩和ケアやペインで丸々1題のみで終了ですということは無いと思う。
聞かれることは去年からは比較的オーソドックスな内容が多いと思う。
筆記試験の過去問ばかり解いて、口頭試験の勉強を始めたのが8月(お盆終わり)ぐらいからでとても不安だった。専門医の先生達の話では、筆記が終わってからの1週間しか勉強していない先生も結構いたが、青本を読めば読むほどそんな短時間ではとても無理だと思って不安が募った。結局、筆記試験までに2年前の青本を1周と過去問3年分を1周しかやる時間がなかった。
今年は、コロナの影響で筆記試験が日曜で、次の木曜に神戸へ移動し金曜に口頭試問というハードスケジュールでした。
筆記試験の疲労と日々の麻酔で、思う様に口頭試験の勉強が進まず、不安なままホテルにつき、ポートピアホテルの大変寝心地の良いベッドで前日12時間も寝てしまいました。朝8時ぐらいから、ざーと青本を眺めているとさらに睡魔に襲われ2時間ほど仮眠。16時からの試験開始までには勉強はあまり出来なかったけど体調は絶好調になっていました。
入室前の5分で症例と予定手術と合併症の概要が書かれた紙とボールペンを渡される。想定される質問から、解答を箇条書きにし終わったぐらいで入室を促される。スーツケースなど持ち物全て室内へ持ち込み荷物をおいて席に着いたら試験開始という具合でした。2名の試験官は1人は狸寝入り、1人は眼光鋭いが優しい物言い。
一度に5つ答えよなど沢山聞かれる問題もあり、自分でいくつ答えたか分からなくなるもあと一つは?と促してくれる。
早口で答えたのか時間が余ったので時間(20分経つ)までそのまま待機してくださいと言われる。沈黙の後で、試験官から色々質問される。
実際、局麻中毒は見たことありますか?体幹部のブロックはやっていますか?どんなブロックを普段しますか?TAPA blockの話で盛り上がったところで外からノックされ終了となりました。
口頭試験の対策として思った事は、各分野で確実に聞かれるであろう問題を何度も口に出して練習するのが近道だと思う。それだけでも合格点に達すると思うが、少し前の年度では割と高度な内様の出題もあった(食道気管瘻Gross Cでの挿管、肺移植、小児をMRIへ連れていくetc)ので、それらについて(聞かれて全くわかりませんは避けるため)解答を何度か見ておく。(去年からの傾向では、大問1題でそこまで高度な問題は来年も出ないと個人的には思うが)
筆記試験から最大で1週間しか時間がなく、疲労もあり日常の麻酔もある状況であることを考えると筆記試験後から全くの0の状態で口頭試問の問題に取り掛かるのは大変難儀だと思う。筆記前までに青本を1周程度は読んでおくと良い。
早いうちから余裕があれば、各分野で絶対に聞かれる(聞かれて然るべき)事項を何度も(できれば誰かに出題してもらい)口頭ですぐに解答できる状態まで繰り返し練習しておくと安心して受けれると思う。
**************************************************************************************************************
以上です。
来年度は2学年同時受験なので、たくさんの先生が合格されることを願います。
口頭試問では青本がとても役に立ちました。
ありがとうございました。
59回麻酔科専門医試験体験談:その13
筆記試験
過去問5年分。まとめノートづくりを含め、昨年度分を除いた4年分を4月からゆっくり開始しました。最初は1冊解くのに数時間かかっていましたが、数をこなすうち、反射で解ける問題が増え、最終的には1冊30分程度で解けるようになりました。夏頃に直前の過去問を解き、A問題の重要性を再確認するとともに、不足する知識を補充していきました。
口頭試問
夏頃から購入した対策資料を読み始め、当直中や空いた時間に念仏を唱えるように回答内容のイメージをしみこませていきました。担当麻酔症例にも過去問同様の問題点抽出、トラブルシューティングなどを暗唱できるようにし、日常業務をしながら対策ができるようにしていきました。10月からは再度筆記試験に集中、直前一週間はA問題のみを黙々と解き続けました。
結果
A問題ほぼ満点、B問題5割、C問題7割程度でした。
初見のB問題に圧倒されましたが、数多くの体験談を心のよりどころとし、できる問題を取りこぼさないようにしました。A問題でしっかり点数を稼げていたのも精神衛生上よかったと思います。
口頭試問は経験のない症例でしたが、過去問でみた設問の組み合わせで対応できました。もう少しよく答えられた設問もありましたが、内容をまとめて簡潔に話すのが大切だと感じました。試験官にも恵まれたと思います。術前評価、麻酔管理、術後慢性疼痛と複数分野が入り混じっており、他医師や患者とのコミュニケーション力も問われているようでした。
改めまして、対策資料の作成誠にありがとうございました。
ぜひ後輩にも勧めたいと思います。
59回麻酔科専門医試験体験談:その14
合格体験記(50歳超の挑戦)
今年はとにかくCOVIDに振り回された.主催者側を含め、受験者側も皆同じ条件と言ってしまえばそれまでであるが、受ける方からすれば必死である.実技試験が免除され、それはそれで一つでも準備するものが減るのはありがたいことには違いないが、試験というのは何が起こるかわからない.一日一日試験日が近づいてくる不安な思いを経験するのは何年ぶりのことだろうか.
個人的には医師になり20数年のキャリアながら、色々あって2013年から麻酔科に転向、2017年から現在の臨床研修医も多く抱えるような病院に勤務となってからは、麻酔科専門医の肩書を持つ必要性を感じていた.それまでは、仕事として手術麻酔をかけ、それで給料がもらえるのなら、標榜医で十分と思っていた.が、環境が変わり、それなりの大所帯で、優秀な後輩は皆専門医.年齢的には上から数えたほうが早いという立場になって、専門医の肩書は言わずもがな必須というプレッシャーを感じるようになってしまった.
更に、専門医プログラムの移行期間とやらもあって、悠長に取得計画を立てている暇はない.40代半ばに専攻を変更し、50歳を超えて資格取得に躍起になっている変わり種であるが、母校の麻酔科勤務の同期からも「大変だぞ」の一言.この歳で励む姿は中年の星だと冷やかされ、ボケ防止にちょうど良いんヂャ無い?と軽口で切り替えしはしたものの、実際には必死にならざるをえなかった.
2017年に現在の職場に移ってから、そのような状況を自覚したので、専門医取得に向けての準備は早かったと思う.試験といえば、過去問.それしかない.王道であると思う.麻酔の合間やスキマ時間を使って過去問を解いた.3年間かけて過去5年以上の問題集を、直前のできなかった問題の答えだけ覚えるという作業を含めれば、7周回したような格好にはなる.歳を取ると記憶力が衰えるとか、いろいろな分析を耳にするが、衰えた分をカバーするためには、早く始めるしか無いと考えた.始めてみれば、頭を使ってなかった期間があまりに長すぎて、自分の記憶力がどれだけ衰えたのかを比較することができないと悟った.ただ勉強すればするほど、吸収するスピードは衰えてないように思うのだが、忘れるスピードはそれ以上に早くなっている気がした.これも実際にやってみないと分からないことである.
試験の傾向と対策の分析をやるべく、パソコンでまとめを作りかけたのだが、世の中には本当にマメな人がいるもので、自分の求めるものを代わりにやってくれている人がいた.このさらりーまん麻酔科医さんには本当に頭が下がる.自分が学生の時は、ひたすら過去問であったが、このネットの時代、情報を共有化してくれるありがたい存在は何事にも代えがたい.医学部に進学している息子の勉強法を見ても、過去問中心の取り組みは変わりないのだが、予備校のリモート授業など我々の時には存在しなかった手法を上手に取り入れていることも参考になった.ググってみれば、ユーチューブでの実技の動画など、求めている情報にいくらでも手軽くたどり着くことができる.
さて、このさらりーまん麻酔科医の青本、値段は決して安くないが、その労力への対価と試験突破の為の効率を考えたら安いものである.試験直前となってしまったが、過去問を何周か回した後、一度、青本を通して読んで整理してから、再び過去問をもう1週回した時、驚くほど正解率が向上していて、効果を実感出来た.歳がいってからの試験勉強、何が一番大変だったかというと、それは記憶力の衰えよりも、視力の衰えであることを痛感した.パソコンで調べ物をする時は、普段使いのメガネをしているのだが、テキストを読む時は、眼鏡ではピントが合わず、裸眼でとなる.この煩わしさ、理解できていない内容は余計にピントが合わなくなる.試験本番では勿論裸眼で挑んだのだが、万一のことを考え老眼鏡まで用意していた.症例問題での画像が小さいと、虫眼鏡まで必要なのでは?と不安になったが、杞憂に終わった.歳をとってから受けるものではない.
ほぼうん十年ぶりに取り掛かった勉強には戸惑いも少なからずあった.特に用語がバージョンアップしている点.心内膜床欠損症はECDと憶えていたのだが、現在では日本語では使ってもそのような略語は使わないと後輩から指摘.AVSDと言うらしい(こちらの方が理解しやすい).妊娠中毒症などもそうである.世の中の年寄り医者というのは、一部の物好きを除いて、自分が試験前に覚えた内容から、適時アップデートするなんてことは、まずやらないし、それでいて特に困らない.この歳になって、このような発見があったのも、ある意味、感謝すべきことなのかもしれない.
私は、学生時代、決して優秀な方ではなかったのだが、大学6年を通して再試が一つもなかったというのを密かに誇りにしている.秘訣もクソもない、最後まで諦めず、危機感を持って必死にやるだけ.特に筆記試験に比べ、その5日後にやってきた口頭試問は、明らかに準備不足を感じ、しかも出発前日はオンコールで夜遅くまで急患麻酔で残され、ほとんど準備に時間を割くことができなかった.そんな中でも、前泊したホテルで缶詰になり、最後まで諦めずにやれた.必死になっているのにも関わらず、集中力が続かないというもどかしさは感じたが・・・.結果は時の運も大きいが、おおよそ試験や選挙というものは、本人の実力以上に、必死さ加点の要素が大きいものだと信じている.ギリギリまで危機感をもって自分を追い込めるか、それだけだ.
それにしても疲れた.どうにか3科目とも合格したようだが、老体には堪えた.ただ、様々な理由で、かなり年齢を召されてから専門医合格を目指されている後続の方々にこの体験を捧げたく思う.気持ちの面で、自らを奮い立たせることに役立てていただけるならばこの上ない喜びである.
59回麻酔科専門医試験体験談:その15
無事に3科目とも合格することができました。ありがとうございました。
対策資料やブログの体験談には本当に助けていただきました。
今年度は新型コロナウイルスの影響でイレギュラーな対応が多く、そもそも試験が予定通り行われるかどうかの不安に始まり、実技試験の評価表依頼や体調管理のプレッシャーなど(当日発熱していたらアウト…)勉強以外の心労が多くかなり気疲れしました。
【筆記試験】
追い込まれると焦ってしまうタイプなので、前の年の夏頃からのんびり過去問を始めてトータル7年分を潰しました。
プール問題は多少改変されていても取りこぼさずに済むように解説の内容もある程度は頭に入れておきました。
(一部まるで解説になっていない解説もありますが…)
C問題はかぶらないのであまり熱心に周回する必要はなさそうですが、問題の雰囲気に慣れるのと予備知識を多少頭に入れておく意味でも一応確実に解けるようにしておきました。
歴史問題・統計問題は過去問に出たものだけ割り切って覚えました。
正解選択肢が解説と矛盾していたり、問題によって〇になったり×になったりする奇妙な選択肢も割り切って覚えました。
どうしてもある程度は丸暗記事項が出てくるので、ピックアップしておいて後でまとめて暗記が効率的かもしれません。
各種ガイドラインと、新型コロナウイルス関連の提言や指針なども学会HPに掲載があるものは目を通しておきました。
試験会場は入口で検温と誓約書の提出があり、長机一つに受験生一人の配置でした。
内容はA問題は例年通り、BC問題もきっと例年並の難易度だったのでしょうが難しく感じました。
Aで凡ミスをせず、BCは取れるところを確実に拾えば概ね大丈夫だと思われます。
【口頭試験】
口頭試験は対策資料を活用させていただきました。
ブログの体験談を読めば読むほど本当に自信が持てなかったので、せめて対策資料で解答例がある内容については答えられるようにすることを目標に、5分間でメモを作る練習と各質問に声に出して答える練習をしておきました。去年から1題のみになり症例がややとっつきやすくなった印象ですが、今年も同様の傾向だったように思います。
ガイドラインの聞かれそうな内容やトラブルシューティングについてはスムーズに答えられるようにしておきました。
試験官の先生お二人は終始穏やかな雰囲気で、5分ほど時間が余りました。
雑談はなく座ったまま無言で終了時刻を待ち、挨拶をして退室となりました。
59回麻酔科専門医試験体験談:その16
筆記試験
私は試験の1ヶ月前に出産予定だったので、早めに準備を開始しようと思い、1月から筆記試験の勉強を始めました。過去問7年分(ただし7年前の1番古いものはA問題のみ)をカウント忘れるくらいやり込みました。最初は時間をかけて、ノートを作りながら解いてました。2年前までの分をスラスラ解けるようになったところで、1年前の最新の過去問を本番と同じ時間内で解いて、自分の実力をはかりました。試験直前の数日はA問題の解き直しとガイドラインの読み込みをしました。
本番は、A問題は例年通りプール問題、B問題は聞いたことがないような言葉が出てくるような難解なもの、C問題はこんなものかという感じです。A問題さえほぼ満点取れていれば他はあまり差がつかないと思いますが、C問題も過去問をやり込むことで画像を頭にインプットして生かすことができます。本番前や合間の休み時間はほとんどの人が青本読んでましたが、私はガイドラインを読んでいました。合間の休み時間はガイドラインの見直しおすすめです。
口頭試問
対策としては青本の過去問を使って、自分で答えを作ってノートにまとめました。分からないことは臨床で上の先生に聞いたりして、自分なりの確固たる答えを自信もって言えるようにしました。
ホテルの一室を使い、アクリル板などでコロナ対策してました。職員用のエレベーターで指定された階に降り、部屋の前に案内されます。隣にはスタッフが付き、時間になると問題用紙とペンを渡されます。指定時間内に問題を読み、問題点や聞かれそうなことをメモします。時間になると用紙とペンをスタッフに預け、部屋に入れるようになると用紙のみ渡されます。ドアは開いてましたが、礼儀を重んじる試験官もいるとの噂だったので3回ノック→失礼します→御辞儀→中に入って受験番号と名前、よろしくお願いします→御辞儀をしました。どうぞと言われて椅子に座り、試験開始です。試験官は2人、1人は優しい感じで質問する方で、もう1人はただ黙ってこちらを見たり下をみたり。人によってはうなずいてくれたりするそうです。画像や追加の所見はモニターに映し出されます。終わった後は、よく出来ていたと思いますと言われ、雑談をしました。時間にならないと部屋から出られないので、その間雑談か静かに待つ感じになるそうです。
59回麻酔科専門医試験体験談:その17
無事に合格できました。
(実技試験)
・今年はコロナの影響で、実技試験はプログラム責任者による評価表による評価。
・期日の10/19までに学会に提出してもらえるように、プログラム責任者にお願いしました。
(筆記試験)
・約1年前からコツコツと過去問で勉強をはじめました。
・過去問5年分を3周プラスαしました。
・自分の苦手な問題や単純暗記内容をノートに手書きでまとめたり、ネットから得たものはEvernoteにまとめて、繰り返し見直していました。
・遠方でしたので、ポートピアホテルに前泊。
・A問題が11時開始で、まとまった昼食時間はなし。終了は17時半くらい。
・受験生は各々短い休み時間にエネルギー補給できるものを持ってきていました。
・A問題は例年通りほぼ過去問からの出題。5年よりもさらに過去の問題からも出ていたか。
・B問題は例年より解き易かった印象。
・C問題は例年より難化。小児、心臓、ペインからの出題比重が増えた印象。周りの人も口を揃えて難しいと言っていました。
(口頭試験)
・実際に対策を始めたのは筆記試験後からです。ただし、過去問を見たり、「麻酔科専門医口頭試験の達人」を読んだりはしていました。
・過去10年分くらいの過去問を見通し、苦手分野から潰していきました。
・声に出して質問に答える練習をするのが大事だと思いました。
・遠方でしたので、ポートピアホテルに前泊。
・集合時間が1時間毎に設定。
・おそらく同じ集合時間の人は同じ問題だったと思われます。
・全体説明の際、説明者の声がとても聞こえづらく(マスクとフェイスガードによって)、近くにいた係員に聞こえません!と言ったら、再度説明をしてくれました。
・ドナドナエレベーター内で「ドナドナ」を歌う人はいませんでした。
59回麻酔科専門医試験体験談:その18
今回の試験では大変お世話になりありがとうございました。
二人の子育て中で夫も当直オンコールで忙しく、なかなかまとまって勉強する時間が取れないと思い、筆記対策は1月から始めました。
まずは1日10問、2年分を一ヶ月でこなし、3月までにトータル6年分を一周しました。それから6月までに2周。8月までに3周。8月頭に58回を時間を図って模擬試験的に解き、A問題は8割ほど解ける状態になりました。BCは今解いても本番とさほど正答率は変わらないだろうと思い、A問題の精度を上げようと○☓問題も始めました。これが良かったです。
本番までに7年分5周しました.
A問題が終わってすっかりリラックスしてしまい、BC問題はあとどれくらい取れるかと思ったら楽しくなってきましたが、周囲では試験時間中もため息が漏れていました。
ペイン関連が多かったように思いますので、ペインの勉強を早めに始めるのも良いかもしれません。
ちょうど前年度にJBPOTの試験も受けていたので、循環器関連も多かった気がしますが簡単でした。
covid関連も増えると思い、学会のガイドラインは何度も目を通しました。
口頭試問対策は、早めに始めよ、という先輩のアドバイスにより、8月の筆記模擬試験のあとから、C問題対策にもなると思い、青本を読みつつ、声に出して答える訓練をしました。青本をベースに自分で調べたことを書き込んだり、ガイドラインを読んだりして、知識を深めました。結局、5年分3周し、それより前の年度も、先輩の青本を借りて、読み込みました。
経験したことのある症例でしたが、普段やってることも緊張すると忘れます。やはり口に出して練習することが大切です。
最後は時間があまり、緊張してましたね〜と試験管の方が勞ってくれました。
やはり早めに口頭試問の準備は進めておいて良かったです。筆記試験後、4日ありましたが、筆記試験翌日は疲労で何もできず、青本を眺めることしかできませんでした。
筆記試験と口頭試問のみでしたが、特に口頭試問では青本にお世話になりました。本当にありがとうございました。
子育てしながら、フルタイム、夫婦ともに当直ありで、なかなか試験勉強時間が取れず、辛かったのですが、なんとか合格できたのは青本のおかげです。
59回麻酔科専門医試験体験談:その19
<第59回麻酔科専門医体験記>
【試験結果】
筆記試験 不合格
口頭試験 合格
実技試験 合格
【試験対策】
〇勉強スケジュール
大学にいたので、1年前より1つ上の先輩が受験する資料をチラ見しながら問題に少し触れました。
本格的に勉強をはじめたのは受験年の3~4月です。学生と違って通常業務がある中での試験勉強はとにかくまとまって時間を確保するのが難しく、勉強法を変えるなどの工夫が必要でした。
〇勉強法
★使ったもの
青本(第59回受験用)、過去問集5年分、医師国試受験の際のまとめノート
◆筆記試験
過去問5年分。直前1ヶ月までは4年分をひたすら周回し、1ヶ月前に腕試しに昨年の問題を通しで解きました。勉強法は、過去問集のA・B問題をガイドライン別に分類し、Wordで問題集を自作しました。
それをPDF化し、iPad miniにいれて時間の合間を見てはとにかく問題を解いていました。
麻酔中に、抄読会の準備のため論文を読んだり寝たり(笑)する時間をその勉強時間にあてた感じ。
青本は過去問5年分で問われた部分はチェック。それ以前のものはスルーしました。
時折もりこまれているさらりーまん先生の語り口調の文言が癒しになりました。
ありがとうございました(笑)。
◆口頭試験
青本のみが頼りになりました。筆記試験が終わって1週間もない時間で準備をしなければならないので結構苦しかったですが、普段の業務内で経験できる症例であれば「普段通り」を意識して、模範解答を覚えこみました。ファイバー挿管等めったにない症例・手技は青本の解答例を参考にイメトレしながら声に出して言えるようにしました。研修医もうまく活用しました。
◆実技試験
新型コロナウイルス感染対策で今年は評価表による合否判定になりました。基準は何なのか。
大学の医局所属なので、そのままプログラム責任者の評価となりました。
先輩からは『ちゃんと菓子折り持って行ったか!?』と冗談で言われましたが(笑)
59回麻酔科専門医試験体験談:その20
無事、合格しました。
ありがとうございました。
結局、成書なぞ読む時間と気力はさらさらなく、
試験対策は青本のみでしたが、本当に十分でした!
青本で勉強したことで、試験対策はもちろんですが、
ふだんの臨床についても改めて勉強することができました。
ありがとうございました。
59回麻酔科専門医試験体験談:その21
初受験でしたが、無事全科目合格することができました。先生の青本のおかげです。本当にありがとうございました。
地方病院勤務で今年の専門医試験の受験が私一人だったので、試験の情報は先生のHPの体験談と青本が頼りでした。
特に口頭試問は、筆記試験が終わってからの4日間で青本を読み込んで勉強したのみだったので、青本が無ければ合格はありませんでした。
コロナで実技試験がほぼ書類審査のみになったぶん、口頭試問が難しくなるのではと冷や冷やしていましたが、結果としては青本で十分でした。(問題の当たりの運もあるとは思いますが…)
筆記試験のC問題でガツンと頭を打たれ、口頭試問へのモチベーションが保てない中、青本は「みんなと同じ勉強をしている」という心の拠り所になりました。
(オンライン版をご用意いただきましたが、紙に書き込んだり「本の真ん中のあの当たりに書いてあった…」という丸暗記の覚え方をする身としては紙版ばかりを使っておりましたので、オンライン版の感想は述べることができません。すみません。
個人的には筆記試験まとめも非常に助かりました。試験の最中に「青本で見たやつだ」と思い出して選択肢を選ぶことができた問題もあったので)
重ね重ねありがとうございました。
今後後輩にも青本を勧めたいと思います。
59回麻酔科専門医試験体験談:その22
大変お世話になりました。
無事に合格することができました。
口頭試験はほとんど対策できず、筆記試験が終わってから、とにかくサラリーマン先生の本を読んでいました。私はまとめノートは全く作っていなかったので、本当に助かりました。全部で20分でした。正直、オーソドックスな問題で、普段の麻酔のみで十分答えられる問題でしたが、焦ってしまいしどろもどろになってしまいました。正直ダメかと思いましたが、何か答えるという姿勢で望むことで合格出来たように思います。
本当にありがとうございました。