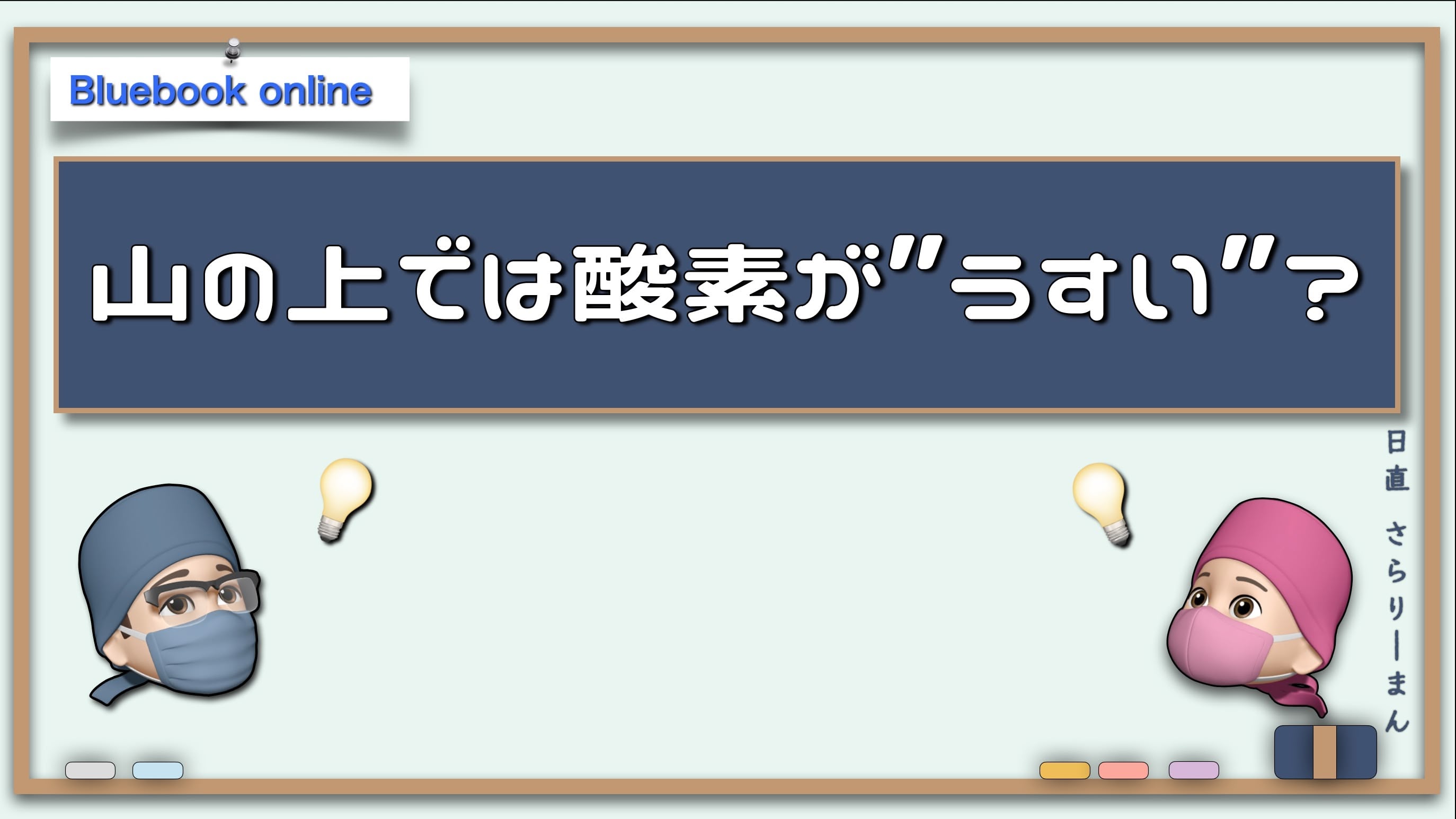👉👉 🇺🇸 All Posts 🇬🇧 / 🇯🇵 記事一覧 🇯🇵 👈👈
♦️ はじめに
 なっちゃん
なっちゃんニュースとかテレビでも「山のてっぺんは空気がうすい」って聞いたことあるのでそう思ってました



私も昔そう思ってた.確かにその表現のほうがピンとくるイメージがあるからね



先生のてっぺんもだいぶうすく・・・



みなまで言うな
酸素がうすいのか・・?
今日は余談を一つ.
よく,エベレストや富士山の頂上で,「ここは地上と比べて酸素が薄いから息が続かない,すぐに疲れるから酸素ボンベが必要」などと言っているのをテレビなどで見たことがあると思います.
でもこうも聞いたことがないですか?「地球上では酸素濃度はどこでもほぼ一緒」と.どっちが正しいのでしょうか?
🔷 酸素”濃度”はどこでも一緒
結論から言うと,地球上では「酸素濃度はどこでも一緒」です.その濃度はおよそ21%(厳密には20.9%).残りは窒素がほとんどで,あとは微量ガスが占めます(温暖化で話題の二酸化炭素も,大気中の濃度は窒素や酸素と比べると微量).
これは砂漠の真ん中でもジャングルのど真ん中でも海のど真ん中でも,ほぼ同じです(これも不思議ですね😃.これは大気の層の厚さや大気の循環などが関与しているそうです).
🔷 それなら地上と高地では何が違う?
では地上と山の上など高地では何が違うのでしょうか.
答えは「圧力(気圧)」です.気圧は天気予報でよく聞きますよね.「高気圧が張り出していて・・」「爆弾低気圧が・・・」「現在の台風10号の中心気圧は・・・」などと.
海抜0mが1気圧.1気圧は1,013hPa(=760mmHg)
この定義は覚えるしかありません.「hPa」や「mmHg」に関しては別の記事で取り上げたいと思いますが,今回はこの数字,特に760mmHgを覚えてください.760mmHgは自分の頭の上に乗っている空気は水銀柱(Hg)を760mm押し上げるくらいの力ということです(昔理科の実験で見たことがあるかもしれません).
ガスの濃度で気圧を”分け合う
とりあえず地表ではガスの集合体(空気)に760という力があると思ってください.そしてこれをガスの濃度の比率で分け合っています.ここでは簡便のために,窒素が80%,酸素が20%とします.
- 地表の大気圧は760mmHgです.
- 窒素は大気圧の約80%を占めています → 760 × 0.8 = 608 mmHg
- 酸素は大気圧の約20%を占めています → 760 × 0.2 = 152 mmHg
このおよそ150mmHgというのが地表での酸素の分圧(酸素の押す力).圧力は突き詰めれば「ある一定の空間に存在する分子の数(密度)」と考えるとイメージしやすいです.分子の数が多いほどぎゅうぎゅうになるイメージです.
圧力は高いところほど弱くなる
重力もそうですが,気圧も地表に近ければ近いほど高くなります.高い山の上では登っただけ気圧が下がります(頭の上にある空気の量が少ないから).
- 富士山山頂(3,776m)ではおよそ630 hPa(約470 mmHg) → 地表の約62%.
- エベレスト山頂(8,848m)ではおよそ330 hPa(約250 mmHg) → 地表の約33%.
地表では760の力があったガスの集合体も,エベレスト山頂ではその1/3,つまりおよそ250の力しかありません.そしてその250の力を濃度の比率で分け合うので,酸素は,
- 富士山頂:470 × 0.21 ≈ 98 mmHg
- エベレスト頂上:250 × 0.21 ≈ 52 mmHg
150 → 50 とおよそ1/3になってしまいました.
高地で息が苦しくなる理由
圧力は「分子の量」に対応しているので,エベレスト山頂には地表の1/3の酸素分子しか存在しません.同じ体積の空気を吸っても酸素が足りなくなっているのです(地表で吸ったら150個吸えたのに,エベレストでは50個しか吸えないのと一緒).
イメージとしては,おなじ濃さのカルピスでも──
コップ1杯飲むのと,半分しか飲めないのとでは,体に入る糖分の“量”が全然違うのと一緒.
これが高地で息が苦しくなる理由です.そのため,できる限り「酸素の量」を確保するために酸素ボンベを使用するということです.
ただし,一般的には「酸素が薄い」と言った方がイメージがつきやすいので,この表現が用いられているのだと思います.
もし地表で気圧をそのままにして酸素の「量」を減らそうとしたら,その空間の酸素「濃度」を下げる必要があります.760の中の50にするので,濃度はわずか6〜7%! 普段の1/3.そりゃ苦しいわ・・ということになります😅
🔷 まとめ
- 高地では酸素の濃度が低いのではなく,圧力(酸素分圧)が低い.
- つまり,その中を占める酸素の「量(分子の個数)」が少ない.
- これは「地表で酸素濃度を下げる」のと同じ効果を生む.