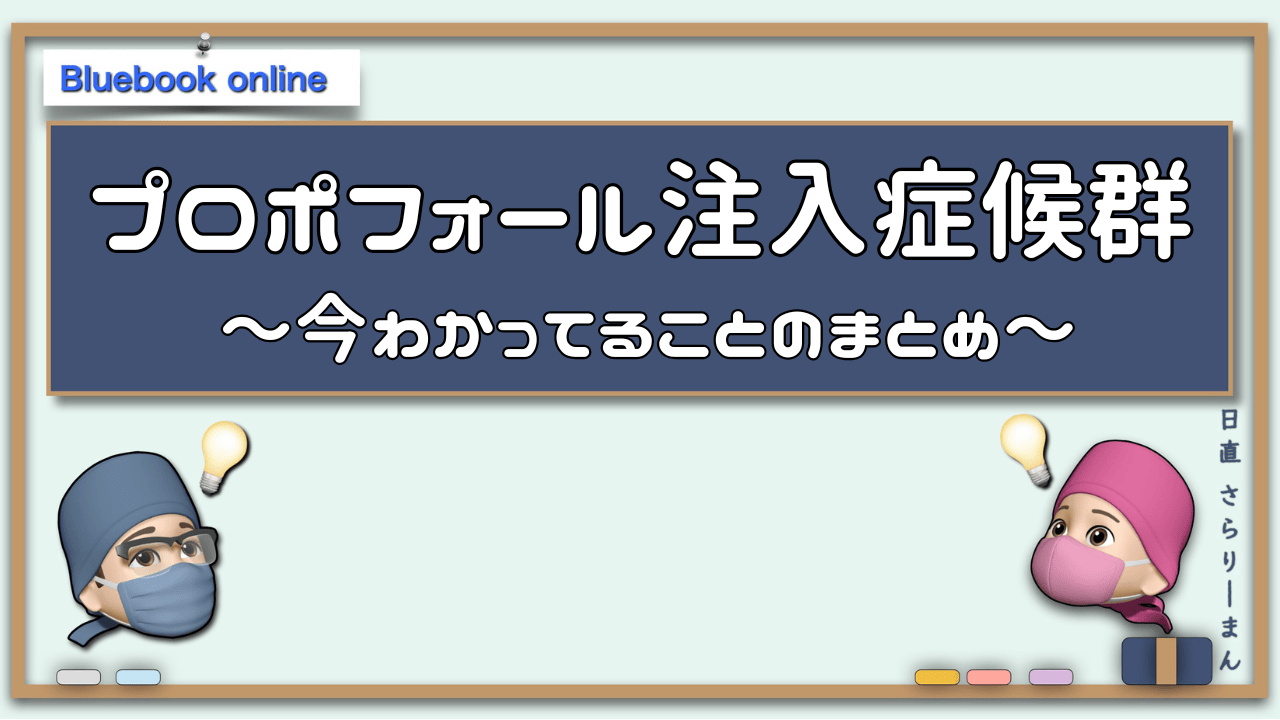👉👉 🇺🇸 All Posts 🇬🇧 / 🇯🇵 記事一覧 🇯🇵 👈👈
♦️ はじめに:知っておかなければ危険な副作用
「導入も覚醒も速い.扱いやすい.」——プロポフォールは現代の麻酔領域を支える所要な薬物です.だからこそ,まれですが致死的な合併症であるプロポフォール注入症候群(Propofol Infusion Syndrome: PRIS)について知っておくことが大事です☝️
1990年が初報,1998年のBrayによる命名とされています.本邦でも2014年の小児重大事例を契機に,2015年には日本集中治療医学会が指針を発表——危険性は広く共有されています.
💡この記事で得られること
- 現場での早期発見・即応のポイント.具体的なサイン,用量・期間の目安,代替鎮静,支持療法まで,定義から予防について.
- 試験頻出ポイントの整理☝️
♦️ そもそもPRISとは何か🤔:定義と診断基準
PRISは「プロポフォール投与中または投与後に発症する急性心不全(徐脈性不整脈、心停止を含む)に,以下の1つ以上の代謝異常を伴う症候群」と定義されます(Kam & Cardone, 2007; Singh et al., 2022)。
🔷 診断基準(必ず以下の1つ以上を伴う)
- 代謝性アシドーシス(BE < -10 mmol/L)
- 横紋筋融解症
- 高脂血症(特にトリグリセリド上昇)
- 肝腫大または脂肪肝
⚠️重要:心停止は必須ではありません.早期には難治性徐脈や心筋収縮力低下(昇圧薬への反応性低下)として現れます.心停止に陥る前に,早期サインを拾うことが肝心です‼️
【試験のポイント】CRASHで覚える☝️
- Cardiac failure(心不全・徐脈・心停止)
- Rhabdomyolysis(横紋筋融解症)
- Acidosis(代謝性アシドーシス)
- Steatosis(脂肪肝)
- Hyperlipidemia(高脂血症)
🔷 発生率と致死率
- 成人ICU患者:0.3–1.1%(Kam, 2007; Singh, 2022)
- 小児ICU患者:1–5%(高用量・長期投与で上昇)
- 手術麻酔(短時間):極めて稀(0.01%未満)
軽症例は見逃される可能性があるため,実際の発生率はもっと高い可能性もあります.一度本格的に発症すれば致死率は18–52%と高率.特に小児52%,成人48%とも言われています(Yasin et al., 2023).
早期発見・早期対応が予後を左右します.
♦️ そもそもなぜPRISは起こるのか:2つのミトコンドリア障害
病態の中核はミトコンドリアの機能不全(Vasile et al., 2003; Singh et al., 2022)とされています.
プロポフォールは主に二つの経路で細胞エネルギー産生に障害を及ぼします.
🔷 ミトコンドリア呼吸鎖の阻害
複合体の番号など,あまり細かなことは覚える必要はありませんが😅,以下のようなメカニズムです.
- ミトコンドリア電子伝達系複合体IおよびII(報告によりIVを含む)を阻害 ⤵️
- ATP産生低下 ⤵️
- 細胞性低酸素 ⤵️
- 心筋・骨格筋の直接的な機能不全に陥る😓
🔷 脂肪酸β酸化の障害
ICUに入室するような重症患者は脂質依存に傾きがち.プロポフォールはカルニチンシャトル(CPT-1/2)やアシルCoA脱水素酵素などを妨げると考えられており,脂肪酸処理不全と毒性中間体蓄積を招きます.
🔷 病態の統合理解
以上の二つの機序が重なり,ATP枯渇 + 有毒物質蓄積 → 代謝性アシドーシス,心筋障害,横紋筋融解症を来します.
🔑 キーワードは,以下の二つ.
- 呼吸鎖阻害によるATP産生不全
- 脂肪酸β酸化障害による有毒中間体蓄積
♦️どんな患者が危険?🤔:5大危険因子
単一の要因があるだけでは高リスクでなく,複数のリスクが重なることでで発症リスクが跳ね上がるとされています.
🔷 1. 投与量と投与期間
4 mg/kg/時(≒67 μg/kg/分)超を48時間以上が典型的ハイリスク(試験にも頻出)(Kam & Cardone, 2007)
⚠️注意:これ以下であれば100%安全というわけではありません.より低用量・短期間でも発症の報告があります(Zhang et al., 2025では累積100 mg/kgで発症)
☝️【国際比較:ICU鎮静の推奨投与量】
- 日本:成人で4 mg/kg/時(67 μg/kg/分)を上限の目安(日本集中治療医学会)
- 南アフリカ(SASA 2020):80 μg/kg/分(4.8 mg/kg/時)上限
- 欧米一般:50 μg/kg/分(3 mg/kg/時)以下を目標とする保守的傾向
📌いずれも閾値であって安全宣言ではないことに注意です⚠️.低用量・短期間が基本方針です‼️
🔷 2. 患者背景
- 若年(特に小児)
- 重篤な基礎疾患(敗血症,外傷性脳損傷,てんかん重積など)
- 高齢(代謝予備能低下)
🔷 3. 併用薬
- カテコールアミン(ノルアドレナリン,アドレナリン)
- 副腎皮質ステロイド
🔷 4. 代謝状態
- 炭水化物不足(飢餓,糖投与不足)
- 高脂血症(ベースライン)
- 腎機能障害
🔷 5. 潜在的な基礎疾患
- 潜在性ミトコンドリア病
- 脂肪酸代謝異常症(原則禁忌)
⚠️ 例:このような場合は特に危険⤵️
重症敗血症 + カテコラミン/ステロイド併用 + 糖負荷不十分のまま4 mg/kg/時で開始
♦️ どうやって気づく?🤔:早期診断のサイン
予後は早期発見で決まります(Singh et al., 2022; Nickson, 2024).
🔷 早期の兆候(最重要モニタリング)
1️⃣ 説明のつかない代謝性アシドーシス
最も早期に出現しやすいとされています.
- 乳酸 ≥ 2 mmol/L(特に ≥ 4)
- BE < −10 mmol/L
- アシドーシス進行(他原因で説明不可)
2️⃣ 循環動態の変化
- 説明のつかない洞性徐脈(進行性)
- 昇圧薬への反応性低下(要求量増大)
- 心拍出量低下(可能なら評価)
3️⃣ ECG(心電図)の変化
進行例で生じるとされています.
- V1–V3のBrugada様ST上昇
- 右脚ブロック
- 房室ブロック
- 幅広いQRS
⚠️注意:ECG変化は重症化のサインで,早期発見には不向きです.徐脈と昇圧薬反応性低下がより重要です.
🔷 進行期の兆候:こうなると危険⚠️
4️⃣ 横紋筋融解症
- CKの上昇(PRISの重要所見ですが,具体的数値閾値はガイドラインで定められていません.臨床経過と併せて総合的に評価が必要です)
- ミオグロビン尿
- AKI
5️⃣ 高トリグリセリド血症
- TG ≥ 500 mg/dL
- 乳濁血清(milky)
6️⃣ 肝機能障害
- AST/ALT上昇
- 肝腫大
- 脂肪肝所見
🔷 注意点☝️
- 数値だけのモニタリングには限界があります.CKや乳酸の数字だけに頼ると「偽の安心感」。臨床所見(徐脈、反応性低下、アシドーシス進行、ECG変化)と総合判断が不可欠です(Van et al.(2023)).
- 緑色尿は緑色尿はプロポフォール代謝産物由来でPRISと無関係(10〜30%に非特異的出現)なため,診断根拠にはなりません.
♦️ どう対応・治療するか🤔
特異的は解毒剤・治療薬・治療法はありません😓
「疑ったら即中止」+「徹底的な支持療法」が原則(Singh et al., 2022)になります.
🔷 Step 1: プロポフォールの即時中止
疑った時点で直ちに中止‼️.これが唯一の根治的な介入になります.鎮静の継続が必要な場合,別の鎮静薬を検討します.
👉代替鎮静薬への切り替え例
- ミダゾラム
- デクスメデトミジン:循環影響に注意.呼吸抑制は少
- 鎮痛ベースの鎮静を考慮:レミフェンタニル等 + 浅い鎮静
➡︎患者の循環・呼吸・鎮静目標で,個別に検討が必要です.
🔷 Step 2: 全力での支持療法
循環の補助
- 体外式ペーシング(難治性徐脈に対して)
- 昇圧剤増量(反応性は低いことが多い)
- ECMO:慣れていない施設ではハードルが高いですが,ECMO(VAまたはECPELLA併用を含む)導入が報告上有効とされています.
代謝性アシドーシスの補正
- 重炭酸ナトリウム
- 適切な換気管理
血液浄化療法(CRRT/HD)
- アシドーシス補正
- 高K対策
- 横紋筋融解症に伴うAKI管理
⚠️補足:透析での直接除去は限定的です.目的は代謝破綻の補正.
高カリウム血症の治療
- カルシウム製剤
- GI療法
- β2刺激薬
- 陽イオン交換樹脂
- 血液透析(重症)
その他
- 十分な糖負荷(脂肪酸依存を下げる)
- 体温管理(代謝需要を抑える)
- カルニチン補充(症例報告レベルのエビデンス)
♦️ PRISの予防は可能?🤔
致死的な疾患ですが,以下の予防・対策が有効であると示唆とされています(Kam & Cardone, 2007; Fox, 2018)😊
🔷 1. 投与量・期間の厳守
- 上限:4 mg/kg/時(≒67 μg/kg/分)
- 期間:48時間超は回避.やむを得ず超える場合は厳重モニタリング
⚠️絶対的安全域ではない.低用量・短期間を徹底‼️
🔷 2. 適切な炭水化物(糖)の負荷
- 小児:6–8 mg/kg/min(Kam,2007)
- 成人:最低2–4 mg/kg/min
飢餓下の投与は避ける.
🔷 3. 高リスク患者での使用回避
- 既知のミトコンドリア病(私は見たことないですけど・・)
- 脂肪酸代謝異常症(CPT欠損、MCAD欠損など)
➡︎原則禁忌.
🔷 4. 脂質負荷の軽減
- 高濃度製剤(例:2%プロポフォール)の検討(Singh A, Anjankar, 2022)
- 2%製剤は静注部位痛の報告増大等もあり,小児には原則使用非推奨.成人では脂質過剰対策として一部推奨例がある程度.
🔷 5. 厳重なモニタリング
- 血液ガス(乳酸・BE):少なくとも1日1回
- CK:48時間ごとまたは臨床的疑い時
- TG:48時間ごと
- ECG:連続的に
- 肝機能(AST/ALT):定期確認
🔷 6. 感染対策
プロポフォールは脂質乳剤で微生物増殖リスクあり。
- 12時間毎のライン交換
- 無菌操作の徹底
- 開封後は速やかに使用(丸石製薬資料)
♦️ 小児における特別な注意点👶
当初は小児での報告が多く,死亡率も52%と高率です(成人48%)(Yasin et al., 2023).
🔷 国際比較:FDA規制の背景
🇺🇸 米国FDA承認
- 麻酔導入:3歳以上
- 麻酔維持:2ヶ月以上
➡︎ICU鎮静目的は未承認・禁忌(Fox, 2018).背景には1990年代の小児死亡例(Parke et al., 1992; Bray, 1998).
🔷 国際比較:小児ICU鎮静の実態
- ミダゾラム,デクスメデトミジン
- 鎮痛ベース:フェンタニル/モルヒネ + 浅い鎮静
- 術後の短期投与:24時間以内ならプロポフォールを慎重に用いる場合があるようですが,手術室外でに使用は慎重であるべきとされています.
🔷 本邦の指針🇯🇵
代替薬の承認状況・経験の違いから「代替薬がない」場面もあります.2015年,日本集中治療医学会の小児持続投与指針が公表されています(リンク:https://www.jsicm.org/pdf/propofol1508.pdf)
小児麻酔においてプロポフォールを使用することは一般的ですが,集中治療における人工呼吸中の鎮静には禁忌となっています.
📝 試験と臨床で活かすPRISの知識
プロポフォールは有用.しかし常にPRISのリスクはあります.発症予測は困難でも予防はできる.
🔷 試験対策として押さえるべき3点✏️
診断基準(CRASH)
- Cardiac failure/Rhabdomyolysis/Acidosis/Steatosis/Hyperlipidemia
病態生理(ミトコンドリア障害)
- ①呼吸鎖阻害によるATP産生不全
- ②脂肪酸β酸化障害による有毒中間体蓄積
危険因子
- 投与量・期間:4 mg/kg/時超・48時間以上
- 併用薬:カテコラミン、ステロイド
- 代謝:炭水化物不足
- 背景:小児、重症
🔷 臨床実践で重要な3点
1. リスク評価
重症度、カテコラミン/ステロイド併用、糖負荷不足の重積を常にチェック。
2. 早期発見
「4 mg/kg/時以下・48時間未満」でも起こることを念頭に:
- 原因不明のアシドーシス(乳酸↑、BE < −10)
- 説明のつかない徐脈/昇圧薬反応性低下
- Brugada様ECG(進行例)
3. 即時対応
疑ったら:
- プロポフォール即中止
- 代替鎮静へスイッチ(ミダゾラム、デクスメデトミジン等)
- 支持療法を開始(ECMO/CRRTの準備を迅速に)
📝 まとめ:Take Home Points
- PRISは「急性心不全+(代謝性アシドーシス/横紋筋融解/高脂血症/脂肪肝のいずれか)」で疑う.必ずしも心停止は要件ではない(早期は徐脈・昇圧薬反応性低下).
- 【暗記】CRASH:Cardiac failure/Rhabdomyolysis/Acidosis/Steatosis/Hyperlipidemia。
- 病態の核心はミトコンドリア機能不全:①呼吸鎖阻害によるATP低下+②脂肪酸β酸化障害(毒性中間体蓄積)。
- ハイリスク条件:4 mg/kg/時超 × 48時間以上(安全域ではない)。低用量・短期間でも発症しうる。
- 危険因子の重なりでリスク増:小児/重症(敗血症・TBI等)/カテコラミン・ステロイド併用/糖負荷不足/腎障害/潜在ミト疾患・脂肪酸代謝異常。
- 早期サイン:原因不明の乳酸上昇(≥2、とくに≥4)・BE < −10、進行する代謝性アシドーシス、洞性徐脈、昇圧薬反応性低下。
- ECG変化(Brugada様ST上昇、RBBB、房室ブロック等)は進行例の所見。早期発見は臨床サイン重視。
- 高度進行でCK ≥ 5,000(とくに≥10,000)、TG ≥ 500 mg/dL、乳濁血清、AKI、肝障害。緑色尿は特異的でない。
- 疑ったら即中止:プロポフォールを直ちに停止し、ミダゾラム/デクスメデトミジン/鎮痛ベースへスイッチ。
- 支持療法:難治性徐脈に体外式ペーシング、ECMOは心停止前の早期導入を検討。アシドーシス補正、高K治療、CRRT/HD(目的は代謝補正;プロポフォール除去は限定的)。
- 予防:投与はできる限り低用量・短期間。糖代謝を守るため十分な糖負荷(成人2–4 mg/kg/分、小児6–8 mg/kg/分)。高濃度製剤(2%)の活用で脂質負荷低減も一案。
- モニタリング(高リスクでは強化):ABG(乳酸・BE)毎日、CK/TG 48時間ごと、ECG連続、肝機能定期。
- 小児:日本集中治療医学会(2015)—2.0 mg/kg/時以下、48時間以内(最長72h)、糖6–8 mg/kg/分以上、厳格監視。FDAはICU鎮静を未承認(禁忌)。
- 明日の臨床での合言葉:「量・時間・糖」を守り、徐脈+アシドーシス+反応性低下を見たらPRISをまず疑う。
📚 References & Further reading
- Bray RJ. Propofol infusion syndrome in children. Paediatr Anaesth. 1998;8(6):491-9.
- Folino TB, Muco E, Safadi AO, Parks LJ. Propofol. In: StatPearls
- Fox SM. Propofol Infusion Syndrome in Children. Pediatric EM Morsels. 2018 Oct 5.
- Kam PCA, Cardone D. Propofol infusion syndrome. Anaesthesia. 2007;62:690–701.
- Nickson C. Propofol-related Infusion Syndrome. LITFL. 2024 Dec 18.
- Parke TJ, Stevens JE, Rice AS, et al. Metabolic acidosis and fatal myocardial failure after propofol infusion in children: five case reports. BMJ. 1992;305(6854):613-6.
- Singh A, Anjankar AP. Propofol-Related Infusion Syndrome: A Clinical Review. Cureus. 2022 Oct 17;14(10):e30383.
- SOUTH AFRICAN SOCIETY OF ANAESTHESIOLOGISTS (SASA). SASA Guidelines for the safe use of procedural sedation and analgesia for diagnostic and therapeutic procedures in adults: 2020–2025. SA J Anaesthesiol Analg. 2020;26(2):VI-75.
- Van S, Lam V, Patel K, Humphries A, Siddiqi J. Propofol-Related Infusion Syndrome: A Bibliometric Analysis of the 100 Most-Cited Articles. Cureus. 2023 Oct 4;15(10):e46497.
- Vasile B, Rasulo F, Candiani A, Latronico N. The pathophysiology of propofol infusion syndrome: a systematic review of the literature. Intensive Care Med. 2003;29(9):1417-25.(abstract)
- Yasin F, Hibberd O, Rhodes H. Propofol-related Infusion Syndrome. Don’t Forget the Bubbles. 2023 Nov 23.
- Zhang H, Liu Y, Liu M, Li B, Li H. Propofol-related infusion syndrome happened in a non-critically ill perioperative young patient: A case report. SAGE Open Medical Case Reports. 2025;13:1-5.
- プロポフォール. フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 [Internet]. [最終更新 2024年10月19日]
- 丸石製薬株式会社. 全身麻酔・鎮静用剤 プロポフォール |丸石製薬株式会社. 2025.
- 日本集中治療医学会. 小児集中治療におけるプロポフォール持続投与に際しての指針. 2015.