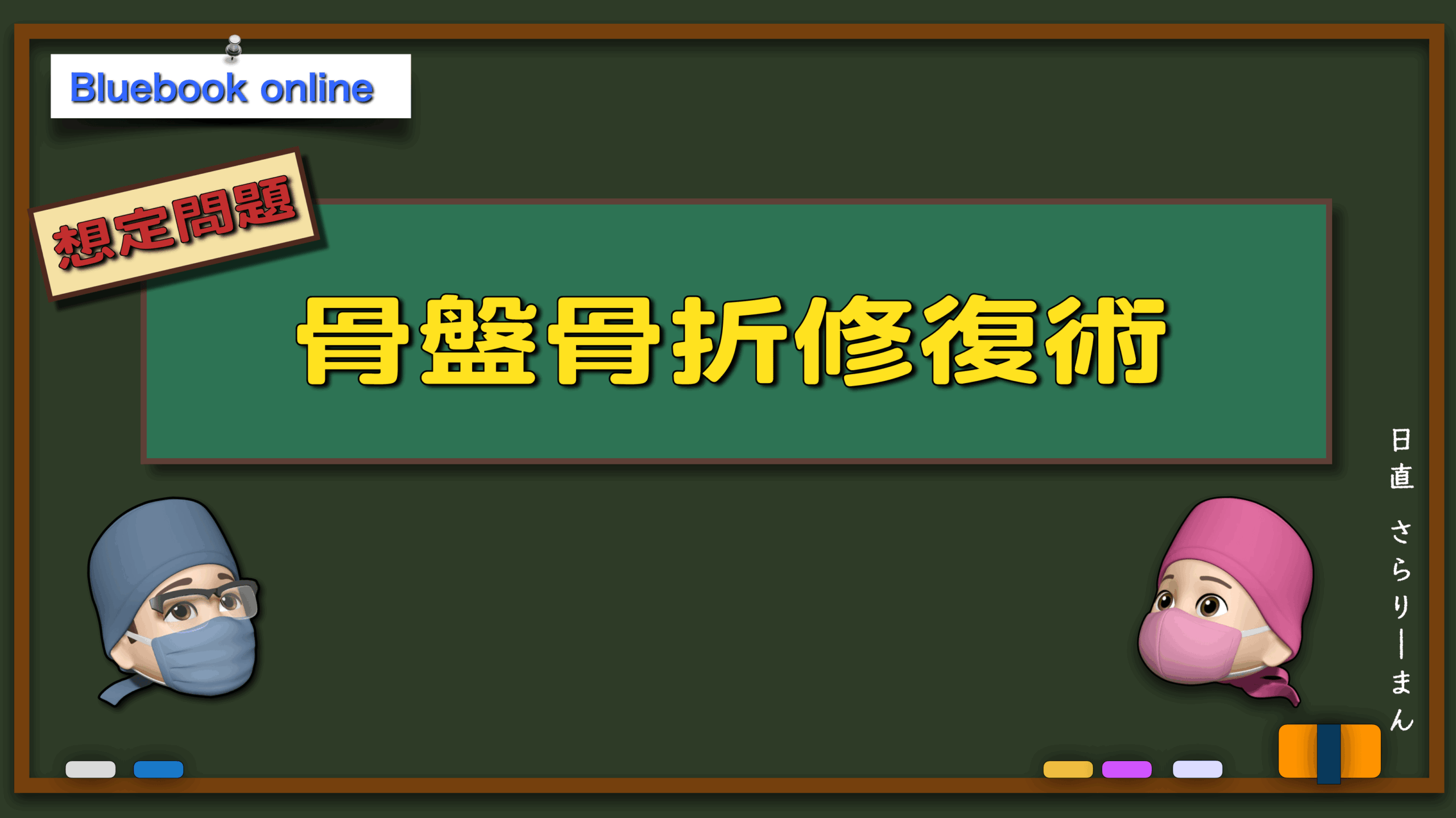症例設定
【患者】
- 28歳女性。165cm、95kg(BMI36.0)
【現病歴】
- 乗用車側面衝突事故(高エネルギー外傷)で受傷し救急搬送。両側恥骨骨折と仙腸関節離開を認める骨盤輪不安定骨折(APC type III)、骨盤腔内からの活動性出血あり。
- ハイブリッドORでIVRを先行的に行い、動脈性の出血を止血した後、創外固定を行うことになりました。
【既往歴】
- Brugada症候群(type 1 ECGパターン、無症候性、ICD未挿入)
- 小児喘息(現在寛解)
- 喫煙:10本/日×8年
【内服中薬剤】
- なし
【家族歴】
- 父が45歳時に突然死
【主な検査所見・バイタルサイン】
ER搬入時バイタルサイン
- BP 92/58 mmHg、HR 118/分、RR 24/分、SpO₂ 94%(リザーバマスク10L/分)、体温 35.8℃、GCS E4V5M6
身体所見
- 気道:Mallampati分類 III度、短頸、頸椎カラー装着中。
- 呼吸:両側呼吸音清、頻呼吸、浅呼吸
- 循環:蒼白、冷感四肢、毛細血管再充満時間>3秒、骨盤部圧痛著明、骨盤ベルト装着中
- ショック指数(SI): 1.28(>1.0で出血性ショック疑い)
血液検査
- Hb 8.6g/dL(搬入後急速に低下)、Plt 15.2万/μL、
- PT-INR 1.42、APTT 42秒、Fib 158mg/dL、D-dimer 25.4μg/mL
- Cr 0.9mg/dL、K 3.8mEq/L、Ca 7.6mg/dL(イオン化Ca²⁺ 0.88mmol/L)、乳酸 4.2mmol/L、BE -6.8mmol/L
画像検査など
- 心電図:V1-V2誘導でcoved型ST上昇(type 1 Brugadaパターン)、QTc 380ms、散発性PVC
- 骨盤部CT/X線でAPC type III骨盤輪不安定骨折、造影CTで骨盤内血管外漏出像、骨盤血腫あり、推定出血量1500mL以上
- 気胸、縦隔気腫なし
- FAST:骨盤腔内液体貯留(+)
- 頸椎病変や症状は否定的。
救急処置:
- 18Gの静脈ライン2本(左右前腕1本ずつ)、右内頸静脈からCVカテーテル挿入(研修医が実施、超音波ガイド下)
- 大量輸液開始済(晶質液2000mL)
- 緊急O型RBC 2単位投与中
- 右内頸静脈からCVカテーテル挿入(研修医が実施、超音波ガイド下)
Q1. 骨盤骨折による大量出血患者の初期評価と救急処置の優先順位について説明してください。
- 一次評価(ABCDE):特に循環動態(ショック指数、末梢循環、尿量)の評価
- 出血源の同定:骨盤内出血(静脈叢、動脈損傷)、腹腔内出血、外出血の鑑別。
- ショックの程度評価:クラスⅠ〜Ⅳ(本症例はクラスⅢ以上)
- 凝固障害・アシドーシス・低体温(死の三徴)評価。
救急処置
- 機械的な出血コントロール:骨盤ベルト/シーツラッピングによる骨盤容積減少
- 急速輸液・輸血:過剰輸液を避ける必要はありますが,収縮期血圧80mmHg以上を目標とします
- MTP開始
- Ca²⁺補充(クエン酸中毒予防)
- 凝固因子管理:早期トラネキサム酸投与とフィブリノゲン補充
- 体温管理:積極的加温・低体温の防止
- 本症例は不安定型骨盤骨折で、血管造影でも活動性出血を認めており、放射線科医や外科医師と緊急カンファレンスを開き,緊急IVRや開腹術の迅速な準備が重要です。
- Brugada症候群が既往にあるため、電解質(特にK⁺、Ca²⁺)管理と体温維持も重要です。
Q2. Brugada症候群患者の麻酔管理において、術前評価で確認すべき事項と麻酔計画立案のポイントを説明してください。
- 最新の12誘導心電図でtype分類
- 症状歴の把握(失神、動悸、心停止既往)
- 家族歴(突然死。今回は父親に既往あり)
- 投薬歴(抗不整脈薬)
- ICD植込み有無の確認が必須(これはレントゲンですぐわかる)。
- 本症例はtype 1心電図パターンを示すハイリスク患者であり、致死的不整脈予防策が重要となります。
- 麻酔計画では
- 不整脈誘発薬物(Na⁺チャネル遮断薬:プロカインアミド、フレカイニド等)の回避
- 交感神経過緊張・迷走神経緊張の回避
- 電解質(特にK⁺、Ca²⁺、Mg²⁺)の維持
- 体温管理(高体温の回避)
- 除細動器とパッドの準備が重要です。
- プロポフォールはNa⁺チャネル遮断作用を持つため,高用量投与は禁忌であり,導入時も低用量使用に留めるなど慎重な対応が推奨されます.ケタミンの単回投与,非脱分極性筋弛緩薬や吸入麻酔薬は比較的安全とされています.
- 術中は心電図モニタリングと不整脈への対応が必須です.
- 今回のような出血性ショック状態では,特に電解質異常や自律神経反射が誘発されやすくなり,より注意が必要です.
ここから先は「オンラインメンバーシップ限定」です. ↓の「新規ユーザー登録」から登録申請を行ってください.