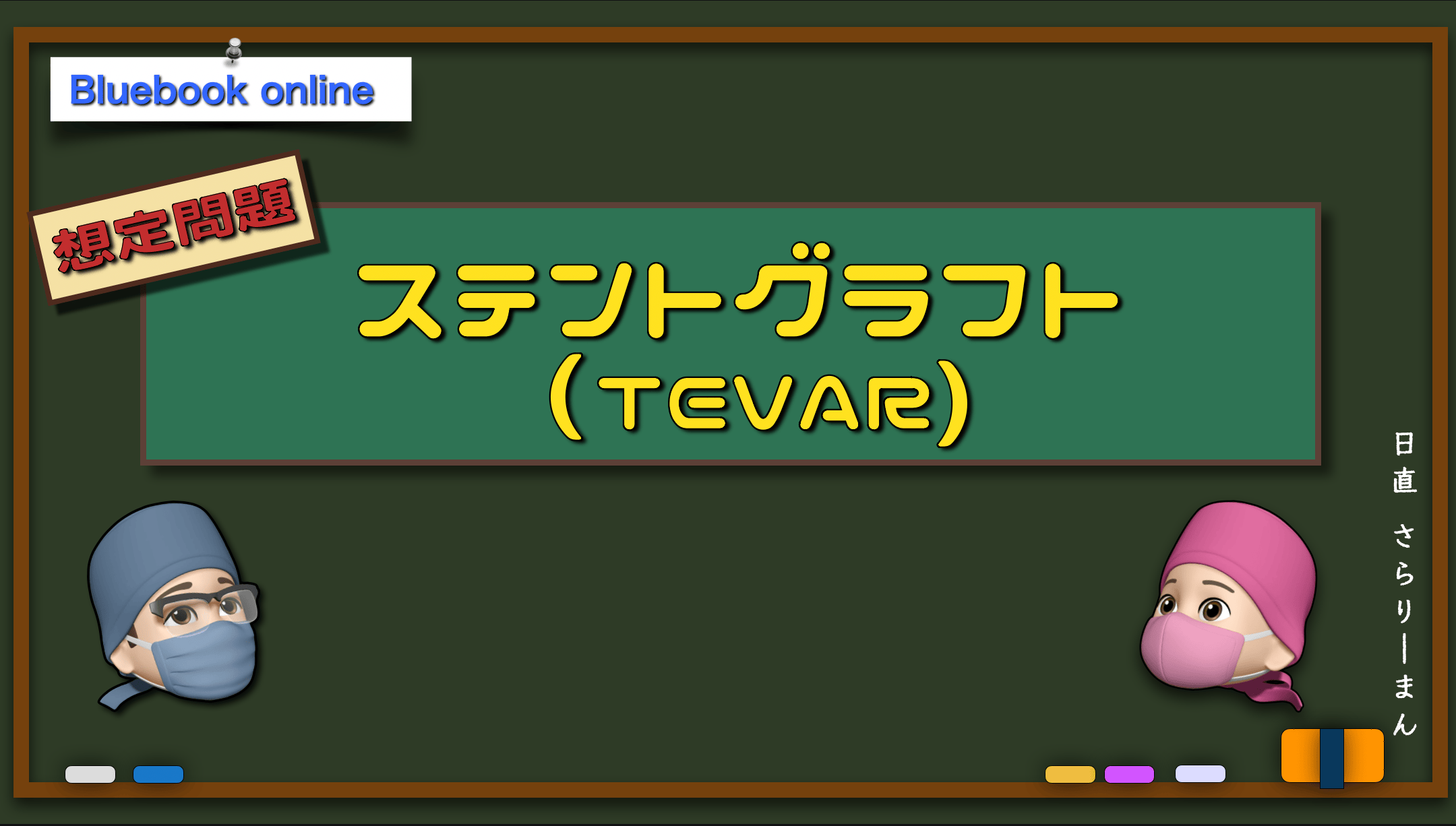症例設定
【患者】
- 78歳男性.165cm,56kg(BMI20.6)
【現病歴】
- 定期健診の胸部X線で大動脈拡大を指摘され,精査目的で撮影された造影CTにて,遠位弓部から下行大動脈にかけて最大径60mmの嚢状動脈瘤と,Adamkiewicz動脈起始部に近接する部位に壁在血栓を認めた.明日,待機的TEVAR手術が予定されている.脊髄虚血リスク軽減のため,昨日,腰部脳脊髄液(CSF)ドレナージが施行された.
【既往歴】
- 高血圧症(20年前から)
- 冠動脈疾患(5年前にPCI施行,右冠動脈#2にステント留置)
- 慢性腎臓病(CKD stage G3a,eGFR 45 mL/min/1.73m²)
- 2型糖尿病(15年前から)
- 腰部脊柱管狭窄症(3年前から保存的治療中)
【服用中薬剤】
- アムロジピン 5mg/日
- カンデサルタン 8mg/日
- メトホルミン 500mg/日
- アスピリン 100mg/日(術前7日前から中止)
- クロピドグレル 75mg/日(術前7日前から中止)
- ロスバスタチン 2.5mg/日
【主な検査所見・バイタルサインなど】
血液検査
- WBC 6,800/μL, RBC 412×10⁴/μL, Hb 13.2 g/dL, Ht 39.1%, Plt 19.2×10⁴/μL, 生化学:
- AST 25 IU/L, ALT 22 IU/L, TP 6.9 g/dL, Alb 4.0 g/dL
- BUN 22 mg/dL, Cr 1.35 mg/dL, eGFR 45 mL/min/1.73m²
- Na 140 mEq/L, K 4.3 mEq/L, Cl 105 mEq/L
- Glu 128 mg/dL, HbA1c 6.7%
- PT-INR 1.08, APTT 32.5秒, Fib 325 mg/dL, D-dimer 0.8 μg/mL
- 血液ガス(room air):pH 7.40, PaCO₂ 40 mmHg, PaO₂ 85 mmHg, HCO₃⁻ 24.0 mEq/L, BE -0.5 mEq/L, SaO₂ 96%
画像検査など
- 心電図: 洞調律,心拍数65/分,左室肥大所見
- 胸部X線: 心胸郭比 52%,肺野清,大動脈弓部拡大所見
- スパイロメトリ:VC 3.25L(%VC 85%), FEV₁ 2.28L(%FEV₁ 80%), FEV₁/FVC 70%
- 心エコー: 左室駆出率 58%,左室肥大所見,局所壁運動異常なし,軽度の大動脈弁閉鎖不全
- 頸動脈エコー: 両側に中等度プラーク形成あり,有意狭窄なし
- Mallampati分類: Class II
搬入時バイタルサイン
- 血圧 142/78 mmHg,心拍数 72/分,SpO₂ 96%(室内気).
Q1. 術中の神経モニタリングを安全かつ有効に行うために,術前に確認すべきポイントを具体的に挙げて説明してください.
- 神経学的評価:術前に下肢の運動機能や感覚機能を詳細に評価します.特に腰部脊柱管狭窄症の既往がある場合は,既存の神経障害の有無を確認しておく必要があります.
- 電極留置部位の確認:刺激電極および記録電極を留置する部位の皮膚状態を評価し,感染や皮膚障害がないことを確認します.
- 末梢神経・血管の評価:下肢の末梢神経障害や末梢血管障害がないかを確認し,モニタリング信号の取得に支障がないことを確認します.
- CSFドレーンの状態確認:術前にCSFドレーン留置部の出血や感染徴候の有無を確認し,ドレーンの機能が正常であることを確認しておきます(搬入後にもう一度確認).
ここから先は「オンラインメンバーシップ限定」です. ↓の「新規ユーザー登録」から登録申請を行ってください.