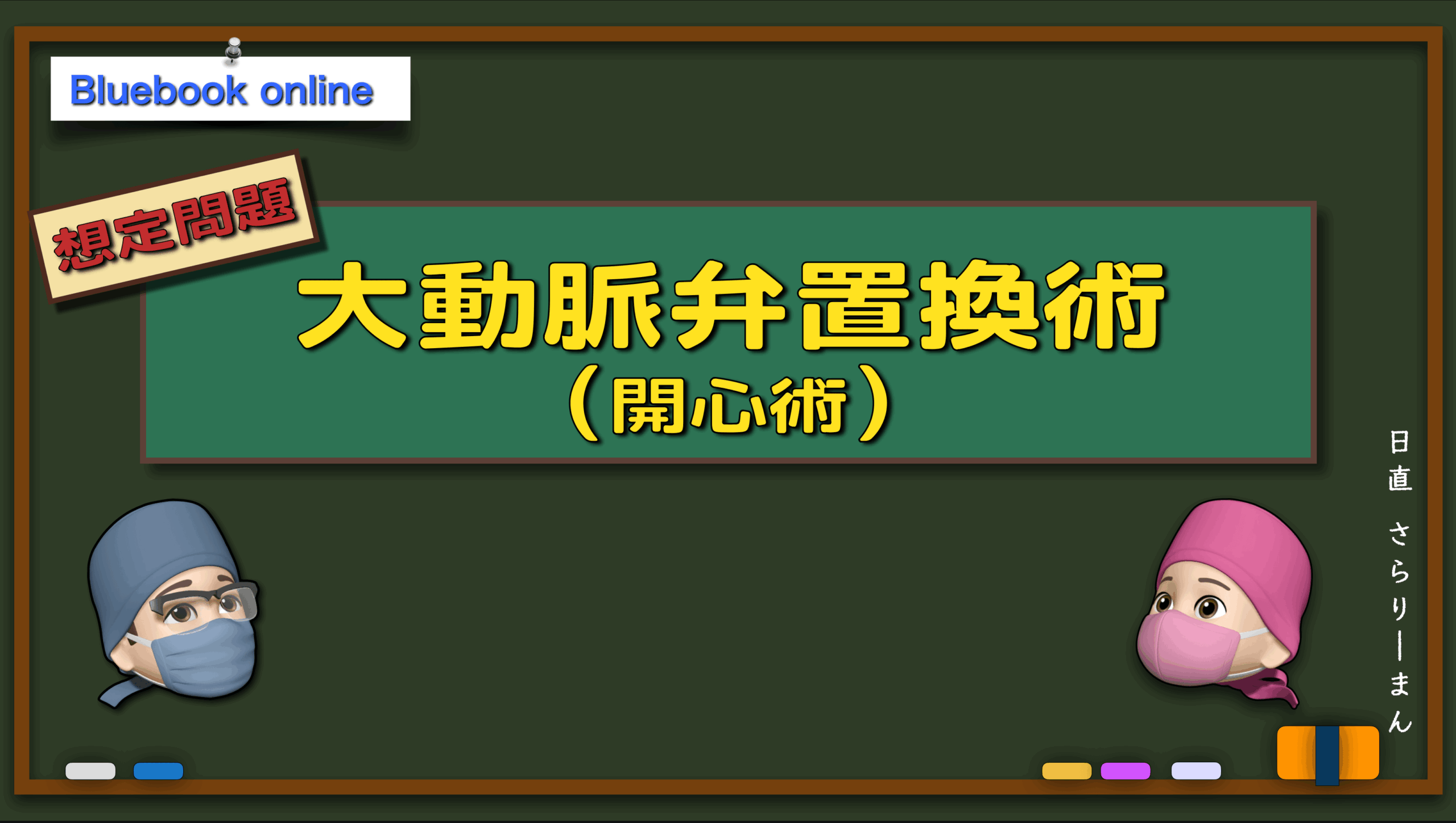症例設定
【患者】
- 68歳女性.156cm,58kg(23.8)
【現病歴】
- 数ヶ月前より労作時呼吸困難(NYHA II度程度),易疲労感が出現し,増悪傾向のため近医受診.精査にて重症大動脈弁狭窄症と診断され,手術目的に当院紹介となった.
【既往歴】
- 高血圧(10年前~)
- 2型糖尿病(5年前~)
- 発作性心房細動(3年前~,CHADS2スコア2点)
- 慢性腎臓病(CKD G3bA1)
【服用中薬剤】
- ワルファリン 2mg/日(発作性心房細動に対する抗凝固療法)
- カンデサルタン 8mg/日
- アムロジピン 5mg/日
- メトホルミン 1000mg/日
🖥️【主な検査所見・身体所見など】
バイタルサイン
- 体温 36.5℃, 血圧 138/78 mmHg, 脈拍 65拍/分(洞調律), SpO₂ 97%(room air)
血液検査
- WBC 6,500/μL, Hb 11.8 g/dL, Ht 35.5%, Plt 18.5万/μL
- TP 7.0 g/dL, Alb 4.0 g/dL
- AST 25 U/L, ALT 28 U/L, LDH 180 U/L, CK 80 U/L,
- BUN 25 mg/dL, Cr 1.4 mg/dL (eGFR 38 mL/min/1.73m²),
- Na 140 mEq/L, K 4.2 mEq/L, Cl 105 mEq/L,
- Glu 135 mg/dL, HbA1c 7.2%
- PT 18.0秒, PT-INR 1.85, APTT 35.0秒
心電図
- 洞調律、心拍数 65/分、左室肥大所見(ST-T変化なし)
胸部レントゲン
- 心胸郭比 55%、軽度の肺うっ血像
心臓超音波検査(TTE)
- 大動脈弁:高度石灰化、開放制限著明
- 重症AS(Vmax 4.0 m/s, mPG 45 mmHg, AVA 0.60 cm² (indexed AVA 0.36 cm²/m²)
- 左室:壁肥厚あり(IVS 13mm, LVPW 12mm), LVDd/Ds 50/35 mm, LVEF 45%(軽度低下), E/e’ 16(拡張能障害あり)
- 軽度MR, TR認める以外著変なし
- 右室機能:TAPSE 18mm(正常下限)
心臓カテーテル検査
- 冠動脈:有意狭窄なし
- 左室拡張末期圧(LVEDP): 18 mmHg
- 肺動脈圧 : 42/20 mmHg(mean 28 mmHg)
頸動脈エコー・MRA
- 両側内頸動脈に軽度プラーク認めるも,脳血管含め有意狭窄なし
呼吸機能検査
- VC 2.50L(%VC 95%), FEV1.0 1.80L(FEV1.0% 72%): 閉塞性換気障害なし
<治療方針:開心術>
- 心臓血管外科・循環器内科・麻酔科・腎臓内科などによるハートチームカンファレンスが開かれた.
- 患者年齢,弁の耐久性,腎機能,外科手術リスクを総合的に評価し,大動脈弁置換術(SAVR)の方針となった理由は以下の通り.
開心術を選択した理由(※TAVIバージョンも別問題で掲載)
- 比較的若年(68歳)であり,長期的な弁の耐久性を考慮するとSAVRが有利と判断(機械弁または耐久性の高い生体弁).
- CKD G3bは存在するが,他の併存疾患を含めてもSAVRの許容リスク範囲内と判断.
- 現行ガイドラインにおいて,75歳未満(または期待余命10年以上)の重症AS患者ではSAVRが依然として標準治療の一つであること.
- ちなみに冠動脈病変がないため,CABG同時施行は不要.
Q1.【術前評価】大動脈弁狭窄症のデータ以外で麻酔科として評価・確認すべき項目を挙げてください.
- 血圧のコントロール状況
- 頸部動脈・脳血管の狭窄の有無:麻酔中・人工心肺中使用による脳虚血のリスク
- 腎機能(CKD G3b):術中・術後の腎保護,造影剤使用や薬剤選択への影響,術後AKIリスク
- 糖尿病コントロール状況(HbA1c 7.2%):周術期の血糖管理目標設定,術後感染リスク
- 心機能(LVEF 45%, 拡張能障害): 麻酔導入・維持,人工心肺離脱時の循環管理への影響,カテコラミン依存のリスク評価.
- 発作性心房細動(PAF):術中・術後の不整脈リスク,抗凝固療法の管理(ワルファリン中止とヘパリンブリッジの要否),心房細動発生時の血行動態破綻リスク評価.
- 呼吸機能: 呼吸機能(術後の抜管戦略,呼吸器合併症リスク評価).凝固能(ワルファリン内服中),栄養状態,フレイル評価なども考慮します.
ここから先は「オンラインメンバーシップ限定」です. ↓の「新規ユーザー登録」から登録申請を行ってください.