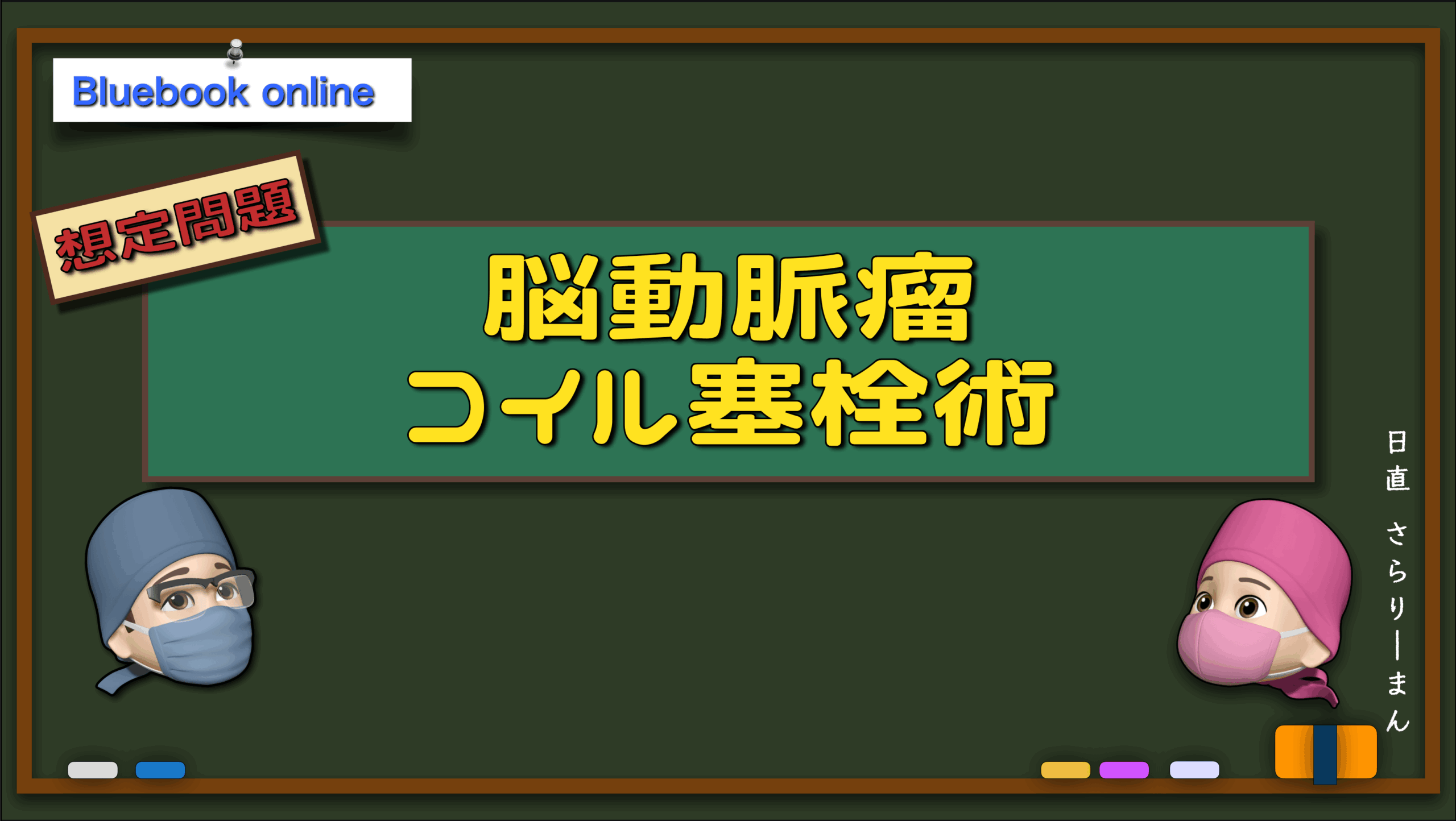症例設定
【患者】
- 56歳男性.172cm,88kg(BMI29.7)
【現病歴】
- 当日朝食後,突然の激しい頭痛と嘔吐で発症.意識レベル低下あり救急搬送.頭部CTでくも膜下出血(Fisher分類 Group 3)を認め,3D-CTAで右中大脳動脈分岐部に7mm大の動脈瘤を確認.Hunt & Kosnik grade III,WFNS grade II.発症から約6時間後,緊急コイル塞栓術が予定されている.
【既往歴】
- 高血圧症(8年前から):内服治療で収縮期血圧140〜150mmHg程度で推移
- 2型糖尿病(5年前から):HbA1c 7.2%,経口薬でコントロール
- 脂質異常症:スタチン内服中
【服用中薬剤】
- アムロジピン 5mg/日
- カンデサルタン 8mg/日
- メトホルミン 750mg/日
- ロスバスタチン 2.5mg/日
【検査所見・バイタルサインなど】
バイタルサイン
- 血圧 158/92mmHg
- 心拍数 88/分,整
- SpO₂ 97%(室内気)
- 呼吸数 18/分
- 体温 37.2°C
- 意識レベル GCS E3V4M6(13点)
主要検査データ:
- 血液検査:Hb 14.2g/dL,Plt 24.8万/μL,WBC 12,400/μL
- 凝固系:PT-INR 1.05,APTT 32秒,Fib 328mg/dL
- 生化学:Na 138mEq/L,K 3.9mEq/L,Cl 102mEq/L,BUN 16mg/dL,Cr 0.82mg/dL
- 肝機能:AST 28U/L,ALT 32U/L,ALP 245U/L,T-Bil 0.8mg/dL
- 血糖値:198mg/dL,HbA1c 7.2%
- 動脈血ガス分析(室内気):pH 7.42,PaO₂ 92mmHg,PaCO₂ 38mmHg,HCO₃⁻ 24mEq/L,BE 0.2mEq/L,Lac 1.2mmol/L
- 心電図:洞調律,左室肥大所見
- 胸部X線:CTR 54%,肺うっ血なし
画像所見:
- 頭部CT:Fisher分類 Group 3のくも膜下出血,脳室拡大軽度あり
- 3D-CTA:右中大脳動脈分岐部に7mm大の嚢状動脈瘤,ブレブあり
- 経頭蓋ドップラー:中大脳動脈平均血流速度 110cm/秒(軽度上昇)
特記すべき身体所見:
- 神経学的所見:明らかな局所神経脱落症状なし
- 気道評価:Mallampati分類III度,開口制限なし,頸部伸展制限なし
- 心音:整,心雑音なし
- 呼吸音:清,左右差なし
Q1. くも膜下出血急性期患者の術前評価において重要なポイントを述べてください.
- Hunt & Kosnik分類,WFNS分類,Fisher分類等を用いて重症度を評価します.
- 本症例では中等度の重症度と判断されます.
- 出血の範囲と量,水頭症の有無を評価します.
- 本症例では比較的広範なくも膜下出血があり,軽度の脳室拡大を認めています.動脈瘤の特徴としては,右中大脳動脈分岐部に7mm大の嚢状動脈瘤でブレブを伴っており,再出血リスクが高いと考えられます.
- 再出血リスク評価を行います.
- 初回出血からの時間,血圧,凝固能などを評価します.発症から6時間程度経過しており,初期の再出血高リスク期にあります.血圧は158/92mmHgとやや高値で,凝固能は正常範囲内です.
- 脳血管攣縮の評価も必要です.
- 経頭蓋ドップラーでは中大脳動脈平均血流速度が110cm/秒とやや上昇しており,早期の血管攣縮が示唆されます.
- くも膜下出血に伴う全身合併症の評価も重要です.
- 神経原性心筋障害(たこつぼ心筋症含む),神経原性肺水腫,電解質異常(特に低Na血症)などの有無を確認します.本症例では心電図で左室肥大所見を認めますが,急性期の心筋障害を示唆する所見はありません.
- 併存合併症の評価を行います.
- 本症例では高血圧,糖尿病,高脂血症があり,これらは動脈硬化のリスク因子であるとともに,周術期管理にも影響します.特に血糖値が198mg/dLと高値であり,周術期血糖管理が必要です.
- 頭蓋内圧亢進所見の評価も重要です.
- 意識レベル低下(GCS 13点)を認めますが,明らかな脳ヘルニア徴候は認めていません.
ここから先は「オンラインメンバーシップ限定」です. ↓の「新規ユーザー登録」から登録申請を行ってください.