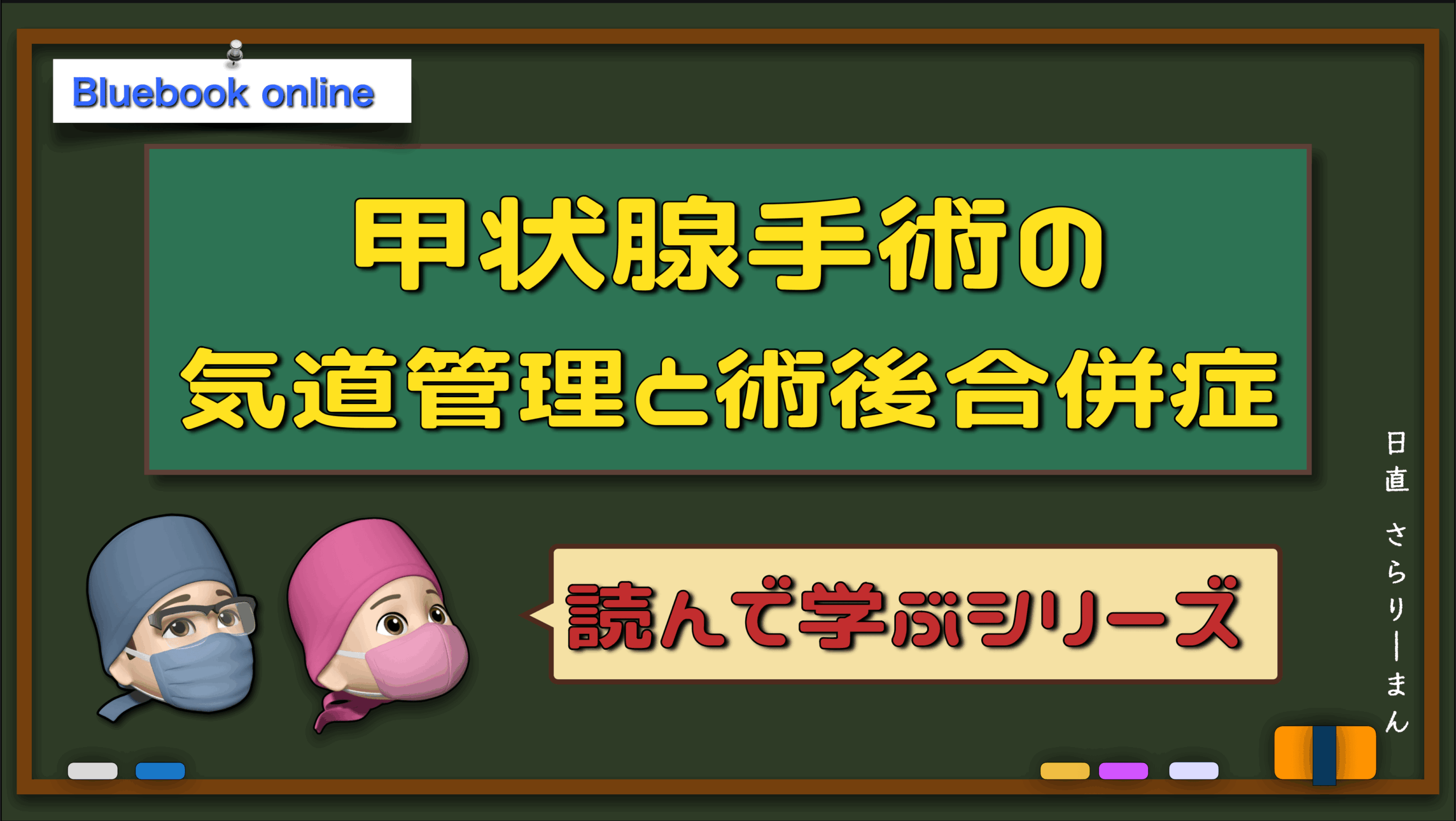内容
- 巨大甲状腺腫瘍の術前評価:身体所見と画像検査
- 身体所見・診察
- 画像検査
- 全身状態と内分泌評価
- 巨大甲状腺腫瘍患者の気道確保戦略
- 意識下挿管
- 麻酔導入と換気
- 緊急気道確保(外科的気道確保)の準備
- 術中管理の注意点
- 術後合併症とその管理
- 反回神経麻痺
- 低カルシウム血症
- 術後出血・気道閉塞
- その他の合併症
はじめに
 まっすー
まっすー明日の巨大甲状腺腫瘍はんぱないんですけど



あぁ,確かに大きいね.気道の評価が超大事だけど,ちゃんとチェックした?



もちです.診察では努力様呼吸は見られなかったですけど,仰臥位になると少し呼吸困難ありました.喘鳴はなし.Mallampatiは3度.肥満はなし.顔面の浮腫はなし.



画像的には?



CTでは気道狭窄ありますね.左右の偏位はなし.最狭部は8mmくらいですね.大血管系への影響はなさそうです.



ほんで?挿管はどうする?



普通に導入するのはこわいので,フェンタニルちょこっとと口腔〜咽頭部の表面麻酔して意識下ファイバー挿管ですかね.あと体位は頭高位をとります.患者さんもその姿勢のほうが楽みたいなんで.



それが一番無難だね.明日の人はそれで大丈夫そうだけど,もっと酷い症例の場合はどうする?



ECMOスタンバイします.といってもそこまでする症例はまだ見たことないですけど.



まぁそう多くないけど,酷い甲状腺腫瘍の人とか,上大静脈症候群を起こしてる縦隔腫瘍でほんとに重症な場合はECMO回すこともある.
まぁ気道確保はそれでいいとして,甲状腺術後の合併症で大事なのは?



術後出血,反回神経麻痺,あとは低カルシウム血症とかですかね.



そう.術後出血は口頭試問でもよく問われるし,低カルシウム血症に伴う症状(Trousseau徴候)も最近出題された.反回神経麻痺は片側だと嗄声で済むけど,両側起こすと声門が閉じて危険なので,術中モニタリングと合わせて抜管前後でも観察が重要.



あしたは無事に終わることをいのります.あ,意識下挿管の時はちゃんと手伝ってくださいね.
巨大甲状腺腫瘍の術前評価:身体所見と画像検査
🔷 身体所見・診察
巨大甲状腺腫瘍患者では,術前に気道狭窄の症状・徴候を詳しく評価する必要があります.安静時や横になるときの呼吸困難の有無、努力呼吸の兆候、喘鳴の有無を確認します.一般に、気道径が高度に狭窄すると安静時にも吸気性喘鳴が生じ、これは高度な気道圧迫を示唆します.
嗄声や声質の変化もチェックします.嗄声は反回神経麻痺や腫瘍による声帯運動障害を示唆しうるため,術前から声帯麻痺がないか,耳鼻科での声帯評価(喉頭ファイバー検査)も考慮されます.
甲状腺腫瘍が上縦隔へ及ぶ場合は,縦隔腫瘍でも問題となり得る上大静脈症候群(顔面・頸部の静脈鬱滞、Pemberton徴候など)が生じることがあります.
ここから先は「オンラインメンバーシップ限定」です. ↓の「新規ユーザー登録」から登録申請を行ってください.