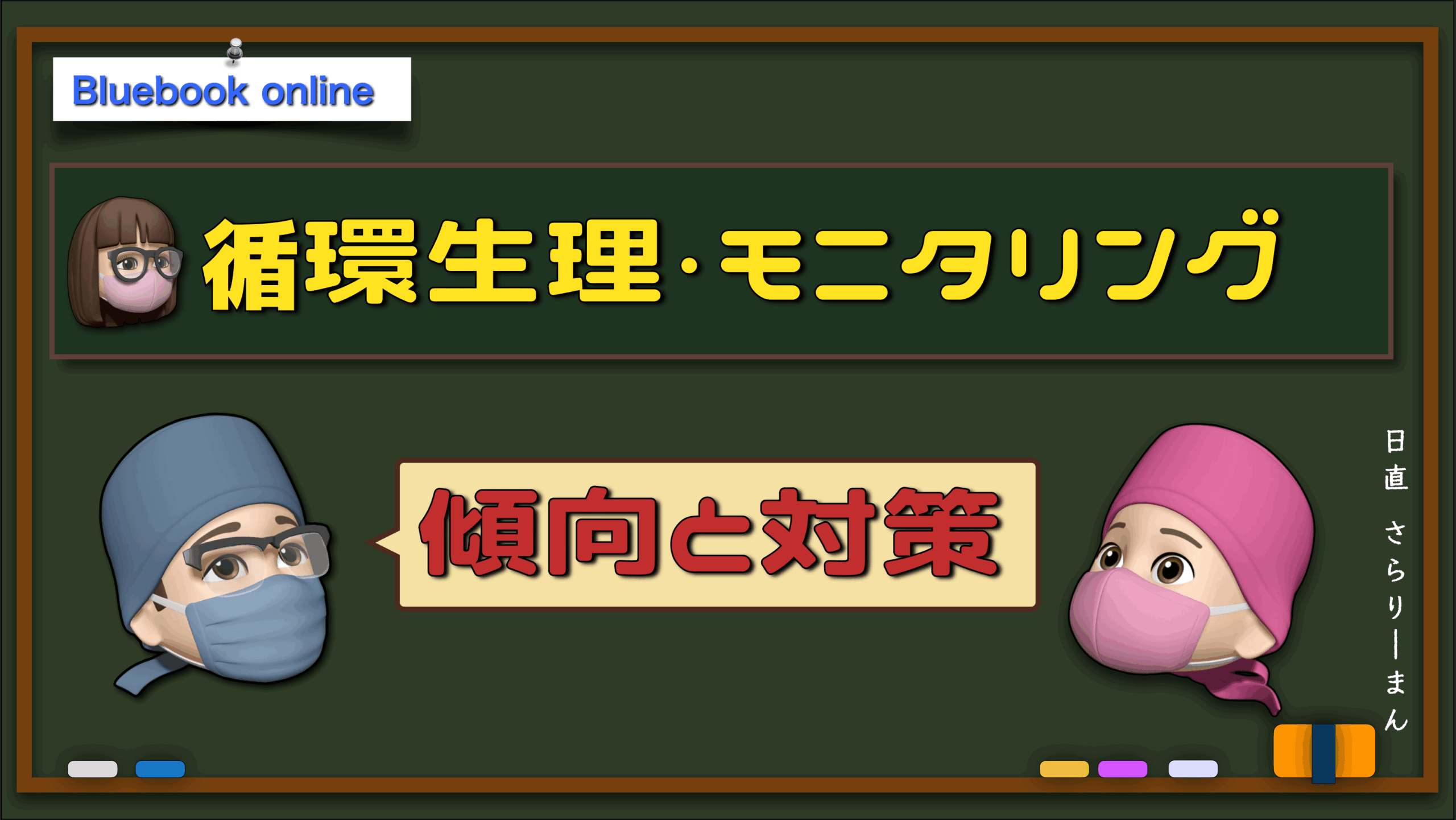- 📘 専門医試験対策目次(blog・note)
- 📝 ゆるく学ぶ周術期管理目次
はじめに
 まっすー
まっすー心電図の読取りはマストですね



そうだね.誰でもわかるVTやVFはいいけど,QT延長とかBrugada,WPWなんかは,モニターの表示が小さいこともあるから,そういう目でよく見ることが大事だね.



その後の問題の経過で必ずトラブルになりますもんね



CVの挿入手順やIABPの波形の読取り,特にタイミング異常なんかはキチンと理解しておくこと.あとTEEも基本の20波形だけでなく,心臓外科でほぼルーチンで計測する部位なんかはと構造物もわかるようにね



覚えること多い〜
心電図
🔷 概略
みんな大好き心電図笑.ただし,世の不整脈の種類は数多けれど,周術期に重要なポイントとなるものは限られています.以下に示します.
- 高カリウム血症の心電図(T波増高やwideQRS)
- 心室細動
- 心室頻拍
- WPW症候群と発作性上室性頻拍(ひょっとしたらVT)
- QT延長症候群とtorsade de pointes
- Brugada症候群
- 虚血によるST低下
- ST上昇
心電図が出題された場合,これらを押さえておけば,後は比較のための正常心電図です.画面の解像度が低い場合,WPW症候群は見落とす可能性があるので,心の眼でチェックしましょう!
🔷 高カリウム血症
実臨床でもそうですが,初めから「高カリウム血症だ!」というのはありません.多くは輸血がらみで高カリウム血症を来します.腎不全患者の輸血では注意しておきましょう.
テント状T〜wide QRSまでの変化をおさえておきましょう.
心室細動・無脈性心室頻拍:VF/pulseless VT
これに関してはあらためて何か言うほどのことはないですね.だれが見ても分かるので.やることは除細動一択(二相性200J)です!脈ありVTの場合は同期モードでカルディオバージョン(二相性100J〜くらい)です.
ただし,診断上では,WPW症候群の場合はpseudo VTもありうるのでそこだけ注意(治療はあまり変わりません).
循環不安定な場合,上室性かVTかでやることは変わりません.除細動一択です(循環が安定している場合は薬物治療もあり).
ここから先は「オンラインメンバーシップ限定」です. ↓の「新規ユーザー登録」から登録申請を行ってください.