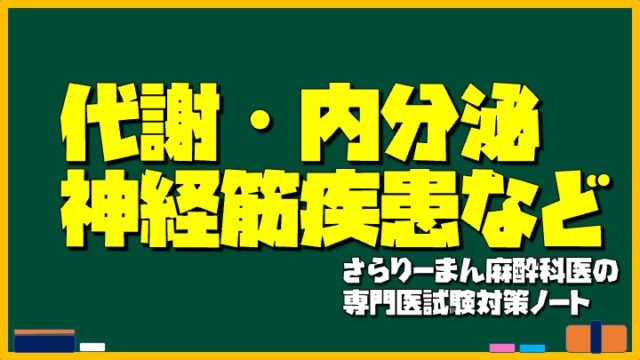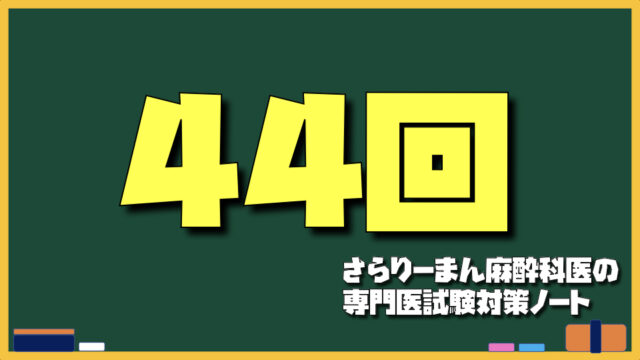5歳の男児。身長108cm、体重18kg。主訴は頭痛と嘔吐。脳腫瘍の診断で他院から紹介された。胸部エックス線、心電図、血液検査に異常はない。
0)この問題を解くために必要な知識
1)術前評価
脳外科から,術前のMRI検査の麻酔を依頼されました.
この症例に,MRI検査室で麻酔を行う際の注意点を2つ述べてください.
-
- 小児であるため安静を保てない⇒適切な鎮静・全身麻酔(施設により鎮静or挿管)が必要になる.
- 麻酔や鎮静は原則としてMRI室の外(手術室やMRI前室など)で行い,呼吸状態が安定してから入室する.
- 場合によっては呼吸状態など患児の観察が不十分になる可能性があるため,モニタリングをどのように行うかの計画を綿密に立てる.
- MRI対応の麻酔器やモニタを使用する(非鉄磁性のものを使用する)
一般に,磁場における安全性確保の要点を2つ述べてください.
- MRI対応の機器(麻酔器,モニタ,ケーブル,点滴台,血圧計など)を使用します(非鉄磁性体の使用).かつガントリーから1.5〜2.5m程度離します.
- MRI対応機器がない場合には,装置をMRIから十分離すか,蛇管やルートを延長して室外に出す必要があります.
- 心電図ケーブルがループを生じていると皮膚との接触で熱傷を生じる可能性があるため注意をする(人体も電導体であるため,皮膚どうしの接触も避ける).
一般に,脳圧亢進患者を麻酔する場合の要点を4つ述べてください.
- 頭蓋内圧が上昇しないような麻酔を行います.
- 低酸素血症、高二酸化炭素血症があれば頭蓋内圧は上昇するので、是正します。
- 二酸化炭素分圧を下げるために過換気にします。目標はPaCO2が25〜35mmHgで、この効果は4〜6時間持続します。ただし、脳血流減少により自動調節能が破綻している部位の虚血を招くため過度の低二酸化炭素は避けます。
- 薬物ではマンニトールやフロセミド、高張食塩水などを使用して脳浮腫の軽減を試みます。
- 他には頭部を挙上すれば静脈還流が増加して頭蓋内圧は低下します。また吸入麻酔薬を使用していればプロポフォールによるTIVAに切り替えてもよいかもしれません。
- 呼吸器の適切な設定を行います(胸腔内圧が上がりすぎないように.PCVの選択やPEEPの低減など).
2)術中管理

開頭腫瘍摘出術にあたり脳外科から,術中に運動誘発電位を測定したいとの希望がありました.
このモニタを可能にする麻酔方法の要点を2つ述べてください.
- 吸入麻酔薬を使用しない(使用してもできなくはないけど).
- 筋弛緩薬を使用しない(使用してもできなくはないけど).
3)危機管理
手術開始4時間後,突然研修医から「気道内圧が急に30cmH2Oに上がったので来てください」と連絡が入りました.
原因として考えられることを4つ述べてください.
- 回路内圧上昇が急激に起きるのか、徐々に起こってくるかにもよりますが(今回は急ですね)、原因となる部位としては、麻酔器・呼吸回路要因などの器械的トラブル、患者要因(肺以外)、患者要因(肺・気道)に大きくわけられます。
- 呼吸回路要因としては、回路のチューブや気管チューブの屈曲、粘調な分泌物などによる回路の閉塞や狭小化、頭低位にした場合の気管支挿管(特に腹腔鏡手術)などがあります(ただしPCVだと気が付かない可能性あり.この場合は一回換気量が低下しETCO2が上昇します)。
- 患者要因としては気管支攣縮やアナフィラキシーによる気道浮腫、バッキングや息こらえ、半覚醒でチューブを強く噛む、肺水腫や気胸、無気肺などが挙げられます。
- 対処としてはまず手動換気、目視(回路・点滴トラブル、気胸でわかりやすい場合はこれで)を行います。
- 聴診をして分泌物・気胸・気管支挿管・気管支けいれんを鑑別します。回路トラブル、気管支挿管であれば是正、分泌物があれば吸引を行います。
- 術中覚醒・バッキングであれば手術の手を止めてもらい、麻酔深度を深くします。
- 気管支けいれんであれば、一時的に吸入麻酔薬を使用、小児ではアドレナリンは原則用いない、β2刺激薬の吸入(専用チャンバーを使用して)、ステロイドを考慮します。
- 気胸であれば胸腔ドレーン挿入(緊張性気胸で間に合わない場合は、鎖骨中線上第2〜3肋間に16G針など刺してとりあえず脱気)を行います。
鑑別方法および対処方法を具体的に6つ述べてください.
- 上記の通り
👆補足事項
結局回路内圧上昇のは原因なんだったんだろう笑