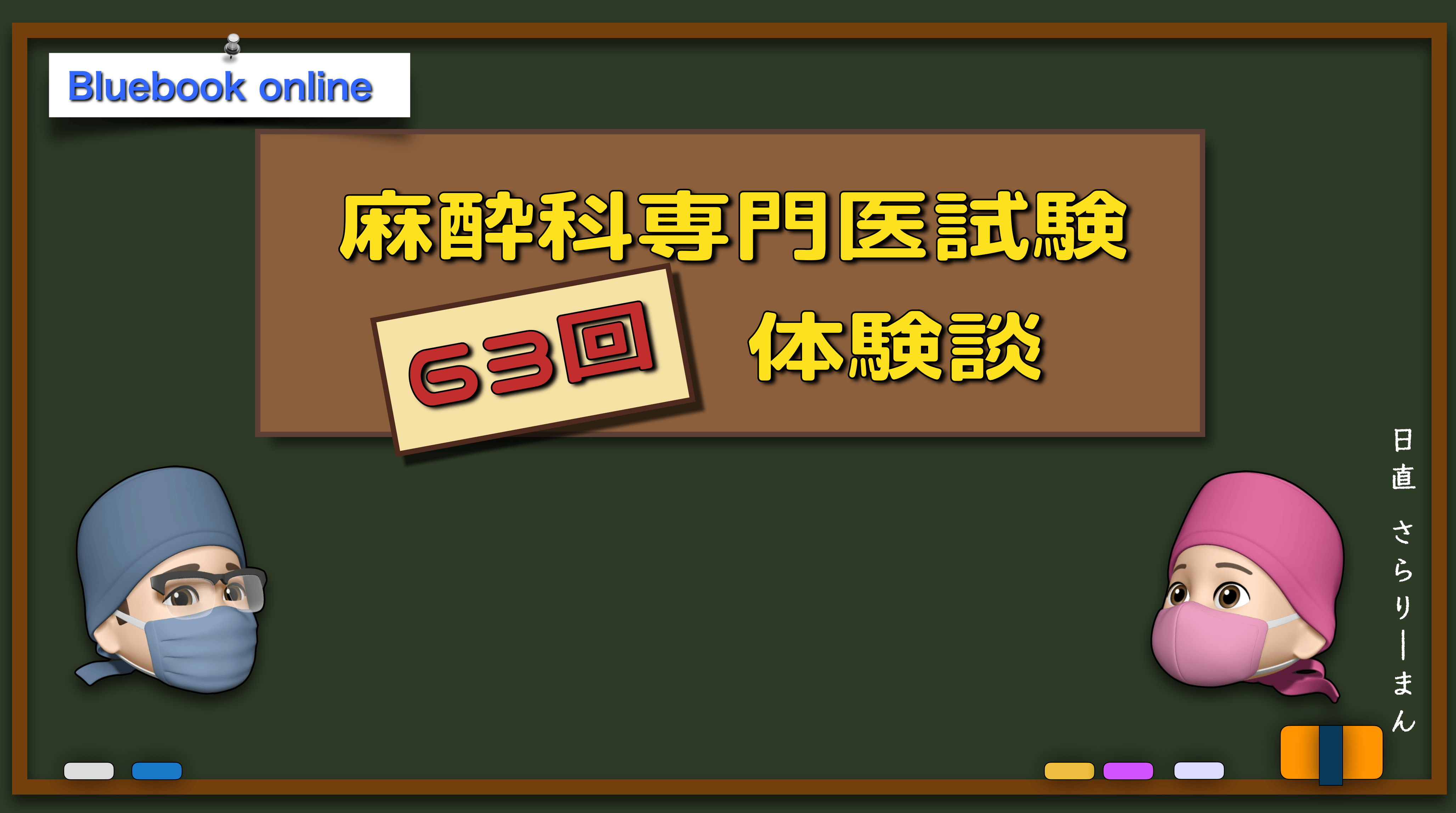さらりーまん
さらりーまん毎年年明けごろから公式の口頭試験過去問の公開があるのと,諸事情で体験談から細かな過去問の内容は割愛させていただいております🙇♂️
適宜追加を行っていきます!
麻酔科専門医試験体験談①
三科目とも合格しました。
勉強方法・勉強時間にかなり個人差が出る試験と思われますので、n=1の感想と思ってくださればよいと思います。また、私は男性、独身であるので、ご結婚されている先生、お子さんがいらっしゃる先生は、休日に勉強以外にリソースが割かれるので、そのあたりは、前もった準備が必要かもしれません。
勤務状況など
私の勤務環境は3次の急性期市中病院で、手術麻酔と麻酔科管理のclosed ICUが主な業務でした。成人心臓手術症例が豊富なほか、小児先天性心疾患の手術も行っており、比較的受験者が弱点となりやすい小児心臓分野へのアレルギーはありませんでした。後期研修中にJB-POTを取得し、心臓麻酔関連領域問題で苦労はしませんでした。また、集中治療も日常的に触れ合っていたので、とくに試験に向けて、新しく勉強することはありませんでした。
一方で、ペイン・緩和分野は全くと言って良いほど、経験がなく不安要素の1つではありました。軽く勉強しておこうと思い、専門医試験の半年ほど前にJ-RACEを取得し、多少理解が深まったと思います。
筆記試験
スタートラインが上記で、試験勉強は6月頃(3か月前)からはじめました。どうやら、過去問5年分を3周したら筆記試験は問題ないということを知り、その通り過去問を周回しました。1周目は時間がかかりましたが、過去問重ねる毎に、知っている問題が増えるので、短時間で回せるようになります。一般問題については、正直なところ、デスフルラン、セボフルラン、イソフルランの薬理学的比較とかほとんどの方が興味がない(興味がある方、すいません)と思いますので、問題と答えを1setで覚えてしまいましょう。学術的に意味のない勉強ですが、教科書と照らし合わせたりしたら、時間がいくらあっても足りないので、ここは試験に受かるための勉強です。
一方で臨床問題は、日々の日常臨床に繋がったり、口頭試問の勉強も兼ねるところになると思ったので、解説だけでは理解が足りないところは教科書で調べたりしました。3周終わった頃には、試験2週間前となり、ここからガイドラインに目を通しました。ただ分厚めのガイドラインである、区域麻酔の抗血栓薬の休薬関連はJ-RACEの時に目を通していましたし、非心臓手術における合併心疾患のガイドラインは、出版された際に上司から口酸っぱく、読みなさいと言われ何度か目を通し、敗血症ガイドラインもICUを業務にする以上避けては通れないものであったので、かなり貯金がありました。結局、volumeが少ないガイドラインをババっと読んで、大まかに内容を理解するだけでした。試験直前に間違った問題をもう1周して、試験に臨みました。
試験はCBT方式で、傾向は変わらず過去問通りでした。5年分をやりきった感じでは、おおよそ75%が過去問から出題されており、25%が新作という感じでした。新作のうち、一部は「こんなん知らんわ」みたいな問題が見受けられましたが、どうせ差がつかないので、テキトーに回答しました。感触的には8割はかたいと思える試験でした。
口頭試験
口頭試問は、2週間空いたので、筆記試験が終わってから対策に乗り出しました。まず専門医合格トレーニングを1周読んで、そこからサラリーマン先生の青本を使い、過去問3年分に目を通しました。このとき、見て、書いて、声に出すようにして、頭に叩き込み、outputも心掛けました。
はじめて問題を見たときは、これはマズいと思い、筆記試験が終わってからの1週間は必死でした。毎日夜中の3時くらいまで勉強していたと思います。3年分を終えると、わりと聞かれていることは同じであること、新作問題への対策は、幅広い分野からの出題のため、不可能であることを悟り、体調管理へシフトしました。1問1答集には手が出ず、ガイドラインを再度見返すことにしました。試験前に2回、模擬試験も行ってもらい、これはとても良いシミュレーションとなりました。是非とも試験前に模擬面接はしてください。
試験は不思議と、あまり緊張しませんでした。
1問目は、70代のTKA。せん妄の既往があり、今回もせん妄が心配という訴えがあるとの設定でした。
2問目は、前回、他院での全麻手術でアナフィラキシーショックとなり手術中止になった既往のある、腹腔鏡下肝切除。前医ではアレルギーに関連した詳細な検査は行っていない(バカヤロー)という設定。
2問とも1分ほど余りました。わからない問題もありましたが、それはみんな同じだろうと思い、引きずらないようにしました。考えるために15秒ほど無言になることは2回ほどありましたが、概ね何かしら答えは出てきました。圧迫面接の可能性があると聞いていましたが、私はそんなことはなかったです(たまたま?)入室したら、ハキハキと、よろしくお願いします!とやや大き目な声で言って、回答もすべてハキハキ答えました。ゴニョゴニョ言うのは良くないと思うので、自信をもって間違った答えを言ってやろうくらいな気分で臨んだのが良かったです。
口頭試問は最近、どんどん難易度が上がってきています。日常的に行っていることが、直結すると思いました。逆に試験直前で、どうにかなるようなものでもなく、形式に慣れるだけで良いと思いました。
口頭試問は、公式回答がなかったので、青本は非常に助かりました。
麻酔科専門医試験体験談②
前日までに15分の質疑応答のシュミレーションをしていても1問目は時間が足りなかったです。最後の答えを言いながら退室という結果に。2問目は急ごうという思いもあってむしろ3分ほど余りましたが、結局知ってる流れはさくさく終わるし、日頃業務に関わらない問題だと勉強済でもゆっくりになってしまいました。産科小児、やはり手強いと感じます。
麻酔科専門医試験体験談③
勉強方法・時期
- 4月中にしっかりと2周読んだ後、知的アプローチの口頭試問編を6月いっぱいまでに1周しました
- 7月からは知的アプローチの口頭試問編の2週目(7月いっぱい)と、土日は筆記試験の過去問7年分(直前まで)を繰り返しました。
- 8月からようやく口頭試問の過去問を解き始めました。
筆記試験
口頭試験
麻酔科専門医試験体験談④
おかげさまで無事3科目合格をいただきました。
筆記試験
勉強は4月から始め、過去問7年分を全てできるようになるまで周回しました。解説にもすべて目を通していました。最初はしんどいですが最初だけです。
当日は一般・臨床ともに55~60%ほどが過去問からの出題だったように思います。新問はちんぷんかんぷんのものが多かったですが、それは皆同じで差がつかないはず…と思いわりと気楽に解いていました。新問にはガイドラインからの出題もありました。
口頭試問
勉強はGW明けから始めました。青本の一問一答を叩き込んで過去問を繰り返し、結局青本以外の教材は使いませんでした。
やはり声に出して答える練習が大事だと思います。わかってはいても、実際に聞かれてすぐに答えるのは練習なしには難しいです。私は麻酔中にもブツブツ言っていて、家でも夫に問題を読んでもらい答える練習をしていました。あとは重要そうなガイドラインはすらすら答えられるようにしていました。
当日はポートピアホテルに前泊しました。朝一の回でしたが、寝坊への不安と緊張で一睡もせずに朝を迎えました…
待合室は集合時間の20分前から開いていました。15分前に行きましたがすでに八割方の受験生が着席しており、ほぼ全員スーツでした。青本を持っている方もたくさんいました。
業務用エレベーターで会場の階に移動した後、廊下で着席して症例の概要が書かれた紙を渡され、読んでメモする時間が3分間もらえました。試験室に持ち込みますが終了後回収されました。
反省
よかった点はほぼありません。冷静に考えれば序盤の問題1つを答えられなかっただけで不合格にはならないと思いますが、序盤でつまずいたことを最後まで引きずりました。それ以降は試験官の質問も正確に理解できず、〇〇についてですよと正される始末でした。1問目と比べて厳しい雰囲気の先生だったことにも動揺しました。かなり時間が余ってしまいましたが、かといってあのパニック状態で何分考えても答えが出てきたとは思えません。退室までお通夜状態で無言の時を過ごしました。
確実に落ちたと思いましたがなぜか合格していました。2問目はボロボロながらも、あまり時間をかけずになんとか回答を絞り出していたことに救われたのかもしれません。普段なら思いつくはずの答えがあの場では出てこなくなります。皆さん言われていますが二度と受けたくない試験です。
時間制限もあるのでよく聞かれる項目には脊髄反射で答えられるようにしておくこと、最低限過去問ができるようになっておくこと、声に出して答える練習を繰り返すことが大事かなと思います。
青本なしには絶対合格できなかったと思います。読みやすくかつ網羅されており、試験が終わっても日々の臨床をしながら読み返したい本です。
この度は本当にありがとうございました。
麻酔科専門医試験体験談⑤
麻酔科専門医試験体験談⑥
筆記試験
口頭試験
- このサイトの対策資料を5周通読
- 過去問7年分の解答をまとめたノートの作成及び通読5周
また最後の2ヶ月は過去問と対策資料のみと決め込んだため、他の問題集や教科書は全く読んでいません。無い知識から言葉を出す事に意味を感じなかった為、大学の模擬試験や同期との問題出し合いも参加していません。
麻酔科専門医試験体験談⑦
筆記試験
口頭試問
麻酔科専門医試験体験談⑧
麻酔科専門医試験体験談⑨
筆記試験
口頭試験
- →3分間のメモの時間
- →いったん紙を回収される
- →部屋に入る直前に先ほどの紙を渡され、そのまま入室
- →1問当たりの試験時間は約15分(くらいだったと思います、、間違ってたらすみません、、、)
- →終わったら退室して、斜め前の部屋の前にそのまま移動
- →先ほどと同様に紙を渡され、以降は同じ
- →2問目が終わって退室したらそのまま解散、帰宅という感じでした。
麻酔科専門医試験体験談⑩
筆記試験
口頭試験
麻酔科専門医試験体験談⑪
筆記試験
口頭試験
麻酔科専門医試験体験談⑫
筆記試験
問題は後半に新問が多く、かなりひねっている印象でした。私は8年分の過去問を3周ほどしましたが、5年で十分だと思います。2年前に問題構成が変わったこともあり、臨床問題の復習が足りておらず、全く同じ過去問が出ていたのに間違えてしまうというミスを6問やらかしたので、隅々まできちんと覚えておくことが大事だと思います…。
口頭試験
口頭試問は2-3年前から明らかに難しくなり、今回の試験も明らかに「答えさせない」問題が作られているように感じました。周りも違う問題でも同じような感触だったようで、これ落ちるかもしれないな…と1週間ひたすら不安な日々でしたが、意外に合格していて、「あっこんな感じでも受かるんだ…これで受かってもいいんだ…」という感想です。みんな日々麻酔の仕事をしながらスキマ時間に勉強しないといけないのでとても大変ですが、他の人もきっと同じ条件だと思うと頑張れました。筆記試験の過去問は2周目ぐらいからパッと答えがわかるようになってくると思うので、周回ゲーと思えばいいと思います。がんばってください!
麻酔科専門医試験体験談⑬
筆記試験
口頭試験
麻酔科専門医試験体験談⑭
麻酔科専門医試験体験談⑮
自身の背景
勉強初めた時期
勉強量
勉強方法
筆記試験について
口頭試問について
最後に
麻酔科専門医試験体験談⑯
麻酔科専門医試験体験談⑰
前日
当日
感想
麻酔科専門医試験体験談⑱
筆記試験対策について
口頭試問対策について
麻酔科専門医試験体験談⑲
麻酔科専門医試験体験談⑲
口頭試験
麻酔科専門医試験体験談⑲
筆記試験
口頭試験
例年どおり神戸ポートピアホテルの客室で実施されました。2日間をいくつかの時間帯に区切って受験者が割り振られました。控室は地下1階の大広間で、集合時間20分前より入室可能でした。
受験番号順に業務用エレベーター(通称:ドナドナエレベーター)に乗って試験会場である客室に案内されました。各客室の前に椅子が置いてあり、スタッフが問題用紙とペンを持って待機していました。3分間で症例の内容を把握してメモを残さなければなりませんでした。合図とともにその紙を持って一斉に入室しました。入室して15分間試験が行われ、すぐに次の部屋に案内されて同様の流れで別の問題に取り組みました。試験終了後、ゲスト用のエレベーターでフロントに降りて解散でした。