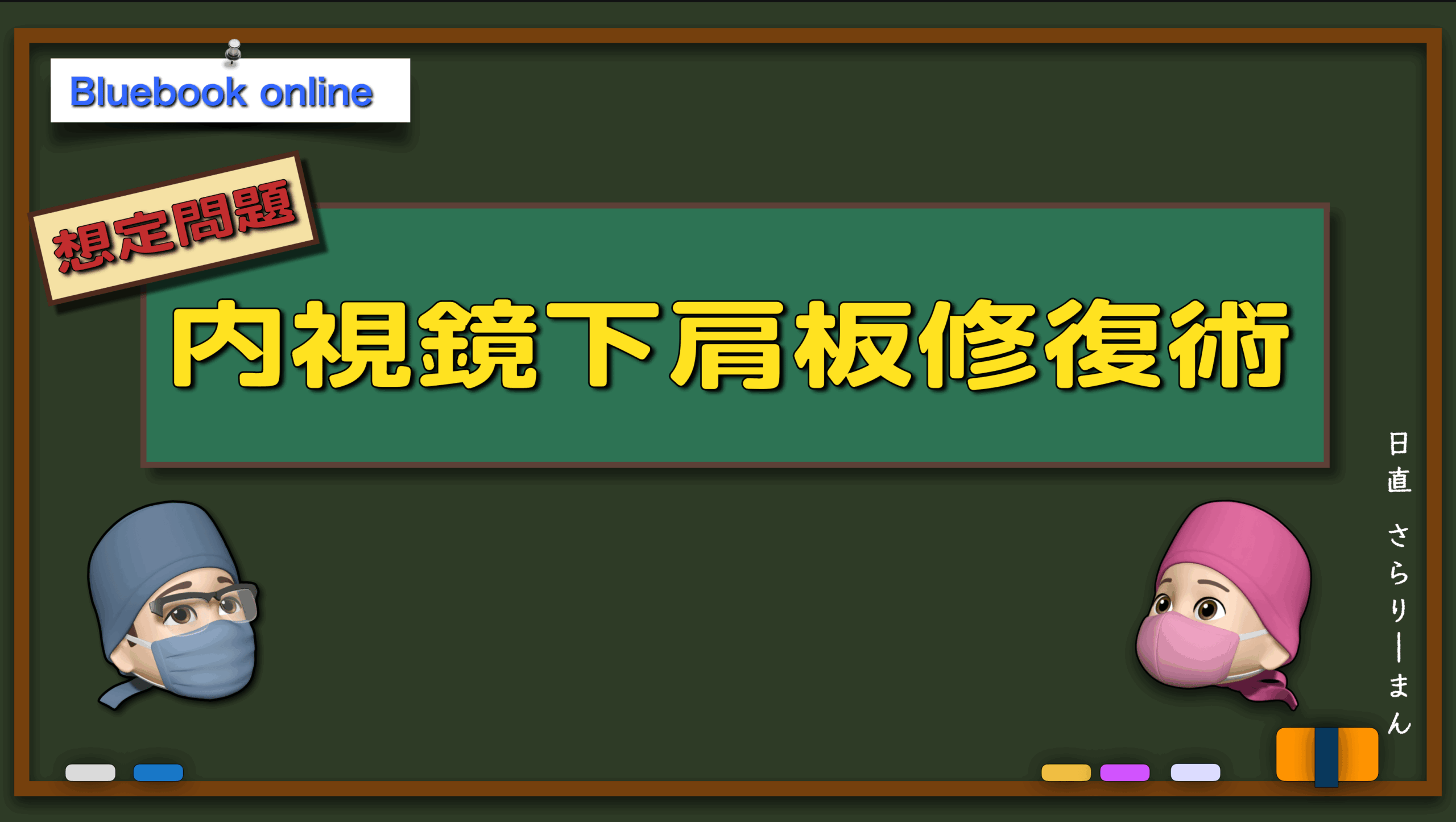症例設定
【患者】
- 52歳男性.175cm,82kg(BMI26.8)
【現病歴】
- 右肩の慢性疼痛と可動域制限。MRIで大・小菱形筋断裂を確認。関節鏡視下肩板修復術が予定された。
【既往歴】
- WPW症候群(15年前に診断、症状なく経過観察中)
- 高血圧症(内服良好にコントロール)
- 軽度睡眠時無呼吸症候群(CPAP未使用)
【服用中薬剤】
- アムロジピン5mg/日
【主な検査所見・バイタルサインなど】
バイタルサイン
- BP 142/85mmHg、HR 82/分、RR 14/分、SpO₂ 96%(室内気)
血液検査:特記事項なし
心電図:PR間隔短縮、デルタ波あり(WPW症候群type A)、明らかな頻脈性不整脈なし
胸部X線:異常所見なし
心エコー:EF 65%、壁運動異常なし、弁膜症なし
気道評価:Mallampati分類II度、頸部可動域良好
Q1. ビーチチェア位での肩関節鏡手術の体位に関連する解剖学的・生理学的変化と、麻酔管理上の注意点を説明してください。
主な解剖学的・生理学的変化
- 頭位が心臓より高くなることによる静脈還流低下と平均動脈圧の低下、またそれによる脳灌流圧低下・脳虚血リスク
- 体格によっては,頸椎の屈曲・側屈・回旋がおきる場合があります。特に整形外科医が腕を引っ張ったりする場合。
- ヘッドギアや固定バンドによる顔面部圧迫による眼球・顔面神経障害・皮膚障害リスク・動脈圧迫リスク などがあります。
麻酔管理上の注意点
- 適切な体位固定(頸部過伸展・過回旋の回避、圧迫点保護)
- 体位変換時の循環変動への対応(段階的な体位変換、輸液負荷・一時的な昇圧薬投与の考慮)
- 脳灌流圧維持(平均動脈圧の適切な維持)
- 気道管理(気管チューブ固定の確認、体位変換後の換気・聴診確認)
- 神経障害予防(眼球・顔面保護、定期的な体位確認)が重要である。
- 特に高齢者や心血管疾患患者では体位変換による血圧低下が顕著となりやすく、昇圧薬の準備と予防的投与を考慮します。また、術中の空気塞栓症リスクも認識し、突然の循環変動や呼気終末CO2低下にも注意が必要である。
ここから先は「オンラインメンバーシップ限定」です. ↓の「新規ユーザー登録」から登録申請を行ってください.