症例設定
【患者】
- 72歳男性.165cm,48kg(BMI17.6)
【現病歴】
- 1ヶ月前より食欲不振と嘔吐,および側腹部痛による経口摂取困難が生じ,3週間で体重が5kg減少.内視鏡検査で胃前庭部から幽門にかけての全周性狭窄を認め,生検にて低分化型腺癌と診断.造影CT検査で肝臓と傍大動脈リンパ節に転移巣を認め,根治手術は適応外と判断.緩和目的の胃空腸バイパス術が予定された.
【既往歴】
- 洞不全症候群:2年前に永久ペースメーカー植込み術施行(DDD設定)
- 高血圧症(20年前)
- 慢性腎臓病(CKD stage G3b)(5年前)
- 2型糖尿病(10年前)
- 慢性閉塞性肺疾患(COPD)(7年前)
【服用中薬剤】
- アムロジピン 5mg 1回/日
- カンデサルタン 8mg 1回/日
- メトホルミン 500mg 2回/日
- チオトロピウム吸入 1回/日
【ペースメーカー情報】
- モード:DDD
- レート設定:下限 60bpm,上限 120bpm
- 最終チェック:1ヶ月前(異常なし,バッテリー残量十分)
- 植込み部位:左前胸部
【主な検査所見・バイタルサインなど】
バイタルサイン:
- 血圧: 138/82 mmHg
- 脈拍: 68/分(ペースメーカー調律.自己心拍30bpm未満程度)
- 呼吸数: 18/分
- SpO₂: 94%(室内気)
- 体温: 36.5℃
身体所見:
- 呼吸音:両側下肺野で軽度の終末呼気性喘鳴あり
- 心音:整,雑音なし
- 栄養状態:やや不良
- 浮腫:なし
- 気道評価:Mallampati分類 Class II,開口良好,頸部伸展制限なし
血液検査:
- Hb 9.8g/dL,Ht 29.3%,WBC 7,800/μL,Plt 24.5万/μL
- AST 28 U/L,ALT 22 U/L,LDH 220 U/L,T-Bil 0.8 mg/dL,
- BUN 28 mg/dL,Cr 1.8 mg/dL(eGFR 31 mL/min/1.73m²),
- Na 138 mEq/L,K 4.2 mEq/L,Cl 102 mEq/L,
- Alb 2.0 g/dL,Glu 142 mg/dL,HbA1c 7.8%
- PT-INR 1.10,APTT 32秒
画像検査など
- 心電図:心拍数 68/分,ペースメーカー調律
- 胸部X線:両肺野に軽度の過膨張所見,心胸郭比 54%,ペースメーカーリード位置良好
- 肺機能検査:VC 2.2L(%VC 71%),FEV₁ 1.2L(%FEV₁ 59%),FEV₁/FVC 55%
- 心エコー:左室壁運動良好,EF 55%,弁膜症なし,右心系拡大なし
- 動脈血ガス分析(室内気):pH 7.38,PaO₂ 72 mmHg,PaCO₂ 43 mmHg,HCO₃⁻ 24 mEq/L,BE 0 mEq/L,SaO₂ 94%
Q1. この患者の麻酔リスク評価を行い,術前に最も注意すべき問題点を挙げてください.
- 洞不全症候群でペースメーカー依存状態にあり,手術中の電気メス干渉によるペースメーカー機能不全のリスクがあり.適切な設定が必要です.
- COPDがあり,%FEV₁が59%と中等度の閉塞性換気障害を認めます.
- CKD stage G3bに相当し,周術期の腎機能悪化リスクがあります.
- 低栄養状態(アルブミン2.0g/dL)と軽度貧血(Hb 9.8g/dL)を認め,創傷治癒遅延や感染リスクの上昇があります.
- HbA1c 7.8%と血糖コントロールは不十分で,周術期の低血糖・高血糖・糖尿病急性合併症(DKAなど)リスクがあります
Q2. ペースメーカー装着患者の周術期管理において,術前に確認すべき事項と準備すべき対策を挙げてください.
- 原疾患の把握,電池残量,最終点検日をペースメーカー手帳参照で確認します.
- 合わせて現在のペーシングモード,依存度,最近の不整脈イベントの有無の確認をします.
- 胸部レントゲン写真で植込部位と,リードの本数・位置を確認,
- ペースメーカー業者(や対応可能な臨床工学技士)への連絡,立ち会い依頼.
- モノポーラ電気メスの使用予定,対極板を貼る位置の確認を行っておきます.
⏩【経過】
- 患者は前日に入院し,術前評価が行われました.バイタルサインは安定してますが,軽度の貧血と低栄養状態,腎機能障害,COPDを認めます.麻酔科医による術前評価の結果,ASA-PS 3と判定されました.
- 術前にペースメーカー外来を受診し,手術に向けたペースメーカー設定の確認と電気メスによる干渉リスクの評価が行われました.患者自己心拍は消化器内科と協議の結果,アスピリンは術前5日前から中止されています.また,メトホルミンは手術前日から中止されています.
- 手術当日朝,静脈路が確保され,抗生剤(セファゾリン1g)が投与されました.また,導入後の中心静脈カテーテルの挿入を依頼されました.
ここから先は「オンラインメンバーシップ限定」です. ↓の「新規ユーザー登録」から登録申請を行ってください.
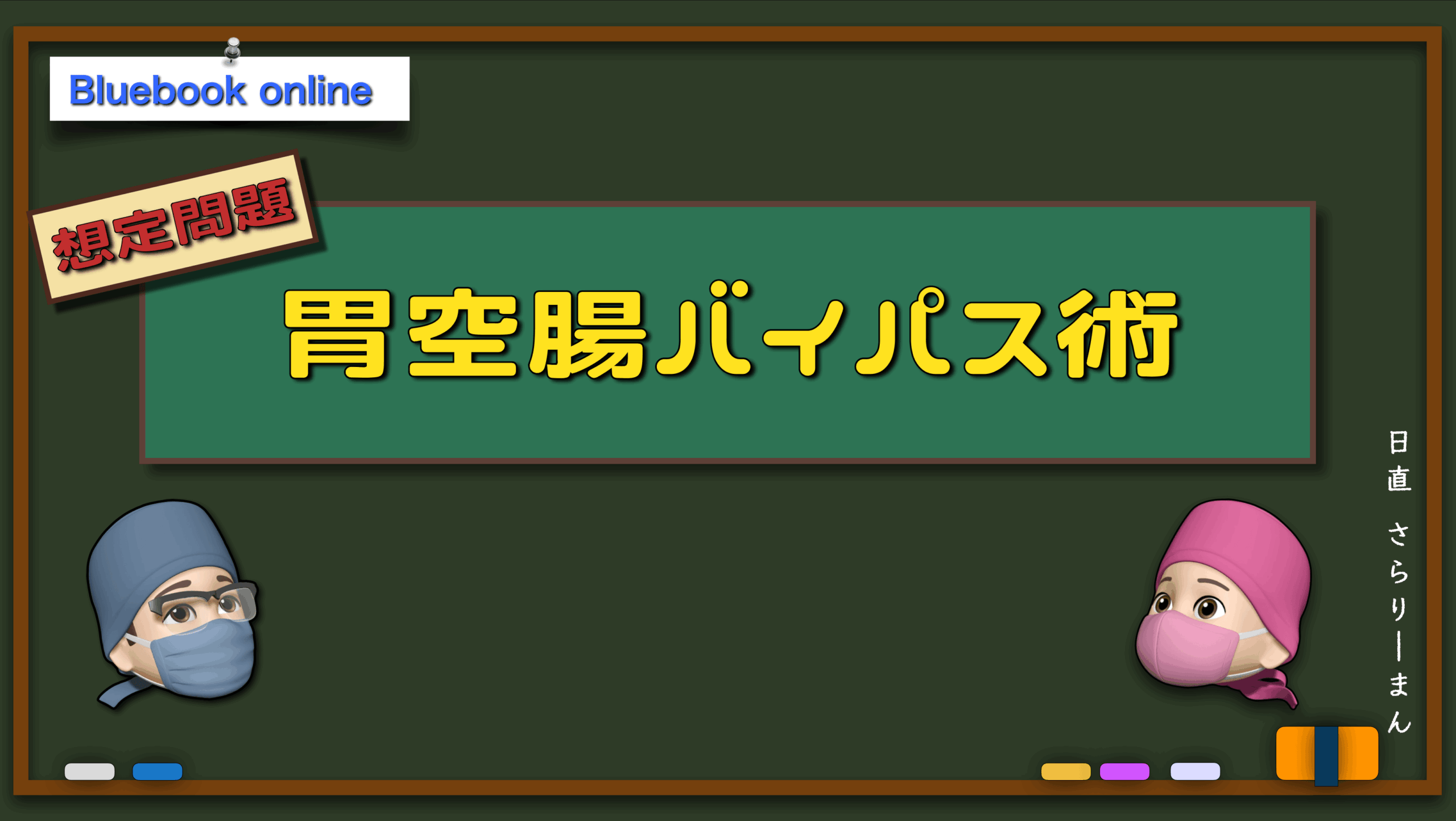
コメント