想定問題
【患者】
- 72歳男性.172cm,75kg(BMI25.4)
【現病歴】
- 本日早朝(朝食前)に突然の胸背部激痛で発症.救急搬送された.造影CT検査でStanford A型急性大動脈解離と診断され,緊急弓部大動脈人工血管置換術が申し込まれた.
【既往歴】
- 高血圧症(20年前から)
- 2型糖尿病(10年前から)
- 慢性腎臓病ステージG3a(eGFR 55 mL/min/1.73m²)
- 心筋梗塞,脳血管障害の既往なし
- 喫煙: 20本/日×40年(現在も継続) 飲酒: ビール350ml/日
【服用中薬剤】
- アムロジピン 5mg 1回/日
- テルミサルタン 40mg 1回/日
- メトホルミン 500mg 2回/日
- ロスバスタチン 2.5mg 1回/日
【主な検査所見・バイタルサインなど】
血液検査
- WBC 12,800/μL, RBC 420万/μL, Hb 13.2g/dL, Ht 39.5%, Plt 17.8万/μL
- AST 35 IU/L, ALT 32 IU/L, LDH 280 IU/L, T-Bil 0.8mg/dL
- BUN 24mg/dL, Cr 1.1mg/dL
- Na 141mEq/L, K 4.3mEq/L, Cl 104mEq/L
- Glu 180mg/dL, HbA1c 7.2%
- PT-INR 1.05, APTT 35秒, Fib 380mg/dL, D-dimer 2.5μg/mL
- BNP: 240pg/mL
- 動脈血液ガス分析(room air):pH 7.41, PaO₂ 85mmHg, PaCO₂ 38mmHg, HCO₃⁻ 24mEq/L, BE 0.2mEq/L, Lac 2.0mmol/L
心電図:
- 洞性頻脈,左室肥大所見
胸部X線:
- 心胸郭比 58%,上縦隔拡大,肺うっ血所見なし
経胸壁心エコー:
- 左室駆出率(LVEF) 55%
- 左室壁運動異常なし
- 上行大動脈拡大(最大径52mm)
- 心嚢液貯留あり(心タンポナーデ兆候あり)
- 大動脈弁閉鎖不全(AR)II度
- 僧帽弁閉鎖不全なし
- 推定右室収縮期圧 36mmHg
気道評価:
- Mallampati分類 II度
- 開口制限なし
- 頸部伸展制限なし
- 上下顎関係 正常
画像所見(造影CT):
- 大動脈基部から弓部大動脈にかけてintimal flapあり(Stanford A型)
- 偽腔開存型,最大径54mm
- 心嚢液貯留あり(最大10mm)
- 主要分枝(腕頭動脈,左総頸動脈,左鎖骨下動脈)への解離進展あり
- 冠動脈への解離,臓器虚血所見なし
- 胸腹部下行大動脈にも一部解離進展あり
搬入時バイタルサイン
- 血圧: 165/90mmHg(右上肢), 140/80mmHg(左上肢)
- 心拍数: 110回/分
- 呼吸数: 20回/分
- SpO₂: 96%(室内気)
- 体温: 36.8℃
予定術式:
- 弓部大動脈人工血管置換術
- 人工心肺使用予定(循環停止下での脳分離体外循環を併用)
⏩【経過】
- 患者は胸背部痛を訴えながら手術室に入室.意識清明だが不安感強い.
Q1. 本症例の術前評価において,既往疾患以外で最も重要な問題点と対策を挙げてください.
- 急性A型大動脈解離に伴う心タンポナーデ伸展によるショック
- 解離伸展に伴う心筋虚血,重症AR,脳梗塞
対策
- 迅速な手術準備と麻酔導入・および手術開始
- 心タンポナーデ解除時の循環動態変化への備え,
- 周術期の厳格な血圧管理(特に急激な血圧上昇の防止) が必要です.
- 具体的には,麻酔導入前から降圧薬(ニカルジピン,ジルチアゼムなど)の準備,複数の血管確保,導入前の動脈ライン確保,心嚢液排出時の急激な血行動態変化への準備(輸液・昇圧薬)を行います
- また,各種モニター(心電図,TEE,NIRSなど)を用いた,解離に伴う臓器虚血(冠動脈,脳血管,腸管など)の有無の評価も重要です.
ここから先は「オンラインメンバーシップ限定」です. ↓の「新規ユーザー登録」から登録申請を行ってください.
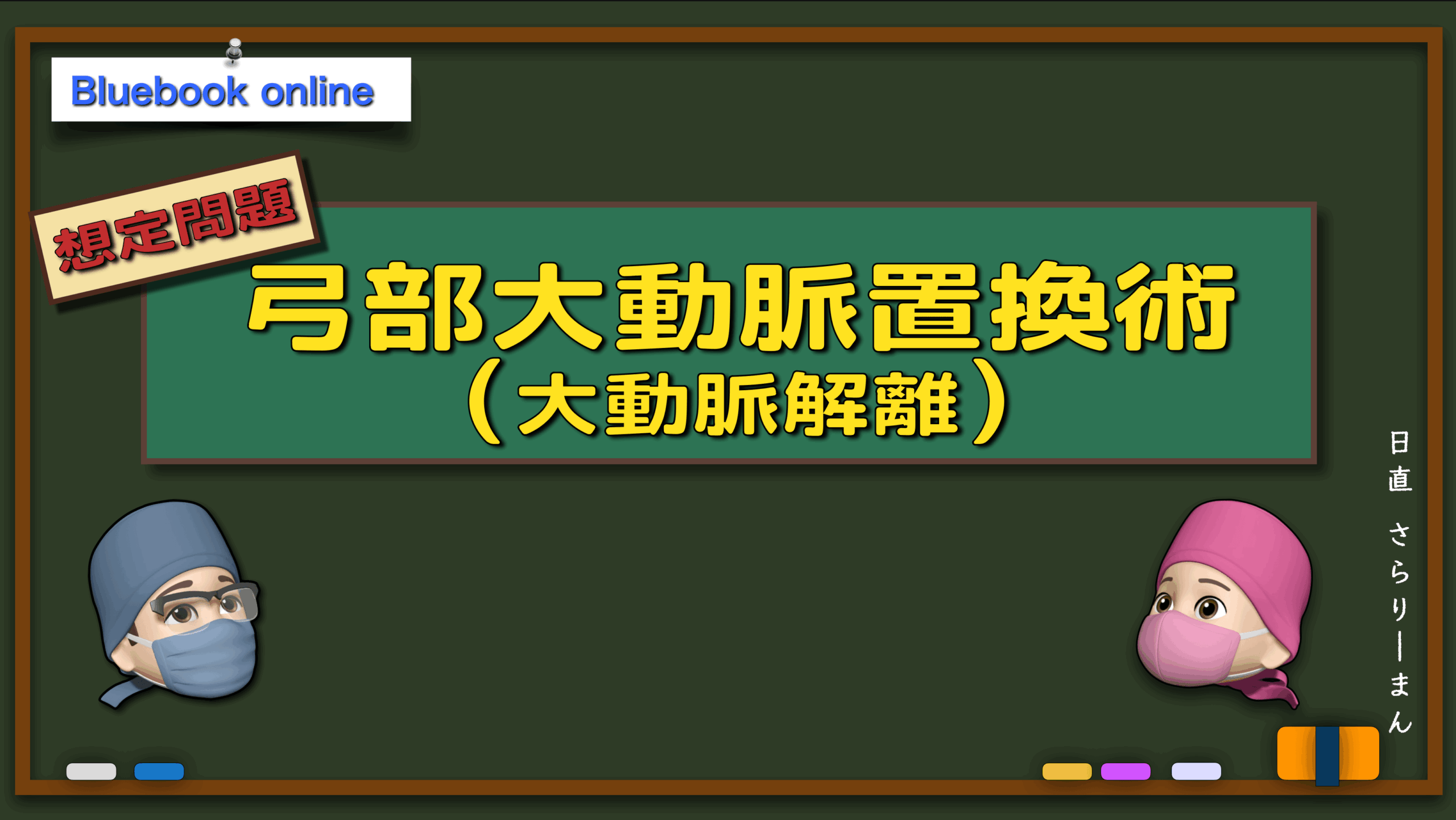
コメント