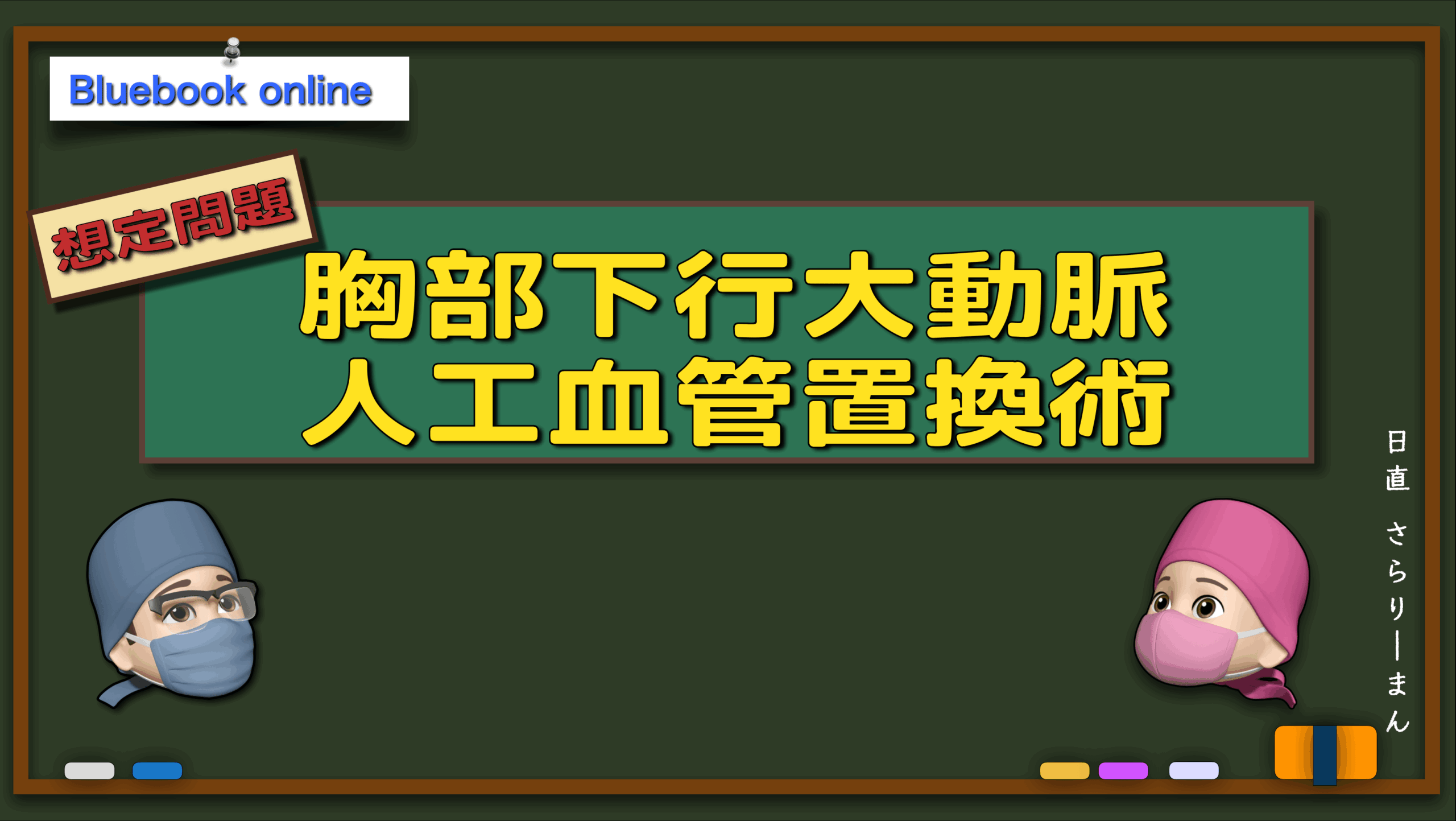症例設定
【患者】
- 72歳男性.170cm, 65kg.
【現病歴】
- 約3ヶ月前の定期健康診断で撮影された胸部CTにて,胸部下行大動脈の拡大を偶然指摘された.自覚症状は特になく,動脈解離や切迫は列を示唆する明らかな所見は認められていないが,動脈瘤径が7.5cmと大きく自然破裂のリスクが高いと判断された(怖).
【既往歴】
- 高血圧症(10年前から,ARBで加療中)
- 脂質異常症(スタチンで加療中)
- 2型糖尿病(5年前から,メトホルミンで加療中,HbA1c 7.0%)
- 慢性閉塞性肺疾患(COPD: GOLD分類 Stage II, FEV1 70% of predicted, FEV1/FVC 65%,禁煙後10年)
- 慢性腎臓病(CKD: Stage G3a,eGFR 55 mL/min/1.73m²)
【服用中薬剤】
- オルメサルタン 20mg 1錠/日(朝食後)
- アトルバスタチン 10mg 1錠/日(夕食後)
- メトホルミン 500mg 2錠/日(朝・夕食後)
- アスピリン 100mg 1錠/日(朝食後)
主な検査所見・バイタルサインなど
バイタルサイン: BP 145/85 mmHg, HR 75 bpm (sinus), RR 16 /min, SpO2 96% (room air), Temp 36.5 °C
血液検査
- WBC 7,500 /μL, RBC 400万 /μL, Hb 11.8 g/dL, Ht 36%, Plt 25万 /μL
- TP 7.0 g/dL, Alb 3.8 g/dL, AST 25 U/L, ALT 30 U/L, LDH 180 U/L
- BUN 25 mg/dL, Cr 1.3 mg/dL (eGFR 55),
- Na 140 mEq/L, K 4.2 mEq/L, Cl 105 mEq/L,
- Glu 130 mg/dL (空腹時)
- PT 12.5秒(PT-INR 1.1), APTT 30秒, Fib 300 mg/dL
- 動脈血ガス分析 (room air): pH 7.38, PaCO2 42 mmHg, PaO2 85 mmHg, HCO3 24 mEq/L, BE -1 mEq/L
画像検査など
- 心電図: 洞調律,心拍数 75 bpm,左室高電位,ST-T変化なし
- 胸部X線: 心胸郭比 55%,肺門部血管影増強,肺野透過性亢進(COPD所見),下行大動脈の拡大蛇行あり
- 呼吸機能検査: FEV1/FVC 65%, FEV1 1.8 L (予測値の70%), %VC 90% (中等度の閉塞性換気障害)
- 心エコー: LVEF 55%, 左室壁運動は正常範囲内,軽度の左室肥大,拡張能障害,弁膜症なし,推定右室収縮期圧 30 mmHg.下行大動脈起始部に拡張を認める.
- 胸腹部CT:左鎖骨下動脈分岐部直下から横隔膜上部にかけて最大径 6.5 cm の紡錘状胸部下行大動脈瘤を認める.壁在血栓あり.解離や切迫破裂所見なし.腎動脈までの距離は十分あり.
身体所見など
- 気道評価: Mallampati class II,開口 4cm,頸部可動域 良好,甲状頤間距離 7cm.気道確保困難の予測なし.
Q1. 本症例の麻酔計画上の注意点を述べてください.
- 麻酔管理としては,それぞれ以下に注意して管理を行います.
- 循環管理:血圧管理(特に遮断/解除時),大量出血への準備(太い静脈路確保,急速輸液装置,血液製剤準備).体外循環確立および離脱のためのTEEの使用
- 呼吸管理:COPDを考慮した肺保護的換気,片肺換気に伴う低酸素血症への対処,気管支鏡によるチューブ位置や分泌物の確認等.術後肺合併症予防のため,術前の呼吸理学療法や術後早期の離床を積極的に行う.
- 周術期AKIの予防:CKD悪化リスクを考慮し,術中腎血流維持(適切な循環管理),腎毒性薬剤の回避,造影剤使用の最小化,術後尿量・腎機能モニタリング.
- 脊髄保護:遮断中の遠位血圧維持,脳脊髄液ドレナージドレナージやMEPモニタリング.
- 代謝: 血糖コントロール,低体温予防.
- 術後鎮痛:フェンタニルIV-PCA主体
ここから先は「オンラインメンバーシップ限定」です. ↓の「新規ユーザー登録」から登録申請を行ってください.