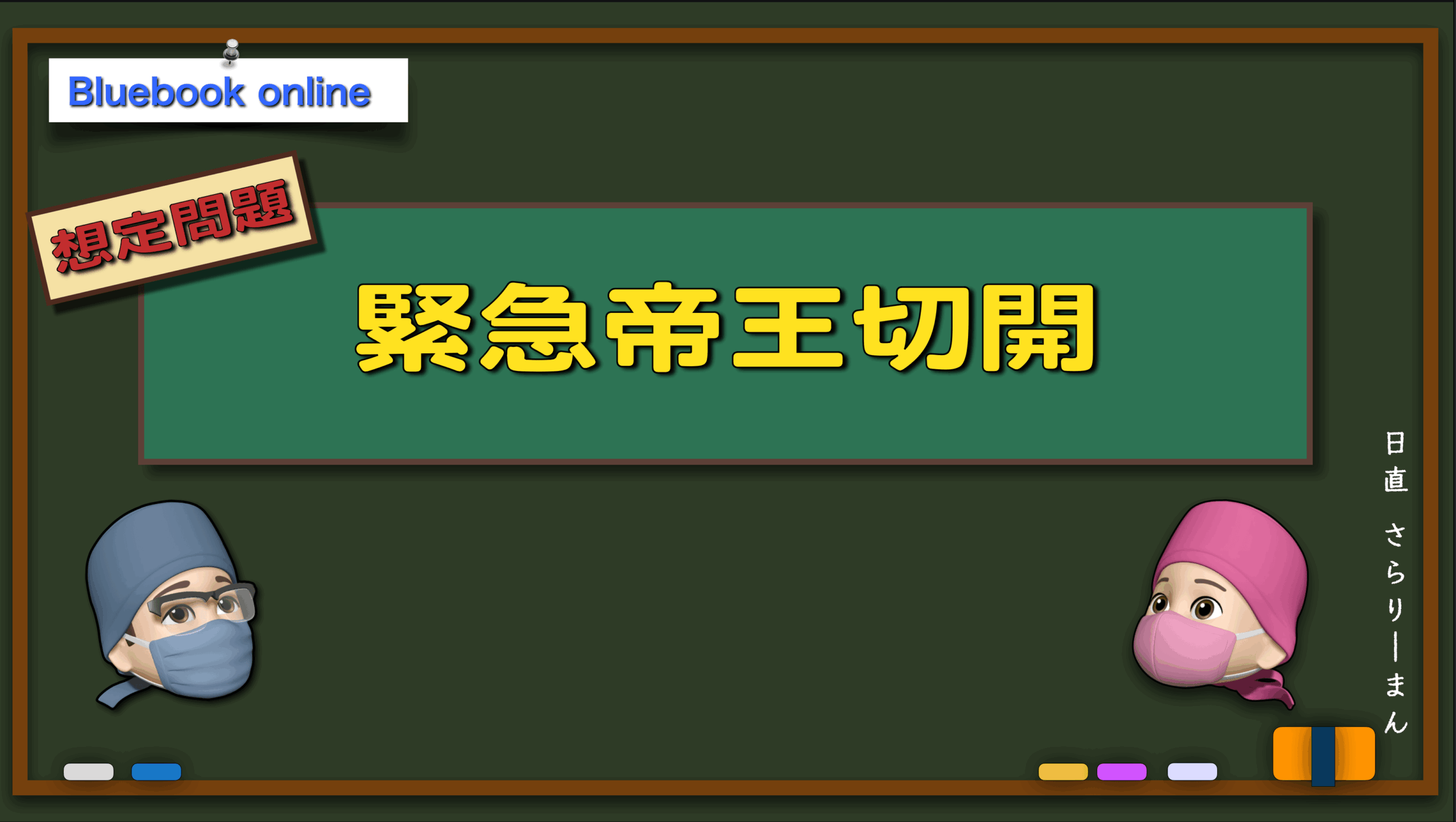症例設定
【患者】
- 39歳女性.G1P0.妊娠37週1日.155cm,72kg(非妊娠時65kg).BMI30
【現病歴】
- 妊娠高血圧症候群(重症,蛋白尿あり)で入院加療中.胎児心拍数陣痛図で胎児徐脈(遅発一過性徐脈)が出現し始めた.胎児機能不全の診断で,帝王切開が申し込まれた.昨日より頭痛あり,本日朝より悪化
【既往歴】
- 妊娠高血圧症候群:妊娠32週から血圧上昇,妊娠35週から蛋白尿(+2)
- 2型糖尿病
【投与中薬剤】
- 妊娠前はDPP-4阻害薬(シタグリプチン50mg/日)内服.妊娠判明後はインスリン療法に変更(現在はインスリンアスパルト4-6-6単位)
- ニフェジピン(20mg 1日3回)内服中
【主な検査所見・バイタルサインなど】
バイタルサイン
- 血圧170/105mmHg,心拍数96/分,SpO₂ 98%(room air),体温 36.8℃
血液検査など
- Hb 10.8g/dL,Ht 33%,Plt 15.2万/μL,PT-INR 1.03,APTT 28秒
- AST 45U/L,ALT 38U/L,LDH 280U/L,Cre 0.78mg/dL,尿酸 6.5mg/dL
- 血糖値:132mg/dL(2時間前食後)
- 尿検査:蛋白(+3),糖(+),潜血(-)
画像検査など
- 12誘導心電図:洞性頻脈,左室肥大所見なし
- CTG:基線150-160bpm,基線細変動減少,遅発一過性徐脈×3回/20分
身体所見
- 顔面・下肢に中等度浮腫あり 眼瞼結膜:蒼白なし,眼球結膜:黄染なし
- 気道評価:Mallampati分類 Class II,甲状軟骨-オトガイ間距離 6.5cm
Q1. この患者の周術期リスク評価を行い,術前準備として重要な点を挙げてください.
- 妊娠高血圧症候群
- 重症高血圧であれば降圧療法(ヒドララジン,ニカルジピン等)の調整が必要.
- 持続的に血圧をモニタリング可能な体制(重症の場合は観血的動脈ライン)を検討.
- 全身麻酔になった場合,咽頭〜喉頭粘膜浮腫等による気道確保困難の可能性あり.肥満もあるためDAMカートは準備しておく.
- 2型糖尿病
- 内服は中止し,以降は速効型インスリンによるスライディングスケールを用いる.高血糖・低血糖ともに注意する.
- 肥満
- 背中お肉付きタイプでは区域麻酔穿刺困難の可能性.難しそうならエコーを補助的に使用する.
- 全身麻酔になった場合は気道確保困難の可能性あり.DAMカート等準備する.
- HELLP症候群や子癇の徴候のチェック
- 肝酵素の上昇や血小板の徴候がないか(本症例では今のところOK)
- HELLP症候群は術後にも発症するため注意する.頭痛・上腹部不快感といった重症化徴候あり.
ここから先は「オンラインメンバーシップ限定」です. ↓の「新規ユーザー登録」から登録申請を行ってください.