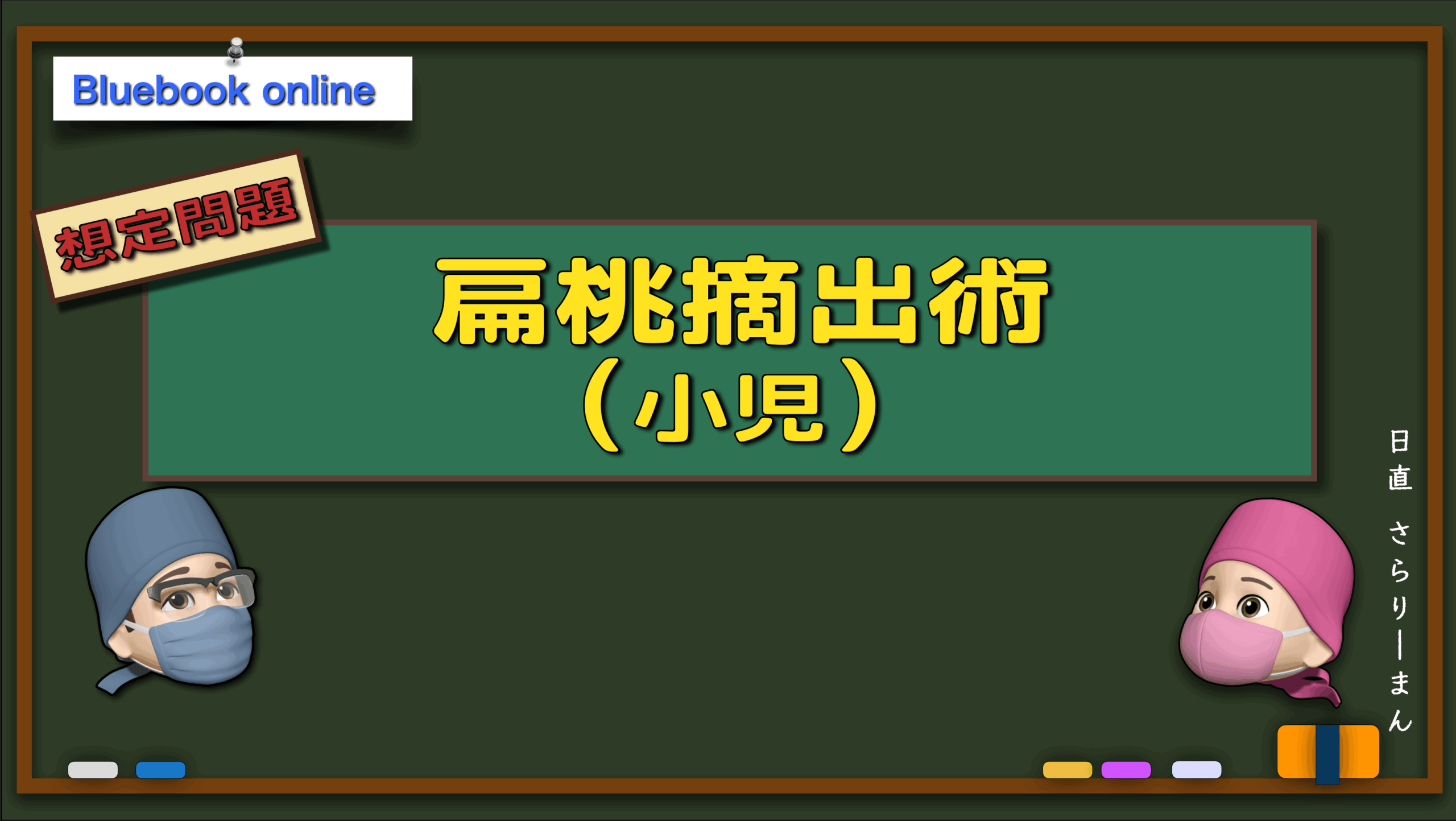症例設定
【患者】
- 5歳男児.108cm,19kg.
【現病歴】
- 夜間の激しいいびきと日中の傾眠傾向があり,耳鼻科を受診.両側口蓋扁桃肥大(Mackenzie分類 III度)に対して口蓋扁桃摘出術が予定されています.2週間前まで上気道炎症状があったが現在は改善している.
【既往歴】
- 気管支喘息(3歳時に診断):月に1-2回の軽度発作あり,サルブタモール吸入で対応.直近の発作は3週間前(上気道炎に伴う)
- 食物アレルギー(卵):3歳時にアナフィラキシーの既往あり
- 睡眠時無呼吸症候群
【服用中薬剤】
- フルチカゾン吸入剤 50μg 1日2回
- サルブタモール吸入 100μg 発作時頓用
- アドレナリン自己注射キット 0.15mg(アレルギー対応用)
【主な検査データ・バイタルサイン】
バイタルサイン:
- 体温 36.8℃
- 心拍数 95回/分
- 血圧 95/58mmHg
- 呼吸数 22回/分
- SpO₂ 97%(室内気)
血液検査:
- Hb 12.8 g/dL, Hct 37.2%, WBC 8,200/μL(好酸球 6%), Plt 28.5万/μL
- AST 22 IU/L, ALT 18 IU/L
- BUN 12 mg/dL, Cr 0.4 mg/dL
- Na 139 mEq/L, K 4.2 mEq/L, Cl 102 mEq/L
- 血糖 85 mg/dL
その他:
- 動脈血ガス分析:未実施
- いびき音の録音で無呼吸指数(AHI)15回/時
画像所見:
- 胸部X線:明らかな肺野の異常陰影なし
- 頸部側面X線:扁桃肥大によるCline線の狭小化あり
特記すべき身体所見:
- 呼吸音:両側肺野で時折軽度の散在性喘鳴あり
- 心音:整,雑音なし
- 口腔内:両側口蓋扁桃の著明な肥大(III度),口蓋垂の視認は困難
- Mallampati分類:評価困難(協力得られず)
- 頸部可動性:正常
Q1. この症例の術前評価で必要な問診項目を4つ挙げ,その理由を説明してください.
- 喘息のコントロール状態の把握(頻度,最終発作時期,治療薬,入院歴)
- OSASの重症度の把握(いびきの頻度,無呼吸の目撃,日中の眠気):両親にもう一度確認
- アレルギー歴の詳細(食物,薬剤,アナフィラキシーの既往):卵・牛乳アレルギーがあり.
- 上気道感染症状の有無と経過:最近(特に2週間程度)の上気道感染は気道過敏性が亢進し,術中・術後の気道合併症リスクを増加します.
- 歯牙の状態(抜けかけの歯などあれば,誤嚥予防のため,あらかじめ歯科で抜歯などの処置をしておく.)
ここから先は「オンラインメンバーシップ限定」です. ↓の「新規ユーザー登録」から登録申請を行ってください.