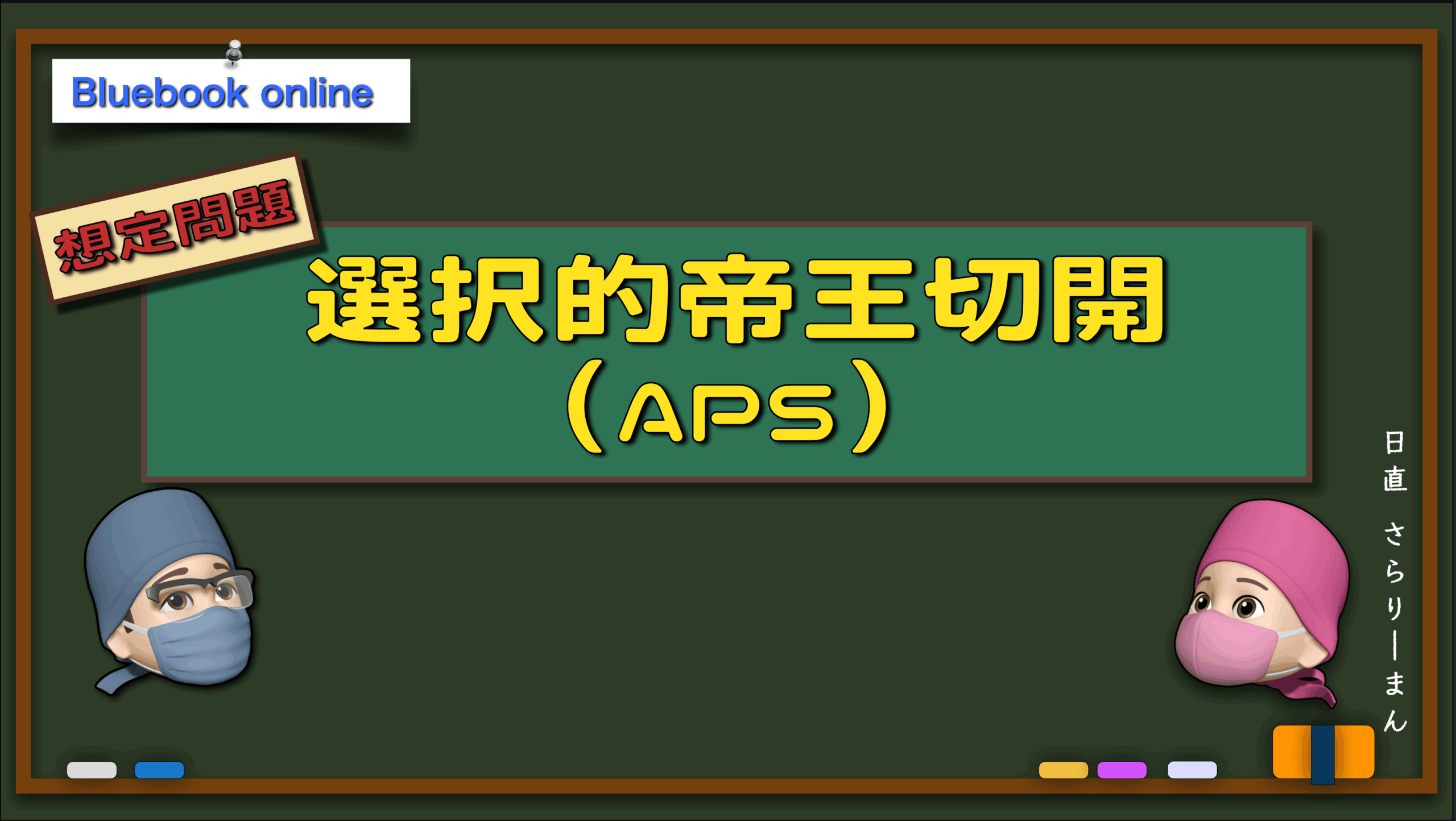症例設定
【患者】
- 35歳女性.妊娠36週5日.162cm,72kg(BMI27.3)
【現病歴】
- 2回の帝王切開歴あり.5年前に抗リン脂質抗体症候群(APS)と診断され,3年前に左下肢深部静脈血栓症(DVT)を発症している.これまで肺塞栓症などの重篤な血栓症の既往はない.
- 今回の妊娠経過は概ね順調.今回3回目の選択的帝王切開の予定で入院となった.
【既往歴】
- 抗リン脂質抗体症候群(APS):5年前.現在の妊娠期間中は低用量アスピリン(LDA)100mg/日(28週0日に終了)と予防的投与量の低分子ヘパリン(エノキサパリン40mg/日皮下注)を使用している.
- 幼少期にペニシリンによる重度のアレルギー反応(全身性発疹およびアナフィラキシー).過去2回の帝王切開では局所麻酔薬に対するアレルギーは認めず,脊髄くも膜下麻酔で安全に施行している.
【服用中薬剤】
- エノキサパリン 40mg/日 皮下注射
- 葉酸 5mg/日 鉄剤(クエン酸第一鉄ナトリウム)50mg/日
【主な検査所見・バイタルサインなど】
バイタルサイン
- 血圧: 120/80 mmHg
- 心拍数: 80 bpm
- 呼吸数: 18回/分
- SpO2: 98%(室内気)
- 体温: 36.8℃
血液検査
- RBC: 380万/μL, WBC: 9,800 /μL, Hb: 11.2 g/dL, Ht: 34.1%, Plt: 22万 /μL
- PT-INR: 1.1, APTT: 32秒(対照31秒), D-dimer: 1.8 μg/mL
- 抗カルジオリピン抗体: 40 GPL単位(陽性)
- ループスアンチコアグラント: 陽性
- 生化学検査:
- AST: 22 IU/L, ALT: 18 IU/L, LDH: 220 IU/L, ALP: 300 IU/L, γ-GTP: 25 IU/L
- BUN: 12 mg/dL, Cr: 0.6 mg/dL
- Na: 138 mEq/L, K: 4.0 mEq/L, Cl: 104 mEq/L
- Glu: 90 mg/dL, HbA1c: 5.4%
胎児エコー
- 推定胎児体重: 2,800g
- 胎盤: 子宮後壁付着,位置異常なし
- 羊水量: 正常
- 胎児心拍: 140bpm,心拍変動正常
下肢静脈エコー
- 両下肢に明らかな血栓像なし
その他
- Mallampati分類 Class II,開口制限なし
- 両下肢に軽度の浮腫は認められるが,妊婦の所見として許容範囲内
Q1. この患者に対する術前評価で特に注意すべき項目を挙げてください.
- 抗血栓療法を中断する必要があるため,抗リン脂質抗体症候群(APS)による周術期の血栓症リスクが高くなります.適切にリスク評価を行います(まぁAPSある時点でリスク↑なんですけど).
- 血液検査(D-dimer,抗カルジオリピン抗体,ループスアンチコアグラント).
- 下肢静脈血栓症(DVT)の現在の状態評価:下肢静脈エコーによる血栓の有無確認. ペニシリンアレルギーの詳細な病歴聴取:具体的な症状,発症時間,重症度の確認.
- 3回目の帝王切開予定のため,出血のリスクが増大します.過去の帝王切開の麻酔記録を確認します:使用薬剤,麻酔効果,合併症の有無.
- 凝固系検査:PT,APTT,血小板数,フィブリノゲン値の確認.
- 重症のペニシリンアレルギー患者はセフェム系の抗菌薬にも交差反応を示すことがあるため原則禁忌となります(軽症であれば大丈夫であることが多い).バンコマイシンやクリンダマイシンなどが用いられます.
⏩【経過】
- 手術室入室時,患者は不安感を訴えていますが,バイタルサインは安定しています.最終のエノキサパリン投与は24時間前に実施済みであることを確認.アレルギー情報を再確認したところ,ペニシリンによるアナフィラキシーの既往が再度確認されました.
- 前回の帝王切開時の麻酔記録を確認したところ,0.5%高比重ブピバカイン2.0mLとフェンタニル15μgの脊髄くも膜下麻酔で,Th4レベルまでの麻酔域が得られており,血圧低下に対してはフェニレフリン持続投与で管理されていました.手術中に特に問題はなかったようです.
ここから先は「オンラインメンバーシップ限定」です. ↓の「新規ユーザー登録」から登録申請を行ってください.