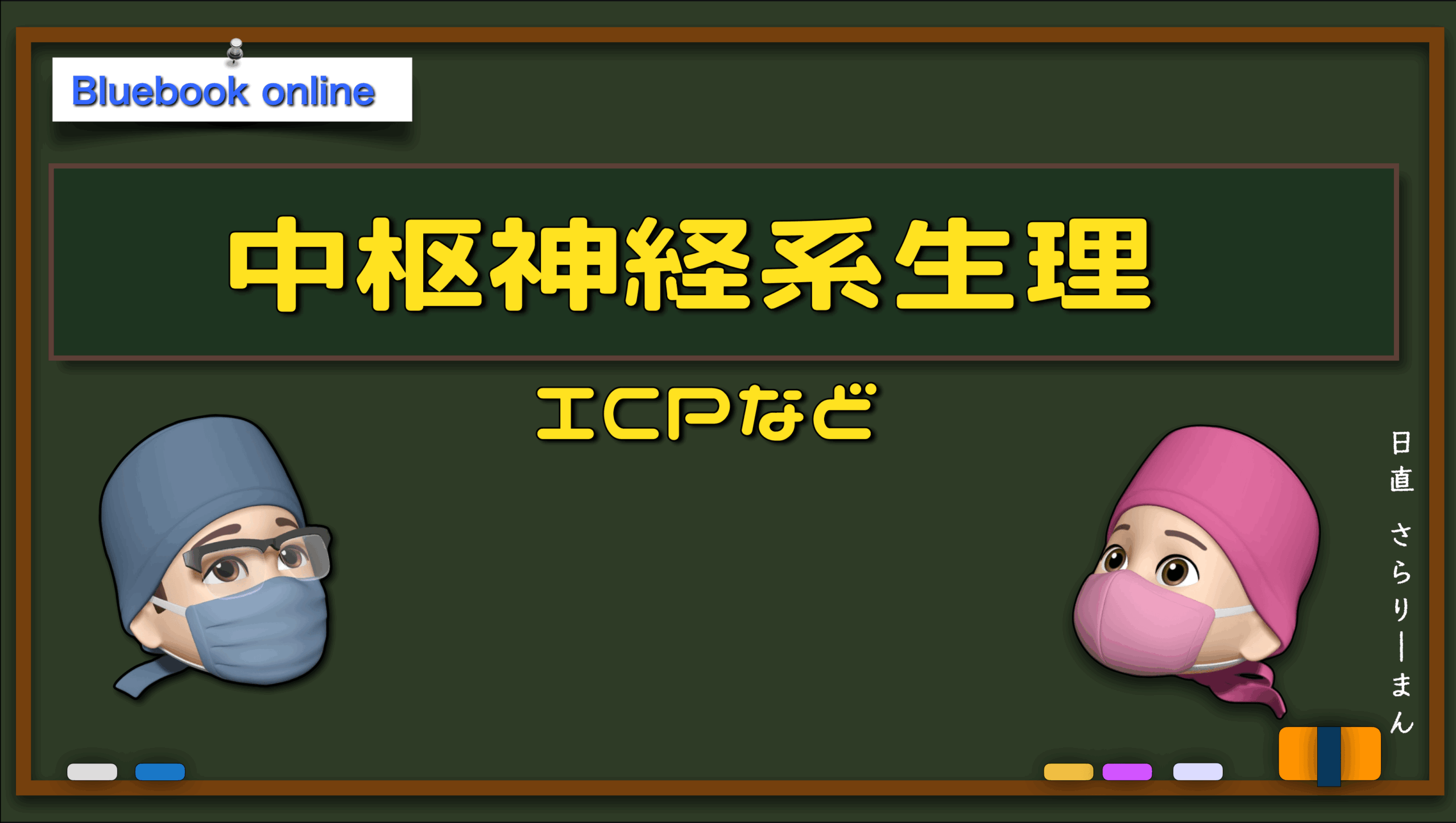- 📘 専門医試験対策目次(blog・note)
- 📝 ゆるく学ぶ周術期管理目次
Contents
📝 問題リスト
- 脳血流量・脳酸素消費量
- 成人の安静時脳血流量と脳酸素消費量はおよそどのくらいとされていますか?
- 脳血流量には,血圧が変化しても流量が保たれる機構(自動調節能)がありますが,それは血圧がどの程度の範囲にあるときですか?
- 脳血流量に影響を与える主な因子を挙げてください.
- 脳血流量を増加させる麻酔薬にはどのようなものがありますか?
- 頭蓋内圧(ICP)と脳灌流圧(CPP)
- 頭蓋内圧(ICP)の正常値はおよそどのくらいですか? また,治療介入が必要となるのはどのくらいからですか?
- 脳灌流圧はどのような因子により規定されていますか?
- 頭蓋内圧の調節とその機序
- 頭蓋内圧(ICP)が上昇する病態にはどのようなものがありますか?
- 周術期に頭蓋内圧を低下させる手段にはどのようなものがありますか.
- 静脈麻酔薬投与で頭蓋内圧が低下するのはなぜですか?
- 過換気により頭蓋内圧が低下するのはなぜですか?
- 部挙上(頭高位)で頭蓋内圧が低下するのはなぜですか?
- 浸透圧利尿薬投与により頭蓋内圧が低下するのはなぜですか?
- 胸腔内圧を低下させると頭蓋内圧が低下するのはなぜですか?
- 胸腔内圧を低下させる方法にはどのような方法がありますか?
👥 はじめに
 まっすー
まっすー特に脳外科で重要な分野ですね!



ポイント中のポイントやね.ICPの下降方法については機序とともに生理しておこう.この周辺は筆記試験でも重要です.



脳血流量3倍にして勉強します!



シャアやん.ついでに3倍働け
Keywords
脳血流量 脳酸素消費量 脳灌流圧 頭蓋内圧 ケタミン プロポフォール 過換気 浸透圧利尿薬(マンニトール) 胸腔内圧 PEEP 動脈血二酸化炭素分圧 PaCO₂
🤔 脳血流量・脳酸素消費量
Q. 成人の安静時脳血流量と脳酸素消費量はおよそどのくらいとされていますか?
- 安静時脳血流量はおよそ45〜55mL/100g脳組織/分とされています.
- 脳酸素消費量は3.3〜3.8mL/100g脳組織/分です.
補足・解説
- 脳血流量はおよそ50と覚えましょう.心拍出量に占める割合はおよそ15%と重量に比べてとても多い.※脳の重量は体重のおよそ2%.
- 脳酸素消費量はおよそ3.5と覚えましょう.全酸素消費量に占める割合はおよそ20%と重量に比べてとても多い.
- ちなみに全身血流量の約15%が脳血流として配分されています.
Q. 脳血流量には,血圧が変化しても流量が保たれる機構(自動調節能)がありますが,それは血圧がどの程度の範囲にあるときですか?
- 一般的に平均血圧がおおよそ60〜150mmHgの範囲とされていますが、この範囲は個人差や基礎疾患(特に慢性的な高血圧)によって変動します.
- 高血圧患者はこの範囲が高いほうに移動(右方移動)しており,健常者では安全とされる比較的低血圧でも脳虚血を生じる可能性があります.
補足・解説
- この値は教科書により微妙に差がありますがおおよそこんなものです.
- 脳血管障害や頭部外傷後は,この自動調節能が障害される部位が生じます.
Q. 脳血流量に影響を与える主な因子を挙げてください.
- 主に血液ガス(PaCO2,PaO2)と血行力学的な因子(平均動脈圧,中心静脈圧,胸腔内圧,頭蓋内圧)により調節され,これらの因子の変化により脳血流量が増加・減少します.
- また,ケタミンを除く多くの静脈麻酔薬(プロポフォールなど)は,脳血管収縮,脳代謝の抑制により脳血流量を減少させます.ケタミンは例外的に脳血流量を増加させます
- 体位も影響し,頭位挙上により脳血流量は減少します.
補足・解説
- 特に動脈血二酸化炭素分圧は最も強力な調節因子です.1mmHgの変化で脳血流量が約2〜3%変化するとされています.
- 二酸化炭素分圧上昇による拡張,分圧低下による収縮で脳血流量に大きく影響します.
Q. 脳血流量を増加させる麻酔薬にはどのようなものがありますか?
- ハロタン以外の揮発性吸入麻酔薬では,脳血管拡張作用により脳血流は上昇します.ただし,脳代謝抑制による脳血流量低下作用も持つため,そのバランスにより効果が決まります.
- 静脈麻酔薬ではケタミンが脳血流量を増加させます(その他は減少する).
補足・解説
- 吸入麻酔薬の中ではハロタンにつづいてエンフルラン,デスフルラン,イソフルランの順に脳血流量増加作用が強く,セボフルランが最も弱いとされています.
- 上記の通り,吸入麻酔薬は脳血管拡張作用と脳代謝抑制作用の両方を持ち,その効果はMAC値に依存します.1MAC未満では脳代謝抑制作用が優位で脳血流量(CBF)は低下しやすく,1MAC以上では脳血管拡張作用が優位となりCBFが増加する傾向があります.ただし,この効果は吸入麻酔薬の種類やCO₂分圧の影響を受けるため,絶対的なものではありません
ここから先は「オンラインメンバーシップ限定」です. ↓の「新規ユーザー登録」から登録申請を行ってください.