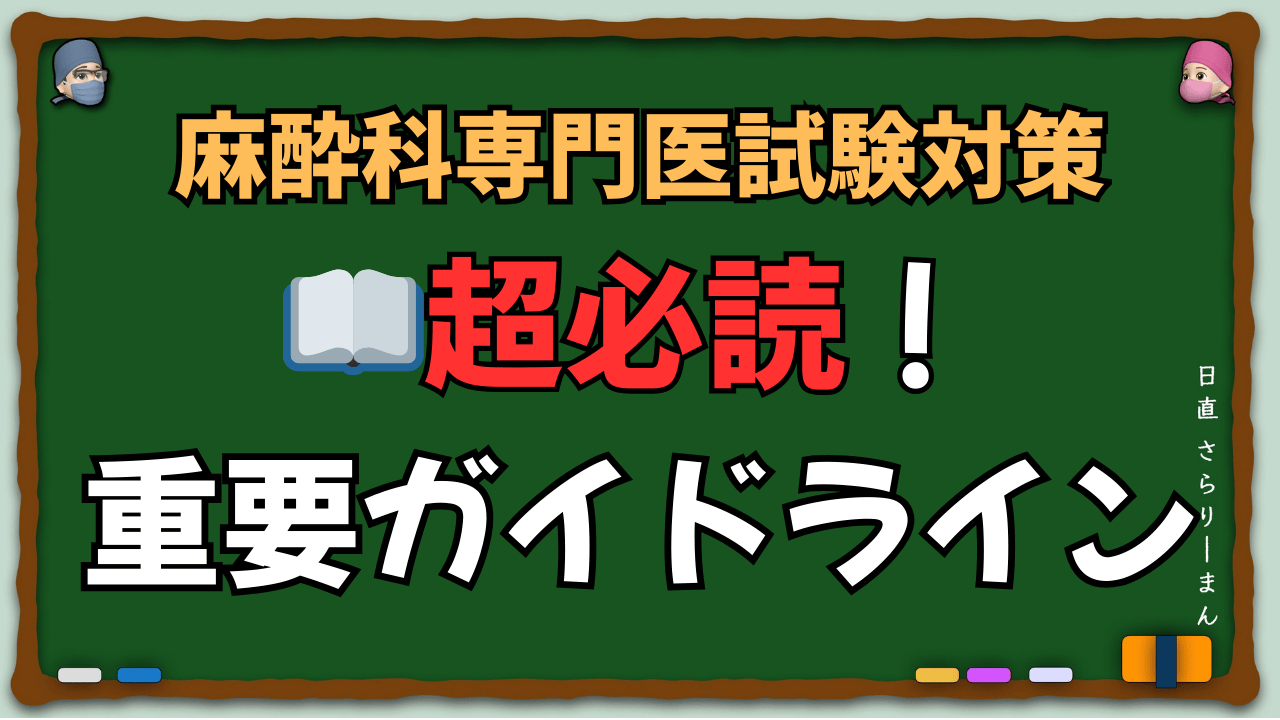- 📘 専門医試験対策目次(blog・note)
- 📝 ゆるく学ぶ周術期管理目次
以下のリンク先は,ほぼ全て公式ウェブサイトのダウンロードページや閲覧ページです.学会規約でリンクが禁止や許可制になっている場合は,名称の紹介のみにとどめている場合があります.
はじめに
 さらりーまん
さらりーまん試験勉強だけでなく,日ごろの臨床においてもガイドラインを読むことは必要だね.以下は読むべきガイドラインやプラクティカルガイドのリスト.



でも,ガイドラインも物によっては分厚くてとても読破できないんですけど・・



確かに.隅々まで読む必要はないかもしれないけど,どのような項目があるかは知っておく必要があるよ.何があるかわからなければ調べることもないからね.重要な表や項目は常に目に付くところに貼っておいてもいいね.全て目は通した方が良いけど,そうもいかないかもしれないから,最低限読むべきポイント等を紹介していきます.
ガイドラインのリスト
🔷 日本麻酔科学会のウェブサイトで閲覧できるガイドライン等(抜粋)(日本麻酔科学会)
- 悪性高熱症管理ガイドライン(2025年3月改訂)
- 麻酔器の始業点検(2022年10月改訂)
- WHO安全な手術のためのガイドライン2009(2015年5月26日改訂)
- 気道管理ガイドライン2014(2015年4月28日改訂)
- 薬剤シリンジラベルに関する提言(2015年3月27日制定)
- 周術期禁煙プラクティカルガイド(2021年9月制定)
- 骨髄バンクドナーに対する麻酔管理(2020年8月改訂)
- 安全な麻酔のためのモニター指針(2019年3月改訂)
- 術前絶飲食ガイドライン(2012年7月制定)
- Awake craniotomy麻酔管理のガイドライン(2012年5月制定)
- 脳死体からの臓器移植に関する指針(2011年5月19日改訂)
- 安全な鎮静のためのプラクティカルガイド
- 術中心停止に対するプラクティカルガイド
- アナフィラキシーに対する対応プラクティカルガイド
- MEPモニタリング時の麻酔管理のためのプラクティカルガイド
- 安全な中心静脈カテーテル導入・管理のためのプラクティカルガイド2017
- 局所麻酔薬中毒への対応プラクティカルガイド
- 産科危機的出血への対応指針(2022年1月改訂)
- 抗血栓療法中の区域麻酔・神経ブロックガイドライン(2016年9月制定)
- NICUに入院している新生児の痛みのケアガイドライン(実用版)(2014年12月27日制定)
- 日帰り麻酔の安全のための基準(2009年2月改訂)
- 宗教的輸血拒否に関するガイドライン(2008年2月28日制定)
- 危機的出血への対応ガイドライン(2025年4月改訂)
- 高齢者における術後せん妄の予防と治療のプラクティカルガイド(2024年12月制定)
- 心臓血管麻酔における血液粘弾性検査の使用指針(日本心臓血管麻酔学会)
- 抗血栓療法中の区域麻酔・神経ブロックガイドライン(日本区域麻酔学会)
🔷 日本循環器学会ウェブサイトで閲覧できるガイドライン抜粋(日本循環器学会 2025年7月26日閲覧)※太字が必須.
- 【1】肺血栓塞栓症・深部静脈血栓症および肺高血圧症に関するガイドライン(2025年改訂版)
- 【2】成人先天性心疾患診療ガイドライン(2025年改訂版)
- 【4】心不全診療ガイドライン(2025年改訂版)
- 【15】非心臓手術における合併心疾患の評価と管理に関するガイドライン(2022年改訂版)
- 【17】不整脈の診断とリスク評価に関するガイドライン(2022年改訂版)
- 【18】先天性心疾患術後遠隔期の管理・侵襲的治療に関するガイドライン(2022年改訂版)
- 【28】冠動脈疾患患者における抗血栓療法(2020年 JCSガイドライン フォーカスアップデート版)
- 【29】弁膜症治療のガイドライン(2020年改訂版)
- 【32】不整脈薬物治療ガイドライン(2020年改訂版)
- 【40】遺伝性不整脈の診療に関するガイドライン(2017年改訂版)
- 産婦人科診療ガイドライン2023 -産科編-(2023年.日本産科婦人科学会)
- 妊娠高血圧症候群 新定義・臨床分類(2018年5月.日本妊娠高血圧学会)
- 産科危機的出血への対応指針2022(日本産婦人科学会.日本産科麻酔学会)
- 2024年改訂版産科DIC診断規準(日本産婦人科・新生児血液学会)
- ARDS診療ガイドライン(日本集中治療学会)
- 日本版敗血症診療ガイドライン2024(日本集中治療学会)
- Sepsis-3(JAMA論文)
- DIC基準(日本血栓止血学会)
- 輸血の副作用(日本赤十字社)
- JRC蘇生ガイドライン2020(JRC日本蘇生協議会)
- NPO法人日本ACLS協会ガイド
- 日本麻酔科学会のCOVID-19関連情報をまとめたページ
- COVID-19診療の手引き(厚生労働省の医療機関向け情報)
- 法的脳死判定マニュアル2024(日本臓器移植ネットワーク)
- 臓器摘出術中の呼吸循環管理マニュアル(案)(厚生労働科学研究成果データベース)
- 無呼吸テスト実施指針(2015年3月27日改訂)
- 慢性疼痛診療ガイドライン(日本疼痛管理学会)
- がん疼痛の薬物療法に関するガイドライン(2020年版:日本緩和医療学会)
- 日本ペインクリニック学会
- せん妄・CAMについて(MSDマニュアルプロフェッショナル版)
- フレイルの基準:日本版CHS基準
- 甲状腺クリーゼ診療ガイドライン2017Digest版(日本甲状腺学会・日本内分泌学会)
各種ガイドラインの概要解説(抜粋)※掲載順
🔷 麻酔科学会のウェブサイトに掲載されているガイドライン
⚫ 悪性高熱症管理ガイドライン(2025年3月改訂)
- 2025年3月に改訂されています.これとは別ですが,昔から色んな手術室に悪性高熱症の緊急時治療法のパンフレットが貼ってありました.
- このガイドラインには,基本的な疫学や病理学的な内容,診断手順,術中治療手順,術後の再燃時の治療手順までが詳細に記載されています.
- 参考文献を除くと11ページとコンパクトにまとまっていますので,筆記試験の勉強も兼ねて一読しておきましょう!



TIVAメインでやっている施設ではますます出会わないですね



まぁそれは確かに・・
⚫ 麻酔器の始業点検(2022年10月改訂)
- まだコロナ前に,実技試験が行われていた頃,始業点検はヤマの一つでした.口頭試問でもちらっと問われたことはあります.
- 試験には出ないだろうと思われがちですが,術中の麻酔器関連のトラブルは,始業試験に関わる項目に関連しています.日ごろはMEさんが点検してくれる施設もあると思いますが,自分でも主要部分はきちんとチェックできるようにしておきましょう.
- 確か少し改訂により項目の数が減少しましたが,内容に大きな変化はありません.初めにおおまかな手順が記載され,後半はそれぞれについて詳しく書かれていますので、特に専攻医1年目の先生たちは,一度はしっかりと読んで構造も含めて理解しておきましょう!



私は毎日自分でやってますよ(えっへん)



別に自慢するようなことではない
⚫ WHO 安全な手術のためのガイドライン2009(2015年5月26日改訂)
- もともとは2009年にWHOによって発行されたガイドラインで,日本麻酔科学会が日本語版を作成しています(紹介ページには英語版もあります).
- ガイドライン自体は100ページ以上にわたるもので,全て読むのは大変ですが,日々の臨床において,必ず確認しておいたほうがよいのは,95ページの「手術安全チェックリスト」と,その後のチェックリストの実施マニュアルです(第3章〜4章).
- おそらく多くの施設で行われている,麻酔導入前,皮膚切開前,手術室退室前に行われているタイムアウトについて詳しく書かれています.日ごろからきちんとやっていると特に「覚えなくては!」というものではありませんが,一度は目を通しておきましょう.
- 95ページ:手術安全チェックリスト
- 96〜103ページ:WHO手術安全チェックリストの実施マニュアル



規模が大きくなくて人の入れ替わりが少ない病院だと,自己紹介微妙ですよね.



タイムアウトの概念が広まったころ,ある部長の先生が執刀するとき「私が●●科医になって早●●年・・」って自分の医師人生語った人もいたよ笑.
⚫ 気道管理ガイドライン2014年(2015年4月28日改訂)
- 麻酔科医だけでなく,研修医や手術室看護師さんにとっても必読のガイドラインです.
- 日本語版と英語版,そして重要図表の3つが閲覧できます.
- 特に,カプノグラムを用いた換気状態の三段階評価(V1〜V3),グリーン・イエロー・レッドの3つのゾーン分類からなる気道管理アルゴリズム(JSA-AMA)は超重要です.
- また,気道評価時に評価すべき危険因子と,該当する因子の数による気道確保困難の発生頻度とオッズ比も確認しておきましょう.ある程度経験のある麻酔科医であれば,肌感覚としてこれらのリスク因子には反応できると思います.発生頻度の細かな数字まで暗記する必要はないかもしれませんが,最高リスクの場合の数字くらいは覚えておいてもよいかもしれません.
- 2〜3ページ:換気の有効性を臨床的に評価する方法(図表あり)
- 5ページ:気道管理アルゴリズムの表
- 7ページ:術前に評価すべきリスク因子とその数に応じた危険度のデータ
- 10ページ:マスク換気を改善させる手段の例



日ごろから意識していれば難しいことはないですね



だね.覚えておくとすれば数字とか,各段階の確実な気道確保の方法かな
⚫ 薬剤シリンジラベルに関する提言(2015年3月27日制定)
- 日々起こり得る薬剤誤投与を予防するためのシリンジラベルの提言です.
- 麻酔導入薬や筋弛緩薬,局所麻酔薬など,薬効別にラベルやカラーコードの提案が記されています.これに関しては過去に筆記試験でも問われたことがあります.
- 短い提言書のため,その意義も含めて確認しておきましょう.



忙しいときとか,真夜中の緊急ではうっかりミスや,無意識のミスが生じやすいですもんね.



そう.間違いを起こしかけるのはヒューマンエラーだからある程度仕方がない.それを患者に投与する前に気付けるシステムが重要だね.
⚫ 周術期禁煙プラクティカルガイド(2021年9月制定)
- 手術・麻酔に喫煙はよくない!禁煙しましょうね!というガイドだけかと思いきや,なんと50ページ以上もあるしっかりとしたプラクディカルガイド.
- 喫煙や受動喫煙が与える影響から禁煙支援,禁煙補助薬,再喫煙の防止などまで,多数の文献をもとにして書かれています.33ページ以降は参考文献やパンフレットなので,一度は目を通しておくとよいと思います.



禁煙しろ!って結果は変わらなくても,データを元に自信を持って言えるようになりそうですね.
⚫ 骨髄バンクドナーに対する麻酔管理(2020年8月改訂)
- 1ページのシンプルな指針ですが,筆記試験では問われたことがあります.
- 基本的な体位や貯血,麻酔法について書かれています.
⚫ 安全な麻酔のためのモニター指針(2019年3月改訂)
- こちらも1ページにまとめられた指針です.これも知らない人はいないと思いますが,基本中の基本のモニター指針です.
- 適応されるのは全身麻酔,硬膜外麻酔,脊髄くも膜下麻酔ですが,基本的に麻酔科医が関わる麻酔ではこれに則って行いましょう.
- 1993年に作成され,現在まで4回の改訂が行われています.
⚫ 術前絶飲食ガイドライン(2012年7月制定)
- 毎日急患を受けている病院では,完全に頭に入っているとは思いますが・・.
- 清澄水,母乳,人工乳・牛乳,固形物の術前絶飲食時間について,多数の文献を元に書かれています.



あくまで目安ね.これらの時間が経過していても,糖尿病や透析,外傷,消化管運動障害があるような患者さんでは,胃内容物が残っていることがある.



術前に取られたCTがあれば確実にわかりますけどね!迅速導入で輪状軟骨圧迫を行っていても完全ではないのが恐ろしところ・・
⚫ Awake craniotomy麻酔管理のガイドライン(2012年5月制定)
- どこでもやっている手術ではないと思いますが・・.筆記試験ではともかく口頭試問では問われにくいとは思います(想定問題は1問作成しましたが).
- 基本的な前投薬,鎮痛,覚醒させるときの手順や覚醒中の合併症(嘔気・嘔吐や痙攣など)について,文献をもとにまとめられています.
- 行っている施設ではプロトコルが用意されていると思いますが,そうでない施設の先生方は一読を.
⚫ 安全な鎮静のためのプラクティカルガイド
- 鎮静の定義や分類,鎮静時の鎮痛,鎮静時の評価,モニタリング等について詳細に述べられています.
- このガイドラインの中でも掲載されている,修正Aldreteスコアに関しては,過去にも出題があるため,1つ1つの項目と点数配分までは覚える必要はないと思いますが,評価項目はしっかりと覚えておいたほうがよいと思います(日ごろから使用している場合は自然に覚えていると思いますが).
- 25ページ:鎮静後の覚醒評価スコア(Modified Aldreteスコア)の表
- 31ページ:MPADSSの表



挿管する場合はいいんですけど,そうでない場合の鎮静が一番気を使いますよね・・



少しは緊張感持ったほうがいいんじゃない?退屈だからって,自分にも”鎮静”かかてるんじゃないだろね?



ばれてる・・・
⚫ 術中心停止に対するプラクティカルガイド
- さまざまな理由(出血や肺塞栓,局所麻酔薬中毒,緊張性気胸,アナフィラキシー,周産期の母体などなど)の心停止についてまとめられた,すばらしいプラクティカルガイドです.
- 各理由の心停止についての,詳細なアルゴリズムも紹介されています.どの項目も心停止に至らずとも超重要なので,必ず一読はしておきましょう!!
- 仰臥位以外での心停止の部分(41ページ〜)は必読です.
- 全部です!が・・以下のフローチャートやアルゴリズムは必ず押さえておきましょう.
- 7〜8ページ:術中心停止の初期対応・心停止治療のアルゴリズムのフローチャート
- 9ページ:蘇生後ケアのアルゴリズム(ROSC後の対応)
- 17ページ:危機的出血への対応アルゴリズム
- 25ページ:心原性ショックによる左心不全の処置アルゴリズム
- 28ページ:局所麻酔薬中毒への対応アルゴリズム
- 41ページ:仰臥位以外での心停止



先生は術中心停止の経験あります?



完全に心停止を起こしたのは研修医のころの酷い外傷症例(出血)で一度,あとは心停止寸前にまでなったのは,同じく出血や,心筋虚血,肺塞栓などであるね.



できれば経験したくないんですけど・・



経験しないにこしたことはないけど,対処をしっかりと知ることでまず動くことはできるから,マストだよ.
⚫ アナフィラキシーに対する対応プラクティカルガイド
- 試験でも筆記・口頭問わず頻出のアナフィラキシーへの対応プラクティカルガイドです.
- 疫学から診断,治療,術後の確定診断まで文献をもとにがっつりと書かれています.
- 対処はもちろんですが,診断も問われることがあるので,しっかりと読んでおきましょう.
- 13ページ:アナフィラキシー高リスク患者における術前診断のフローチャート
- 19〜20ページ:発症時の鑑別診断
- 22ページ〜:アナフィラキシーの治療
- 25ページ〜:術後の診断(確定診断)



これも経験ありますか?



未知のラテックスアレルギーと,救急外来でハチに刺されてなった症例はあるんだけど,周術期のアナフィラキシーの原因の多くを占める,抗菌薬,筋弛緩薬,スガマデクスに関してはまだない.そしてこれからもないと信じたい.
⚫ MEPモニタリング時の麻酔管理のためのプラクティカルガイド
- MEPのモニタリング方法など基礎的なことから,各科手術の振幅低下時の対応など実践的なことまでが詳細に書かれたプラクティカルガイドです.
- 基礎的なことももちろん大事ですが,特に14ページからの科別のモニタリング方法と低下時の対処については必ず理解しておくことが重要です.
- 特に,脳外科手術では,「手技のせいなのか,そうでないのか」,大血管手術では「脊髄虚血の場合にどのような変化が起こるのか」をしっかりと理解してしておきましょう!
- 10ページ:定義
- 14〜28ページ:各科(脳外科・脊椎外科・血管外科)のモニタリングとMEP低下時の対応.



脳外科の場合は,直前の操作から戻ることで戻ることが多いですけど,血管外科のMEP低下は怖いですよね・・.



対麻痺は術後のQOLに直結する重篤な合併症だからね.とにかくMEP低下が生じた場合に,きちんと鑑別できて,適切に対処,意見もできるようにしておこう.
⚫ 安全な中心静脈カテーテル導入・管理のためのプラクティカルガイド2017
- 実技試験が現在試験としては行われていないこともあり,口頭試験の中で問われることもありますが,それも最近はあまりない印象です.筆記試験では合併症も含めて問われやすい部分のため,しっかりと読んでおきましょう.
- このプラクティカルガイドは多くの文献をもとに書かれているので,関連知識を整理するのには最適です.経験則によるものにはいい加減なものも混じっていることがあるので,こういったガイドラインはとても助かりますね.
- 手技に関しては,日常的に行っていればほぼ問題ないと思いますが,今一度確認を.合併症をその対処に関しては特に見直しておきましょう.
- 45ページからは感染対策について述べられています.推奨されることとそうでないものもありますので一読を.
- 14ページ:各穿刺部位の特徴(長所や短所)
- 16ページ〜:穿刺手順
- 40ページ〜:合併症について
- 45ページ〜:感染対策



基本的には内頸静脈から穿刺することが多いと思うけど,鎖骨下から行う場合も超音波ガイド下で行うなど,気胸を起こさないように気をつけよう.



肥満で首が短い人とか,拘縮がある人,いかり肩の人とか,典型的な体系でない場合は特に緊張しますよね・・.



そうした場合は,留置期間なども参考に穿刺部位を変える必要もあるね.PICCなんかも選択肢の一つ(流量はしょぼいけど).
⚫ 局所麻酔薬中毒への対応プラクティカルガイド
- 麻酔科医とは切っても切り離せない局所麻酔薬.脊髄くも膜下麻酔,無痛分娩を含む硬膜外麻酔,末梢神経ブロック,癌性疼痛に対する神経ブロックなどなど,その使用は多岐にわたります.
- 脊髄くも膜下麻酔程度の使用量ではまず起きることはないでしょうが,硬膜外麻酔(特に血管が怒張している妊婦さん)や末梢神経ブロックでの血管内誤投与,血管豊富な部位における末梢神経ブロックでは特に危険です.
- 投与前吸引,分割投与などの予防方法,中毒発症時の症状,診断時の対処(脂肪乳剤など)については,必ずすらすらと言えるように!
- 短いプラクティカルガイドなので,初めからしっかりと目を通しましょう.
- 4ページから,予防・症状・治療になります.



特に症状の発現順と,脂肪乳剤の投与量に関してはマストだね



まだ経験したことないんですけど,いつか起こりそうで怖いです.
⚫ 産科危機的出血への対応指針(2022年1月改訂)
- 下記の産婦人科関連のガイドライン参照
⚫ 抗血栓療法中の区域麻酔・神経ブロックガイドライン(2016年9月制定)
- 日本区域麻酔学会のガイドラインページにも掲載されています.
- アスピリン,クロピドグレル,プラスグレルといった抗血小板薬,ヘパリンやワルファリン,DOACなどの抗凝固薬内服患者の区域麻酔についての,術前中止期間の目安,カテーテル抜去時の時間の空け方など,エビデンスをもとに非常に丁寧に作られています.
- 特に,8〜9ページのDOACに関する事項,19ページの手技別のリスク分類,21・23ページの各抗血栓薬の中止期間などがまとめられた表はいつでも見られるように印刷して,貼っておいてもいいかもしれません.
- ガイドライン発行後に寄せられた質問に対するアンサーも「追補版」として公開されていますので,目は通しておきましょう.
- 8〜9ページ:DOACの特性と,硬膜外麻酔実施に関する指針の表
- 19ページ;区域麻酔,神経ブロック手技に際する,出血リスク分類の表
- 21ページ:抗血小板薬の取扱表
- 23ページ:抗凝固薬の取扱表



確かに,高齢者になると何かしら飲んでる人のほうが多いですもんね



毎回参照することで,自然に覚えられるようになると思うけど,少しでも迷ったら,記憶に頼らずしっかりと確認するクセをつけよう.万が一硬膜外血腫を起こしたときの大変さを考えると,それくらいはマストです.
⚫ NICUに入院している新生児の痛みのケアガイドライン(実用版)(2014年12月27日制定)
- 自ら明示的に痛みを訴えることのできない新生児の疼痛に関するガイドラインです.
- 新生児の痛みを評価するためのツールの紹介や使用方法,意義について書かれています.
- 採血や処置時に実施可能な非薬理的緩和法(環境調整、ポジショニング、おしゃぶりなど)が具体的に示されており, 痛みのケアを「第5のバイタルサイン」として日常診療に組み込む重要性が強調されています.
- 従来「新生児は痛みを感じない」と考えられていた誤解を科学的根拠で修正し,新生児医療における倫理的配慮の必要性を提示しています.
- 具体的な鎮痛薬の使用方法が掲載されているものではありません.
⚫ 日帰り麻酔の安全のための基準(2009年2月改訂)
- 1ページの簡潔な安全基準についてまとめられています.
- これらに関しては筆記試験で問われることがありますので,確認しておきましょう.
⚫ 宗教的輸血拒否に関するガイドライン(2008年2月28日制定)
- 確か今まで出題があった記憶はない(少なくとも口頭試問では)のですが,倫理的な面も含めて重要な問題です.想定問題でも1題作成しています.
- これに関しては,高校生のころに,北野武さんの『説得』というドラマがあり,見た覚えがあります.現場での医師や看護師の思い,両親の思いが交錯し,見ていて歯がゆく辛かった記憶があります(今も見られるのかな?).
- これに関しては指針を元に,各病院の倫理委員会でもおそらく話し合われていると思いますので,院内文書等も確認しておきましょう(色々な病院もウェブサイトで公開していますね).
- ガイドラインにはフローチャートも用意されていますので,内容を整理しておきましょう.
- ポイントは,年齢(18歳以上),自己決定能力の有無,確認書類の有無,15歳未満の場合です.
⚫ 危機的出血への対応ガイドライン(2025年4月改訂)
- 産科危機的出血への対応指針と合わせて,見たこともない人はいないと思います(たぶん).
- 小規模の手術しか行わない施設ではほぼ起こらないとは思いますが,専門医研修を行うような施設では,心臓手術,大血管手術,肝切除術,胸部外科手術など,いつ大量出血を起こしてもおかしくない手術が毎日行われていますので,必読ガイドラインです.
- 特に,予想される場合の準備,指揮系統の確立,輸血製剤の準備と選択が重要です.近年はトロンボエラストグラフィが導入されている施設も増えてきているため,それらを活用した問題も出題される傾向にありますので,それと合わせた勉強が必要です.



万を超える出血はまれだと思うけど,数千程度の出血はリスクのある手術や患者ではいつ起こってもおかしくないという心構えが重要だね.



中規模施設だと,血液製剤の在庫が少なくて困ることありますよね・・



ある!リスクが高い場合はあらかじめオーダーされてるけど,予期せぬ場合のスピード感は確実に大病院より劣ってしまうから,術野を見てあやしい場合は,早めに手配するのが超重要!ちなみに,この前出血したとき,県内から輸血が消えていて手配に難渋してひやひやしたよ.



たぶんどこかの大規模施設で大量に使用されたんでしょうね.知らんけど
⚫ 高齢者における術後せん妄の予防と治療のプラクティカルガイド(2024年12月制定)
- 近年の試験を見ていても,せん妄に関してはトピックの一つです.リスク,診断,対処,予防とまんべんなく問われる可能性があります.
- 50ページほどあるなかなか読みごたえのあるガイドですが,せん妄のリスク因子(23ページに表),予後に与えるリスク,DSM-5による専門診断規準や,過活動型などの分類(16ページに表).予防方法(29ページに表)については理解しておきましょう.
- 16ページ:せん妄の診断規準と分類の表
- 17〜18ページ:CAM日本語版,CAM-ICU日本語版の表
- 23ページ:せん妄の術前のリスク因子の表
- 25〜26ページ:せん妄の術中・術後のリスク因子の表
- 29ページ:予防方法の表(Hospital Elder Life Program)



起こしちゃうと,術直後の不穏と一緒であとで何も覚えてないんですよね・・



そう.予後にも影響するから,特にリスクの高い患者さんや,大手術後,ICU入室患者さんではかなりの高齢者でなくても注意が必要.
🔷 麻酔関連学会のガイドライン
⚫ 心臓血管麻酔における血液粘弾性検査の使用指針(日本心臓血管麻酔学会)
- 日本心臓血管麻酔学会のガイドラインページには,表題の血液粘弾性検査の使用指針の他,教育ガイドライン,筋赤外線脳酸素モニターの使用指針,スワンガンツカテーテルの使用に対するステートメント等が掲載されていますので,必要に応じて読んでください.
- 血液粘弾性検査の使用指針も50ページほどありますが,全て読むのはなかなか大変なので,以下のページから押さえておきましょう.
- 14・15ページ:TEG®6sの使用方法,TEG®6sの結果の解釈
- 26ページ:周術期の止血治療に用いる血液製剤とその適応
- 31・32ページ:成人心臓手術での血液粘弾性変化
⚫ 抗血栓療法中の区域麻酔・神経ブロックガイドライン(日本区域麻酔学会)
- 上記の通り
🔷 日本循環器学会ウェブサイトで閲覧できるガイドライン抜粋
(日本循環器学会 2025年7月26日閲覧)
- すばらしい包括的なガイドラインが多数掲載されています.ガイドラインと一緒に解説動画もありますのでとても勉強になります!
- 一つ一つのガイドラインはとても分量が多いので,全部読むのはなかなか厳しいですが,要所要所の記述や絶対見ておいたほうが良い表などてんこ盛りなので,必要部分は印刷したり勉強会で使用したりしても良いかも知れませんね.
- 番号は,公式の閲覧ページに付けられたガイドラインの番号です.
- 必ず目を通すべきガイドラインは以下に示す5つ(【1】【15】【28】【29】【32】)です.
【1】肺血栓塞栓症・深部静脈血栓症および肺高血圧症に関するガイドライン(2025年改訂版)
- 全188ページもあります.
- VTE,APE,PHは試験に関係なく麻酔科も深く関わる部分なのでしっかりと勉強しておきましょう.
- 18ページ:VTEのおもな危険因子の表
- 28ページ:Wellsスコアの表
- 58ページ〜:第3章:VTEの予防.具体的な個別の予防法の記述は61ページから
- 60ページ:VTEのリスクと推奨される予防法・VTEの付加的な危険因子の強度
- 61ページ〜:各診療科での予防法
- 143ページ〜:新生児期のPH.NOについても記載.



DVTに関しては入院時からスクリーニングや予防の処置がとられますね



そうだね.特に私たちがかかわる手術患者さん達の中には,リスクが高い場合がかなり多いからね.起きたときは大変だけど,できることからしっかりと対応できるように.施設によってはできる治療とできない治療があるから,日ごろから関連の診療科とも話し合ってくことも重要だね.
【15】非心臓手術における合併心疾患の評価と管理に関するガイドライン(2022年改訂版)
- 全131ページ.
- 第2章は術前評価で麻酔科にも関連の深い章になっています.特に非心臓手術の心合併症リスク分類,RCRI,非心臓手術の術前評価アルゴリズムなどは必ず目を通しておきましょう.
- また,Part2(GRADEに沿って作成したClinical Questionと推奨)には,非心臓手術前の感結構再建やTAVI等についての推奨について書かれていますので、こちらも推奨がどうなっているかは最低限覚えておきましょう.
- 特に第2章:術前評価の部分は必読
- 23ページ:心合併症発症率からみた非心臓手術のリスク分類の表
- 28ページ:RCRI:Revised Cardiac Risk Indexの表やイベント発生率
- 34ページ:非心臓手術術前の循環器評価アルゴリズム
- 72ページ〜:Part2 GRADEに沿って作成したClinical Questionと推奨



たしかに,このあたりは最近のポイントになっているみたいですね



概要だけでも知っているのと知らないのではだいぶ違うし,わざわざ術前評価と銘打ってASA-PSなんかも載せてくれてるから,第2章は必読!
【17】不整脈の診断とリスク評価に関するガイドライン(2022年改訂版)
- メジャーな不整脈ついての詳細なガイドラインです(全98ページ)
- 第2章からが各不整脈の各論になっており,通常の徐脈性・頻脈性不整脈の診断と,QT延長症候群やブルガダ症候群を初めとする遺伝性不整脈の記述がそれに続きます.どちらかというと検査や診断がメインのガイドラインのため,それぞれに対する治療・対処に関しては【32】の不整脈薬物治療ガイドラインを参照したほうがよいかもしれません.
【18】先天性心疾患術後遠隔期の管理・侵襲的治療に関するガイドライン(2022年改訂版)
- 表題の通りのガイドライン(全133ページ)です.
- 試験対策だけを考えるとヘビーすぎる内容ですが,筆記試験対策のバックグランドとしての最近の知識や治療に対するアップデートやエビデンスの確認としてはいいかもしれません.
- 小児先天性心疾患に対する治療が進歩した現在,そういった患者さんが他の疾患で手術を受けに来る可能性は高まっています(多くは大規模病院に行くとは思いますが・・).依然にLiSAでもFontan術後の妊婦さんの特集もありましたし,未治療のASDが発見される患者さんもいますので,典型的な血行動態の理解はしておきましょう!
【28】冠動脈疾患患者における抗血栓療法(2020年 JCSガイドライン フォーカスアップデート版)
- ほとんどは循環器科・内科向けの内容ですが,第5章(心臓手術・非心臓手術における周術期の抗血栓療法)は麻酔科医と関連が深い章になります.
- 筆記試験や口頭試問でも,PCI後の待機手術期間や抗血栓療法の中止等について問われることがありますので,ポイントを絞って読んで覚えておきましょう!
- 35〜36ページ:PCI(POVAやDESなど)施行後の待機的非心臓手術の推奨施行時期の表
- 38〜39ページ:冠動脈疾患患者における非心臓手術施行時の抗血小板薬の休薬の表と,術後の再開時期の表



絞扼性腸閉塞とか,消化管穿孔とか,大動脈解離,頭蓋内出血とか命に関わる緊急手術の場合はしょうがないですけど,やっぱり複数飲んでたりすると,明らかに止まりにくいですもんね



だね.とりあえず待期的手術では色々止めるけど,アスピリンは継続することが多いのを覚えておこう.知ってると思うけど
【29】弁膜症治療のガイドライン(2020年改訂版)
- これも132ページもあるガイドラインですが,まずは試験でも問われやすい,第2章の僧帽弁閉鎖不全症と,第5章の大動脈弁狭窄症に目を通しておきましょう.
- 特にエコーを用いた重症度分類,手術適応は重要なので,数値まで覚えておきましょう.
- また,TAVIが普及した現在,その選択に関しても問われる可能性があるので,66ページからの外科治療とカテーテル治療の部分も読んでおきましょう.
- 25ページ:心エコー図検査によるMRの重症度評価
- 30ページ:重症一次性MRの手術適応
- 37ページ:左室収縮機能低下に伴う二次性MRの手術適応
- 63ページ:心エコー検査によるAS重症度評価
- 65ページ:ASの重症度評価(低心拍出量の場合も含めたフローチャート)
- 69ページ:重症ASの手術適応のフローチャート,AS患者の治療方針決定において弁膜症チームで協議すべき因子(SAVRかTAVIのどちらを考慮するかの表)



TAVIも随分普及したから,そろそろ口頭試問でも出てもおかしくないね.まぁ最近の口頭試問は総合的に問われることも多いから,TAVIの詳細をつっこんで聞かれることはないかもしれないけど.



施設によっては経験せずに研修終了することもありそうですけど,基本的なことは押さえておかなきゃですね.
【32】不整脈薬物治療ガイドライン(2020年改訂版)
- 不整脈全般を扱うガイドラインで全154ページとなかなかの分量です.
- ポイントとなるのは,心房細動のリスク評価や,心拍数コントロール,QT延長とTdP,ブルガダ症候群,WPW症候群とpseudo VTなどへの対応です.VTやVFもありますが,こちらはみなさんACLS等で十分理解されているとは思います.
- 24ページ:第2章 徐脈性不整脈
- 45〜47ページ:CHADS₂・CHA₂DS₂-VAScスコアと脳梗塞発症率の表
- 50ページ:HAS-BLEDスコア
- 67ページ:頻脈性心房細動に対する心拍数調節療法の治療方針のフローチャート
- 91ページ:器質性心疾患に合併する再発性/反復性の心室頻拍に対して使用される薬物の選択フローチャート
- 93ページ〜:第8章 多形性心室頻拍・torsade de pointes
- 96〜97ページ:二次性QT延長症候群の主な原因の表と,急性期の薬物治療フローチャート
- 97ページ〜:ブルガダ症候群など
- 102ページ〜:第10章 心室細動・無脈性心室頻拍・心停止



読むべきポイントも多いけど,この辺は試験でも何度も出題されているポイントだし,実臨床でも出会う可能性が高い部分だからしっかりと復習しておこう



たしかに,実際に危険な不整脈までは起こさなくても,基礎疾患としては多いですもんね.試験だと頻発しますけど.
🔷 産婦人科関連のガイドライン
⚫ 産婦人科診療ガイドライン2023-産科編-(2023年)
- 日本産科婦人科学会ガイドラインページから閲覧可能です.
- 妊娠〜産褥までの管理や異常時の処置,胎児に関する問題,合併症妊娠等,幅広い包括的なガイドラインです.もちろん全部読むのは厳しい(400ページ以上あります・・😅).
- ただし,エビデンスレベルを含めたQ&A方式になっていますので,各質問の頭の部分だけを拾っていくだけでもかなり知識の確認になるのではないかと思います.
- 8〜19ページ:妊婦のDVTについて
- 56〜61ページ:妊婦・授乳中の予防接種について
- 156〜161ページ:前置胎盤・低置胎盤について
- 173〜175ページ:常位胎盤早期剥離について
- 176〜188ページ:妊娠高血圧症候群関連
- 196ページ:HELLP症候群・急性妊娠脂肪肝
- 233ページ:胎児心拍数陣痛図の評価について
- 253〜256ページ:子宮収縮薬について
- 261〜263ページ:選択的帝王切開時の管理について
- 271〜274ページ:産科危機的出血への対応について
- 360〜365ページ:新生児蘇生について
⚫ 妊娠高血圧症候群 新定義・臨床分類(2018年5月)
- 日本妊娠高血圧学会のウェブサイト(学会誌・刊行物 名称・定義について)から閲覧できます.
- 全8ページのPowerPoint風の資料なので,すぐに目は通せます.
⚫ 産科危機的出血への対応指針2022(日本産婦人科学会)
- 日本産科婦人科学会や,日本産科麻酔学会のウェブサイトで閲覧できます.
- 対応フローチャートが見やすいです.産科手術を行う部屋には貼っておきましょう.
- ガイドライン内には異型輸血や産科DICの表も載っていますが,産科DICは日本産婦人科・新生児血液学会により,新たな基準(2024年)が出されています(下記).よりシンプルに計算もしやすくなっています.



口頭試問で産科があたったときは,出血する可能性が非常に高いので,しっかりと対応を述べることができるようにね.
⚫ 産科DIC診断規準(日本産婦人科・新生児血液学会)
- 日本産婦人科・新生児血液学会のウェブサイトで確認ができます.2022年に暫定版が,2024年6月に「2024年改訂版産科DIC診断規準」が発表されています.
- 従来は採点項目も多く,やや計算がしづらい印象がありましたが,2024年改訂版はかなりシンプルになって覚えるにも比較的簡単になっています.
- 同じページに,非凝固性分娩後異常出血の定義についても示されていますので是非目を通しておいてください.
🔷 集中治療関連のガイドライン等
⚫ ARDS診療ガイドライン2021(日本集中治療学会)
- 日本集中治療学会のガイドラインページから閲覧可能です.
- 詳細版は何と1216ページ(!!!!)です.全部読むのはほぼ無理なので,特に麻酔科の関わる人工呼吸関連の部分を読みましょう.目次の部分にはCQとそれに対する答え(推奨)が合わせて掲載されていますので,まずはここで気になる部分を見て,推奨の部分だけでも把握しておきましょう.
- 472ページ〜:領域C 侵襲的呼吸補助
- 特にCQ19〜25.



麻酔科が関わる部分では,敗血症患者のARDSが多い印象ですね



そうだね.あとはひどい誤嚥を起こした場合も発症する可能性が高いから,誤嚥の対処と合わせても勉強しておこう.
⚫ 日本版敗血症診療ガイドライン2024(日本集中治療学会)
- 同じく日本集中治療学会のガイドラインページから閲覧可能です.
- 全149ページですが,初めにCQ一覧があります.ポイントを押さえて読んでおきましょう.
- CQ1-1〜2:敗血症の定義や,診断と重症度分類
- CQ1-9:初期輸液蘇生に不応の敗血症の管理場所
- CQ2-3:抗菌薬の選択について
- CQ3-1〜8:初期蘇生における指標や,初期輸液,昇圧薬の使用,ステロイドなどについて
- CQ4-1〜2:PMX-DHPと,AKIに対する早期腎代替療法について
- CQ5-1:敗血症性DICの診断について



敗血症は筆記・口頭試験に関わらず超重要事項ですね



口頭試問では消化管穿孔との組み合わせで出題される可能性が高いね.定義,指標,初期輸液蘇生や昇圧薬等の使用方法について,しっかりと答えられるようにしておこう.
⚫ DIC基準(日本血栓止血学会)
- 日本血栓止血学会のガイドラインページから閲覧できます.
- DIC診断基準2017年度版(全23ページ)の,383〜384ページ(PDF右上のページ番号)に基礎疾患や鑑別診断,診断規準が掲載されています.基準の細かな点数を覚えるのは大変だと思いますが,DICの型,算定項目やおおまかな内容,何点以上で診断とするかに関しては把握しておきましょう.
⚫ 輸血の副作用(日本赤十字社)
- 天下の日赤のウェブサイトです.医薬品情報の中に輸血の副作用が特集されています.
- 最も重篤な(今はシステム的に起こしにくいですが)溶血性輸血副作用,発熱,アレルギー反応,GVHD(これも今は放射線照射により報告はなくなっているようですが),TRALI/TACO,高カリウム血症などが詳述されています.
- 特にTRALI/TACOに関しては,試験でも重要なポイントなので,診断規準や鑑別,治療や予後についても復習しておきましょう!
⚫ JRC蘇生ガイドライン2020
- JRC日本蘇生協議会のガイドラインページに掲載されているガイドラインです.
- PDF版も提供されており,第1〜4章が,BLS,ACLS,PLS,NCPRになっており,詳述されていますので,必ず読んでおきましょう.
- また,5章は妊産婦の心肺蘇生となっており,日ごろ経験する可能性は低いと思いますが,一度は目を通しておきましょう.



手術室にいるとあまり心肺蘇生することはないですね



まぁ,そうならないように管理するのが仕事ではあるから・・.でも,危機的出血,肺塞栓や空気塞栓,どんづまりの心筋虚血などではいつでも起きる可能性があるから,リスクのある患者では最低限の心構えはしておくことだね.
🔷 COVID-19関連
⚫ 日本麻酔科学会のCOVID-19関連情報をまとめたページ(日本麻酔科学会)
- 2022年までの学会からのアナウンスをまとめたページです.
- すでに数年前の情報ですし,当時とは状況も全く異なりますが,次またいつ同様の事例が起こるかわかりませんので,整理するという意味では有用だと思います.
- ワクチン摂取後の手術待機期間や,手術後の摂取までの期間,感染症患者への対応などは復習しておきましょう.
⚫ COVID-19診療の手引き(厚生労働省の医療機関向け情報)
- 厚生労働省の新型コロナウイルス感染症の,医療機関向け情報がまとめられたページです.
- 最新のCOVID-19診療の手引きは,2024年4月に公開された10.1版です.おそらくはこれが最終版になるのではないかと勝手に思っていますが・・.
- ただし,治療薬や基本的な対応は,筆記試験でも問われる可能性がありますので,代表的なものは押さえておきましょう.
🔷 脳死判定・臓器移植関連
⚫ 法的脳死判定マニュアル2024(日本臓器移植ネットワーク)
- 日本臓器移植ネットワークの法令集&マニュアルのページから閲覧できます.
- 最新版は2024年版です.
- 脳死判定マニュアルだけでなく,臓器提供施設のマニュアルや,臓器提供時のフローチャートなどもまとめられていますので,ぜひ一読を.
- 脳死判定マニュアル自体も13ページと長くないため全部読みましょう.
- 3ページ:脳死提供ができない場合(除外項目)
- 5ページ〜:脳死判定の具体的な項目とその手順(深昏睡の確認や脳幹反射の確認,脳波の測定方法など)
⚫ 臓器摘出術中の呼吸循環管理マニュアル(案)(厚生労働科学研究成果データベース)
- 表題の通りです.掲載ページを見つけることができなかったため,直リンクアドレスを載せますが,問題がある場合はお知らせください.削除いたします(PDFファイルへのリンク).
- 手術室搬入前〜術中の管理方法,バイタルサイン等の管理目標値などが掲載されています.
- 移植を行う施設はある程度限られており,経験することはあまりないかもしれませんが,臓器摘出術に関しては小規模施設を除けば出会う可能性はあると思います(ヘルプの麻酔科医は来てくれるようですが,基本的に管理する医師は当該施設の麻酔科医です).
🔷 ペインクリニック・緩和医療関連
⚫ 慢性疼痛診療ガイドライン(日本慢性疼痛学会)
- 日本慢性疼痛学会や,日本ペインクリニック学会などいくつかの学会でもPDFが公開されています(書籍版も市販されています).
- 全278ページあるため,試験のために全部読むのはきついですが,CQ形式になっていますので,気になるところや重要ポイントは拾って読む必要はあります.
- ペインクリニック・緩和医療領域は,ローテートシステムがしっかりとしていないと,特に若手のうちはなかなかしっかりと経験できないことも多いですが,基本的な定義や評価方法,投薬方法などは押さえておきましょう.
- CQA1〜4:総論.慢性疼痛の病態や分類など
- 48〜49ページ:慢性疼痛治療に対する使用薬物の一覧表
- CQC-1〜12:薬物療法.NSAIDsや抗けいれん薬など
- CQD1,D4・5:硬膜外ブロックや星状神経節ブロック,交感神経節ブロックに関して
⚫ がん疼痛の薬物療法に関するガイドライン(2020年版:日本緩和医療学会)
- 日本緩和医療学会は,リンクに関して許可制となっているため,リンクは貼っておりません.各自検索して閲覧してください.「日本緩和医療学会 がん疼痛の薬物療法に関するガイドライン」で検索すると,該当ページが表示されると思います(市販の書籍のページもヒットしますが・・).
- 基本的な内容はすべて記載されていますので,ぜひポイントを絞って読んでみてください(購入してもいいですね.私も5年前に購入しました).
- 2章 背景知識 4. 薬理学的知識
- 2章 背景知識 5. 非オピオイド鎮痛薬
- 2章 背景知識 6. 鎮痛補助薬
⚫ 日本ペインクリニック学会のガイドライン
- 治療指針・ガイドライン・ステートメントのページに色々な治療指針やガイドラインが掲載されています.
- 中には会員限定公開のものや,書籍販売のものも含まれるため,必要に応じて学会員になるか,購入しましょう.
- ペインクリニック治療指針改訂第7版(amazon)
- 術後痛ガイドライン(amazon)
- 非がん性慢性疼痛に対するオピオイド鎮痛薬処方ガイドライン改訂第3版(amazon)
🔷 その他のガイドライン等
⚫ せん妄について(MSDマニュアル プロフェッショナル版)
⚫ フレイルの基準:日本版CHS基準
- 近年周術期管理でもトピックのフレイルについての基準です.
- 口頭試問や筆記試験でも問われる可能性があるため,少なくとも項目は覚えておきましょう.
- 色々なページで掲載されていますので,ご覧ください.
- 日本版CHS基準(J-CHS基準)(Google検索)
⚫ 甲状腺クリーゼ診療ガイドライン2017Digest版(日本甲状腺学会)
- 日本甲状腺学会の診療ガイドラインページから閲覧できます.
- 試験においては,悪性高熱症との鑑別や,症状への対症療法などが問われる可能性がありますので,目を通しておきましょう.30ページほどのガイドラインですが,フローチャートや図表なども多いため読みやすいです.特に診断と診療のステートメント一覧,初期治療に関しては見ておきましょう.