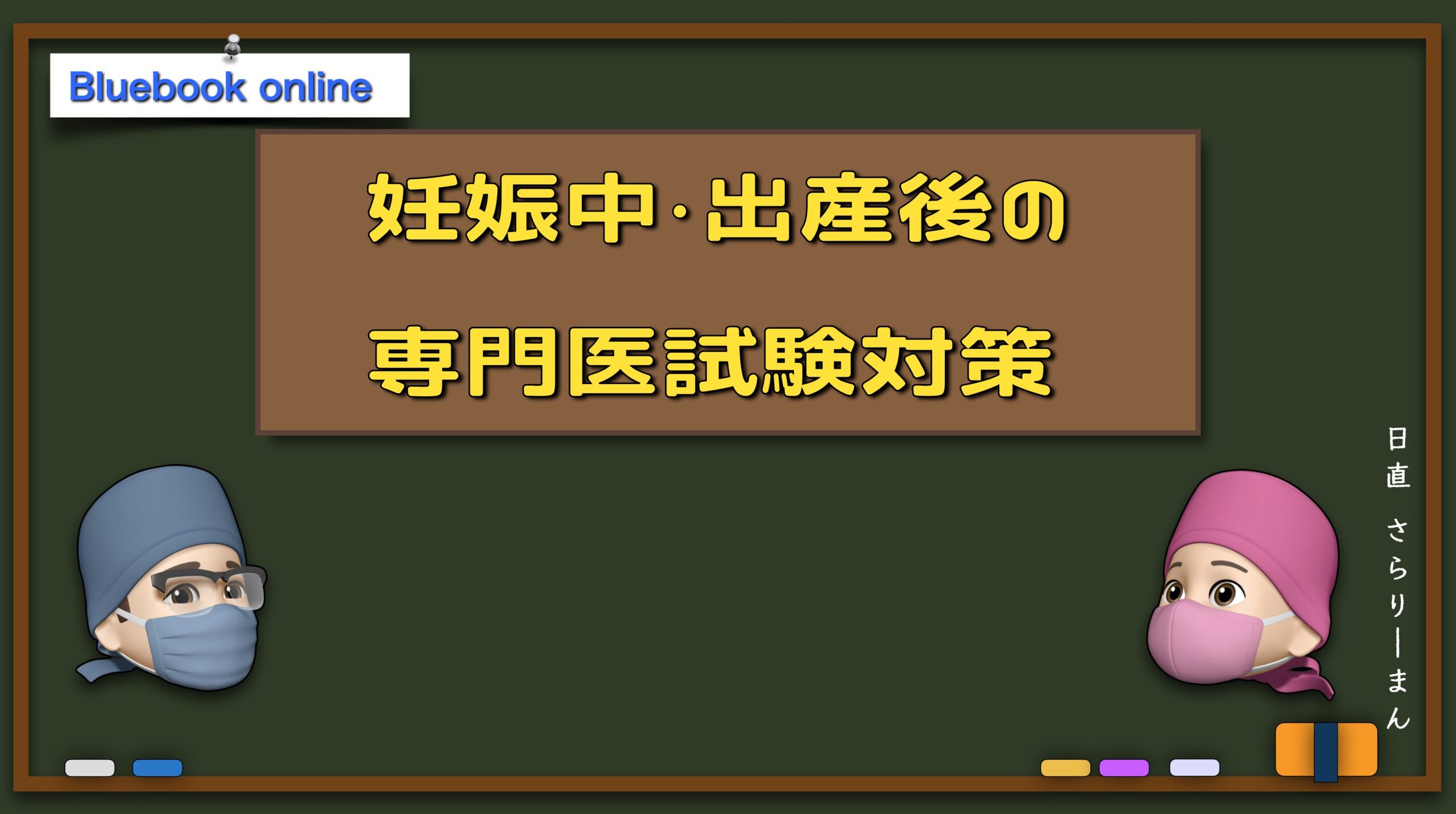さらりーまん
さらりーまん今日は妊娠中に麻酔科専門医試験を受けることになった先生の体験談から対策を紹介していくよ!



確かに,そういった先生たちも多いみたいですね!体調管理とか,タイミングによっては大変そう・・・



全文載せると大変なので,ポイントをしぼって紹介していくね.灰色部分が体験談からの抜粋(一部抜粋・編集)です.



お願いします!私も参考にします!
いきなり出てきましたけど,麻酔科専攻医始めたばかりの”まっすー”です.よろしくお願いします!



安直なネーミングにびびってますが,よろしくね.
麻酔科専門医試験会場(口頭)にエチケット袋の持ち込みは可能?
妊娠が発覚し、試験一週間ほど前に事務局へエチケット袋の持参をお願いしました。
お返事としては持ち込みは可能だが、長時間の試験であり体調に十分配慮して受験を考慮してほしいということでした。
集合場所に到着すると、スタッフにエチケット袋の持参の件を耳打ちすると、紙袋を渡されそこに入れて試験会場に持ち込むようにと指示がありました。
同じくマタニティマークをつけている受験者や、かなりお腹の大きな受験者も同時間帯だけで数人見つけられたので、対応も慣れていると思います。



エチケット袋はOKみたいですね!よかった.



どうみても不正にはつながらないからね😅
男には一生わからないつらさです・・.



マタニティーマイクも良いアイデアですね!特につわりが出始めのころは,まだお腹が大きくなくて周りにはわかりにくいですし,会場につくまでにも優先席に座れますしね.



ネットですぐに買えるので両方とも用意しておきましょう!ちなみに,筆記試験がまだ神戸や東京会場で行われていたときには以下のような配慮もあったようですよ.やはり対応には慣れているようです.ぜひ事前に報告しておきましょう.
妊娠中だったので、あらかじめ学会にその旨をメールで伝えてありました。その為か、席は受験番号に関係なく1番後ろでした。おそらく、途中退出しやすいような配慮かと思います。他の妊婦さんらしき先生も1番後ろにいらっしゃいました。
会場には当日到着でいい?
午後〜の集合だったので、前泊せずに電車で行きましたが、満員電車が⚫か月妊婦にはしんどすぎました。



会場が近くても,大事をとって前泊がよさそうですね・・・



会場でもゆっくり座れるとは限らないから,ポートピアホテルでレイトチェックアウトとかにしておくと,集合時間ちょっと前まで部屋で休めるしね😃
専門医プログラム中(専攻医トレーニング中)の妊娠・出産で休んでいた場合は,4年目に受けられない?
専門医試験自体はプログラム4年目であればどのような状況でも受けられるということだったので、今回受験を選択しました。意外と知られてない制度ですので、共有できればと思います。ただし注意点としては、試験の合格の有効期限は4年間だそうで、その4年間で、実務経験4年を経なければいけません(半年の休業一度までであればみなしの実務として休みノーカウント)



とりあえず4年目だったらいいんですね!しかも有効期限が4年間もあるのは嬉しい情報ですね!



確かに.安心して出産できそうだね.ちなみに細かな認定や再認定や休業の取り決めはややこしいので,規約を読んだ後,確認のために学会事務局に問い合わせをしておいたほうが安心ですね!



事務局って怖そうだけど,皆さん誠実に対応してくれますもんね!
妊娠中・出産直後の勉強方法・時期は・・?



妊娠・出産時期や職場復帰,他の子どもがいるかどうか,周りの人たちの協力など,状況は千差万別ですが,代表的なものを紹介していきますね.
今年5月に出産を控えていたため、1月中旬ごろから筆記試験対策を始めました。(中略)
口頭試問対策は出産後、6月ごろからはじめました。なんとか青本を一読し、そのあとは過去問を見て自分で解答を考える→青本の答えを確認する、という作業を繰り返しました。
試験の1ヶ月前に出産予定だったので、早めに準備を開始しようと思い、1月から筆記試験の勉強を始めました.
試験1年以内の出産だったため、準備は1年前くらいから過去問を眺める感じでスタートしていました。夏終わりに復職し、麻酔の合間に勉強していました。
とにかく時間はありませんでしたので、効率よく勉強できるさらりーまん麻酔科医先生の参考書にはとても助けられました。オンライン版も、子供を抱っこしながら勉強することができてかなり隙間時間を利用するのに役立ちました。



つわりから脱する時期や出産時期による計画が大事そうですね



特に臨月と試験の時期が重なったり,出産直後の試験担ったりする場合は特にですね.
夏に出産、試験前に職場復帰をして臨んだ専門医試験でしたが筆記・口頭とも無事合格することができました。妊娠が分かった頃からは元気な時はなるべく過去問を進めるようにしていました,産休中は、集中力もなく思ったほど勉強は進みませんでしたが、まとまった時間がとれるので小児や心外といった苦手分野をノートにまとめたりしていました。
子供が生まれると一人で勉強できる時間が減るので、臨月に入ってからは「まだ生まれないでくれ〜」と祈りながら勉強していました(笑)。
産後1ヶ月は、夫がかなり協力的だったもののほとんど勉強はできませんでした。口頭試験で使ったのはさらりーまん麻酔科医先生の青本のみです。夫に試験官役をやってもらい声に出す練習を中心にやりました。
職場復帰に関しては、元々する予定ではなかったのですが、試験前の職場復帰している時期は夫が育児休業を取得しており、専業主夫のような形でサポートしてもらえました。母乳で育てていたので夜間は私が面倒を見ていました。幸いよく寝るタイプの子だったのでなんとかなりましたが、それでも体力的にきびしくて何度か風邪をひきました。職場復帰したことで臨床のカンみたいなものは戻ってきたので口頭試験には有利に働いたかなと思います。結果的には試験前に復帰してよかったと思っていますが、あまりお勧めはしません。



復帰に関しては最後の一言が全てを物語っているような・・・笑



だんなさんが協力的でよかったですね.でも体力的にしんどそう・・.では次.
子育てしながらでした。勉強時間確保に難渋することが容易に予想できたのでかなり早かったですが2年前から少しずつ(1日数問程度)ですが、勉強開始しました。
第二子の出産が試験の1年前だったので、それまでに4年分程度は1周して、じっくり調べるようなことはだいたい済ませておきました。(産んだらじっくり机に座って勉強するのも難しく)出産後は抱っこしながら、子供が寝た後など隙間時間に過去問を見直し、最終的には5年分5周、さらに3年分を夏ごろから追加して2周、直前は間違えた問題を中心に見直しました。例年の傾向からAB中心に最後は見直していましたが、今年はC問題が被ってたので、過去問は隅々まで見ておいた方が良かったなと思いました。(ちなみに復帰は口頭試問のことも考え、試験を受ける年の夏ごろにしました。試験受けるころには大分麻酔の感覚も取り戻せてきたように思います。)



さ・さすがに試験の準備としては早すぎでは・・・



う・・うん.ここまでできる人は何やっても困らないかも笑.上でもありましたが,復帰する時期は勘を取り戻すという意味でも大事かもですね.
勉強を初めたのは4月頃です。仕事の合間に青本と専門医合格トレーニングを読む感じでした。5月頃〜妊娠悪阻で一旦勉強集中できなくなって7月頃〜本格的に過去問解きはじめました。8月中旬頃〜本格的にやばいと思い始めて、子どもたちを寝かしつけた後の1時間と朝の15分ほど必死に勉強しました。
9月の毎週土日どちらかは夫に子どもを任せてカフェ勉や図書館で勉強させてもらいました。感謝です。



この先生他にも子どもさんがいらっしゃったんですね



ここでもだんなさんのサポートが光ってるね.尊敬します.私もおむつをかえてたころが懐かしい.



(自分のおむつだったりして)



なんか失礼なこと想像してるだろ
一歳の娘がいて子育て、家事、仕事をしながらでの受験だったので、ほとんど勉強する時間がなく、半年以上前から子供を寝かしつけた後に、過去問を少しずつ解いていました。本格的に勉強したのは、3ヶ月前くらい。でも、また妊娠&悪阻で最後の追い込み1ヶ月は死んでました。。。
仕事の合間に勉強したりしていましたが、やはりあまり時間はとれず、平日にしっかり勉強するのは無理だったので、土日に待機をして子供を勤務先の託児所に預けて緊急オペが入らなければ勉強できる〜みたいな感じで3ヶ月間は集中して勉強してました。



この先生もハードモードですね・・



他のお子さんがいると大変ですよね.つわりもひどいひともいれば比較的軽度の人もいるし・・.いかに周りの環境を整えて勉強時間を確保するかですね.
出産後に試験を受験される先生も多いと思いますが、市中病院で夜間休日の当直を一度も経験しないまま受験する場合、不利な面がある(特に口頭試験)と感じました。
入局して早い段階で妊娠・出産・育休に入ると、いわゆる重症症例や急患の経験数が減ります。必要経験症例も、心臓血管外科は二人まで症例数に入れて良いとされているので、自分が1stの症例が少ない場合はさらに合格に不利だと思いました。
それぞれの勤務先で状況は様々だと思いますが、重症症例・心外症例の経験値は重要だと思います。



確かに,切実ですね・・.



経験させてあげたいけど,無理もさせられないし・・.がっつりやりたい派の先生もいれば,できればしばらくは楽なほうがいいという先生もいるしで,下手すると他の先生からも陰口叩かれるしで,差配する先生は大変かも・・
試験前に出産、産休育休が重なり、臨床から離れた状態での試験勉強になりましたが、先生の臨場感のある解説で、実際に症例を経験している感覚で勉強することができました。
また有料のメンバー限定のホームページも、育児でなかなか席について勉強する時間がとれませんでしたが、育児の傍らスマホを片手に、効率よく勉強を進められました。



なんですか?感謝されてうれしかったんですか?



ちょっとくらいいいじゃん・・
まとめ



参考になりました.体験談を提供してくれた先生方に感謝です!



だね.男は出産はありませんが,もし麻酔科の先生を奥さんに持つ先生は,妊娠・出産が試験と重なる場合は最大限の協力を!でないと一生恨まれるかも・・・😅
- 出産時期から逆算して,早めに計画を立てて勉強を開始する.
- 出産後の試験は子育てもあり大変だが,勘を取り戻す点では有用.
- 周りの人たち(特に夫)に協力してもらって,勉強できる環境を整える.
- 妊娠中の試験の場合は学会に必ず報告しておく.マタニティーマークも有用!
おまけ:今は行われていないけど・・・実技試験時は胸骨圧迫するの?
ACLSは妊婦と伝えてあったので、心マはさせられないと思っていたら、普通にさせられました。終わった後に試験管に聞いたら、本部から連絡がなかったとのことでした(T . T)
本来なら妊婦さんは心マしなくていいみたいなので、ご安心を〜指示だけしてくださいとのことです。
もし、させられそうになったら妊婦という事を伝えてください!!



か・かわいそう・・・



だ,大丈夫.いまは実技ないから・・.