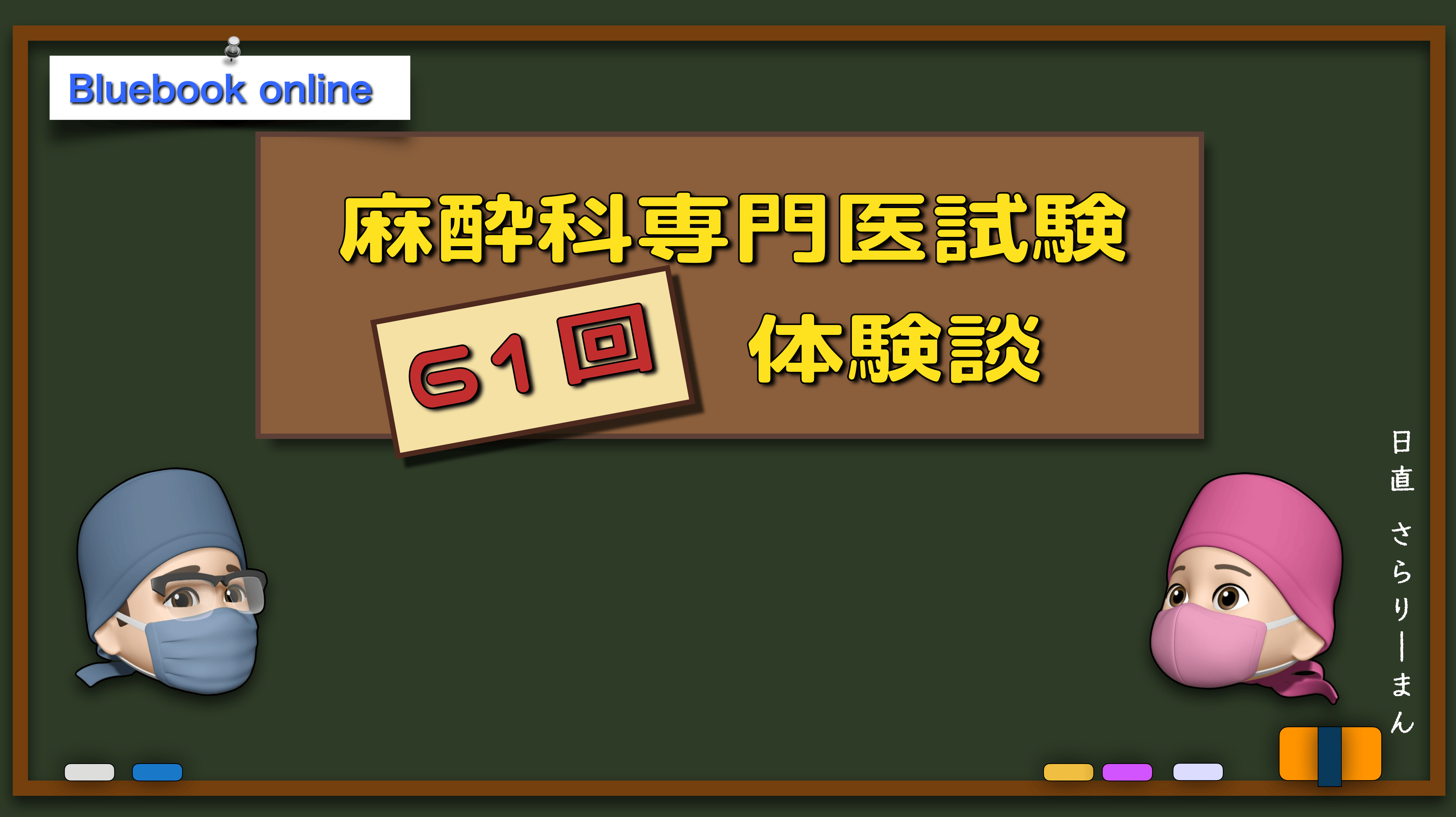さらりーまん
さらりーまん筆記試験に関してはCBTになったので参考程度に
青本・試験への感想に関しては こちら から.
麻酔科専門医試験体験談:その1
今年から2題にもどって問題量が減るのかと思いきや、盛りだくさん。表示されるスライドの量も多く、ほとんど考える時間はありません。試験時間は5分の問題読む時間と10分の試問です。答えるときにちょっとでもうーんとなると、試験官から次の問題に行かれてしまいます。なので逆に言えば時間切れにはならないかなと思います。5分の読む時間で聞かれそうなことはあらかじめメモしておくと時短になると思います。
麻酔科専門医試験体験談:その2
<筆記試験>
○今年から一般問題と臨床問題の2部制になりました。
○試験中途中退室は原則認められません!!試験終了時間が12時50分で次の開始が13時5分。元々15分しかない上に解答用紙の回収・確認が終わるまで退室不可だったので、実質休憩時間は10分強しかなかったです。。きっとトイレも混んでたんじゃないかな。途中退室不可なことを明記しといて欲しかったです。
○問題はどちらも過去問多めでした!臨床問題は過去問出ないかなと思ってさらっとしか見れておらず、これ過去問にあった…!!ってのが5問はあって、こりゃ来年また頑張ろうと思いました。。
○過去問多めなのでサクサク進むから時間には余裕あると思います。回答の数がほんとバラバラなので、マークの見直し必須です。
○環境は、私は寒くもなく暑くもなく快適でした。
→→→結果、不合格。。直近の過去問がうろ覚えだったのが敗因です。だってB問題もC問題もそんなに使いまわされるなんて思ってへんかってんもん。。過去問数年分ABC全部完璧にしていったら大丈夫そうな印象でした!なので来年は確実に受かります!!!
<口頭試験>
→→→結果、合格!!!!
どちらの部屋でも苦笑を頂き、呆れ果てられた感じだったのでこりゃだめかなと思っていたら、合格でした!!!!
<感想>
正直、筆記試験も口頭試問も自信がなく、実際筆記試験は落ちてしまいましたが、口頭試問は合格できて本当に良かったです。筆記試験は過去問覚えてったら勝てるけど、口頭試問は対策の仕方がわからない。。。私が口頭試問受かったのは、自分で言うのもなんですが、人となりを評価してもらえたのかな、と。。多少知識がなくても現場で誰かに助けを求めてカバーできると思ってもらえたのかなあ。わかりませんが本当に受かって良かったです!!ありがとうございます!!
麻酔科専門医試験体験談:その3
<感想>
お聞きになっていると思いますが、筆記試験は問題数が変更になったとはいえ、一般問題も臨床問題も半分以上は過去問と同じでした。3年分をしっかりやっていれば全く問題なかったと思います。私はびびっていたので7年分やりましたが、結果的には不要でした。まさか臨床問題まで過去問と同じ問題が出るとは思いませんでした。受験したほとんどの方が合格されたのではないでしょうか。私の担当の試験官の先生方は、いずれもやさしく誘導してくれました。運もあったと思います。
麻酔科専門医試験体験談:その4
無事合格しました。
感想としては、過去に既出の質問と新問が幅広く出題されて、深く突っ込まれる話題もありボリューム感があった印象です。自分は時間内にすべて解答できましたが、同期は最後の質問の途中で終わったと言っていました。
先生の過去問集をベースに勉強した上で、同期と今年のトピックスやLiSA、各ガイドラインやスコアを手分けして教え合ったりして一通り目を通していたので答えられるところは答えられたといった感じです。
あとは試験官は運次第だと思います。1人目は優しい雰囲気で最後時間が余ったのでおまけとしてひとつ前の質問に付け加える解答がないか確認してくれましたが、2人目は終始厳しい雰囲気で淡々と進み、余った時間は無言の時を過ごしました。
麻酔科専門医試験体験談:その5
- この度は大変お世話になりありがとうございました。おかげさまで無事に合格することができました。形式の変更に関しては、初回受験であり比べようがないことからさほど気になることはありませんでした。みな同じ条件でしょ?と思っていました。
- 神戸受験でしたが縦にも横にも上にも広い会場なのにただならぬ圧迫感は見事でした。
- A問題を解き始めて順調!順調!から始まり、ん?え?から絶望に追いやられる感じ、、、B問題のほうがまだマシに思えました。
- トイレも混むし、記載されている時間よりも正味の休憩時間は短くて、バタバタ感もありました。
- 完全に魂を吸い取られて、ポートライナーで三宮に戻りました。
- 声を出す元気もない私と、仲間同士で試験の振り返りをする若者たち、、、年齢の差を感じました。笑
- 口頭試験は、最初の説明で「麻酔科医として世間に認められる素質を求める」といったくだりがあり、コミュニケーション能力を見てる感じもありました。とりあえずそこは頑張ろうと思いました。
- 移動では「これがドナドナエレベーターか!」と一人なごみ、嬉しくなりました。笑
- フロアについて思ったことは、何というお金のかかった試験なのか⁉、このホテルと学会は蜜月なのか⁉といったことです。
- それだけ気合が入っていると理解し試験に臨みました。
- 一部屋目は症例提示の紙がまぁ詳しくて、、、そこからたくさんの問題を推測するものの、一つしか当たらずでした。
- 患者説明やその場に応じた対応力をみてるのか?と思う質問、あとは尋ね方が難しく、試験官の言わんとされていることが読みにくかったです。聞かれ問い返し、とにかく喋りまくりました。黙ったら終わる、というのは本当ですね。穏やかな先生ではありましたが、最後は時間の関係でまきまきで質問くださいました。
- 二部屋目は症例提示の紙がシンプルすぎて、、、ASすごい高齢者という情報ものみで、こちらのほうがかえってシンプルでした。主に実際の臨床知識を順に問うていく感じで、勉強していればなんてことはないものでした。
- 多くの過去の受験者から「受かった感じがしない試験」「二度と受けたくない試験」と聞いていましたが、本当ですね。もう二度と受けたくありません。
- さらりーまん麻酔科さんが作られた本と、麻酔へのアプローチから出ている「問題集」「口頭試験対策」ともに勉強しました。あと、過去問を7年分を2-3周ほど。
- きついテストですが、麻酔の分野の知識をなべて整理するには本当に役立ったと思います。
- しかし、もう少しやりようもあるんじゃない?とも思いました。
- 以上、長くなりましたが感想になります。
- この度はお世話になりました。今後の活動を応援しています、ありがとうございました。
麻酔科専門医試験体験談:その6
ドナドナエレベーターで出荷され、ホテルの廊下に受験生とアテンドの人が1:1で各部屋の前に配されました。試験開始時刻が近づくとアテンドの方々がそれぞれのタイミングで注意事項を読み上げるので、「カエルの歌は」の輪唱状態でした。5分間、問題の書かれた紙にメモする時間が与えられます。
試験は2問で、1問は全く知らない知識を聞かれることも多くかなり動揺しました。もう1問は、まだ答えられたと思いますが、1問目の余韻で若干しどろもどろになり時間が足りなくなってしまいました。
麻酔科専門医試験体験談:その7
青本のおかげで3科目とも合格できました。ありがとうございました。
筆記試験対策は1ヶ月前から本格的に始めて、過去問のA問題B問題のみ5年分丸暗記するまでまわしました。C問題は3年分しかやりませんでした。
口頭試問は筆記試験後から青本の一問一答を読み込みましたが、いざ開いてみると筆記試験対策にも大いに役立ったことがわかり、もっと前から読んでおけばと後悔しました。
一問一答集が非常に網羅的で短期間の勉強時間でもなんとか合格することができました。
口頭試問は,雰囲気は2部屋とも非常に穏やかで、ときに誘導質問もありました。時間があまり、色々とお話もしていただけました。
麻酔科専門医試験体験談:その8
半年前から過去問を始めました、本格的に試験勉強を開始したのは3ヶ月前です。過去問5年+A問題のみ7年やりました。
<筆記試験>
問題数が少なくなったためか肉体的には楽でした。
ほぼ全員私服でした。会場が寒かったので防寒具を持って行けば良かったと思います。休憩時間に昼食をとれますが歯磨きする場所がありません汗。
トイレは激混みです。受験人数と休憩時間とトイレ数を計算すると予測できたはずですが。時間は余りました。
<口頭試験>
待合室が劇寒でした、防寒具を持って行けば良かったと思います。
なぜかスピーカーが外人で試験案内が片言の日本語でした。(お金ないのか、人が集まらなかったのか)
宿泊はポートピアホテルをお勧めします(荷物を部屋に置いたまま受験できるのでむしろ安いです)
1問目 肥満の麻酔 SAHの頭部CT 麻酔計画と術中術後管理について、一般的な内容でした。
2問目 非心臓手術の術前循環器評価をガイドラインに沿って説明してください。 →まったく知らない内容だったので適当に答えましたが、ここはゼロ点に近いと思います。
筆記試験は過去問とほぼ同じ問題はほぼ解けましたが、新作問題はおそらく3割くらいの正答率と思います。
口頭試験は全く知らないことを聞かれるとかなり焦りましたが、なんとなくそれに近いようなことを答えました。
無事に合格できましたありがとうございました。
麻酔科専門医試験体験談:その9
<筆記試験>
8年分5週と直前2日間で間違った所のみ見直しました。
最終的には選択肢だけで答えが分かるレベルになっていました。
今年は多くが過去問で、過去問さえやっていれば合格点に届いたと思われます。
新作問題も一部ありましたが、過去問さえ分かればあまり合否に関係無かった気がします。
試験が終わって手応えは充分、といった感じでした。
<口頭試験>
勉強法としては筆記試験の勉強で分からなかったこと、大事だと思う事を大まかにノートに書きました。あとはさらりーまん麻酔科医先生の対策本を用いてよく聞かれる事をパターン化して答えを覚えました。
医局の勉強会や同僚にお願いをして喋る練習を何度も行いました。
最終的に5年分を実際に口頭試問の形式で練習しました。
試験官も頷きながら反応してくれたので非常にやりやすかったです。
その他試験の感想としては時間配分に気を使った方が良いと思いました。問題数が10問以上あるので一問一分も使えないはず?なので悩んでる暇は無いと思い絞り出しながらテキパキ答えました。実際残り時間は一分もありませんでした。
以上です。
来年受験の先生方、頑張ってください。応援しております。
麻酔科専門医試験体験談:その10
<口頭試問>
1問15分ですが、質問の量も多く、割とパッパと進んでしまいます。えっと…と考えていると、ヒントをくれたりしますが、おそらく試験監督の先生の中でこの問題は何秒経ったら次に行く、みたいなのがあるんだと思います。考える時間が少なく、手応え的には全然答えられませんでした。パッとスライドでバイタルを出されたり、口頭でバイタルを言われてもそれを瞬時に理解するのは難しかったです。
1問目は初めてだったこともあり、本当にパニックのようになってしまい、出血したら全身麻酔だ…という思い込み?が働いてしまったためうまく答えられなかったです。試験官の先生お2人も真面目そうな方で、余計に緊張してしまいました。
2問目は試験官の女性の先生が雰囲気を和やかにしてくれて、1問目同様、あまり模範解答となる答えは出せなかった気がしますが、少し落ち着いて答えられました。最後は50秒ほど時間が余り、1問目はどうでしたか?と聞かれたのでパニックになってしまい全然答えられませんでした等の会話ができました。こっちはちゃんと答えられてるけどねぇと言ってくださいました。
体験談としては以上になります。本当に15分はあっという間ですし、質問量が多くて時間がありませんでした。私が受けた2問は振り返るとそんなに難しい問題ではなかったですが、当日の緊張は想像以上で、自分の実力が全然発揮できなかったなと悔しく思いました。これは落ちたなと思っていたらまさか受かっていたので、何を評価されたのか自分でもわかっていません…
個人的な話になりますが、私はテレビゲームが大好きで、試験勉強があるからと言ってゲームをやめるのはすごく嫌だったので1年前から勉強を始めました。試験直前には過去問7年分を5周、さらりーまん先生の対策本2周(うち1周は同じく医師の旦那に対策本を渡して15分測りながら実際の口頭試験っぽく行いました)が終わった状態で臨みました。もしも今後、私のようにゲームを愛してやまない専攻医の先生がいらっしゃれば、1年前から頑張れば受かるかもよ!というメッセージを届けたく、余談となりましたが記載させていただきました。
長くなりましたが、無事に試験に合格できたのは先生のおかげです。本当にありがとうございました。
なぜ自分が受かったのかわからずじまいですが、これからも日々勉強して試験監督の先生方の評価に見合う麻酔科医を目指して頑張ります。
麻酔科専門医試験体験談:その11
口頭試問、ほとんど先生の本で乗り切らせていただきました、ありがとうございます。
お陰様で無事、1回で合格することができました。
<筆記試験>
子育てしながらでした。勉強時間確保に難渋することが容易に予想できたのでかなり早かったですが2年前から少しずつ(1日数問程度)ですが、勉強開始しました。第二子の出産が試験の1年前だったので、それまでに4年分程度は1周して、じっくり調べるようなことはだいたい済ませておきました。(産んだらじっくり机に座って勉強するのも難しく)出産後は抱っこしながら、子供が寝た後など隙間時間に過去問を見直し、最終的には5年分5周、さらに3年分を夏ごろから追加して2周、直前は間違えた問題を中心に見直しました。例年の傾向からAB中心に最後は見直していましたが、今年はC問題が被ってたので、過去問は隅々まで見ておいた方が良かったなと思いました。(ちなみに復帰は口頭試問のことも考え、試験を受ける年の夏ごろにしました。試験受けるころには大分麻酔の感覚も取り戻せてきたように思います。)
<口頭試験>
6月ごろまでにさらりーまん先生の対策本ベースに過去問5年分、麻酔科専門医試験合格トレーニング、稲田先生の新しく出た口頭試問の対策本を一通り読んで、10月ごろから過去問2週目+さらに3年分さかのぼって不足した知識を補いました。筆記が終わってから対策本2冊の苦手な分野を中心に復習しました。夫に問題読んでもらったりして実際に声に出したり、実習の学生に世間話も一切せず勉強したことを説明しまくって練習しました。筆記が終わってから2週間弱で結構詰めこめました!
二例目の先生は2人ともかなり優しかったです。誘導もして下さいましたし、2人ともうんうん、と頷きながら話して下さいました。
これも時間余って最後は一例目はどうでしたか?とかどこから来たの?とかお話してくれました。1例目がいまいちと答えたら、「最後までいったならまあ大丈夫ですよ~」と慰めて下さいました笑 試験管の先生に助けられた1例でした。
【感想】こんなにも頭の中が真っ白になるとは思いませんでした。普段なら考えればわかることもこの場になると、わからなくなります。自分の納得のいく回答を出せなかったのが悔やまれました。あとは試験管の先生の雰囲気とか当たった問題で答えやすさも変わってきますし、本当に運の要素も強いと思いました。(2日目でしたが、1日目に受けた人の問題が難しくて驚愕しました。)結果的には合格していましたが、普段からしっかりと考えて術前から術後まで丁寧に症例を積み重ねることの大切さが身に染みてわかりました。正直落ちたと思っていたので発表まで心臓に悪い日々を過ごしました。もう2度と受けたくありません。。。
後輩達がどんどん専門医になっていく中、一緒に受験する後輩もバリバリの急患や重症を担当しているのを片目に、子育てもあって、中々、最近の急患や超重症例の麻酔の経験も少なく本当に大丈夫かと不安な中での勉強でしたが、隙間時間の確保と家族の協力、子供を産む前の麻酔経験で何とか乗り切れました。試験前に同じような境遇の先生がどんな感じだったか気になっていたのもあったので、この体験談が少しでも今後受験される先生方の参考になれば幸いです。
さらりーまん先生の本は抱っこしながら、麻酔の落ち着いてる時間などの空いた時間にさっと読めたので大変助かりました。ありがとうございました。
麻酔科専門医試験体験談:その12
60回を受験し、筆記は合格しましたが口頭試験で落ちてしまいました。
61回の口頭試験までの1年間は、ずっと辛かったです。常に口頭試験のことが頭の片隅にちらついて、プレッシャーがかかっていました。
口頭試験の試験対策として、不合格だった際は筆記試験からの1週間程度しか勉強していなかったので、今回は3か月前から本格的に勉強始めました。
青本を参考にしながら、過去問を学会のHPに上がっている分は全てやり、青本で答え合わせをしました。また、青本の一問一答や予想問題もやりこみました。それに加えて、山陰先生の「麻酔科専門医合格トレーニング」と、稲田先生の「知的アプローチ 口頭試問問題集」を参照しました。また、学会が出しているガイドラインは全て目を通し、加えてCOVID関係のガイドラインも読みました。
一緒に受験する人が私の施設にはいませんでしたので、問題を出し合ったりの練習はできませんでした。かなり勉強していましたが、不安は常に拭えませんでした。
去年は三ノ宮のホテルに泊まって落ちたので、今回はポートピアの近くのホテルに泊まりました。綺麗は綺麗ですが古くてお化けが出そうな感じでした。やっぱりポートピアに泊まるのがオススメです。朝早い場合もあるし。それから、移動手段は去年は新幹線で落ちたので、今回は飛行機で行ってみました。
<感想など>
受験した次の週の木曜に合格発表があり、無事に合格していました…全く手応えはなかったです。他の人の話を聞くともっとえげつない問題もたくさんあったようで、CABGの問題は基本的だったので助かったなぁと。
何年も前から言われているかもしれませんが、日常の臨床を大事にすることが本当に重要だなと、改めて思いました。何となくで済ませても何となくできてしまうこともありますが、そういう時にちゃんと勉強していればな…と思う自分でした。
問題の傾向が急に変わってきている(難しくなっている)印象で、普通に対策できないような部分もあると思われますが、やはり青本をベースにして基本的な質問には必ず答えられるようにすることで、自分は合格出来たと思いました。
特に自分の施設は心外や呼吸器、特殊な小児がないので、さらりーまん先生の本がかなり頼りになりました。読み込みすぎて、さらりーまん先生の心の声が自分も時々出るようになっていました笑
来年以降受験される方は、本当に大変だと思いますが、青本は頼りになる本で心の支えでした。皆さん頑張ってください。さらりーまん先生、本当にありがとうごさいました。
麻酔科専門医試験体験談:その13
<試験対策>
試験の結果、3科目とも合格しました。
私はプログラムの初めの3年間は大学病院に勤務し、4年目の専門医試験受験の年の4月に、時間外勤務が月80時間を超えるハイボリュームセンターに移動しました。移動して3ヶ月間は施設のシステムや、新たな業務に慣れるのに精一杯で、正直勉強どころではありませんでした。中堅の先生に相談したところ、業務や臨床のことは周りの人に聞けばいいから、先生は試験勉強に集中していいよと言われ、それからは臨床業務は自分で調べたり勉強する前に他の先生に聞いて、なんとか時間を作ることができました。
具体的に勉強を始めたのは、3年目の1月頃から、Y先生の口頭試験対策本を読み始め、試験対策も兼ねて普段から臨床上注意すべき点を意識するようになりました。
筆記試験は4年目の6月頃から過去問を古い方から5年分解きました。分からなかったところは直前に見返せるように付箋を貼っておきました。また、分からなかったところを中心にノートにまとめて覚えました。最終的に、ノートはルーズリーフのバインダー2冊になりました。
試験の2ヶ月くらい前から付箋を貼っておいた過去問を見返して、最終的には分からなかった部分は3周くらい解いたと思います。
1ヶ月くらい前から、解説で分からないところや採点除外問題について週2回ほど業務開始前(7:30から30分間)に勉強会をしました。幸いにも同期が6人いたので、何かしらディスカッションできてありがたかったです。
<筆記試験>
筆記試験は前日からポートピアホテルのエグゼクティブフロアに泊まりました。これは先輩のお薦めでした。エグゼクティブラウンジで勉強しながらアフタヌーンティーとカクテルタイムを楽しみました。その後19:00くらいからはホテルのジム、プール、サウナで息抜きしました。その後はまた部屋に集まって23:00くらいまで勉強しました。
筆記試験当日は朝、ラウンジでビュッフェを食べて、ラウンジで少し勉強してそのまま会場に向かいました。試験開始はお昼でしたが、朝食をたくさん食べたので、間の休憩時間もお腹は空かなかったです。また、今回は途中退室も認められておらず、インターバルも少なかったので、休憩時間に何か食べられるのは期待して行かない方がいいかもしれません。筆記試験終了後は同期で三宮で打ち上げをしました。ラウンジを自由に使えますし、食事のことを考えなくてもいいし、私もエグゼクティブフロアの宿泊をお勧めします。もし次に1人で受験するとしてもエグゼクティブフロアに泊まると思います。(早めに予約しないと埋まってしまいます。)
<口頭試験>
口頭試験の過去問は筆記試験が終わってから読み始めました。筆記試験で分からなかったところも復習しました。最終的に過去問は5年分くらい読みました。口頭試験前日は同期とメリケンパークのホテルに泊まりました。一人だと不安ばかりが募るので、近くに同期がいてくれて本当によかったです。夕食は神戸牛のお店に行き、ちょうど全国旅行支援のクーポンがあったので、ホテルの高級なバーで一杯だけ飲んで寝ました。
当日の待機場所では書類は開けますが電子機器は使えないので、紙の参考書もあると安心できると思います。服装は男性はみんなスーツにネクタイ、女性もスーツが多かったです。同じ時間の集合は40人くらいで、20人ずつくらい2グループに分かれて試験が行われます。私は1番目のグループだったので、待機時間はありませんでした。
業務用エレベーターで移動して各部屋の前に用意された椅子に座ります。クロークなどはなく、キャリーケースも一緒に移動します。時間が来ると一斉に試験の説明が読み上げられ、その後試験の問題と筆記用具が渡され、5分間、問題用紙に自由にメモを取ることができます。
私は1問目は想定通りだったので、聞かれそうなことをさっとメモ書きしました。5分経過すると問題用紙と筆記用具は一旦預られ、時間になって試験部屋に入室する際にメモをとった問題用紙だけ再度渡されて、口頭試験が始まります。
やはり、口頭試験は一発勝負なので非常に緊張します。何を言ったか覚えていないくらいでした。考えても分からない問題もあったので、飛ばしてもらいました(試験管が頃合いを見計らって次に進めてくれました)。最後の問題が終わった後、少し時間があったので、試験官が「緊張した?ちゃんと答えられていたから大丈夫だよ。次の問題も頑張って。」と言ってくれて、少し安心しました。今回から口頭試験は2問になって、1問目が終わると2問目は反対側の列の部屋に移動します。2人ペアで向かいの部屋と入れ替わる方式です。
この調子で2問目に意気込んで問題用紙を見たら、なんと3行しか書いてありません。特に何もメモすることも思いつかなかったので、緊急手術に関する様々な思考を巡らせながら5分経つのを待ちました(後から同期に聞いたら、ACLSの蘇生手順をメモしていた人がいました)。
この問題については、まず試験問題読む5分間、何すればよいか分からず、動揺したまま試験部屋に入り、試験官からの情報量が多すぎて、よく理解できませんでした。最後の方にはどんな先天心だったか忘れたので聞き返してしまいました。この部屋の試験官は無愛想な方2人で、終わった瞬間落ちたと思いました。最終的には合格していたので、分かる範囲で答えられる問題を答えていけばいいのかなと思いました。
移動してきたハイボリュームセンターがかなり過酷な労働環境だったため、試験勉強もしなければいけなかったのは非常にストレスでしたが、理解のある上司と同期のおかげで合格することができました。試験のタイミングで異動するのは精神衛生上よくないかもしれませんが、周囲に助けてもらえる時には助けてもらって乗り切るのが良いのではないかと思いました。それから、試験を経て、同期との絆が深まりました。
麻酔科専門医試験体験談:その14
筆記試験は5月ごろから過去問を始めて5年分を4-5周しました。結果、本番は例年以上に過去問が多かったので何とかなったかと思っております。5年分で足りなかった内容は青本の1問1答が役に立ちました。
口頭試問対策は8月に青本を購入(ギリギリすぎたと反省しています…)したのと、麻酔科専門医合格トレーニングを通読しましたが正直筆記が終わってから焦って対策し、口頭試問は想像以上に緊張し、言葉に詰まり、2問とも答え終わって30秒程度しか時間が余りませんでした。どちらの先生方もこちらが回答に詰まると他にはないですか?、〇〇に関する質問ですよ?と言って促してくれる感じがあり、決して落そうとしているのではないのは伝わってきました。
思った以上にマスク換気に関する内容が多かったのと、緊張から言葉に詰まるタイミングが多かったので普段から口に出す練習をしておかなければ、と思いました。参考になれば幸いです。
麻酔科専門医試験体験談:その15
おかげさまで、この度無事に専門医試験に合格することができました。
本当にありがとうございました。
口頭試問は過去問の解答例がなく対策が難しかったので、青本があって大変助かりました。また先輩方の感想もリアルな声が聞けてよかったです。
以下、各試験の感想です。わずかながらお役に立てれば幸いです。
<筆記試験>
過去問5年分を4周、さらに2年分3周ずつ解きました。最初の1周は知らないことばかりで途方に暮れましたが、次第に出題傾向や憶えるポイントがわかるようになりスイスイ進むようになりました。麻薬の換算やSOFA等のスコア、抗凝固薬など、暗記リストを作りました。口頭試問対策にもなります。始める時期は人それぞれですが、私は日中の時間が取りやすかったので7月末から始めて間に合いました。
今年は出題傾向が変わり、一般80問・症例(旧C問題)55問となりました。一般はプール問題(A)でなくすべて新作(B)なのでは⁉︎などと戦々恐々としておりましたが、蓋を開けてみたら一般・症例ともにおよそ半分以上は過去問と同じかよく似た問題で、従来通り過去問を解いていけば対応可能なものでした。
コロナ対策のためか、例年と異なり試験時間中の退室は不可でした。東京会場では15分弱の休憩時間にトイレが混み合い、軽食を摂る時間もほとんどありませんでした。ちなみに持ち物にHBかBの鉛筆と記載がありましたが、事前に事務局に確認したところシャープペンシルの使用もOKとのことでした。計算問題もあるのでシャーペンがいい方はお持ちいただくといいかと思います。座席は一人につき長机一つがあてがわれ、周囲も気にならず快適に受験できました。
<口頭試験>
各種ガイドラインを一度は通読することをおすすめします。筆記試験後から対策としてさらりーまん麻酔科医の青本で過去問とその解答例に目を通しつつ、今年7月に発売された稲田先生の「麻酔への知的アプローチ 口頭試問問題集」で予想問題を解き知識の拡充をはかりました。電子媒体もありますが、待機場で使用できるよう紙媒体にしました。スマホなどは万が一にも鳴ったら怖いので、宿泊したホテルの部屋に置いて本だけ持って行きました。会場に泊まれば移動がエレベーターのみで楽ですし、終わったら即着替えられるのでお勧めです。(ちなみに全国旅行支援で宿泊代5000円off+1000円分の金券をもらえたうえ、上層階の広いお部屋にアップグレードしてくれました!)
試験官は2題ともめちゃくちゃ優しい先生方でした。試験の部屋の前で設定の書かれた紙を渡され、5分間、読んだり付属のボールペンで書き込んだりする時間が与えられます。入室の際はその用紙と自分の荷物を持って入ります。試験官と自分の間にパーティションがありました。問題文がゆっくり読み上げられ、検査データや画像のみ横のテレビモニターに映し出される仕組みでした。画像を見る際には「見終えたら教えてください」と時間を取ってくれます。問題の最後までいくのが大事と聞いていたため、「〜なことを5つ挙げてください」といった問題で3、4個しか思い浮かばず焦って次々に進めてもらった結果、逆に時間が余ってしまいました。終了まで試験官の方とお話ししました。コロナ対応は先生の病院では多いですか、普段から集中治療の経験はありますか、などの質問で終始穏やかな雰囲気でした。
試験対策に誰かと問題出し合うのがいいと言われますが、院内に同期がいなかったり友達少なかったりで相手がいなくても、本番を想定して前を向いて声に出す練習をしておけば大丈夫だと思います。頻出テーマ(例:挿管困難の導入など)は何も見ずにスラスラ言えるように練習しておきました。
<感想など>
専門医試験の勉強は、仕事や家庭などの色々と重なりなかなか時間も取れず大変だと思いますが、一度やっておくと自分の糧になりますし、経験の少ない分野も標準的なレベル(?)までの知識は得られたのかなと自信になります。一度で合格できるに越したことはないですが、そうでなくてもとりあえず挑戦する価値はあると思います。
麻酔科専門医試験体験談:その16
筆記試験
持ち物:筆記用具(マークシート)、受験票(各自学会ページから印刷したもの)、受験前確認書(コロナ対策、こちらもホームページにある試験案内から各自印刷したものを持参)、時計(席が後ろだと非常に見づらいです)
60回までと出題形式が異なり、一般問題(60回で言うA問題とB問題)と臨床問題(C問題)に分かれました。
10時から開場、説明開始11時まで電子機器でも紙媒体でも見ることが出来ます。
11時の説明開始になったら全て鞄にしまうよう言われました。
一般90分
結構時間がギリギリで見直しもざっとしか出来ませんでした。前半既出50問、後半新問40問。
5年分やって見たことない問題はなかったように思います。選択肢の順番とかマイナーチェンジしてるやつはありました。2問ほど計算問題が数字変わってました。
間の休憩が15分くらいしかなくてトイレくらいしか行けず、トイレすらもかなり混みました。
食事に関しては、朝しっかり食べるか、少しつまめるくらいだと思います。
臨床問題90分
一般よりは時間の余裕があったように思います。
前半新問20問、 後半既出25問。
終わって途中退出は不可だったように思います。
試験番号ごとに退場するように言われました。
口頭試験(筆記終わってから2週間弱)
持ち物:筆記と同じく受験票、試験前確認書(コロナ対策)
筆記用具はなくても大丈夫でした。症例のメモに使うボールペンは指定のものを渡してくれます。
※ほとんど全員スーツでした。荷物とか上着とかは常に持って歩かないといけないので注意です(どこかに置くのではなく試験の部屋まで持っていく)
試験日は11/4-6(金-土)のいずれかでした。
9/30に届いた学会からのメールで、受験番号と一緒に口頭試験の日付と時間が書いてありました。
指定された集合時間20分前から待合室入れます。
試験前確認書チェック回収あります。
待合室入室後、iPadは禁止されているはずですが見てる人もいました。特に注意はされていなかったと思います。
説明開始以降は置いてある封筒に携帯とか電子機器全て電源OFFで入れて、自分のカバンの中に入れるよう指示がありました。
説明後案内があれば移動。半分ずつくらいで呼ばれるので、その部屋の後半の番号になっているとプラス30分ほど待機時間がありました。
例のエレベーターで移動しました。
問題は2つで、15分ごとで部屋入れ替え(ホテルの客室)でした。ホテルの部屋の前に座って、横のスタッフからまず紙わ渡されて5分間症例読んでメモ書きしました(症例のさわりが書いてある)
後から見ながら答えることが出来るので、思いつくことはメモしておくと良いかと思います。
5分経つとストップウォッチが鳴って一旦回収
部屋に入るよう言われます。
まず荷物を置くように言われ、試験番号と名前を言ったあとに座ってくださいと言われました。
座って右側の人が進めていき、左側の人は接遇問題の患者などの役になっていました。
検査値・問題によっては質問・画像・動画などは横のモニターに映し出されます。
ほとんどの質問内容は試験官から口頭で言われます。
モニターの文章読み終わったら教えてくださいとモニターに出る度に言われる。
指し棒が置いてあって、必要な場合それで位置を指すよう指示がありました。
(以下症例など記憶が曖昧ですので間違っている場合があります。ご了承ください)
麻酔科専門医試験体験談:その17
この体験記を書くことが出来てとても嬉しいです。
自分も何度もこちらの体験記を読んでとても励まされましたので、特に産後の方の参考になればと思い、書かせていただきます。
〈勉強開始時期について〉
私は医師●年目の夏ごろに産休に入りました。機構専門医プログラムでは、3年間の研修期間が過ぎると前倒し受験ができ、4年間のプログラムのうち半年以内の休止は申請により認められます。
そのため半年以内の復帰を目指し、試験勉強は産休中に開始しました。試験の1年程前からです。
子供が生まれたら勉強出来ないだろうと思い、妊娠中から勉強をしようと思いましたが、気分もすぐれず仕事をするので精一杯でしたので、結局産後からの開始となりました。
〈筆記試験〉
筆記試験の勉強は皆さんの言う通り過去問で行いました。7年分をガイドラインなどを調べながら解いていきました。勉強時間の確保が難しかったので、先に進むことを目標とし、時間をかけずにまずは7年分をざっと解きました。必要なガイドラインは全てiPadに入れ、いつでも見直せるようにしておきました。ノートまとめなどをする時間は確保出来なかったのですが、過去問で繰り返される問題は暗記し、教科書での理解が必要な部分は調べるといった形で勉強し、7年分5周以上は解きました。
筆記試験は今年から形式が変わったとはいえ、過去問からの出題が多いことには変わりなかったので、やはり今後も過去問を覚えるほど繰り返すという方針で良いのだと思います。
〈口頭試問〉
受験者の中で最も臨床経験が期間的に少ないという点で、始めからとても危機感を感じていました。筆記試験の合格率は9割を超えるのに対し口頭試問は今年は8割を切っていたようです。筆記試験よりも勉強時間を割く必要があると思い対策しました。
まずは青本で過去問とその答えを確認することから始めました。その中で、知識が曖昧なところは早めに確認しました。私の場合はfontan循環の症例、CAGの読み方、IABPの波形、胸腔ドレーンなどの知識に不安があったため、教科書で勉強したり他科の知り合いに聞いたりして理解を深めました。
また、産休中は授乳時間が多くありその間に手軽に携帯で見ることの出来るオンライン版を利用していました。青本より古い過去問の答えが載っており、オンライン版の形式もとても使いやすかったのでスキマ時間によく利用していました。
青本は過去問の部分は5周ほどして、一問一答は苦手な分野を集中的に読みました。
最近の口頭試問の問題は細かいことが聞かれる印象なので、毎日の術前診察も丁寧に行いました。内服薬や画像所見など気になったことはすぐに調べたりガイドラインを見直したりして、曖昧な知識を整理するようにしていました。麻酔中に研修医が自分についている時は、研修医に問題を出しているフリをしてアウトプットの練習をしていました。また他の人の症例でも気になった症例の麻酔は見に行ったり、カルテを良く見るようにしていました。
〈最後に〉
中々思うように勉強が出来ず試験が終わるまではずっと不安でしたが、合格することが出来て本当に良かったです。
子育てをしながら試験勉強をするのはとても大変でしたが、今までの勉強不足や臨床経験不足をカバーするという意味で必要な経験でした。
自分は決して元々優秀な方では無かったので、産後復帰した時には何度も仕事も試験勉強も辞めたいと思うことがありましたが、最後まで諦めなくて良かったです。自信に繋がりました。
スキマ時間に効率良く勉強し、毎日少しずつでも知識を身に付け、日々の臨床から最大限に学ぶ姿勢が大切だと思いました。
本当にありがとうございました。
麻酔科専門医試験体験談:その18
<筆記試験>
●筆記試験(東京会場:TOC有明)
・今年から試験形式が変わりました。一般問題(今までのA+B)マークシート80問90分、休憩15分を経て、臨床問題(今までのC)マークシート55問90分となりました。
・昨年度の試験講評で「A問題は出来が良いのにB/C問題は5割程度で、過去問をやってるだけというのがバレバレ、今後は出題に工夫が必要」というニュアンスが掲載されていたこともあり、試験形式を変えたということは問題も新作問題が多いのでは…とはいえ過去問を頑張るしかない…と警戒していました。
・蓋を開けたら、一般問題:8割がA問題からの過去問、新作問題も一部はA/B問題の改変、臨床問題:半分以上はC問題からの過去問が出題されました。今までC問題からの過去問が出題されたことはなかったと思うので、C問題対策を手薄にしていた私は試験中にかなりへこみました…また、C問題の新作問題の一部は、60回口頭諮問を改変したものが出題されていました。60回口頭諮問問題は筆記試験後にやろうと思って大事にとっておいたので、いざ勉強を始めたとき更にへこみました…
・今回は過去問からの出題ばかりだったので、時間配分にもかなり余裕がありました。とはいえやはり過去問からばかりの出題となったため、解きながら「一問のミスが命取りとなるだろうなー」とケアレスミスに気を付けていました。
・休憩時間は中15分しかなく、その上女子用お手洗いは1会場あたり4個しかなかったので、休み時間はお手洗いは長蛇の列で、入室時間がギリギリでした。ほかのフロアにもあったらしいですが、道に迷ったり遅刻したりした時のリスクを考えると怖くて探検できませんでした。もちろん臨床問題の対策をする暇もなかったので、一般問題の試験中は時間に余裕があったことだし、挙手して途中退室しておけば良かったと後悔しました。
・余談ですが、東京在住なのに帰りのバスを乗り間違えて、20分の行程を60分近くバスに揺られる羽目になりました。お帰りまで十分に注意してください。
<勉強法、その他感想など>
・頭もあまり良くなく、自分は時間と回数を稼ぐしかないだろうなと思っていたので、試験対策は60回試験が終わった頃から少しずつ始めました。「麻酔中にのんびり読む・問題を解く」というスタイルで、試験直前1か月までは家では勉強していません。
・筆記試験対策として過去問6年分(56回は過去問を入手できなかったのでそれを除く54-60回分)を5周しましたが、はじめの2周は解説までじっくり読み込む→3周目で間違えた問題は要点をGoodNotes5に書き出し→以降正解した問題は該当ノートを削除、5周目でなお間違えている問題は問題を写メってGoodNotes5に貼り付けて丸暗記、本番はGoodNotes5を印刷して試験会場に持ち込みました(筆記試験会場ではiPadなど電子媒体を使うことは
できますが、念のため)。
・稲田先生の「麻酔への知的アプローチ」「同問題集」も買いましたが、難しすぎて途中で挫折しました。もちろんミラーなどその他成書も全く開いていませんし、そもそも持っていません…
・口頭諮問対策は、筆記試験対策と並行して進めていました。過去問1年分を終えたらさらりーまん先生の青本の過去問ページを7年分通読する、という形で、わからない知識は都度調べて知識の補強をしました。また覚えておきたいアルゴリズムや悪性高熱症・局所麻酔薬中毒など学会から出されているガイドラインもスクショしてGoodNotes5に保存、こちらも印刷して神戸に持っていきました。
・昨年度口頭諮問直前に販売された「麻酔科専門医合格トレーニング」も2-3周し、青本に加えて神戸に持っていきました。
・私は同期がおらず、また現在は関連病院へ出向中のため学年の近い先生もいらっしゃらないため、筆記試験も口頭諮問もどちらも対策が難しかったです。特に口頭諮問は「同期同士や先輩・後輩で問題を出題しあう」ことができず、対策方法に困りました。苦肉の策として夫に青本の問題を棒読みしてもらい、私の回答にキーワードが入っているか・網羅されているかを確認してもらいましたが、夫は非医療系職のためお互いかなり苦労しまし
た…
・口頭諮問は試験時間が15分(?)と短いため、話すのがスローペースな先生はお気を付けください。完走できないと加点が足りなくなってしまってもったいないです。またとにかく完走することが大切だと思いますので、話しすぎない・キーワードを簡潔に述べるといった時間配分にも注意する必要があると思います。
・流行りの話題として、コロナ対策やオンダンセトロン・レミマゾラム、実技試験がない分CV挿入手技やACLSはキモとなるだろう…とある程度ヤマを張り、直前にも再確認しました。
・私の口頭諮問の回答を見て頂けたらお分かりかと思いますが、かなり出来が悪いです。頭が悪い上に勉強が嫌いで、試験1か月前までは家で勉強もしない怠惰な生活を送っていましたので、後輩の皆さんには見習わないでほしいと思います。
・試験後は「もっと勉強しておけばよかった」「こんなに不真面目な自分は麻酔科医に向いていないのかな」などと思い悩んで枕を涙で濡らす夜が続きましたが笑、ほぼザルな実技試験も含めて3科目すべて合格できました。おそらく合格者の中では最下位だと思いますが、合格してしまえばこっちのものなので、後輩の皆さんは余裕をもって真面目に取り組んで頂けば合格間違いなしだと思います。応援しています。
麻酔科専門医試験体験談:その19
<筆記試験>
5年分のA問題とC問題を2回、直近3年分を3回やりました。
苦手な分野や知識不足の分野についてはこの時点でさらりーまん麻酔科医先生の本の該当箇所に目を通しました。
今年から傾向が変わると聞いていたのでC問題は新作が増えると予想し、A問題をしっかりおさえることを重視して勉強しましたが蓋を開けたらC問題の中に過去問とまったく同じものが多くあり本番中に戦略を間違えたことを後悔しました。
<口頭試験>
筆記試験の勉強で手一杯だったため、筆記が終わるまで手つかずでした。筆記が終わってから青本を使って過去問を解き、また稲田先生が出している本をサラッと読みました。
口頭試問は最終日でした。集合場所で、最初にえらい人のお話を聞き、北野天満宮のお札?を見せられました。スーツ着てない人は数人で、待っている部屋に時計なく、腕時計を持ってこなかったことを後悔しました。
前半組、後半組に分かれて、後半組は15分程度、集合場所で待たされました。その後、10人ぐらいずつエレベーターで移動しました。
試験場となるホテルの部屋にも時計はなく、ここでも腕時計を忘れたことを後悔しました。症例については必死で答えていたため、詳細が思い出せず、申し訳ありません。
麻酔科専門医試験体験談:その20
2022年度の麻酔科専門医試験、筆記、口頭試問合格いたしました。
青本は試験直前まで読み込んで、ボロボロになるまで使い込みました。本当にお世話になりました。①筆記について
会場はエアコンが効いて寒かったり、暑かったり、さまざまなので、脱ぎ着ができる衣類を着ると良いと思います。膝掛けなどあると女性の方は便利です。
試験中飲み物は机に置いて大丈夫でしたが、目薬は禁止されてました。
飲食は許可されており、試験前や試験の昼休みなどにみなさん軽食を食べてました。
時計は大きなデジタル時計が置いてあり、後ろの席からも見えました。
試験の合間の休憩時間は短く、トイレ休憩のみで終わりましたり試験内容は今年は形式は変わりましたが、基本的には過去問中心で、3-5年分を満遍なくやることが重要と思います。
②口頭試問
三ノ宮駅近くのホテルに前泊しました。
試験当日は、集合場所で説明を受けた後、すべての荷物を持ってエレベーターで口頭試問を受ける部屋にあるフロアに移動しました。試験の部屋は一般のホテルの部屋を使ってました。試験監は2人で、質問をする人と点数をつける人。テレビ画面には問題に関連するデータなどが表示されました。
大動脈弁狭窄症の患者に関する問題と、産科出血に関する問題でオーソドックスな問題でした。
正解がわからない問題もありましたが、自分なりの答えを作って、全て答えました。
明らかに違っているであろうことは、試験監から何度か聞き返されました。
2問とも時間は余りました。前半は無言で数分待機、後半は試験管と少しおしゃべりをして解散となりました。圧迫感はなく、一般的な面接でした。
口頭試問の対策は、筆記試験を終えてから開始しました。青本の過去問を暗記することを第一とし、その他は満遍なく苦手分野や、普段の臨床麻酔でやったことのない分野(小児や産科麻酔、エクモ関係など)は教科書を読み込んで、基本的な知識をつけました。知らないことを聞かれて無言にならないように、何かキーワードだけでも言えるように準備しました。
自分の性格上、あまり本番で緊張するタイプではなかったので、面接練習、声に出しての練習はあまりやっていません。
総じて言えることは基本に忠実に、初歩的なテキストに記載されていることはすべて答えられるように、複雑な問題は皆解けないから差はでない、と思いながら勉強していました。